
目次
- はじめに
- 著者のセブンスデー・アドベンティスト時代
- ファンダメンタリズムからカリスマ派へ
- 福音主義教会のカオスの中で
- 真理はモザイク状のものなのか?
- 「あなたに与えられている光」に真実に生きればそれでいい?
- 定義のない看板文字
- 彼は「越境」しなければならなかったのか?
はじめに
マシュー・ギャラティン著「神に飢え渇くーー浅い井戸の地にて(Thirsting For God: in a Land of Shallow Wells)」(Conciliar出版社、2002年)を読みました。
著者のマシュー氏は、過去20年以上に渡り、プロテスタントのカルバリー・チャペル牧師および賛美リーダーを務めておられましたが、その後、東方正教会に転向し、現在は、洗礼者ヨハネ・アンティオケ・オーソドックス教会に在籍しつつ、ノース・アイダホ大学の哲学科で教鞭をとっておられます。
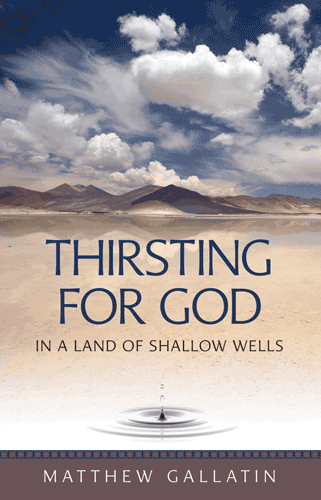
副タイトルの「浅い井戸」という表現は、著者の幼少・青年期のセブンスデー・アドベンティスト時代、及び、20代から40年半ばまでの福音主義・カリスマ派時代の霊的環境を暗示しています。
本書は3部構成で、パート1は、主として著者の霊的自叙伝、パート2は、正教会への改宗後に起こった著者の内的変化、パート3は、エヴァンジェリカルが疑問を抱きやすい正教会の代表的教理(聖母マリアやイコンへの崇敬、典礼、祈祷書を用いた祈り、聖人への祈り)への弁証がメインとなっています。
また本書全体を通し流れている基底メッセージは、「いかにプロテスタンティズムの土台が間違っているのか」という「新教」論駁にあります。
著者のセブンスデー・アドベンティスト時代
私は個人的に、多くの部分で、著者の指摘や証しや魂の呻きに共感すると共に、多くの部分に不同意し、またそれと同時に真正なるチャレンジを受けました。
まず感動したのは、真理を追うて止まない著者の純粋な心の態度と姿勢でした。彼は求道の結果、12歳の時に、両親と共に、セブンスデー・アドベンティストの教えが聖書的真理であることを確信し、SDAに入信しました。
その後、SDAの牧師として献身すべく、アドベンティスト大学の神学科に入学するのですが、大学2年の時に、レビ記11章の「きよい肉、きよくない肉」のSDA教団旧約解釈に深刻な疑問を抱くようになります。
ある土曜日の朝、彼はSDA青年会を導く教師として、教材準備に取り組んでいました。その時、何の前触れもなしに、「マシュー、あなたは自分が信じていることを理解しているのか?自分が信じていることを本当に知っているのか?」という御霊の声を彼は聞いたのです。驚いた彼は主に答えました。「ええ主よ、もちろん、私は知っています。」
すると、主は次のように答えました。「そう、あなたは自分が信じていることを知っている。だが、それは果して真理なのか?」
この語りかけは彼の魂を根柢から揺さぶりました。そして彼は「たといこの先、自分の未来がどうなろうと構わない。僕は自分の信じている内容が真理であるのか、そうでないのかを探求する」と覚悟を決め、いざ真理探究の航海に乗り出すことにしました。
彼はまず、SDA関係の註解書、解説書、信仰書の類をすべて脇にやり、欽定訳聖書(KJV)とストロングのコンコーダンス辞典だけを頼りに、教理研究をすることにしました。
「しかし」と彼は思いました。「僕が知っているのは、ただSDAの聖書解釈だけだ。それ以外の解釈は何も知らない。しかしSDA解釈が正しいか間違っているかを真に知るためには、他の諸解釈との比較対照という作業がやはりどうしても必要ではないだろうか?」そこで彼は、比較対象として、プロテスタントのファンダメンタリスト(根本主義)解釈を選び、その後、5年間に渡り、両者の主張を一つ一つ徹底的に吟味していったのです。
こうして探求の結果、彼は、根本主義者たちの解釈の方が、聖書により忠実な解釈であるという結論に達し、アドベンティスト教会の教職を辞職し、根本主義者たちと交わるようになりました。これが第一回目の「越境」です。
ファンダメンタリズムからカリスマ派へ
しかし次第に、彼は根本主義教会の中で、霊的に枯渇していく自分を発見していくようになります。12歳の時に体験したイエス様とのあの親しき交わり!ああ、あのような親しき交わりはもうどこにも見いだすことはできないのだろうか?そんな最中、ある友人の誘いを受け、初めて、「カリスマ派」と言われる教会に足を運びました。
「カルバリー・チャペルは、『静かなカリスマ派 "quietly charismatic"』の教会だから、こわがらなくてもいいよ」とカルバリーのその友人は後押ししてくれたのですが、確かに、彼の目に、その教会は、秩序の内に(1コリント14章)に聖霊の賜物が行使されており、そこには霊のあたたかさ、そしてデボーショナルで敬虔な雰囲気が漂っており、それは根本主義教会の内には見い出すことのできないものでした。そしてその晩から、彼はカルバリーの忠実なメンバーになりました。第二回目の「越境」です。
福音主義教会のカオスの中で
その後、20年以上に渡り、彼はカルバリー・チャペルの牧師として奉仕に邁進しました。「私が(牧師ではなく)一信徒だったとしたら、もしかしたら、今も私はカリスマ派の人間として留まっていたかもしれません」と彼は回想しています。
しかし群れを導く指導者として、彼はカリスマ派内部・福音主義教会内部のさまざまな問題に、より真剣に直面せざるを得なくなりました。また、聖霊の賜物の実践を通した活き活きとした力、内的高まり、afterglowセッションの静けさの中での主への待望、、そのどれもがすばらしい、、、それなのに、なぜ私の内側はこんなにも空っぽなんだろう?
それに加え、さまざまな教理の違いゆえに、福音主義界は仲たがいし、分裂を繰り返していました。「なぜ、『聖書のみ』を堅く信じている人々の間で、これほどまでに互いに相反する教理が生み出され、また主張されているのだろう?」
「我々プロテスタントのクリスチャンにとり、真理というのは結局のところ、あなたや私が各自それと『解釈するもの』ーーそれに他ならないのだろうか?そう考えない限り、このカオス状況に説明がつかないではないか。」
真理はモザイク状のものなのか?
こういった混沌や分裂状態になんとか「納得のいく」説明をつけようと、私たち福音主義クリスチャンはいくつかの典型的な回答を持っていると彼は言います。
その一つが、「真理はモザイク状のもの」という見解です。これは何かというと、神の真理に関し、異なるクリスチャンのグループが、それぞれ多種多様な見解を持っているというのは、まさに神の御意図であるという捉え方です。
この見解によると、未来において神の民は、真理に関する完全なる知識に導かれますが、目下のところ、神は、プロテスタンティズム内に散らばる様々な諸教派の間にパズルのように真理を散らしておこうと決断されました。そして主の再臨の時、それぞれの教派の持つ真理の一片が集められ、こうして私たちは一つに合わせられた、美しいモザイク状の真理を目の当たりにすることになるのです。
それではなぜ神はそのように決断されたのでしょうか?その理由づけの一つとして次のような回答が用意されています。「神は、ご自身の民が、一貫性なく調和しないさまざまな信条・見解を持つことをお許しになられた。それにより、誰も『自分こそすべての真理を知っている』と高ぶることのないためです。」
「しかし、それは違う!」と彼は叫びます。もしも各教派やグループが真理の一片しか持つことを許されていないのだとしたら、それぞれのグループの残りの部分には、虚偽が包含されているということになる。そしてこの見解を擁護するためには、私は、神が人類のためのご計画を成し遂げるに当たり、虚偽を用いてそれを執行することをお選びになったか、もしくはそれを余儀なくされたということを認めなければならなくなる。しかし、神は偽ることのできないお方であり(テトス1:2)、それゆえ、こういった見解を受け入れ、自分を納得させることはできない!ーーそう彼は告白しています。
「あなたに与えられている光」に真実に生きればそれでいい?
プロテスタント教会の中に混在する多種多様にして特有な諸見解の正当性を擁護するに当たり、私たちはまた次のような別の金言も持っていると著者は述べています。この金言は次のように言います。
「福音主義教会内の他の人々が、真理に関し、いろいろと別の理解の仕方をしているということにあなたは神経質になったり落ち込んだりする必要はありません。あなたは自分自身に与えられている確信に真実でありさえすればいいのです。『あなたに与えられている光』ーーつまり、あなたが真理だと信じているところのものーーに真実であってください。それを神様は望んでおられるのです。」
しかし、この線上での思考は、結局、「確信に対する真実さ・誠実さ」というものを鍵とみなすことになると彼は主張します。「私たちはとことん真実であり、且つ、とことん間違っているということもあるのです!」
こういった考察から次第に、著者は、プロテスタンティズムの混沌を作り出しているのは結局、この「聖書のみ」という標語・スローガンであり、宗教改革の土台そのものに何か根本的問題があるのではないかと絶望感を深めていきます。*1
しかし私の見解では、もしも著者が、神の啓示と人間の認識という点でもう少し包括的な考察アプローチをしていたら、ここまで絶望に陥ることはなかったのではないかと思います。
神は私たちに真理の一片ではなく、「神のご計画の全体を、余すところなく」(使20:27)啓示することを望んでおられると思います。その意味で、著者の言うように「真理モザイク論」は間違っていると思います。また、真摯さが万事を計るものさしになるわけでもないという点にも同意します。
しかし私の目に、著者の見解は、(罪性および有限性による)人間認識の限界に対する考察の詰めが今ひとつ甘いように映っています。そしてもしも認識論をもう少し詰めることができていたなら、彼は「『聖書のみ』というプロテスタンティズムの土台にこそ、もしかしたら根本的誤りがあるのではないか?」という懐疑に陥ることからあるいは守られていたかもしれません。*2(*重要追記があります*3.)。
定義のない看板文字
「人間認識の限界に対する詰めの甘さ」という事を前に書きましたが、この点が、第三番目の彼の「越境」ーープロテスタント教会から東方正教会へーーを、より強烈かつ原理主義的性格のものにする背景的遠因になっているように思いました。
彼は言います。「こういった諸問題で葛藤していた時、ある雑誌で、一人のプロテスタントが、別のプロテスタントの見解を『彼の教理は主観的である』と批判しているのを読みました。でも、それは結局、どんぐりの背比べでは?と私は思わざるを得ませんでした。
こういった言明をするに当たり、私が合理的に一貫性を持ち得る唯一の道は、『私の教理は絶対的真理であり、私と同様の見解を持たないその他のプロテスタントは異端です』と言い切れるようなプロテスタント教徒であることに尽きます。しかし、もし私が神についての相反した諸見解を持つ人々ととにかく信仰において一致していると思いたがっているプロテスタント教徒なら、その時、私は、『教義的主観性および相対主義は完全にナチュラルで受容可能なものである』と信じなければならなくなります。」
こういった思考の線上から、彼の中での、大文字のキー・ワードが「絶対的な性質」を帯びつつ、本書の中盤から頻繁に登場してくるようになります。ーーそれは大文字のChurch, 大文字のFaith, そして大文字のHoly Traditionです。
著者が、この3語を大文字で書く時、それは自動的に、オーソドックス教会、オーソドックス教徒の信仰、オーソドックス教会の聖伝を意味しています。そこに定義づけは全くなく、なぜ大文字で書くことにしたのかという説明書きもありません。そしてこの大文字3語に異議を挟もうとするいかなる行為も、「それこそ、プロテスタント的合理主義が生み出す個人主義的・自己愛なのだ」と糾弾されます。つまり、彼の中ではここは神聖不可侵の領域なのです。
この「プロテスタント的合理主義」に関してですが、おそらく著者の念頭にあるのは、東方教父に比べ、西方教父の方がギリシャ哲学の影響を受けてきており、ルターもカルヴァンも(アウグスティヌスを始めとする)そういった西方教父の哲学および合理主義から逃れられておらず、それが今日に至るまでプロテスタンティズムの一大欠陥になっているという見解ではないかと思います。
もしもそうなら、確かに西側と東側の相違点ということでこの指摘は深く考慮するに値するとは思います。しかしながら、彼はそこから一歩進み、「プロテスタントは神について『考え』、正教徒は神を『体験する』のです」という短絡的結論に陥っています。しかし、本書の主目的である、正教会の正当性弁証と、プロテスタンティズムの虚偽性の論証という行為自体、logicが必要不可欠であり、著者はこの点における自家撞着をどのように考えておられるのだろうと思いました*4。論駁という彼のこの行為自体が、「プロテスタント的、あまりにプロテスタント的」なのですから!
また、Holy Tradition(聖伝、経外伝説)というのが、一体、どの時代からどの時代までの言い伝えを指しているのかも本書の中で明らかにされていません。それがポリュカリポスやエイレナイオス、殉教者ユスティノスなどのニカイア公会議以前の使徒教父たちの言明を含むことは分かります。ですが、apostolic tradition(使徒の伝承)と、聖伝(holy tradition)というのが二つ別々のものであることを教会史家のデイビッド・ベルソーは次のように述べています。
「しかし、どうか使徒の伝承を、後にできた人間的な伝承と混同しないでください。『人間的な伝承』というのは、ローマ・カトリック教会や、ギリシャ正教会が取り込んだ聖伝(holy tradition; 経外伝説)のことを指しています。これらの教会の伝承は、コンスタンティヌス時代以降に生じたものであり、初代キリスト教徒の知るところではありませんでした。、、しかし、こういった信条によって、使徒時代のキリスト教の教えは、不純物を含んだものになってしまいました。この不純化をあらわす最上例を挙げるなら、それは、紀元431年のエペソ公会議での法令でしょう。この公会議で、次のようなことがーーつまり、誰であれ、マリアを〈神の母〉(ギリシャ語でTheotokos)と告白しない者はのろわれよ、と宣言されるに至りました。〈神の母〉という称号を提案した神学者たちは、「この用語は、マリアを神格化するものではない」と主張していました。しかし、一般の人の目からしたら、これは誰がみても間違いなく、マリアの神格化でした。現に今、世界のある国々においては、御父よりもマリアに祈りを捧げる人がもっと多いのです。」*5*6*重要追記*7
さらに著者は、正教会がこの2000年に渡り、数々の殉教者を生み出してきたという点を強調し(それは実際正しいのですが)、しかしそれと同時に、正教会が悪魔の手先となり、キリストのしもべたちを迫害してきたというもう一つの側面には全く触れていません。*8
それは、プロテスタント教会が、迫害の歴史・殉教の歴史と共に、弁解不可能なほど明確なる加害の歴史をも持っているのと事情は同じです*9。しかし、大文字の Churchは絶対不可侵にして完全なる教会のはずですから、そのような大文字のChurchであり「神の国」の中には恥辱の歴史は入ってこれないし、また入ってきてはならないのです。
と、少々厳しい書評を書いてきましたが、本書にはすばらしい点も多くあります。その一つが著者の「礼拝に対する情熱」です。実に本書の大部分は、神を礼拝することについての正教会の姿勢および著者の証しが中心となっています。私がとりわけ感動したのは、次の部分です。
「礼拝というのは、礼拝する対象を映し出すものでなければならないということです、、ですから、不変であられる神を対象とする礼拝は、それ自体で、本質的な不変性を帯びていなければなりません。(礼拝者を楽しませようとの企図でこしらえられた)ランダムな礼拝行為を通して、同一なるこの御方に触れようとするのは、譬えていうなら、自分自身は回転式コンベアーの上に立ちつつ、堅い土地の上に不動に立っている誰かを抱擁しようとするのに等しい行為だといえましょう。」
確かに、典礼(礼拝)における正教会の不変性・恒久性という窓から、私たちは永遠なる世界、不変にして永遠なる神を仰ぎ見ることができます。そして、残念ながら、この点において、プロテスタント教会の大勢は、この世の余興物を礼拝に取り入れるという世俗主義・刹那主義により、神の不変性・恒久性に覆いをかけてしまっているように思われます。著者は続けてこのように書いています。
「私たち現代のクリスチャンは、変わることのない不変なる神が、ご自身に近づく方法として私たちのためにお定めになった礼拝のあり方を勝手に変えてしまっています、、現代の雑多にして、非伝統的なコンテンポラリー・プロテスタントの様式は、神礼拝において、彼らクリスチャンたちを互いに分裂させています。」*10
プロテスタント礼拝の世俗化およびエンターテイメント化に対するこういった外部批判を真摯に受け止めるなら、私たちは宗教改革の土台の一つである、「礼拝における規制原理(RP)」を再訪し、このベーシックに立ち返ることが今後ますます大切になっていくのではないかと思います。*11
彼は「越境」しなければならなかったのか?
こうして福音主義教会内の分裂と混乱と礼拝における浅薄さに絶望した著者は、プロテスタンティズムからオーソドックスへと三番目の「越境」をしました。セブンスデー・アドベンティスト⇒根本主義⇒カリスマ派⇒正教会と、彼は旅を続けています。
「国境」地帯には、興味深い人間たちが数多く生息しています。そして時に私たちは、リスクを冒してでも「越境」しようとする旅人を目にすることがあります。あるいは「越境」しようとする彼に背後から、「越境しちゃ絶対あかんぞ!」と警告する朋友たちを目にすることもあります。
「越境する/越境しない」という行為の選択により、こちら側とむこう側の「問題の所在」が共々明らかにされます。そして「越境する/越境しない」という行為をするに当たり、私たちは自分の信仰の土台が本当に真理の上に立っているのか、それとも〔相手の糾弾するように〕虚偽の上に立っているのか自らに厳しく問いかけます。枝葉末節なものが削ぎ落され、本質的な議論だけが浮き彫りにされるようになります。
さて、これが著者の旅の最終地点なのでしょうか。それとも、彼には次なる「越境」が待っているのでしょうか。そして私やみなさんは、現在、「どこ」にいるのでしょうか?
ーーーーーーー
2020年1月 追記
探求の旅を続けた結果、2018年中盤に私はついにプロテスタンティズムに別れを告げ、東方典礼カトリックに「越境」しました。そしてそこで私は真剣なる求道生活を送りました。その後、さらに「越境」し、2019年12月、私自身もまた著者のギャラティン師と同様、最終的に東方正教に改宗しました。
*1:関連記事
*2:2018年4月追記:しかし、この問題は当初私が考えていたよりもずっと複雑であり、「聖書のみ」の教理への批判の中にも本質を突く鋭いものが多くあることに気づかされました。私の考えは甘かったようです。
2018年5月追記
*3:2018年7月3日追記「聖書のみ」の教理に対するさらなる探求を続けた結果、私ももしかしたら著者マシュー氏と同じような結論に導かれつつあるのかもしれません。詳しくは下の記事をご参照ください。
2018年8月20日追記
2018年9月7日追記*ついに「聖書のみ」撤回。
*4:
*5:デイビッド・ベルソー『世界中をひっくり返した神の国』p96、120。
*6:〔管理人注〕ただし、「聖母マリアや聖人たちに対するvenerationとworshipは違う」と著者マシュー氏が述べているということを付け加えておきます。また、正教会は、カトリック教会の正統教義である(聖母マリアの)無原罪懐胎説、(聖餐における)化体説、教皇無謬説などをいずれも拒絶しているということが本書の中で明示されています。
*7:2019年4月27日
*8:参照:E・H・ブロードベント著『信徒の諸教会ーー初代教会からの歩み』伝道出版社、1989年。それから、Peter Hoover with Serguei V. Petrov, The Russians' Secret: What Christians Today Would Survive Persecution?

*9:
*10:
*11:「礼拝における規制原理」に関し、重要追記があります。
関連資料:聖画やイコンについて。
ニカイア公会議以前の初代教会は一貫して聖画やイコン使用を認めていなかったという事を源泉資料から論証するVTR(by デイビッド・ベルソー師、保守メノナイト教会)
それに対する正教会指導者側からの反論VTR(by ガブリエル・T・ライトナー師、東方正教会)