自分は、、この世界、そして他者とどのようにつながっているのだろう。。(出典)
目次
Jens Zimmermann, Hermeneutics: A Very Short Introduction, Oxford Academic (拙訳)

Jens Zimmermann, Trinity Western University, Canada Research Professor, Humanities
智慧から認識論へ
解釈の衝突
14世紀以降、徐々に進行していった人間精神と世界との間の紐帯断絶は、知に関する古代見解を根本から変質させました。
多くの社会的・政治的諸要因がこの断絶の一因となっていますが、その中でも最も重大なものは、いわゆる「解釈の衝突」と呼ばれている問題です。例えば、科学と宗教のことを考えてみてください。
それ以前には、科学と宗教というのは ‟二つの書 'two books'”という解釈的枠組みを通し互いに調和し合っていました。「神が自然に関する書の筆者であると同時に、聖書の筆者でもある」とする見解はつまり、科学はけっして宗教の敵ではあり得ないという事を意味していました。
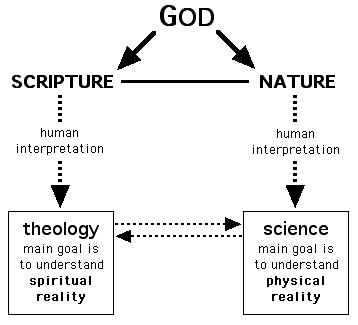
Two Books of God - Bible & Nature (interpreted in Theology & Science)
しかし、コペルニクスが地動説を唱えた際、彼は中世キリスト教会によって聖書的だと判断されていたアリストテレスの天動説による宇宙解釈と断交しました。
さらに支配的キリスト教の各宗派の間の敵意や戦争によっても問いが出されました。ーー真理に関し一体だれの(どちらの)解釈が正しいのだろうかと。人はいかにして真の知識のための確固たる土台を得ることができるのでしょうか。。
基礎づけ主義の誕生
確実なる真理に対するこういった不安はやがて基礎づけ主義(foundationalism)の勃興をもたらしました。基礎づけ主義ーーつまり、知識のための揺るぎない土台を見い出そうとする試みです。こうして、疑う余地のなき、確実なる真理の基盤の上に、人はレゴ式に知識をどんどん積み重ねていくことができるのだとされました。

教化から証明へ
確実性に関するこういった懸念と共に、知に関する対話は「智慧への配慮」から「認識論への没頭ーー正しい知に関する諸理論への没頭」へと変わっていきました。
古代人が、「いかにして知が有徳なる生活を可能にするのか?」と問うていたのに対し、現代人は「なにかが真であるということを人はいかにして知ることができるのか」という認識論的問いに、よりフォーカスを置くようになっていきました。つまり強調が教化(edification)から証明(verification)へとシフトしていったのです。
精神と世界の分離
ルネ・デカルト

フランスの数学者であり哲学者であるルネ・デカルト(1596-1650)は、知に対するこういった現代的態度を示しています。
確実なる知識を得るべく、デカルトは、古代世界がそれまで知における「信憑性のあるリソース元」だと考えてきたものすべてを疑いました。信憑性のあるリソース元とはつまり、伝統によって継承されてきた諸真理、宗教的ないしは世俗的諸権威、身体、感情、感覚です。
デカルトが言っているように真の知というのは「諸感覚ーーそして同時にあらゆる先入観ーーから退くことのできる能力および願望を持つ」者たちに属するものです。こうして残るのは世界から分離され、確実である事象のみを意識するところの精神です。ーーつまり思考するという行為そのものです。
合理主義
そしてこの確実性を信憑性のある唯一の出発点として、デカルトは人間理性を、ーー一つの確実な思想から次の確実な思想につなぐーー知識の確実なる体系の建造物であるとしました。これが合理主義です。理性的精神が真実性(verities)というお城を建設するのですが、このお城は概念的れんがによって積み立てられており、人生やその他の精神とはつながりを絶たれています。
伝統からの理性の独立
独立した、批判的思考への呼びかけ、及び、理性のみが真理を決定することができるとする彼の楽観主義にはそれなりに深く感嘆すべきなにかはあると思います。
デカルト没後約100年した後、ドイツの哲学者イマヌエル・カント(1724-1804)が「啓蒙主義」と呼ばれる文化時期に関し、同様の所感を表明しています。カントにとって、知的成熟性というのは、伝統からの理性の独立を意味していました。
しかしながら、それと同時に、デカルトの基礎づけ主義は、哲学に深刻なる問題を残していくことになります。デカルトは合理的諸真理の確実性を手に入れましたが、それは「精神を世界から分離させる」という代価を伴うものでした。
こうして私たちは、「自分の内的諸信条(信仰)が果たして本当に‟彼方にある”リアリティーに対し真であるかどうかを私はいかにして知ることができるのか?」という証明の問題を抱え込むことになりました。
影響その①
精神と世界の間の断絶は、その後の解釈学に二つの重要な影響を及ぼしました。まず第一は、「客観的知識は何ぞや」という問いに関する再定義です。
デカルト以後、客観的知識とは、偏見なく、価値判断に基づかない(unbiased, value-free)事実だとみなされるようになりました。
知に関する中世の諸理論の中で、「客観的知識」という語がはじめて使われた際には、ラテン語 objectivusは、ただ単に「精神への、対象の現れ(appearance of an object to the mind)」ということを示していたに過ぎませんでした。
そしてデカルト以後になってはじめて、「客観的に知る」=「確実なる知識を得るべく、われわれ自身の生活の文脈を排除すること」という意味なのだと私たちは考えるようになったのです。こうしてついに人々は、真の知識を得るべくこの要件を満たす唯一の方法は、経験諸科学という科学的方法論を通してである、と考えるようになりました。
ですから、現在私たちが目の当たりにしている、「知識」と「信仰」の分裂、「理性」と「信仰」の分裂、「科学」と「宗教」の分裂は、こういった一連の歴史的発展に由来しているのです。
影響その②
精神と世界の隔絶によってもたらされた第二番目の重要な影響は、「いかにして他者の精神に接近するか」をめぐっての問題です。太古より受け継いできた、テクストを基盤とした解釈文化全体は、「文芸/歴史/法/神学テクストは(それが神的なものであれ人間のものであれ)他者の精神の諸表現を含んでいる」と前提しています。
そのため、リアリティーに関する過去や現在の作者の洞察は、後代の読者たちによって把握され得ます。なぜなら、すべての精神は、意味を含んだ宇宙に参与することにより、時間や文化を超え、互いにつながっていたからです。
深い裂け目が生じるーー二重の不安
しかしながら、精神と世界の分離により、私たち解釈者は、「自分自身の精神」と、「作者の精神」との間を隔てる深い裂け目というものに直面しています。
現代の解釈者はその意味で、二重の不安を経験しています。
1)世界に対する自分の知覚〔の正当性〕を、私はいかにして立証することができるのだろう?
2)他の人が言ったことに対する自分の知覚〔の正当性〕を、私はいかにして立証することができるのだろう?
たといデカルトの基礎づけ主義が論理的に働いていたとしても、彼の確実性は思考世界の中にのみ存在しており、深い裂け目が、内的精神の確実性を、歴史や他者の精神という外的世界から分離させています。
この裂け目に私たちはいかにして橋をかけることができるのでしょうか。いかに克服することができるのでしょうか。現代の解釈学は実質上、この問いに答えようとする一連の試みであるといっても過言ではないでしょう。
ー終わりー
関連記事
「科学&宗教」 VS 「科学主義」について by ロバート・バロン師
デカルトの錯覚 by R・C・スプロール師
