
目次
Vern Poythress, Redeeming Philosophy: A God-Centered Approach to the Big Questions (2014), Part 6 Interacting with Defective Philosophies, p.240-247.

ヴェルン・ポイスレス(ウェストミンスター神学大、新約解釈学)
『純粋理性批判』の冒頭
それでは一例としてイマヌエル・カント(1724-1804)の思想について考えてみることにしましょう。*1
カントは複雑にして捉え難い哲学者ですから、本稿での考察はほんのさわりの部分だけになると思います。カントは『純粋理性批判』の冒頭部分で次のように述べています。
![[カント]の純粋理性批判 1 (光文社古典新訳文庫)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41BgM-yUx8L.jpg)
第一節 純粋な認識と経験的な認識の違いについて
001.経験なしでは何も始まらない
わたしたちのすべての認識は経験とともに始まる。これは疑問の余地のないところだ。
認識能力が対象によって呼び覚まされて活動し始めるのでなければ、そもそも何によって動き始めるというのだろうか。対象はわたしたちの感覚を触発するが*2[対象が感覚に働きかける道は二つあり]、対象みずからが感覚のうちに像を作りだすか*3、人間の知性[=悟性]のもつ能力に働きかけるのである*4。
働きかけられた知性は、対象の像を比較し、これらを結びつけたり分離したりすることによって、感覚的な印象という生の素材から、対象の認識そのものを作りあげるのであり、この活動が経験と呼ばれる。
だからわたしたちのうちの認識において、時間的にみて、経験に先立つものは何もない。すべてが経験とともに始まるのである。
002. 認識は合成されたものである
このようにわたしたちのすべての認識が経験とともに始まるとしても、すべての認識が経験から生まれるわけではない。
というのも経験によって生まれた認識というものですら、一つの合成物であると考えられるからである。
[この合成物を構成しているものは二つあるが、その]一つはわたしたちが[感覚的な]印象によって受けとったものであり、もう一つはわたしたちに固有の認識能力がみずから作りだしたものである(この作用において感覚的な印象は、[認識を作りだすための]たんなるきっかけの役割をはたすだけである)。
ところでわたしたちは、長いあいだの訓練によって、認識が合成物であることに注目し[印象に付加されたものを]巧みに分離することができるようにならなければ、この[付加されたものを、感覚的な印象という]土台となる素材から分離することができないのである。」
(以上『純粋理性批判1 (光文社古典新訳文庫)』(カント, 中山元訳)より抜粋)*5
カントは続けて、私たちの「認識能力」より来る付加物であるものがアプリオリ(先天的)な認識であると説明し次のように言っています。
「ところで、このように経験から独立して生まれる認識を、アプリオリな認識と呼んで、経験的な認識と区別することにしよう。経験的な認識の源泉はアポステリオリである。すなわち経験のうちにその源泉があるのである。」*6
冒頭でのこの議論の中で、カントはすでに、知性よりの寄与(アプリオリ)と、源泉が経験のうちにあるものの寄与(アポステリオリ)との間の区別を確立する方向へと踏み出しています。
カントにとり、この区別は、科学における理性行使のための実際的土台の確立、および理性領域の諸制限の確立するために重要でした。つまり、ここでのカントの議論は、彼の全体系において重要な役割を果たしているのです。
カントにおける一般恩寵
まずカント哲学の内にみられる一般恩寵の要素を考えてみることにしましょう。カントは、認識者の視点から人間の認識に関する全像を見ています。そして人間主体としての私たちがいかにして、自分たちの持っている主観的経験を持つに至るのかを問うています。
彼は、ーージョン・フレームが実存的視点と呼んでいるところのものーーと類似した仕方で考察を進めています。この視点は実際、(神のことを含め)人間が認識しているすべての事象に対しての視点です。
キリスト教世界観の中では、この実存的視点は、規範的(normative)および状況的(situational)視点と調和し連結し合っています。*7
神(規範的視点のフォーカス)と世界(状況的視点のフォーカス)は共に、人間としての私たちが経験し、それらについて認識できることについての視点から見ることができます。実際、こういった視点から神および世界を見ることができるのは洞察力に富んだことです。*8
カントも同様の視点を持っていました。パースペクティブを用いる時、私たちは複数の他のパースペクティブを介し、それまで気づかなかったり見落としていた点に気づかされます。そして新しい洞察を経験します。
実験心理学、実験神経科学、人間の感覚器官の複雑性にかんする実験的検証という20世紀における発展を鑑みる時、カントの観察眼の鋭さはやはり際立っていると思います。

実験神経科学(experimental neurology)
また、人間経験の産出の中で、大量の生理学的・神経学的処理がなされていることを私たちは見い出します。感覚的経験についてのカントの言明および、20世紀の(実験的)探求の営為には、一般恩寵による多くの肯定的洞察が含まれています。
しかし残存する困難点は何かと申しますと、それは前章で述べた視点(perspectives)に関することです。特に、非キリスト者の文脈の中においては、一つの視点が排他的「鍵」として用いられる場合が多いのです。
そうなると、使用者は「万事が、一つの視点によって特定されている諸次元に還元され得る」という印象を人々に与えることになります。
特にカントは、アプリオリの認識と、経験からの認識(アポステリオリ)との間の区別が、世界の根源へと私たちを至らしめる根本的洞察であると考えています。そしてその区別は的確であると彼は捉え、単一的視点(monoperspectivally)で考えています。
しかし、結局、カントはーー少なくとも「純粋理性」によってはーー私たちは神を認識することができないという結論に至りました。
そして、「物自体 “the thing in itself”; Ding an sich」という形式の中にあっては私たちは世界を認識することができないという結論に至りました。カントの解釈によれば、神と世界は、実存的視点という諸次元に還元されているのです。
しかしこの点においてでさえ、そこには一抹の真実が含まれています。確かに、神がご自身を認識しているのと同じ仕方、そして同じ深さで神を認識することは私たちにはできません。また神が認識しているのと同じ深さで私たちは世界を認識することもできません。
ここでカントが言っていることは実に興味深い事です。なぜなら彼は、人間の知識の諸限界に関する純粋なる洞察を打ち込んでいるからです。しかし歪曲も忍び込む可能性があります。
実際、カントの場合において、それは然りです。おそらく「純粋理性」は最終的に自律的理性と化し、己をして偽りの神もしくは偽りの絶対と成さしめるかもしれません。そして、人間の知識統制に関する己の期待に適合できないような「神」であるならどんなものであれ「それは全く知り得ないものだ」と宣言するに至るかもしれません。
しかしそれらは、カント哲学の後期発展形態であり、私たちはちょっと先走りすぎたかもしれません。ここでのポイントは、〔『純粋理性批判』の中で展開されている)全ての議論や結論を細かく考察していくことではなく、カントの哲学的考察の初めの段階における実存的視点の意味解釈が、最終段階に対し大きな影響を及ぼしているという事を指摘することでした。
冒頭部分には一抹の真理が含まれているため、たしかに妥当な響きがあります。しかしすでに出だしの段階で、実存的視点の性質は、ーー秘かにしてーーしかも決定的な仕方で誤解釈されているのかもしれません。
そして、それにより一般読者(そしてカント自身も)それを見抜くことができずにいるのかもしれません。実際、それ以降の諸結論はこの出発点に組み込まれています。
用語の分析
それではカントの冒頭議論を分析するに先立ち、まずは鍵となる用語を見ていくことにしましょう。こういった用語には曖昧さや両義性があるかもしれず、それにより実存的視点に関する歪曲された見解が導入される可能性があります。
そしてこれらの用語は一見したところ、リアリティー(あるいは少なくともリアリティーの認識論的側面)に関する深層構造を私たちに約束しているように見えるかもしれません。しかしそれらは完全に明確ではないため、困難性を抱え持っています。
さて冒頭句ではどのようなキーワードが登場してきているでしょうか?--「知識」「経験」「認識能力」「対象」「わたしたちの感覚」「像、表象(フォアシュテルング)」「人間の知性〔=悟性;フェアシュタント〕」「結びつけたり分離したり」「感覚的な印象という生の素材」「経験と呼ばれている対象の認識」。
こういった表現はどれ一つをとっても明確に定義されていません。全てかなり一般的です。私たちはサリーという名の馬に関する知識や、妻が八百屋で買ってきたリンゴのことを話しているのではなく、高度なレベルにおける一般概念(一般性;generality)のことを話しているのです。
私たちは一般用語である一(いつ)と、(個々の馬やリンゴ等)個別経験である多との関係性をどのようにして知ることができるのでしょうか?
何が「認識」を構成しているのかという事に関し、私たちはそこにある種の緊張ないしは難題を見い出すことだろうと思います。例えば、最初の段落の中で、カントは「経験と呼ばれている対象の認識 “that knowledge of objects which is entitled experience”」(中山元訳:〔感覚的な印象という生の素材から〕対象の認識そのものを作りあげるのであり、この活動が経験と呼ばれる。)と述べています。
そしてここでは「経験」がほとんど認識のシノニムとなっています。しかしこれに先立つ文において、彼は「私たちの感覚を触発する対象」のことを述べ、私たちの知性の活動が「感覚的印象という生(なま)の素材」に働きかけていると言っているのです。
対象に関する認識を作りだすナラティブ
ここには一つのナラティブがあります。認識を構成する「経験」をいかにして私たちが得るに至るかについてのストーリーです。
このストーリーには幾つかの段階があります。まず、それは「私たちの感覚を触発する対象」で始まります。そうです。ここに「対象」があります。そして対象が働きかけます。ーーこれらは結果をもたらす原因であり、「私たちの感覚を触発」します。そして「像〔=表象〕を作りだします。」
「表象/像」とは何か?
さて、この「像(表象;Vorstellung , “representations”)」とは一体何なのでしょうか。
おそらくカントは心的観念に類似したなにかを意味していたのかもしれません。そして対象はなにかを「喚起(“arouse”)」します。「喚起」という因果用語がここに登場しています。
そして喚起させられたものが「私たちの知性〔=悟性〕の活動」です。そしてこの活動は対象の像を「比較し」、これらを「結びつけたり分離したり」します。ここにはさらなる因果的諸行為が見い出されます。
そしてこの文章の終わりの部分において、要約がなされているように思われます。つまり、働きかけられた知性は、「感覚的な印象という生の素材から、対象の認識そのものを作りあげます。」
「働きかける」という出来事の中にさらなる因果的諸行為が見い出されます。働きかけられたものは何かというと、「感覚的な印象という生(なま)の素材」です。
そして、この「働きかけ」が生み出す産物は、生の素材がなにか別のものーーつまり、「経験と呼ばれている対象の認識」ーーに変えられることです。
ここでの明らかな問いは「認識」に関するものです。もしも「認識」というものが、最終段階もしくは、ナラティブの最終的産物に属しているのに過ぎないのであれば、カントは残りの部分全てをいかにして認識しているのでしょうか?
そして(カントによると)私たちはいかにして知り、認識することができるのでしょうか。
とりわけ疑問なのが次の部分です。つまり、「感覚的な印象という生(なま)の素材」が「働きかけられ」、認識へと変えられるそれ以前には、私たちは一体いかにして「感覚的な印象という生の素材」がそもそも何であるのかを認識することができるのでしょうか?
もしもカントが、ーーナラティブがその目的地に到達する前に(⇒つまり、認識への到達)ーーすべての諸段階を認識しているのだとしたら、それはおそらく、私たちもまた、(「働きかけられる」前に存在しているとされている)感覚的経験に関する認識を持っているからだと言えましょう。
例えば、今、目の前にリンゴが一個あるとします。しかし私たちは、なんとか集中することにより、自分が今一個のリンゴを見ているという認識を抑え込み、「いや、私はただ色彩や明るさの斑点を見ているに過ぎないのだ」と捉えることも可能です。
そこから生じる効果は、芸術的な例でいうと、いわゆる「点描画法」(pointillism;絵画などにおいて線ではなく、還元された点の集合や非常に短いタッチで表現する技法)に似ているかもしれません。

点描
しかしリンゴの存在をあえて「無視し去り」、そこにある色彩と空間的配列だけを考えるというのは、かなりの知的集中力と一心不乱さを必要とします。
そしてこういった知的集中力の使用は、「生(なま)の素材」というカントの表現と緊張関係にあるように思われます。
色や明るさの斑点の経験というのは、文字通りの「生の素材」ではなく、むしろ、経験におけるその他すべての次元を意識的に「考えないようにし/無視し去り」、視覚的領域のさまざまな「点(spots)」に属している色や明るさにわき目もふらず集中するという、洗練された知的効果であると言えます。
「あえて考えないようにする/無視し去る」というこういったメソッドは、創造的な新しい方法で「経験」を見ようと人に望ましめる深い個人的動機があってこそ可能です。
同様に、知覚神経や脳の感覚皮質に関する神経学の研究は、かなりの知的耐火性(能力)を必要とします。それはお世辞にもあまり「ナマ」であるとは言えません。
ですから、おそらくカントはこういう方向には進みたくなかったのかもしれません。そして「そういった事を我々は推論(inference)によって認識しているのである」と彼は言うかもしれません。
多数の前提、多数の視点
それではどんな推論がカントのナラティブをもたらしたのでしょうか?それぞれ人は異なるナラティブを持っているのでしょうか。また、彼らの知的能力は、人間生命をその形而上学的骨格に至るまで分析するさまざまに異なる試みを作り出すべく、さまざまに異なる方法で用いられるのでしょうか?
経験論者 vs 観念論者
経験論者たちは、感覚経験における非還元性の部位を欲しています。そして彼らの意味する「経験」とは、私たちが「対象」に「働きかける」以前の経験のことです。彼らにとっての対象とは、「私たちの感覚を触発するもの」というよりはむしろ、後に作られた構築のことを指しています。
一方、観念論者たちは、(思考・知性の中の実体であるところの)知識や観念ないしは思想をスタート地点にしたいと望んでいます。なぜなら、それらを回避することは不可能であると彼らは考えているからです。
彼らの見解によれば、「ナマの素材」について語ることはナンセンスです。なぜなら、それに至るアクセスが私たちには皆無だからです。そのため、彼らは、認識探求についてのカントのナラティブは、理性の限界を超えた、純粋なる推論に過ぎないと考えているかもしれません。
人間の認知を研究している現代の生理学者や神経学者たちはまた彼ら自身のナラティブを持っており、それらは、人間の体の部位機能に関する有益な状況的視点(situational perspectives)です。
しかしそういったナラティブは、その他すべてに対し、形而上学的優位性を持っているのでしょうか?カントのそれはどうしょうか。もしくは、私たちキリスト者は、一つのパースペクティブとして、「神が私に現行の経験を与えてくださっており、主を認識する知識を与えてくださっている」と言うことができるのでしょうか。
「対象」とは何か?
それでは「対象」とは何でしょうか?カントは「経験」を「感覚」経験に制限しようとしています。そうなりますと、こういった経験の一部としての「対象」は、個々の椅子、リンゴ、馬といった感覚的対象でしかあり得ないということになります。
しかし、経験論者にとって、真の「感覚経験」とは、さまざまな場所に存在する色の斑点で構成されており、それゆえ、椅子やリンゴなどの対象は、椅子やリンゴの先行概念の使用を通し、高度に構築されています。
仮に私たちが経験論者の反論を無視し、個々の椅子やリンゴからスタートしたとしても、カントの方法論は依然として還元主義的です。
神の臨在を抑え込み、抑圧しようとしたところで、結局、私たちは神の臨在を経験しています。また私たちは他者に耳を傾け、彼らの著述を読むことを通し、彼らの思想を消化しています。
そうです、私たちは、「感覚」だけに限らず、いわば、人や彼らの思想を「経験している」のです。カントは「感覚」に焦点を置くに当たり、最初の地点で神、言語、そして人々を排除しています。
このようにして、カントはすでに、何が形而上学的に究極であるのかを決定する線路を敷くという方向に踏み出しています。そしてそうするに当たり、彼は議論ではなく、諸前提からその事をしています。
しかしそういった諸前提は、語彙や冒頭ナラティブの中では隠蔽されています。しかしそうするより他にないとも言えます。なぜなら、哲学者たちは言語を使わなければならず、言語の使用は常に諸前提に依拠しているからです。
しかしそれはひどく無垢、明瞭、そして魅力的にみえます。なぜならそれは実存的視点という一つのパースペクティブを活用しているからです。そして同時に、それは歪曲された使用でもあります。なぜなら、それは自身が部分的ではなく、究極のものであると主張しているからです。
脱構築
脱構築は、カントの持っているようなナラティブを脱構築していくことに楽しみを見いだしています。脱構築主義者たちは、個々の単語が滑り回ることがある、という事に気づいています。*9
それに加え、哲学的ナラティブには、ナラティブ構造という観念的お荷物が付随しており、それは〔ストーリーの〕筋の展開において典型的様相を持っています。
例えば、カントのナラティブに内在している筋の相を次のように列挙することができるでしょう。
①願望(観察者の思考。今まだ取得していない知識を得たい);
②筋の動き(因果関係、そしてさらなる因果関係。結び合わせたり分離したりしながらーーはたして我々は目的地に達することができるのだろうか?);
③試験(「~に働きかける);
④決断(「そら、ついにたどり着いたぞ。我々は認識に達したのだ。」)*10
脱構築主義者たちは言語に敏感であり、彼らは、カントやその他の古典的哲学者たちが、数多くの諸前提を持ち込んでいるという事実に気づいています。そして一般恩寵により、この点において、脱構築主義者たちには幾つかの良い洞察が与えられています。
しかしここで明確にしておかなければならないのは、私たちがキリスト者としての見地から言語を省察する際、私たちには異なる諸前提があるということです。
冒頭に続く『純粋理性批判』の中で、カントはさらに論を推し進めています。彼は注意深く、知性によってなされた成果と、対象の働きかけによってなされた成果との間を峻別しようとしています。
それゆえ、知性と、外的対象が、一つのストーリーの中の二人の主人公のようになっています。そしてカントはそれぞれどんな効果が、二人の「登場人物」に及んでいるのかを評価しています。
ウラジミール・プロップの昔話の中に出てくるお姫様の父親像のように*11、カントは、物語のヒーローたちに、それぞれの成果に応じ、報酬を与えようとしています。そして彼のナラティブは従来型(お決まり型)の筋に従っています。
キリスト教世界観
他方、キリスト教世界観では、知性と対象は相関しています。知性は実存的視点に焦点を合わせ、対象は状況的視点に焦点を合わせています。
(原型と区別したところの)模写的同時内在(ectypal coinherence)により、知性か対象か、どちらかを一つの視点として用いることが可能です。しかし私たち人間は、両者それぞれの貢献内容を区別する、完璧なる心的分離を会得することはできません。
なぜなら、主体と客体の間の相関関係に関する奥義の原型(archetype)は、神的元型(divine original)だからです。神はご自身を認識しておられます。御父は御子を認識しておられます。そして御父も御子も共に、同時に主体であり客体であるのです。
*1:Cornelius Van Til, Survey of Christian Epistemology, In Defense of Biblical Christianity 2 (n.p.: den Dulk Christian Foundation, 1969), 106–14;

Vern S. Poythress, Logic: A God-Centered Approach to the Foundation of Western Thought (Wheaton, IL: Crossway, 2013), appendix F1;

John M. Frame, A History of Western Philosophy and Theology: Spiritual Warfare in the Life of the Mind (Phillipsburg, NJ: P&R, forthcoming), title subject to change.

*2:〔中山元注釈〕触発するという語は、「刺激する」とほぼ同じ意味と考えてほしい。
*3:〔中山元注釈〕ここで「像」と訳した語の原語はフォアシュテルングである。これは前に(フォア)置く(シュテレン)、思い描くという意味のフォアシュテレンという動詞から作られた名詞である。
カントの翻訳ではこの語は「表象」と訳されることになっているが、本書ではこの訳語は使わない。表象という日本語はさまざまな意味で使われていて、カントの使った用語とはずいぶんかけ離れていることが多いからだ(東京大学教養学部の表象文化論のことを考えてほしい)。
思い描かれたものとしては、触発してきた対象についての像と、その像についての観念が考えられる。
これはここで言われている二つの道のそれぞれに対応した違いであり、感覚において思い描いたものは像となるだろうし、知性で考えたものは観念となるだろう。
だからこの語は「像」あるいは「観念」と訳すが、必要に応じて〔=表象〕という注をつけておくので、ほかの翻訳では表象と訳されていることを想起してほしい。
またこの語には、思い描くという行為の側面と、思い描かれたものとしての観念や像という側面の、両方の意味があるが、表象と訳してはその違いはわかりにくい。
定訳というものには、そう訳していれば安心であるという思考を停止させる強い働きがあるものだ。あえて定訳を使わないのは、読者にも立ち止まって考えてほしいからだ。
*4:〔中山元注釈〕ここで「知性」と訳した語は、通常は「悟性」と訳される。理解する(フェアシュテーエン)からカントが作りだした名詞フェアシュタントの訳語である。
「理性」は了解する(フェアネーメン)から作られた名詞フェアヌンフトの訳として定着しているので、本書でもこれは理性と訳すが、フェアシュタントに悟性という訳語は使わない。
第一部の超越論的な感性論では、この語は、認識する能力の意味で使われているので、ほぼ一貫して知性と訳す。なおカントはこの語を文脈でさまざまに使い分ける。たんなる認識と判断の能力のことではなく、理性の意味で使うことも多い。その場合には「理性」〔=悟性〕と訳すことにする。
また、感覚する能力であるジンリッヒカイトは、知性に合わせて「感性」という定訳を採用した。日本語の感性という語には、「豊かな感性」という表現に示されるような、感覚能力の卓越さの概念と、理性と対立した衝動や欲望の存在という意味が強く含まれるが、カントはあくまでも認識のための一つの能力と考えているので、注意が必要である。
*5:Immanuel Kant, Immanuel Kant’s Critique of Pure Reason, trans. Norman Kemp Smith, unabridged ed. (New York: St Martin’s, 1965), 41–42 (B1–B2, i.e. pp. 1–2 from Kant’s second edition).
*6:同著., 42–43 (B2).
*7:〔訳者注〕規範的視点、状況的視点の詳細については以下の論文をご参照ください。John M. Frame, A Primer on Perspectivalism
*8:John Frame, Doctrine of the Knowledge of Godを参照。
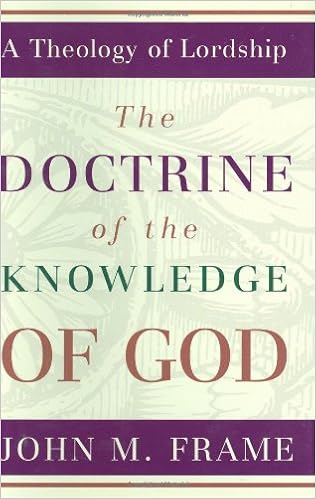
*9:
*10:Vern S. Poythress, In the Beginning Was the Word: Language—A God-Centered Approach (Wheaton, IL: Crossway, 2009), chaps. 24–29.

*11:Vladimir Propp, The Morphology of the Folktale, 2nd ed. (Austin: University of Texas Press, 1968), 79.
〔関連資料〕古典的弁証学の立場からのカント哲学批評 by R・C・スプロール