
目次
- 学生時代に聞いた問いかけ
- 3種類の回答
- カルヴァンは実際に何と言っているか
- 考察ポイント①
- 考察ポイント②
- 虚偽のダイコトミー
- オールタナティブな見解およびその立場の抱える矛盾
- ノックダウン議論なのだろうか
Neal Judisch, Calvin on ‘Self-Authentication’, 2009(拙訳)
学生時代に聞いた問いかけ
もしも聖書だけが私たちの権威であるのなら、私たちはそれを聖書から証明することができてしかるべきではないでしょうか。そして仮にそうできず、(にもかかわらず)とにかくそれを受け入れようとするなら、その時私たちは事実上、聖書を凌駕するある権威を受け入れているのではないでしょうか。
それに「どの書が聖書に属するものであるか」という事を説明するために私たちはそもそもそうする必要があるのではないでしょうか。そしてこれら一連の議論はある意味における「自己指示的矛盾(self-referential incoherence)」に私たちを追いやるのではないでしょうか。
ーーーーー
何年も前、(当時改革派キリスト者であった)私は、上記のような問題のことを耳にしました。それは何か屁理屈のように聞こえました。神経にさわる苛立たしい問いーーまあ、誰かがこれに対して回答してくれているだろうけれども自分の時間とエネルギーを注いでまで確認しようとは思わない種類の問いーーでした。
しかしその後、私はある時点で「いや、それはもしかしたら単なる屁理屈ではないかもしれない」と考えるようになり、これに対する回答はいかなるものであるのかということを一度しっかり自分で調べてみようと思い立ちました。
3種類の回答
そこで分かったこと。それは、この問いに対する回答は、実に次に挙げる3つだけだということです。
①「聖書は自己証明的である(アウトピストス;“Scripture is self-authenticating”)」というカルヴァン式回答。
②一般に普及している「聖書は無謬の文書によって成り立つ誤りを免れない選集(“Scripture is a fallible collection of infallible documents”)」だという回答。
③「ほら、僕らに必要なのは聖書に対する信仰だけなのであって、こういう事に頭を悩ませるには及ばない」という回答。
本稿において私は主として①に焦点を当てようと思います。かつて私は①のこの回答を諳んじ、支持していましたが、現在、これは吟味に耐え得ない理論なのではないかと考えています。
カルヴァンは実際に何と言っているか
以下にカルヴァンの『キリスト教概要』1篇7章を引用しますが、これが「聖書はそれ自身で自らを形成する」という立場のエッセンスです。

「しかし、『聖書は教会によって容認される限りにおいてのみ意義があるのだ』という、はなはだ有害な誤りが極めて広範に浸透している。ーーあたかも神の永遠にして不可侵の真理が人間の決断によるかのように!
というのも彼らは聖霊に対して大いなる侮辱を加え、こう尋ねるのだ。『ある書を崇敬の内に受容し、別の書を排除するよう、いったい誰がわれわれに説得し得るというのか?ーー教会がそういった事柄全般に対し確実なる規範を制定しない限り、誰も説得できないではないか。それゆえに、、どの書物がその正典(canon)のうちに入れられるべきであるかは教会の決定によるのである』と。
、、しかしもしもそうであるならーー、つまり、そういった一切の約束がただ単に人間の判断に依拠しているのだとすれば、永遠の生命についての確かなる保証を求めている哀れな良心はどうなってしまうのであろうか。
、、聖書を裁断する力が教会の役目であるとか、その確実性は教会の同意に依拠していると見せかけるのは無駄ということになる。それゆえ、確かに教会は聖書に対するその認証印を受け、与えるが、そうだからといって、疑わしく論争の的になっている箇所が真正なものと宣告しているわけではない、、
先ほどの質問(『それが教会の制定によるものでない限り、私たちはいかにしてそれが神から来ているということに確信を持つことができるのか?』)に関してであるが、これはあたかも誰かが、こう問うようなものではないだろうか。ーー光と闇、白と黒、甘味と苦さの境はどこからなのかと。実際、聖書はそれ自身の真理を明確なる証拠として完全に顕示しており、それは白色と黒色のものが自らの色に対し為し、甘味と苦さが自らの味に対し為しているのと同様である。
それゆえ、次の点を確定しよう。聖書によって内的に教えられている者は、真に聖書の上に基礎を置き、かつ聖書は実際、アウトピストス(self-authenticated)である。よって、これを証明や論証に従属させることは正しくない。
そしてわれわれが抱くべき確実性は、聖霊の証言によって得られるのである。なぜなら、たとい聖書がそれ自身の威厳によって、自身に対する崇敬の念を勝ち得たとしても、それは御霊を通してわれわれの心に刻印される時にのみ深遠にわれわれの心を動かすからである。
それゆえ、主の御力に照らされ、ーーわれわれ自身によってでなく、またその他いかなる人の裁定によってでもなくーー聖書は神から来ているということをわれわれは信じている。しかしそれは人間の奉仕によりまさしく神の口からわれわれに流れてきているということを、全き確信をもってわれわれは是認しているのである。ゆえにわれわれは(自らの裁定の拠り所となるような)真正さの証明やしるしの類を一切求めていない。」*1
彼の情熱的レトリックはさておき、冒頭の質問に対するカルヴァンの回答は不十分です。
考察ポイント①
まず第一に、彼は明らかに区別すべき二つの主張を融合しています。つまり、「どの書が霊感を受けておりどの書がそうではないかに関する、御霊に導かれた無謬なる認識」というのがあたかも「教会がそれらの書を霊感されたものに仕立てた/教会がそれらの書に、依然は所持していなかった神的権威を授与した」というのとイコールであるかのように語っているということです。
これは混同です。ある書が霊感されているか否かは、ひとえに聖霊がその人間記者を ‟動かし” それを書かかせたか否かにかかっています。
もし神が実際そうしたのなら、その書は霊感され権威があり、それゆえ神のみ旨に従い、正典に入れられるべきです。逆に神がそうしなかったのなら、正典に入れられるべきではありません。
当該の諸書が実際にその霊感された地位を所持しているのかを「いかにしてわれわれは知ることができるのか」というのは、別の問いです。
そして「(正典に入れるべき)正当なる書を認識し正しい決断をなすべく、聖霊が誤りなく教会を導いた」というカトリックの主張があったとしても、それは決して、どの諸書が実際にその地位を所持しているのか〔どの書が、いかなる人間の決断からも離れたところで客観的に真に「永遠にして」「不可侵なる神の真理」を含んでいるのか〕というのがどういうわけか「人間たちの決断」に依拠しているとか、もしくは、「神の御約束」が、「彼らの裁定にかかっており」彼らによって「真正なものだと宣言」されなければならない、ということにはなりません。
考察ポイント②
二番目に、カルヴァンのこの理論は、煎じ詰めると、この点に関し、各個人が教会の活動に置き換わることができるという考えに帰着しています。
つまり、実質的に彼がここで言っているのは、「どの書が霊感されていてどの書が霊感されていないのかについて御霊が公会議における教会に指し示すことができる」と言うのは、聖書に対する名誉棄損である一方、神がそれを、各個人と共に為していると言うことは栄誉にして敬虔なことであるということではないでしょうか。(各個人という一種のミニ教会がそれぞれ単独に立っているイメージを持っていただくと分かりやすいかと思います。)
もちろん、カルヴァン自身は自分のことをそのようには見ていなかったと私は真実に考えています。しかしそれがそうなのはひとえに彼が、次のように前提することで問題を不透明にしていたからだと考えられます。
すなわち、何かが彼にとって明瞭にして明白なのは、御霊が直接的に彼に語り、ありのままの消息を彼に提供しているからであり、それとは反対に、誰かがカルヴァンが見ている通りに物事を見れていない場合、それはその人が〔カルヴァンの如き〕非媒介的な霊的洞察を得ておらず、なにかしら他の解釈的 ‟フィルター” によって盲目にされているからだ、という考え方のことです。
この ‟考え違いをしている” 当人は当人で、もちろん、自分自身の信条内容についてカルヴァンと同様、内的確信を抱いていることでしょう。しかしもしもそうなら、双方共に、結局自らを欺いているのであり、自らの根拠なき心理学的確実性を、神ご自身の証言と取り違えているのです。
これはかなり典型的な啓蒙主義的観念であり、同時代の哲学者、神学者たちの多くが実際この部分に引っかかる傾向を持っていました。そしてこれにより、一見したところ困惑を催させるカルヴァンの主張(どういうわけか彼は自分の ‟論理的思考” や ‟裁定” を脇に置くことで、御霊が彼に事の真相をーー彼自身の知的・認知的活動が何ら関与しないような方法でーー‟内的に” 語ることを可能にさせる、という彼の主張)がよりよく分かってきます。
実際、彼の考えの底辺に横たわっている思想というのは、ーーあなたには真理へのダイレクトにして曇りなきアクセスがあるために、‟仲介者” を排除することができる。一方、あなたに異論を唱え、あなたと意見を違わせている人々に同じ真理が見えていない理由は、①彼らが ‟内的に” 御霊によって教えられていないからか、もしくは②彼らが、自らを盲目にし彷徨わせるところの解釈学的(or 伝統的)グリッドを通して、その真理を間接的にしか見ることができていないからなのです。ーーそして後者の状態に関して言いますと、あなた自身は決してその状態に陥ることなどありえないのです。
このようにして見てきますと、なぜカルヴァンが聖書のことを「自己証明的」性格のものであると言い得たのか説明がつきます。つまり、この文脈においての「自己証明的」が持つ意味は、「私によって、真正なものだと誤りなく認識されたもの;“infallibly recognized as authentic by me.”」ということになります。
カルヴァンが意識的に自らのことを無謬と考えていたのではないことはもちろん言うまでもありません。彼は御霊が無謬だと信じていたのであり、(無謬的にその証言を受け取っていることを確証しつつ)この御霊が無謬的に正典について彼に個人的に証言しているということを信じていたのです。言い換えますと、彼は、聖伝を守る義務をもたない一種の単独教導権(one-man magisterium)だったということが言えると思います。
虚偽のダイコトミー
そうしますと、ここにカトリックとカルヴァン主義それぞれの立場のパラレル関係が明瞭になってくると思います。そしてこのパラレルは、冒頭の例で挙げたような混同によって不明瞭にぼかされています。
カルヴァンはここで虚偽のダイコトミーを提示し、その上に自らの議論を打ち立てています。つまり、もしある人が「霊感された諸書がどれであるかを誤りなく認識することができるよう聖霊が教会を導いた」と言った場合、「それらの諸書は霊感されたものだと教会によって‟宣告”されており、それらが本質的に持っていない真正性(authenticity)を授与された」と言っているのも同然であると受け取られます。
他方、もしもある人が「霊感された諸書がどれであるかを誤りなく認識することができるよう聖霊が個々のクリスチャンを導いた」と言った場合、それは単にテキストが「自己証明的;“self-authenticating”」であると言っているにすぎません。
しかしこういった区別を付ける上での原則的理由はどこにも存在しません。もしも後者の事例において聖書が「自己証明的」であるのなら、それは前者の事例においても等しく「自己証明的」です。しかし仮に前者の事例においてそれがそうでないのなら、後者の場合においてもまた然りです。
ですから、(a)両事例において、聖書は、それ自身の内に神的作者性のしるしを所持しており、御霊がその事実を人間に知らせ、それゆえ、聖書の神的源泉を証言しているか、もしくは、(b)両事例において、私たちは「聖書を裁定する力」が人間の内にあると偽っており、「その確実性は究極的に人間の同意にかかっている」ということを言っているか、そのどちらかということになるでしょう。
そしてここの部分において「個人」を「教会」に置き換えた結果、何か違いが生じるだろうと考え得る理由はゼロです。
カルヴァンの提案を魅力的なものにしているのは、「御言葉の真理および私たちに対するその適用性に関し、聖霊は私たちに証言および保証を提供しており、この真理は『御霊を通してわれわれの心に刻印される時にのみ深遠にわれわれの心を動かすのである』」という彼の正当なる主張に在ります。
しかしながら、それと、「それゆえに、真のクリスチャンであるなら皆、‟白と黒” の違いを見分けるような容易さでもって、何が霊感されており何がそうでないのかを誤りなく決定することができる」と言うのとには開きがあります。
例えば、『箴言』を読んでいる時と同じように『知恵の書』を読んでいる時にも自分の心が燃やされるということを認めたからといって、自分と御霊との交わりになにか欠陥があるとか問題があるとか、そういうことはないと思います。
また、正直に言って、『伝道者の書』よりも『集会の書』を読む時、心満たされる時がより多くあるのですが、それなんかはどうでしょうか。そのような受け取り方をしてしまう自分はなにかおかしいのでしょうか。いや、そんなことはないと思います。
というのも、自分の胸に手を当て、なぜ『エステル記』が正典の中に入れられるべきで、『ユディト記』はそうすべきではないのかということが私にははっきり分かると断言できる人は果しているのでしょうか。

ユディト記(出典)
あるいは、『ユダの手紙』は正典に入れられるべきで、それに対し、例えば、『第一クレメンスの手紙』は除外されるべきだということが私にははっきり分かると断言できる人はいるのでしょうか。
また、自分自身の個人的洞察や御霊との親しさは、聖アウグスティヌスのそれを遥かに凌駕しているため、「第二正典すべてを聖書に含めるべきだ」と主張していたアウグスティヌスの見解などはパスできると自信を持って言える人は果しているのでしょうか。(カルヴァンをはじめとするプロテスタントは第二正典を拒絶しました。)
そして、聖アウグスティヌスのような人々が「真のクリスチャンではなかった」とか、「彼らはあまりに盲目だったので白と黒の区別がつけられなかった」という明らかに荒唐無稽な推論を受け入れることがカルヴァンの仮説を採用することを意味するのだとしたら、私はこのような仮説を受け入れることはできないと思います。
オールタナティブな見解およびその立場の抱える矛盾
それでは仮に、「それぞれ個々のクリスチャンが、どの書が正典でありどの書がどうでないのかを誤りなく知っている」という考え方を拒絶し、さらに、カトリック側の提案も拒絶したとします。
こういった立場は次のようなオールターナティブを提供します。すなわち、「ヒッポおよびカルタゴ等において達した諸決定はもしかしたら(おそらく)正しかったのかもしれないーー少なくとも新約聖書に関してはーー。しかし、これらの諸決定は無謬的になされたわけではなかった。それゆえに、われわれにしろ、彼らにしろ、そこでなされた諸決定が正しかったのかどうかということに関する厳密なる確実性は誰も持っていない。」
そしてこれが多かれ少なかれ、R・C・スプロールを始めとする人々の下した解決案であり、その際に彼らは、聖書は「聖書は無謬の文書によって成り立つ誤りを免れない選集(“Scripture is a fallible collection of infallible documents”)*2」というスローガンを唱えています。

これは深刻に意に満たない解決策です。クリスチャンは聖書の言葉や御約束に関し全き確実性を有していると言いながら、その一方において、その中のどの言葉や御約束が聖書に属するものであるかどうかに関する確実性は否定するというのは、あり得ない主張です。
また、どの書が聖書に属するかに関しカトリックが確実性を持ってそのことを知ることは可能であり、プロテスタントにはそれが不可能であるとするなら、「聖書に関するプロテスタント伝統の見解はカトリックのそれよりも優れている」と主張することもできないということになると思います。
〔R・C・スプロール等の下した〕解決策は、‟論証” や真正性の原則的 ‟しるし” によって正典決定を求めないという点ではカルヴァンのそれに類似していますが、両者はある重要な仕方で異なっています。そしてその相違はロバート・レイモンドの次の言明の中にはっきりと顕れています。
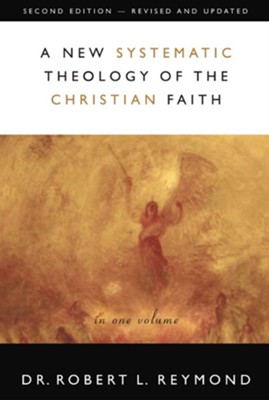
「正典に関するこういった問いに対し、自律的に考えたいと望む人々の精神を完全に満足させるような答えはありません。
なぜなら、クリスチャンの学者が自分は各書の正典性に関する唯一の正しい基準ないしは唯一の正しい基準の目録を所持していると考えていようがいまいがそれには関係なくーー、クリスチャンは、教会が、御霊の摂理的導きの下に、正典の数および ‟目録” を正しく確立したということを信仰によって受け入れなければなりません。なぜなら、神は教会に、新約聖書の各書が収録された特定の目録を提供していたわけではなかったからです。
教会史の最初の4世紀間に関し確実に私たちが知っていることから提示されるのは、神の御霊が摂理的に27の文書を採用するよう、ーー非知覚的にしかし厳然とーーご自身の教会を導いたということです。そして神格が決定されたこれら27の文書〔新約聖書〕は、教会の教理的教えの土台として用いられ、ゆえに、キリスト教史を通し、贖罪史における客観的そして中心的出来事に対する誤りなき証言をしてきました。そして教会の御思いの中で、時の経過と共に、権威づけられ確立された‟使徒的伝統”がまさにこの誤りなき土台および証言として用いられてきました。」*3
一読すれば、レイモンドのこの言明には、偽りの慰めを提供しているプロテスタント的解決策が包含されており、他方、それには、ーープロテスタントが心地よく採用することのできない種類のーー慰めを与える応答が包含されています。
まずレイモンドは、諸問題のことは忘れ、‟自律的に” 考えようとすることを止めようではないかと提案しています。そして、ただ(目録や数は他の誰かによって決定された)聖書の各書に従って考えるべきであると彼は言っています。しかしこれではただ単に問いを後ろに押し込んでいるだけです。
一連の公会義に関与していたクリスチャンたちは当然、‟基準” に関する諸問題を無視できなかったはずですし、ただ単に文書の目録や27という特定の文書数 ‟に従って考える” こともできなかったはずです。というのも、その目録や文書数それ自体がまさに、彼らが決定しなければならない内容だったからです。
他方、レイモンドは、彼らの下した決定は摂理的かつ無謬的に御霊の導きによるものであったということを明確に述べています。
しかしもちろん、ここでの難点はそれがカトリックの解決策であるということです。そして一人のプロテスタントがこのような提案をすることに伴う唯一の問題は、プロテスタンティズムが(私たちにそれが正しいと思わせる理由を与えるような)神学的土台を明白に拒絶している点です。
考えてみてください。「神は、われわれの正典が確立されるまでの時期の間は誤りなく教会公会議を導いた」ということを ‟信仰によって受け入れる” よう読者に提示しながら、今度は一転して、(私たちに今しがた手渡された)その正典を盾に、「神はそういう種類のことはなさらない。なぜなら、正典自体が我々の持ち得る唯一の誤りなき権威であるから」と論じようとしているのです。こういった言い分のどこに一貫性があるのでしょうか。
「そもそも聖書がどのようにして形成されたのか」ということに関する私たちの確信が不可避的にカトリック教義の一部(たといそれが一時的なものであるにせよ)から借用されたものであるとするならば、「聖書の排他的無謬権威」に対する信仰は、いかにして矛盾を逃れることができるのでしょうか。前者は後者とまったく調和していないのですから。
ノックダウン議論なのだろうか
これはいわゆるノックダウン議論(「決定的論拠」)に相当するのでしょうか。私には確かなことは分かりません。神学においても哲学においても、あなたを床に押し倒し、なにがしかの結論を飲み込むよう強いるこういった‟ノックダウン” 議論はすり抜けるのが非常に困難です。(特にそれらが、顕著な諸事実という、周囲から隔絶された中で検証される時は尚更。)しかしこれは少なくとも自分にとって真であるように思われます。
私たちが(改革派の人々の多くが同情的な方法論の一つである)‟前提主義的スタイル” のアプローチを採るとします。そして「全体として見た時に、プロテスタントとカトリックの見解そのどちらが、最も内的に矛盾なく一貫性があり、どちらが自らの弱みにより、自己崩壊しやすいと思うか?」と訊いてみたとします。
そうしますとやはり、全般的にみて、カトリックのスタンス(聖書と伝統)にはこれといって決定的な問題がないのに対し、プロテスタントのアプローチは、治癒不可能な種類の内的矛盾を抱えていることが明らかになってくるのではないかと思われます。
一方において私たちはこう聞かされます。「聖書が唯一の権威なのだから、それが何と言っているかを合法的に‟超える”ことはできない。」しかし、どのテキストが聖書に属するものであるかを規定するためにも、私たちは聖書が何と言っているかを‟超える”ことを余儀なくされます。(ですが、私たちは本来それを超えてはならない、のです。)
そしてとにもかくにもそれらの聖書各書に行き着いたのなら、今度は、「いかなるものであれ、それが聖書的に明示されていない限りはそれを受け入れてはならない」という命題を堅持することが私たちに求められています。(ですが、この命題はそれ自体、聖書的に明示され得ないものです。)そのため私たちは再度、それを規定するべく聖書を‟超える”ことを余儀なくされます。(ですが、私たちは本来それをやってはいけないとされています。)
もちろん、こういったものは、クリスチャンが正当に誇ることのできる神学的伝統の不可欠な一部分ではあるでしょう。しかし伝統の中の誇りと、その伝統に対する聖書的支持は別物です。そしてこれがまさに当該伝統〔=プロテスタント伝統〕が最も必要としていることではないでしょうか。
プロテスタント伝統が、「聖書こそがわれわれに真理を与える。聖書こそがわれわれに真理全体を与え、真理のみを与える」と主張していることは全く正しいのですが、ただそこに、聖書自身が教会を真理の「柱また土台」(1テモテ3:15)と捉えているという重要な事実のための余地が作られる必要があるのではないかと思います。
ー終わりー
*1:John Calvin, Institutes of the Christian Religion, I.vii.1, 2, 5, John T. McNeill, ed., trans. Ford Lewis Battles, Philadelphia: Westminster Press, pp. 75-76, 80.引用は訳者による個人訳。
*2:R.C. Sproul, Essential Truths of the Christian Faith, Wheaton, IL: Tyndale House (1992), p. 22.
*3:Robert Reymond, A New Systematic Theology of the Christian Faith, Thomas Nelson (1998), p. 67.