
Vern Sheridan Poythress, Understanding Dispensationalists,
Westminster Theological Seminary, PA, 1986(インターネットにて公開)
- 著者紹介
- はじめに
- 用語定義・聖書の歴史的形態・ジョン・N・ダービーについて
- スコフィールドのディスペンセーション主義の特徴
- ディスペンセーション主義のヴァリエーション
- 契約主義神学の中でのいくつかの進展
- 代表的かしら性(REPRESENTATIVE HEADSHIP)
- 千年王国と万物の成就を巡っての意見の一致と相違について
- 単純な反論ではほぼ不可能
- いろいろな社会的要因
- ディスペンセーション主義の朋友との対話のために
- 患難期前携挙説にとっての問題聖句 1コリント15:51-53
- 「字義的“LITERAL”」解釈とは何でしょうか?
- 旧約聖書のイスラエルにおける解釈学的見地
- 予型(よけい)について
- ヘブル人への手紙12:22-24
- キリストにあるイスラエルの成就
- 追記―1993年
- 文献目録(BIBLIOGRAPHY)
著者紹介
ヴェルン・ポイスレス氏は1946年、カリフォルニア州マデラで生まれました。ヴェルンは父ランサム、母カローラ、そして兄ケネスと共に5才まで農場で育ち、9才の時に公にイエス・キリストに対する信仰を告白し洗礼を受けました。その後、氏は、カリフォルニア工科大学で数学の学士号を取得し(1966)、ハーバード大学で数学博士号を取得しました(1970)。そしてカリフォルニア州立大学で数学の教鞭を取った後、ウェストミンスター神学大に入学し、神学修士号(1974年)、および弁証学修士号(1974年)を取得しました。その後、1977年、ケンブリッジ大学で新約聖書学の文学修士号、81年に、南アフリカのステレンボッフ大学で新約聖書学の博士号を取得しました。
1976年以降、氏は、ウェストミンスター神学大で新約聖書学を教えています。ヴェルン氏の関心分野はジェンダー包括語訳問題、数学、論理、科学、社会学、聖書解釈、キリスト教認識論、哲学全般など広範囲に及んでいます。また、1971-72年にはノルマン・オクラホマにて言語学および聖書翻訳学を学び、74年、75年、77年には、Summer Institute of Linguisticsで言語学を教えました。ヴェルン氏は、1983年にダイアンさんと結婚し、二人の間にはランサムとジャスティンという二人の息子がいます。また彼はサイエンス・フィクションやバレーボール、コンピューターにも関心を持っています。
謝辞
本論文をわが妻ダイアンに捧げます。そして執筆をするに当たり私を励ましサポートし続けてくれた彼女に感謝を捧げます。ウェストミンスター神学大学は、1983年秋学期に、私に研究のための長期有給休暇を提供してくれました。また私は、ブルース・ウォルケ博士およびウェストミンスター神学大の学生の皆さんから、ディスペンセーション主義に関する背景や懸念について建設的な助言をいただきました。またダラス神学校で研究する間、私は当校においてディスペンセーション主義者の方々から多くの建設的な提案をいただき、またダラス神学校の教授陣のみなさんから手厚いもてなしを受けました。そのことにも感謝しております。さらに今日、多くのディスペンセーション主義者および契約神学者双方が、過去に抱いていた偏見を一旦脇に置き、自分とは違う陣営にも存在する幾つかの良い洞察を進んで認めようとしていることを私は尊く思い、かつ感謝しています。
はじめに
これまでディスペンセーション主義の正誤を明かそうと多くの著述がなされてきました。そういった弁証・反証の著作には各々それなりの存在意義があります。文献目録はそういったもののサンプルでもあります。しかし本書において、私はそれとは違ったアプローチを取ろうと思っており、双方の立場の方々にとって有益な対話および私たちの理解を深めることができるような、そのような方法を探索したいと思っています。
ディスペンセーション神学側の「硬派(忠実派)」と、契約主義神学側の「硬派(忠実派)」の間であってさえも、原則として対話は可能だと私は信じています。現在に至るまで、双方の「硬派(忠実派)」の代表者のみなさんは、対岸の陣営にいる人々のことを「目の開かれていない人とみなしたい」――そのような誘惑に駆られてきました。相手側の見解はあまりに馬鹿げて見えるので、ついつい彼らの見解をヤジるようなことを言ったり、あるいは怒りを感じたり、反対の陣営にいる人々と話すことさえ止めてしまうこともままあります。
しかし、親愛なる読者の方々、もしもあなたが今、相手の立場を馬鹿げているとお感じになっているのなら、その立場内にいる人々もまた同じように、あなたの立場のことを馬鹿げていると思っているとお考えになって間違いありません。本書では、こういった衝突に一条の光を当てることを望みます。
もちろん、ディスペンセーション主義と契約神学との論争の中において、皆が正しいことはあり得ないでしょう。一つの立場が正しく、もう一つの立場は間違っているのかもしれません。あるいは、一つの立場が大半において正しいけれども、もう一つの立場の持ついくつかの価値ある点からも何か有益なことを学ぶことができるかもしれません。ですから、大切な何かを見逃してしまってはいないか確かめる上でも、私たちは一つ以上の見解に対し、これらに真剣に耳を傾けようとする姿勢が大切だと思います。
私たちの探求の結果、ある陣営にいる人々が基本的に誤っているという結論に導かれたと仮定してみてください。しかしそうではあっても、彼らの神学のすべての側面や懸念が間違っているということにはなりませんし、その神学に関わっている人々から何かを学ぶことはできないなどということもありません。人間というのは、ただ単にある神学的「立場」を代表する人として以上の価値があります。ですからここには単に私たちの立場を決める以上のことがかかっているのです。私たちはまた、自分たちとは意見を異にする人々といかにして最善なるコミュニケーションをとり、そして私たちのできる限りにおいて純粋に、彼らの心に寄り添うよう努めるべきだと思います。
古典的な語義において、私はディスペンセーション主義者ではありません。しかしまさにそうであるからこそ、私はあえて時間を費やして詳細にディスペンセーション主義を考察し、この立場を採る方々が重要だと考えていることを理解するよう努めることが望ましいと思ったのです。本書ではディスペンセーション主義の競合相手である契約主義神学については同じだけの時間は費やしません。そうするためには、もう一冊別の著書を書く必要があるでしょう。しかし本書においても契約神学内でのいくつかの発展について少し触れてみたいと思っています。それによって、二つの競合する立場の間の相互理解において、関係改善および双方の成長の機会が与えられたら幸いです。
一言でいいますと、私たちは単に自分の立場を決めるだけではなく、他者を理解するよう努めたいと願っているのです。しかしそれと同時に、私たちは真理に対する懸念を決してないがしろにすることはできません。ディスペンセーション主義および契約主義神学双方によって提起された問いはいずれも重要なものです。聖書の教えが本当には何を言っているのかについて私たちは皆それぞれが決定を下さなければなりません。それゆえに、人々は往々にして激しい反論文を書いたり、時には腹を立てたりもします。
こういった論争のただ中にすぐに飛び込んでいくのも興味湧くことでしょう。しかし読者のみなさんの中には一連の神学の背景についてそれほど詳しくない方々がおられるのではないかと察しています。それゆえに私はまず、第2章ー3章で、ディスペンセーション主義の過去および現在の諸形態についてまとめてみたいと思います。また最近、修正ディスペンセーション主義に歩み寄ろうと、契約主義神学者の方からもなされているいくつかの動きについて第4章で取り扱おうと思います。こういった一連のことにすでに詳しい方は、本書の第7章から読み始めるのがよいかと思われます。
契約神学もディスペンセーション主義も今日それぞれ、立場内にスペクトル(幅)がありますので、私が言うすべてのことが皆に当てはまることはないでしょう。多くの契約神学者や修正ディスペンセーション主義者たちはすでに第11章ー13章で取り扱っている内容の多くに順応していますが、それでもこれらの章から何かしら得るものはあるかもしれません。
それではまず、ディスペンセーション主義の歴史的起源および現在の諸形態についてご一緒にみていくことにしましょう。ディスペンセーション主義者の方々はもちろんこれに関心を持っているはずですが、非ディスペンセーション主義者の方々も同様に関心を持ってしかるべきだと思います。非ディスペンセーション主義者であるあなたに対し私は一つお願いがあります。どうか相手をいたわる気持ちを持ち、彼らのことを理解しようと努めてみてください。同意せよと言っているのではありません。ただ理解しようと努めていただきたいのです。ここには聖書に対する統合されたある一つのアプローチがあり、このアプローチは、「内側から」同情心を持って見る時、たしかに「理に適っている」のです。そしてそれはちょうど、あなた自身のアプローチが、「内側から」同情心を持って見た時に「理に適っている」のと同じなのです。
用語定義・聖書の歴史的形態・ジョン・N・ダービーについて
「ディスペンセーション主義者」という用語について(THE TERM “DISPENSATIONALIST”)
「ディスペンセーション主義者(Dispensationalist)」とはどういう意味なのでしょうか。この語は、ディスペンセーション主義者たち自身によって一つ以上の用いられ方をしています。
そのため、その使用の多様性が少々混乱を生じさせています。ですから、分かりやすさのために、新しく、しかも完全にニュートラルな称号をご紹介したいと思います。ーーディスペンセーション主義神学者(D-theologians)です。ディスペンセーション主義神学者という時、私が意味しているのは、一般的な福音主義神学に加え、J・N・ダービーおよびC・I・スコーフィールドの特徴的な預言的体系を奉じておられる方々のことです。
代表的なディスペンセーション神学者として挙げられるのは、ルイス・シュペリー・シェイファー(Lewis Sperry Chafer)、アルノ・C・ゲベレイン(Arno C. Gaebelein)、チャールズ・C・ライリー(Charles C. Ryrie)、チャールズ・L・フェインバーグ(Charles L. Feinberg)、J・ドワイト・ペンテコステ(J. Dwight Pentecost)、ジョン・F・ウォールヴード(John F. Walvoord)などです。こういった方々の間にも、所々、重要な神学的見解の違いがありますが、主要な目的においては、上記の方々はおおむね、このグループを代表する基準としての役割を果たしているといって差し支えないと思います。
これらの人々が共通して持っているのは主として、「イスラエル」と「教会」のパラレルかつ別々の役割および定めという特有の見方です。そしてこの見解に沿って、特有な聖書解釈のスタンスが採られ、「イスラエル」のことが言及されている箇所と、「教会」のことが言及されている箇所の間に注意深い区別がなされます。「イスラエル」のことが言及されている箇所はその性格において「地上的」であり、「字義的(“literally”)」に解釈されなければならないとされます。*1
さて、ディスペンセーション主義神学者は、一般に「ディスペンセーショナリスト」と呼ばれていますが、その理由はこれらの人々が、神の人類に対する取り扱いの歴史をいくつかの特徴ある時代に分割しているゆえです。そして、その各時代において、神はご自身の全体的計画の中における特異な局面(段階)を為しておられるとされています。さらに、それぞれの時代は「ディスペンセーション(経綸)」ないしは特定の局面を表象しており、それぞれの経綸の中で神は、独自の方法をもって、世界を統治され、人間の従順/不従順を試しておられるとされます。しかし「ディスペンセーショナリスト」という語は、ディスペンセーション主義神学者のことを総称するのに最も適切な用語とは言えないでしょう。なぜでしょう?
と言いますのも、キリスト教会のすべての教派、そして歴代にわたるすべての教会は、(時にそういった時代区分に対する意識がおぼろになることはありつつも)実質上、この世界の神のご統治における特定の時代ないしは「ディスペンセーション(経綸)」を信じてきたからです。ですから、異なる時代間に対する区分認識は、ディスペンセーション神学者だけに限ったものではありません。しかしながら、ディスペンセーション主義神学者のある人々は、「ディスペンセーショナリスト」という語を時には広義の意味で用い、ある時には狭義の意味で用いておられ、そのことで少々混乱が生じています。
広義の意味においては、それは、世界の神の統治においてそれぞれ特定の時代が存在することを認める人すべてを含みます。それゆえ、フェインバーグによれば(1980年、p69、シェイファーより引用、1951年、p 9)次のようになります。
1)動物犠牲を捧げるよりはむしろキリストの血潮に信頼を置く人は誰であれディスペンセーション主義者である。
2)神が永遠の相続地としてイスラエルに約束された土地に対するいかなる権利も権原(title)も放棄する人は誰であれディスペンセーション主義者である。
3)第7の日ではなく、週のはじめの日を遵守する人は誰であれディスペンセーション主義者である。
これは本当に広義な語使用です。しかし他方、別の箇所において、ディスペンセーション主義神学者の人々は、(私たちが一般にディスペンセーション神学者と呼ぶところの)自陣営にいる人々だけを指し示すべくこの語を今度は狭義に用いています。例えば、シェイファーを引用した直後、彼は次のように続けています。
「その〔シェイファーの〕立場の正当性は、反ディスペンセーション主義者であるハミルトンが、彼の構想の中において、①モーセ以前、②モーセ時代、③新約聖書という三つの経綸を設定していることからも充分に裏付けられます。」
ここでハミルトンは「反ディスペンセーション主義者」と呼ばれていますが、その実、彼はシェイファーの定義する広義な意味における「ディスペンセーション主義者」の基準を満たしています。それゆえ、ここにおける「反ディスペンセーション主義者」というのは、ディスペンセーション主義神学者たちに反論しているという事における、狭義の意味合いで用いられています。術語におけるこのような意味の移り変わりはたしかに私たちの助けにはなりません*2。一つの用語に対して二つの意味を持たせるという事が生み出す弊害は、教会史について議論をする上での、正確さの欠如ないしは、明瞭なコミュニケーションの欠如です。
何人かのディスペンセーション主義神学者は時に、ディスペンセーション神学の新規性を最小限に抑えようと、過去の教会史の中で、各時代に区分がなされていた事実を多く列挙しています。*3その一つとして、これらの人々は、これまでに存在したすべての前千年王国説支持者たちを、彼らの霊的祖先(前任者)とみなしています。すべての前千年王国説支持者は、千年王国がこの時代とも永遠の状態とも区別された時代であるということを認識しています。そして、一般的に言って、彼らは、堕落以前と堕落後の状況の間に、それから旧約聖書と新約聖書の間に、皆に広く受け入れられている区分をも認めています。
それゆえ、すべての前千年王国説支持者は、特定の贖罪的各時代ないしは「ディスペンセーション(経綸)」を信じているわけです。そのため、彼らはディスペンセーション神学者の霊的祖先と捉えられているのです。しかし、経綸についてのこのような考え方を用い、さらに広範囲な捉え方が発生してきます。例えば、アーノルド・D・エフラート(Arnold D. Ehlert)は、ジョナサン・エドワーズ(や、ジョナサンに類似するような人たち多数)を、『ディスペンセーション主義の文献史』(1965)の中に含めています。しかしながら、ジョナサン・エドワーズは後千年王国説支持者であり、しかも、彼はいわゆる「契約」神学者です。

Jonathen Edwards
言ってみれば、彼はディスペンセーション神学のいわば対極側の陣営の住民として分類されるでしょう。しかしジョナサン・エドワーズは、著書『贖罪の歴史』の中で、贖罪的各時代についてのテーマにとりわけ繊細な注意を注いでいます。それで、そこの部分をベースに、ジョナサン・エドワーズやその他多くの人々は、『ディスペンセーション主義の文献史』の中に含められているのです。
ですから、実際には、そのような経綸(贖罪的各時代ないしは神の統治における各時代)に対する信奉は、ディスペンセーション主義神学者の特徴的形態としての特有性とはほとんど無関係ということになります。*4
それではなぜそもそもこういう主題が取り上げられるのでしょうか?それはなぜかと言いますと、ディスペンセーション主義神学者は、特定の経綸の内容や意味――特に教会時代および千年王国期の経綸――についての特有な見解をそこに持っているからです。ですから重要な点は、ディスペンセーション主義神学者たちがそれらの経綸について言っている内容であって、経綸が存在するという事実ではないのです。それゆえ、教会史についてのライリー、フェインバーグ、エフラートの見解は、正しいには正しいのですが、大方において、それらは的を外しているといえます。*5
そしてこれらの人々は、「ディスペンセーション神学は教会史において新奇な教えである」と言っている人々に対してしっかりした回答を与えていません。これに関して、一つ譬えを挙げましょう。仮にあなたがある一群の人々に対し、「あなたがたは罪に関し、新奇な教えを説き広めています」と彼らを非難したとしましょう。そしてもしも彼らがその回答として、「罪に対する解決としてのキリストの復活」という主題に関する過去の教会史の事例を持ち出し、それらと彼らの立場の持つ多くの共通性を指し示したとしたら、あなたはどう思いますか。
なにかそれと似たようなことが実際ここで起こっています。反対者たちは、「イスラエルと教会がパラレルかつ別々の役割と宿命を担っているというディスペンセーション神学のその基本教義が新奇なものである」と批判しています。それなのに、何人かのディスペンセーション主義神学者たちは、「経綸という思想は新奇なものではない」という事実を指摘することでそれに応答しようとしているのです。
私はこういった議論が高次のレベルに進まないことを残念に思います。おお、ディスペンセーション主義神学者であられる私の兄弟たちよ、これまでの長い思想史の中で、イスラエルと教会がパラレルにして且つ別々の役割と宿命を担っていたことを証明する良い弁証をなさってください。ーーもしもそういう証拠が挙げられるなら。
そしてお願いですから、「ディスペンセーショナリスト」という用語を操作することで議論の地盤をはぐらかさないでください。また、仮に歴史的立証が不可能であったとしても、それはそれで、比較的最近発見された真理として、その真理のために立ってください。依然としてあなたは、あなたの信じるその真理が歴代の教会において漠然と意識されていたものであると述べることができますし、それが「単なるイスラエルの直線状の継続ではないという意識である」と述べることもあるいはできるでしょう。
しかし今また、本題に戻りましょう。ここで議論されているのは、ディスペンセーション(経綸)が有るか無いかではないのです。というのも、もちろんそれは有るからです!またここで議論されているのは、経綸がいくつ存在するのかという「数」の問題でもありません。現に、より詳細な区分を導入すべく、各人それぞれが望むままに多くの経綸を設定することができます。それゆえ、厳密に言って、「ディスペンセーショナリズム」というのは、ディスペンセーション主義神学者の特異性(特徴)を呼びならわす呼称としては不正確で混乱を招く用語であると言わざるを得ません。
しかしディスペンセーション主義神学者の特徴を言い表すための用語はやはり必要です。明瞭さを考慮した場合、彼らの特定の神学はおそらく(その最初の提唱者の名にちなんで)「ダービー主義(“Darbyism”)」と呼ぶことがあるいはできるかもしれません。もしくは、イスラエルと教会の別箇の宿命・定め・目的(destinies)というその主要教義の一つにちなんで)「二重天啓(目的地)主義(“dual destinationism”)」、あるいは、イスラエルのための意味と教会のための重要性の間に解釈学的分離を設ける原則にちなんで、「受信者分岐主義(“addressee bifurcationism”)」と呼ぶことができるかもしれません。*6
しかしながら、現在までのところ、私たちは「ディスペンセーション主義」および「ディスペンセーション主義者」という用語を用いざるを得ないようです。とはいえ、これでも全体像は捉えられていません。と言いますのも、多くの現代ディスペンセーション主義者の方々は、上述したようないわゆる「古典的」形態のディスペンセーション神学を大幅に修正しています。*7
これらの人々はイスラエルと教会が二つのパラレルな目的(destinies)を持つ二つの神の民であるとは捉えておらず、「別々の受信者(distinct addressees)」という解釈学的分離も実施していません。しかしながら、それでも依然として、これらの人々はディスペンセーション主義者と呼ばれることを望んでいます。彼らがそう望む理由は、彼らが過去に受けた知的訓練が古典的ディスペンセーション主義であったからというだけでなく、イスラエルが神の目に依然としてユニークな国家的そして民族的グループであるという見解を保持しているからでもあります(ローマ11:28-29)。国家的イスラエルは依然として、千年王国期にアブラハムの土地の約束の成就を享受することが予期されています。
さらに、これらの人々が古典的ディスペンセーション主義の人々と共に信じているのは、この世からの教会の携挙は、マタイ24:21-31および黙示録に記されている大患難に先立つという事です。ですから今日、私たちは、複雑なスペクトルを帯びたさまざまな信仰に直面しています。ラベル付けしたどんな体系もすべてを把握することはできません。しかしながら便宜上、私は「古典的ディスペンセーション主義」という用語を、ディスペンセーション主義神学者たちの神学を表すものとして用いようと思います。
そして「修正ディスペンセーション主義」という語は、単一の神の民を信じつつも、依然としてディスペンセーション主義者と呼ばれることを望んでおられる人々の神学を表す際に用いようと思います。しかし両者間の境界線は曖昧です。座標軸にして、一つの極を「古典的ディスペンセーション主義」、もう一方の極を「非ディスペンセーション主義的前千年王国説主義」とした場合、その中間部分には両者の隙間を埋めるような、多種多様な立場的スペクトルが存在します。
聖書の歴史的形態(THE HISTORICAL FORM OF THE BIBLE)
次に、私たちは、ディスペンセーション主義の方々が答えようとこれまで尽力してきた大きな問いに対し感謝すべきだと思います。私たちは皆、聖書の歴史的形態を考慮しなければなりません。聖書は何世紀という時の経過の内に書かれました。そして聖書の全ての箇所が同じ仕方で私たちに適用されたり、語られたりしている訳ではありません。例えば、現在、私たちはレビ人たちの動物犠牲のシステムをどのように理解したらよいのでしょうか。エルサレムの神殿や旧約の諸王を私たちは自分たちとどのように関連づけて理解することができるのでしょうか。
こういった事は現在にあっては過ぎ去った過去のことです。なぜなら、キリストの死と復活によってある決定的な遷移が行われたからです。これはどのような種類の遷移だったのでしょうか。さらに、(キリストの死と復活ほど劇的ではないかもしれませんが)それでも尚、目覚ましい種類の事が、福音書に記述されている出来事の中ですでに始まっていました。そうです。バプテスマのヨハネが「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから」(マタイ3:2)と宣言したのです。そしてこのヨハネの出現期に危機が到来しました。イスラエルおよび全人類に対しての神の関係のどんな種類の変化が、ここに伴っているのでしょうか。
真剣な聖書の読者であれば誰でも、こういった問題に取り組まざるを得ないでしょう。そしてこういった問題はけっして容易ではありません。なぜなら、ここには「連続性」と「非連続性」という両方の要素が包含されているからです。神は唯一であり、救いに当たってもまた一つの道しか存在しません(連続性)。しかし、キリストの到来は、過去との断絶および、既存の諸形態の途絶・変化をも含んでいます(非連続性)。
倫理的な諸問題もここで持ち上がってきます。もしも聖書の中のある要素が直接的には私たちに関係しないのだとしたら、自分たちの倫理的規範として私たちは何を受け取ればいいのでしょうか。旧約聖書や福音書や使徒行伝の中の掟や行動モデルはどのくらい私たちにとって妥当なものなのでしょうか。どの掟が今日にも適用されるべきもので、どの掟がそうではないのでしょうか。聖書の中の模範をどのくらい私たちは模倣すべきなのでしょうか。もしもあるものがもはや実践しなくてもよいものとされるなら、(それに隣接する)すべてを拒絶することを私たちはどのようにして避けることができるのでしょう。こういった問いは、キリスト教神学が歴史に重きを置かなくなる時にはいつでも、より困難なものとされます。
ディスペンセーション主義的時代区分は、19世紀に初めて勃興しました。この時期、大方の正統派神学――特に組織神学――は、聖書的啓示の歴史的・漸進的性格を十分に取り扱うことをしていませんでした。組織神学は聖書全体がそれぞれ特定の主題について何と言っているかを取り扱います。しかしこの点で、つまり、その統一性の中において全聖書のメッセージを見ていくという過程で、組織神学は、異なる時代や時期に与えられる神の言葉の多様性や力学的性質を軽視してしまうきらいが時としてあります。
ディスペンセーション主義は、ある部分において、そういった各時代間に存在する相違や多様性に取り組もうという試みの一環として勃興したと言っていいと思います。そしてそれは、神の御言葉それ自体の中で衝突もしくは矛盾とも映りかねないような相違性に、一貫性を持ち且つ明瞭な関係性をもたらそうと試みました。
他の論者の方々がすでにディスペンセーション主義の発展経緯についての詳細論文を書いておられますので*8、ここで彼らの論点を繰り返す必要はないと思います。しかしディスペンセーション主義がその草創期より、応答しようとしてきた二つの点についてここで触れたいと思います。
ディスペンセーション主義は、①恵みによる救いの純粋性の是認、そして②キリストの再臨に対する待望の刷新運動として興りました。そしてこの二点は、ディスペンセーション主義の最も顕著な時代区分の最初の提唱者であるジョン・N・ダービーの生涯の内にもパワフルな形で顕れています。ですからダービーは重要です。彼が重要なのは、ディスペンセーション主義の創始者としてだけでなく、今日に至るまでディスペンセーション主義者の持つ強い関心・懸念となっているいくつかの要素を表象する人ともなっているからです。
ジョン・ネルソン・ダービー(1800-82)

John Nelson Darby
ダービーの生涯は、彼自身の個人的生活における純潔性および、共同体としての教会生活における純潔性に対する二重の関心によって特徴づけられています。彼の人生の中である決定的な変化、つまり「解放」が起ったのは、彼が足のけがで療養を余儀なくされていた時期でした。ダービーはその時の事を手紙の中で次のように描写しています。*9
「孤独の中、相反する思いが私の中で増していった。しかし魂の懸命の働きにより、御言葉が私の上に完全なる統治をするようになった。自分は天においてキリストと結ばれているのだという理解に至った時(エペソ2:6)、そしてその結果、神の前における私の場所が主ご自身によって代表されてあるのだという理解に達した時、私はこう結論づけざるを得なかった。すなわち、律法の要求の眼前で、6、7年余りに渡り、自分を疲労困憊させていたこの呪われた「自我」ーーこの「自我」がもはや神との間にあって問題ではなくなったのだということを。」
ダービーはこのようにして、罪びとに対する神の恵み、そして救いの確信および神との平和の土台としてのキリストの御働きの十全性について、以前に増してずっと深く感謝するようになりました。このような経験により人は根本から揺るがされるでしょう。こうしてダービーは、律法からではない、真の聖さ、真の義を得たのです(ピリピ3:9)。
これに深く関連して、教会および公同の純潔性についてのダービーの見解にもまた変化が起こされました。上述の手紙をダービーは次のように続けています。*10
「その後私の中で明確になったのは、神の教会とは、キリストと一つに結ばれている人々だけで構成されているということだった(エペソ2:6)。一方、外面的に『キリスト教国』と見られるものは、実はこの世に過ぎないのであり、『教会』とはみなされ得ないのだ。」
キリストの崇高なご性格およびキリストとの一致に対する彼の評価の裏面として、ダービーはその当時の目に見える教会に対して非常に否定的評価を下すようになりました。しかし彼のその結論には確かにそれなりの正当な理由がありました。ジェームス・グラント*11は、ダービーが生きた当時の教会の、低俗にして霊性に欠ける性格について次のように述べています。
「当時、宗教的な事に関する人々の心はかなり乱れており、英国国教会の中の優れた人々の多くが教会を去り、また去りつつありました。なぜなら、そこには全く霊的生活が欠けており、また不健全な教えが蔓延していたからです。その結果、多くの霊的な人々は、社会の上位層にいた人々よりもより霊的と考えられていた、教会統治の諸教理や原則を受容する傾向にありました。」
ダービーは教会に対する自分の見解を、彼のキリスト論の上に直接的に打ち建てました。そしてそれには大きな魅力がありました。「キリストに結ばれた真の教会こそ天的であり、それは地上的堕落にある既存状態〔の教会〕とはまったく関係がない」と彼は考えました。ダービーは、後にプリマス・ブラザレンと呼ばれるようになった教会刷新運動に加わりました。この運動は、彼と同じく聖めに対する願いを持っていました。こうしてダービーは瞬く間に、この運動の主要な指導者の一人になりました。彼の貢献はキリストに対する熱意から始まったといえます。しかしながら、それはやがて彼自身の考えに服従しない全ての人に対する無差別な拒絶という形を取るようになっていきました。
「神は私たちに言われた。(主がそうなると宣言しておられるように)教会が完全に堕落する時、私たちはこれら全ての堕落状態を拒否し、その中にいる人々を拒否しなければならない。そして御言葉に立ち返らなくてはならない。」*12
そしてここから発してついに、ダービーは、〔プリマス〕ブラザレンだけがキリストの御名の中で集っている信者だと言い始めるに至りました*13。
「堕落した教会の回復は不可能である。なぜなら、このディスペンセーションは崩壊状態にあるからである。*14*15」こうしてダービーに同意しないプリマス・ブラザレンの何人かに対し破門戒規が出されました。
終末論におけるダービーの特有な思想は、キリストとの一致に関する彼の理解、および彼の教会観に起源していると思われます。ダービーは次のように言っています。*16
「私のキリストとの一致という意識は、現在における天的な栄光の分け前を自分に与えるものとなった。一方、この章〔イザヤ32章〕は明らかに対応する地上的分け前を示している。」
①「キリストの天的なご人格」、そして②律法による行ないとは別の「恵みによる救いの現実」というこの二点により、ダービーは、キリストと結ばれている自分自身の状況と、イザヤ32章に描かれているイスラエルの状況との間に、圧倒的な距離感を感じたのでした。
イスラエルと教会は、天と地ほど、そして律法と恵みほど違う。ーーこれは確かにパワフルな訴えです。もちろん、ダービーも現在のディスペンセーション主義者も、自分たちは諸教理を、単なる神学的推論の上ではなく、あくまで聖書の上に打ち建てようとしているということを強調しています。しかしながら、神学的推論が重要な確証的影響を与えているという事もまた同時に言えます。現在のディスペンセーション主義者は所々でダービーと異なっているかもしれませんが、同じ訴えが今日に至るまでこれらの人々の間に残存しています。不幸なことに、ダービーは、彼が知覚した距離や相違というのが一通り以上の方法で解釈し得るのだということに気づくことができませんでした。
そしてダービーは、主としてそういった相違をーー天と地、そして、二つの領域に住む二種類の民の間に存在する「垂直的で」固定的な区分として解釈しました。彼はこういった相違が主として歴史的なもの、つまり、「水平的なもの」であり、さらに、ーー地上的予型的用語で表現された『御約束のことば』と、最終的なリアリティー(神のご臨在のリアリティー、イエス・キリストの中において人間の元に来る天国の到来)の用語で表現された『成就のことば』との間に存在するものであるかもしれないという可能性について考えてみたことはなかったようです。
ダービーは、聖書の非歴史化された理解、つまり、贖罪的各時代の間に存在する相違にほとんど目を向けようとしない聖書理解に対して反動を起こしました。しかしながら、私の判断では、ダービーは、彼が反動したところの諸問題から完全には自由になれていなかったと思います。彼は依然として御約束から成就へと至る歴史的漸進に関わる諸変化の重要性を十分に考慮することができていませんでした。それゆえ、ダービーは、パラレルな二つの神の民の、パラレルな宿命(destinies)の間に、擁護しがたい「垂直的な」二元論を据えるよう余儀なくされたのです。
しかし、少し先走りし過ぎてしまったようです。ここでぜひとも留意したいのは、ダービーは自分が見た相違ーー実際に聖書の中に存在する相違ーーに対して全く正当な取り扱いをしたいと願っていたことです。また終末論に関するエペソ2:6の重要性、ならびにイスラエルに対する理解についても、そういった部分を正当に取り扱いたいと彼は望んでいたのです。こうしてダービーのエペソ2章(やその他の箇所の)理解から、教会とイスラエルの間の厳密な区別が生じました。
「教会は天的であり、イスラエルは地上的です。*17。」ダービーは言います。
「〔キリストとサタンの間の〕大いなる戦いは、地上的なもののために行なわれる、、、それはユダヤ人の内にあり、もしくは教会のために、、、それは天的な場所にあります。」
ここから解釈、釈義に対する二分法的アプローチが導き出されました。ダービーは言います。*18
「第一に、預言の中で、(彼らの歴史の中における異邦人の挿入句を除いて)ユダヤの教会ないしは国が関与する時、つまり、言及がユダヤ人に対し向けられている時、私たちは平易にして直接的な証をそこに見い出そうとします。なぜなら、地上的な事がらは、ユダヤ人に妥当な分け前だからです。そして、それとは反対に、言及が異邦人に対し向けられている時、つまり、その中に異邦人が関わっている時、私たちはそこに象徴を見い出そうとします。なぜなら地上的な事がらは彼らの分け前ではなく、彼らにとっての啓示システムは象徴的なものでなければならないからです。それゆえ、言及が、存続するからだとしてのユダヤ人教会に対し向けられている時、私は彼らを、神が地上において直接的に取り扱った民として、そこに、平易にして、コモンセンスな、そして字義的言明を見い出します。」
最後にもう一つダービーの引用をしたいと思います。以下の引用から明らかなのは、ダービーの頭の中で、
①(教会の純潔性に対する懸念としての)キリスト論と、それから
② 解釈学的分岐(hermeneutical bifurcation)
という二つの要素が密接につながっていたということです。
「預言は、それ自体、適切に地上に適用され、その目的は天ではない。それは地上において起こるべき事柄についてのものである。そしてこれを理解しないことでこれまで教会は判断を誤ってきたのである。私たちは自分たち自身が、自分の内部に、そういった地上的祝福の成就をすでに持っているとこれまで考えてきた。
しかし実際には私たちは、天的祝福を享受するよう召されているのである。教会の特権は、天的な場所においてその分け前を得ることであり、その後に、地上的人々の上に祝福が注がれるのだ。
教会は、地上的な民が拒絶されている間、なにか完全に隔たったものーー一種の天的なエコノミー(経綸)ーーであり、これらの地上的民は、彼らの罪のために現在捨てられており、国々の間から追放されており、、、こういった国々の間から、神はイエスご自身との天的栄光を共に享受する人々をお選びになるのである。
主は、ユダヤ人によって拒絶され続けているが、主は全き天的なパーソンとなられた。これは特に、使徒パウロの著述の中において見い出される教理である。
もはやユダヤ人のメシアではなく、高く上げられ、栄化されたキリストである。そしてこの至高な真理に対する理解が欠けていることで、教会はこれほどまでに弱体化しているのである。」*19
よって、ダービーの中では、以下の事が互いに密接に結びつけられていることが分かります。
① 律法と恵みの間における鋭利な区分。
②「地上的」な神の民/「天的な」神の民、「イスラエル」/「教会」の間における鋭利な垂直的区分。
③ 預言の「字義的」解釈の法則:預言成就を、地上的レベル(ユダヤ人)と提携させる。
④ その結果として生じる、この成就の時を待望する強い前千年王国説への強調点。
⑤ 既存の教会に対する否定的にして分離派的評価。
前千年王国説に基づく力点・強調点(④)は、ダービーの区分法が、米国で確実な地歩を得る最初の主要な入口になりました。しかし分離派的な強調点である⑤を除く他のすべての強調点もまた、またたく間に、米国ディスペンセーション主義を特徴づけるものになっていきました。その後、分離派的強調点が米国で優勢になるのは、――根本主義が米国の諸教派のメインストリームを統制する希望を失いつつあった――1920-30年になってからです。*20
スコフィールドのディスペンセーション主義の特徴
では、ダービーの後、ディスペンセーション主義の教えには何が起こったのでしょうか。ディスペンセーション主義は、ジョン・ダービーの、米国における数多くの講演活動を通し、また、ダービーやその他のプリマス・ブラザレンの著作類を通して、アメリカにもたらされました。ディスペンセーション主義は、19世紀の後半から20世紀の初頭にかけて行なわれた預言会議の影響で普及しました。
フラー(1957, 92-93)は、ディスペンセーション主義がアメリカに根を下ろした主要因は、「二種類の神の民としての『イスラエル』と『教会』というダービーの概念」を基盤にしてというよりはむしろ、その「終末論的教え」がベースになったと指摘し、次のように言っています。
「アメリカは、『神の二つの民』というダービーの基盤概念よりも、『キリストは今すぐにも再臨されるだろう』という彼の思想の方にむしろより強固に惹きつけられたと考えられます。後千年王国説は、千年王国を希望の主眼としました。それに対して、ダービーは、――『キリストは今すぐにも再臨されるだろう』という彼の力点により、他のどんな出来事とも離れたところで、キリストご自身を、希望の主眼になさしめたのです。ダービーが〔アメリカで〕受容された理由ですが、これは往々に起こる事ですが――ある極端を離脱した人々が、その対極にあるもう一つの極端によって提示されるオールターナティブ(代替)を採用したという事情があると思われます。」
留意していただきたいのは、ここで再び、キリスト論が、ディスペンセーション主義の魅力を形作る深い土台となっていたことです。この運動内において、『スコフィールド引照・注解付き聖書』が特に、米国でのディスペンセーション主義普及にあたって最大の貢献をしました。その広範囲な使用ゆえ、この注解付き聖書は、現在、実質的に「標準」となっています。

『スコフィールド引照・注解付き聖書』
それゆえ、私たちはまず初めに、この中でなされている教えを把握する必要があります。その後、私たちは、そういった教えがどのようにして他のディスペンセーション主義の人々によって修正されていったのか見ていくことができるでしょう。ディスペンセーション主義というのは今や多様性を持つ運動となっていますから、スコフィールドのアプローチの全ての特徴が、全てのディスペンセーション主義者にそのまま当てはまるのかというと、そうではありません。
C・I・スコフィールドの一般教説

C.I.Scofield
サイラス・I・スコフィールド(1843-1921)は、ジョン・ダービーと共有している多くの見解を、ジェームス・ブルックスやブラザレンの著述類から得ました。それでは彼の注解聖書にはスコフィールドのどのような見解が記されているのでしょうか。
まず第一に、スコフィールドの教えと注釈は福音主義的です。それは穏健カルヴァン主義的であり、神の主権に対する高い見方を保持しています。またスコフィールドは、聖徒の永遠堅持および無条件の御約束の存在を肯定しています。さらに、全歴史の上にある神のご計画に対する彼の強調はもちろん、神の主権に対する高い見方とも調和しています。それではどのような要素が、スコフィールドをその他の福音主義者と違わせているのでしょうか。そこには4つの主要な相違点が存在します。
第一番目に、スコフィールドは、聖書を解釈する際に、「字義的」アプローチを採っています。この領域は複雑に入り組んでいますので、第5章でこの事について詳しく取り扱いたいと思います。
第二番目として、スコフィールドは、「イスラエル」と「教会」を、神の二つの民として鋭利に区別しており、二つの民がそれぞれ別の目的と宿命を担っている、そして前者(イスラエル)は地上的で、後者(教会)は天的であると説いています。例えば、『スコフィールド引照・注解付き聖書』は創世記15:18の箇所を次のように注釈しています。
(1)「わたしはあなたを大いなる国民とする。」は、次の三つの方法によって成就する。
(A)自然的子孫。「地のちりのように」(創13:16、ヨハネ8:37)、すなわちヘブル人。
(B)霊的子孫。「さあ、天を見上げなさい、、あなたの子孫はこのようになる」(ヨハネ8:39、ローマ4:16,17、ローマ9:7,8、ガラ3:6、7、29)、すなわち、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、信仰によるすべての人。
(C)イシュマエルを通してもまた成就(創17:18-20)。
ローマ11:1の注釈にはこう書かれてあります。
「クリスチャンは天的なアブラハムの子孫(創15:5,6、ガラ3:29)、そしてアブラハム契約の霊的祝福に与る(創15:18)。しかし国家(nation)としてのイスラエルは常にそれ独自の場を持っており、地上的神の民としてその最大の高揚に今後与ることになる。」
スコフィールドの見解に近い見解を持つルイス・S・シェイファーは、「二つの民のパラレルな宿命」という思想について次のように妥協のない仕方で述べています。

Lewis Sperry Chafer (1871–1952)
「ディスペンセーション主義者は、時代を通し、神は二つ別々の目的を追求しておられると信じている。一つは、地上的人々ならびに地上的諸目的に伴う地上に関する事。もう一つは、天的人々ならびに天的諸目的に伴う天に関する事である。天も地も共に新しくされた後でさえも現在の天地間の区別は存在し、また御言葉が、地上的人々をそのようなものとして永遠の中に指定し、天的な召しの内に宿る天的な人々もまた永遠の中に指定しているという事実に照らし合わせた時、なぜこの信条がこれほどすばらしいものとみなされるべきなのか。これとは対照的に、部分的ディスペンセーション主義者は、おぼろげに幾つかの明らかな区分はしているものの、己の解釈を、『神は一つのことだけをなされている。つまり、善と悪の一般的分離をなさっている』という推測の上に打ち建てており、この制限された理論が生み出すあらゆる混乱があるにも拘らず、地上的な人々は天的な人々の中に融合されると主張しているのである。」
第三番目の特徴点は、世界の歴史を、時代ないしは「ディスペンセーション(経綸)」に分割するという緻密な構想です。スコフィールドは、エペソ1:10の注釈として、このディスペンセーションのことを「地上における人間生活を条件づける秩序立った諸時代」と記しています。
無垢の時代(エデン、創1:28)
良心の時代(洪水の前まで、創3:23)
人間による統治の時代(ノアからバベル、創8:21)
約束の時代(アブラハムからエジプト、創12:1)
律法の時代(モーセからバプテスマのヨハネ、出エ19:8)
恵みの時代(教会時代、ヨハネ1:17)
御国の時代(千年王国期、エペソ1:10)

もちろん、非ディスペンセーション主義である人々もまた上記のような7つの分割期があることを認めるかもしれませんし、それだけでなく、「それぞれの時代における人類に対する神のお取扱いについての顕著な特徴を抽出するに当たってこれらの時代分割は適切である」と言う方もいるかもしれません。第1章で述べましたように、ディスペンセーション(経綸)に対する単なる同意だけでは、ディスペンセーション主義を、他の多くの諸見解から区別するものにはなりません。
スコフィールドの特異性が表面化するのは、各経綸における、神の人間に対するお取扱いについて彼が「具体的に何を信じていたのか」ということを私たちが問う時に明らかになります。この時点において、幾つかの特異性は度合の問題です。スコフィールドは各経綸の間の非連続性をより「シャープに」強調しているかもしれません。しかし最も注目すべき相違点は、「千年王国期」に関連する「教会時代」についてのスコフィールドの見解に在ります。
それによると、教会時代、地上的イスラエルに対する神のプログラムは一旦脇に置かれます。そしてその後、教会が携挙される時に、そのプログラムは再び起動し始めます。教会期は、地上的イスラエルに関しての「挿入句(“parenthesis”)」であり、この挿入句は、預言が沈黙しているところのものです。(なぜなら、預言はあくまで「イスラエルの」将来に関して言及しているからです。)ですからここから見て取れるのは、各経綸が帯びている特異性の「性質・種類」に関するスコフィールドの見解というのは、イスラエルと教会に関する彼の見解の反映であるということです。
第4番目にして最後の特徴点は、患難前携挙に対する信奉です。スコフィールドによると、キリストの再臨は二段階に渡って行われます。最初の段階、つまり「携挙(“rapture”)」において、キリストはこの地上から教会を取り去るために来られます。しかしその際、キリストはすべての人に見える形では現れません。この出来事の後に、七年間の患難期が続きます。そしてこの七年の後、キリストは国々を裁くために目に見える形で現れ、そして、この地は新しくされます。(下の図表2.1をご参照ください。taken from Jensen 1981, 134)

これは、一般に広く受け入れられているディスペンセーション主義の最も有名な側面の一つではありますが、この患難前携挙説自体は、その他の特徴点ほど根本的なものではありません。この説はその他の特徴点から生み出された産物に過ぎません。とは言え、これは重要な産物です。スコフィールドの主張点というのは、教会とイスラエルがそれぞれ別個のパラレルな宿命を担っているということです。「預言はイスラエルに関するものであり、教会に関するものではない。」ですから、旧約預言が再びその成就に向けて始動することが可能になる前に、教会は携挙によって舞台から取り除かれなければならないのです。そうして後、イスラエルは回復され、そしてダニエル9:24-27の完成が可能になります。
もしも教会が取り去られなければ、教会とイスラエルの二つの宿命が混合(mix)してしまう恐れがあります。それゆえに、「パラレルな二つの宿命」というこの理論は実質上、「二段階再臨」を要求するわけです。しかし、二段階再臨は、それ自体においては、「パラレルな二つの宿命」理論を必ずしも必要としているわけではありません。
さらなる考察のための追加資料(ジョージ・エルドン・ラッド『終末論』(第5章 再臨についてのことば)より)
今度は、多くの福音主義の教会において悲劇的論争の主題となってきたひとつの問題を取り扱わなければならない。第1章で論じたように、ディスペンセーション主義は、キリストの再臨は二つ存在する、もっと正確にいえば、キリストの再臨は二段階で起こる、と教える。
ディスペンセーション主義では、神の二つの民――つまりイスラエルと教会――が存在し、そして神は二つの異なった計画――つまりイスラエルに対する計画と教会に対する計画――をもっておられると教えていることを私たちは見てきた。イスラエルに対する計画は地上の神権政治の計画であり、教会の計画は霊的天的な計画である。この主張に符合するのは、キリストの再臨における二つの段階である。
次の章で見るように、神の国とサタンの力の間の闘争は、サタンと教会の間の短期間ではあるが恐るべき闘争において頂点に達し、そこでは悪魔があらゆる人をキリストから離反させようとする、と聖書は教えている。これは、恐るべき殉教の時であり、大患難と呼ばれている(マタイ24:21、黙示録7:14)。キリストは患難期の前に来られ、天においてご自身とともにあるように、まず死んだ聖徒たちをよみがえらせ、次に生きている聖徒たちを携え挙げる(携挙)、とディスペンセーション主義者は主張する。
そのようにして、教会は大患難を免れ、「聖徒たち」に対する迫害はイスラエル、つまり生きているユダヤ人に対して向けられる。患難期の終わりに、キリストは再臨する。このときキリストは教会を伴い(1テサロニケ3:13)、イスラエルを救出し、千年王国に導かれる。
以上のキリストの二つの到来は、それぞれ携挙――教会を携え挙げるためにやって来るとき――と顕現と呼ばれている。携挙は、教会によってのみ知られる秘密の来臨である。顕現は、公の見える来臨であり、そのときキリストは力と栄光をもって来られ、王国を確立される。キリストが患難期の前に再臨し、死んだ聖徒たちをよみがえらせ、生きた聖徒の教会を携挙するという教えは、ディスペンセーション主義者の最も特徴的な教理である。
私たちは、大患難前にキリストが再臨されるとする見解を新約聖書が支持しているかどうかを判断するため、新約聖書で使用されている用語を吟味しなければならない。新約聖書において、再臨を描写するために三つのことばが使用されている。第一に、「到来」「出現」また「臨在(プレゼンス)」を意味する「パルーシア(Strong's Greek: 3952. παρουσία (parousia) -- a presence, a coming)」がある。これは、主の再臨に最も頻繁に使用されている用語であり、教会の携挙に関するものとして使用されている。
15私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。
16 主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、
17 次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。
(1テサロニケ4:15-17)
キリストが秘密のうちに再臨するということを上の箇所の中に見出すことはきわめて困難である。その再臨には、号令と御使いのかしらの声と神のラッパの響きが伴っている。ある人は、号令とラッパの響きは死者を目覚めさせるのに十分な大きな音だろうと言っている。さらに、キリストのパルーシア(到来)は教会を携挙し、死せる義人を携挙するだけでなく、不法の人、つまり反キリストを滅ぼすためにも起こる。「その時になると、不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨(訳注・パルーシアス)の輝きをもって滅ぼしてしまわれます」(Ⅱテサロニケ2:8)。
キリストのパルーシアは、光輝く顕現であるのだから、これは明らかに秘密の再臨であるはずがない。さらに、この箇所はパルーシアを患難期の終わりに位置づけている。死せる聖徒たちの復活、生きている聖徒たちの携挙、そして反キリストに対する審判は、すべて同時に、すなわち患難期の終わりのイエスのパルーシアにおいて起こる。まさに引用した箇所を比較対照することで、おのずとそのような結論がもたらされる。
さらには、イエスがご自身の聖徒すべてを伴ってやって来るのはパルーシアにおいてである。パウロは、神が「私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒とともに再び来られるとき(訳注・パルーシア)」(1テサロニケ3:13)、テサロニケの人々を、聖く、責められるところのない者としてくださいますようにと祈っている。パルーシアにおいて、主は死せる義なる者をよみがえらせ、生ける信仰者を携挙し、反キリストを滅ぼし、すべての聖徒たちを伴って来られる。
パルーシアは栄光に溢れた出来事である。キリストは不法の人を御口の息と「来臨(訳注・パルーシアス)の輝き〔文字どおりには、「エピファニー」あるいは「光を放つこと」〕」(Ⅱテサロニケ2:8)をもって滅ぼす。「彼の来臨(訳注・パルーシアス)の明るさ(訳注・エピファネイア)によって」とする英欽定訳の翻訳は正しい。このエピファニー(訳注・輝き)は、パウロが「大いなる神であり私たちの救い主であるキリスト・イエスの栄光ある現れ(訳注・エピファネイアン)」について語っているゆえ、栄光に溢れた出来事である(テトス2:13)。
私たちは、イエスのことばの中に、だれにも明らかな、栄光に溢れたパルーシアの同じ教えを見出す。「人の子の来るのは、いなずまが東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来る(訳注・パルーシア)のです」(マタイ24:27)。それは、栄光に溢れ、すべての人に明らかな稲妻のひらめく電光のようである。これらの事実に対して、キリストの再臨を二つの部分に分離する人々は通常、こう答える。パルーシアは「臨在(プレゼンス)」を意味し、それゆえ携挙と患難期初期から始まる期間全体に及んでいるのだと。したがって、パルーシアは携挙におけるキリストの来臨、あるいは患難期の終わりにおける顕現かのどちらかを指している、と説明される。
確かに、パルーシアが「臨在」の意味をもつ場合もある。パウロは、ピリピの人たちと一緒にいること(パルーシア)を、離れていること(アパウシア)と対照させている(ピリピ2:12)。コリントの人々はパウロを、「手紙は・・・力強いが、実際に会った場合(訳注・パルーシア)の彼は弱々し」い(Ⅱコリント10:10)ので一貫性がない、と責めている。とはいえ、このことばは常に「臨在」を意味しているとは言えない。たいていの場合、「到着」を意味している。エペソでパウロがコリントからの使節を迎えたとき、彼らのパルーシア、つまり彼らの来訪あるいは到着を歓喜した(1コリント16:17)。
パウロはコリントの事態を案じていたとき、テトスの到着(パルーシア)によって慰められた(Ⅱコリント7:6)。慰めをもたらしたのは、テトスがその場に存在すること(訳注・プレゼンス)ではなく、コリントからの吉報をもたらしたテトスの到着であった。パルーシアを「臨在(プレゼンス)」と解釈すると、それがもっている固有の意味を見失ってしまう。
このことは、「兄弟たち。主が来られる時(訳注・パルーシアス)まで耐え忍びなさい。・・・あなたがたも耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られる(訳注・パルーシア)のが近いからです」(ヤコブ5:7-8)、「キリストの来臨(訳注・パルーシアス)の約束はどこにあるのか」(Ⅱペテロ3:4)で例証されている。
それらの箇所において、「臨在」とする解釈は文脈に適合しない。考えられているのは、主の到来、来臨、出現である。私たちが現在、吟味検討している箇所において必要とされているものは、キリストの臨在ではなく、キリストの到来である。死者がよみがえらされ、生きている者が携挙されるのは、キリストの到来、つまり出現においてである。「臨在」という解釈は、文脈に適合しない。
キリストが聖徒たちを伴うのは、その到来つまり出現においてであって、臨在においてではない。キリストの到来つまり出現は、稲妻のひらめきの電光のようである。キリストのパルーシアは再臨である。それは救いと審判の両方をもたらす。すなわち聖徒の救いと世界の審判である。
主の来臨について使用されている第二のことばは、「顕現」を意味するアポカリュプシス(Strong's Greek: 602. ἀποκάλυψις (apokalupsis) -- an uncovering)である。
患難期前再臨説の立場の人々は、キリストのアポカリュプシスあるいは顕現を、教会の携挙と区別し、キリストが世界に審判をもたらすため栄光のうちに到来する患難期の終わりの出来事として位置づける。もしこの見解が正しいとしたら、キリストのアポカリュプシスは、第一義的にクリスチャンにとって祝福された望みではなくなる。顕現が起こるとき、聖徒たちはすべてに携挙されており、肉体にあってなした行為に応じて報いをキリストの手から受け取っていることになる。
彼らはすでにキリストとのいのちと交わりの全き喜びに入っている。すなわち、キリストのアポカリュプシス(訳注・顕現)は、悪しき者の審判のためであり、教会の救いのためのものではなくなってしまうのである。患難期前再臨説によれば、キリストの秘密裏の再臨における携挙は、祝福された望みであり、好ましい期待の的であるが、顕現はそうではないということになる。けれども、このような教えを聖書に見出すことはできない。私たちは「熱心に私たちの主イエス・キリストの現れ(訳注・アポカリュプシン)を待っています」(1コリント1:7)。
患難期前再臨説によれば、私たちは顕現など待ってはいない。携挙を待っているのである。教会はキリストのアポカリュプシスの時まで苦難に会わなければならない。
「つまり、あなたがたを苦しめる者には、報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなたがたには、私たちとともに、報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。そのことは、主イエスが、炎の中に、力ある御使いたちを従えて天から現われる(訳注・アポカリュプセイ)ときに起こります」(Ⅱテサロニケ1:6-7)とパウロは語っている。
患難期前再臨説によれば、この迫害からの安息は携挙においてすでに実現してしまっており、イエス・キリストの顕現まで待つ必要がない。しかし神のことばによれば、この安息は顕現において受け取られるべきものなのである。近年、そのギリシヤ語の表現は「主イエスが顕現されるとき」ではなく「主イエスの顕現の期間中」を意味している、つまりキリストが顕現する瞬間的な時ではなく、顕現が起こる期間を意味しているのだと主張されている。キリストが顕現されるとき、苦しめられた人たちはすでに安息を楽しんでいるのだと。
しかしながら、これはパウロのことばのきわめて不自然な解釈である。「苦しめられているあなたがたには、私たちとともに、報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。そのことは、主イエスが、・・・現われる(訳注・アポカリュプセイ)ときに起こります。」
「報いを与える」という動詞は、
①あなたがたを苦しめる者には苦しみ、そして
②苦しめられているあなたがたには安息、
という二つの対象を考慮に入れている。苦しみという報いと安息という報いの双方は「主イエスが現れる(訳注・アポカリュプセイ)ときに」起こる。
もし苦しみがキリストの現れるときに与えられるとしたら、同時に安息もキリストが現れるときに与えられるのでなければならない。安息がすでに受け取られ、喜び楽しまれていると解釈すると、用いられている語と矛盾する仮説をこの箇所に押し付けることになってしまうのである。
ペテロは同じ表現を使用している。今私たちはキリストの苦しみを共にする者とされている。「それは、キリストの栄光が現れる(訳注・アポカリュプセイ)ときにも、喜びおどる者となるためです」(1ペテロ4:13)。これは、燃えさかる火の試練がキリストのアポカリュプスにおいて初めて終結することを示唆している。さらに、ペテロは私たちの信仰の真実性が「イエス・キリストの現れ(訳注・アポカリュプセイ)のときに称賛と光栄と栄誉」(1ペテロ1:7)をもたらすと語っている。
患難期前再臨説によれば、この光栄と栄誉はそれよりも前の段階、教会が携挙されるときに経験するものである。しかしこの箇所は、キリストのアポカリュプスの目的のひとつは、信仰の忠実さのゆえに光栄と栄誉をご自身の民にもたらすことであると断言している。
最後にペテロは、私たちが恵みにおいて完全な者とされる望みは、イエス・キリストの顕現のときにもたらされると保証している。もし携挙と顕現がひとつの同じ出来事であるとしたら、それらの箇所の意味は完全なものとなる。しかしながら、もしそれらの祝福が顕現においてではなく、それ以前の携挙において受け取られるものであるとしたら、それらの箇所はわけがわからないものとなってしまう。この二つの出来事をどのように区別できるのかを考えることは困難である。顕現は私たちにとって祝福された望みであり続ける。それゆえ、携挙はキリストの顕現のときに起こらなければならない。顕現以前に携挙が起こるという主張は、聖書のどこにも書かれていない。
キリストの再臨について使用される第三のことばは、エピファネイア(Strong's Greek: 2015. ἐπιφάνεια (epiphaneia) -- appearance)である。
これは「輝き」を意味し、したがって患難期前再臨説の体系によれば、患難期が開始されるときの教会の携挙やキリストの秘密の来臨を指しているのではなく、患難期の終わりにおける、世界に審判をもたらすための、聖徒を伴ったキリストの顕現を指しているのである。キリストは「来臨の輝き(訳注・エピファネイア)」(Ⅱテサロニケ2:8)をもって不法な人を滅ぼしてしまうのであるから、実際に、それは顕現の意味において使用されている。キリストがエピファニー(訳注・輝き)をもって出現するのが患難期の終わりであることは明らかである。
しかしキリストのこのエピファニーは、キリストのアポカリュプスと同じように、信仰者の望みの対象である。もし教会が前もって携挙のときに望みの対象を受け取っていたのなら、そうなることはあり得ないからである。パウロは「私たちの主イエス・キリストの現れ(訳注・エピファネイアス)の時まで」(1テモテ6:14)命令を守り、傷のない、非難されるところのない者であるよう勧告している。
生涯の終わりにおいて、パウロは「今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現われを慕っている者には、だれにでも授けてくださるのです」(Ⅱテモテ4:8)と語り、自分が勇敢に戦い、そしてキリストの裁きの御座において報酬を受け取る日を待ち望んでいる確信を表明している。
このような箇所から、パウロが報酬の日として期待している「その日」がキリストのエピファニーの日であるとしか結論できない。したがって、それはクリスチャンが愛情を注いでいる日、クリスチャンの望みの対象である。そしてそれは信仰者に報酬が授けられる日である。患難期前再臨説は、報酬が与えられる審判を、携挙と顕現の間に位置づけている。しかしここでは、それは患難期の終わりのエピファニーの時に位置づけられている。それは顕現と同じ時である。
ここで熟考されている事柄は、テトス2:13と14により決着させられている。「祝福された望み、すなわち、大いなる神であり私たちの救い主であるキリスト・イエスの栄光ある現われ(訳注・エピファネイアン)を待ち望むようにと教えさとしたからです。キリストが私たちのためにご自身をささげられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良いわざに熱心なご自分の民を、ご自分のためにきよめるためでした。」
教会の祝福された望みとは、大いなる神であり、私たちの救い主であるキリスト・イエスの栄光あるエピファニーなのである。教会の携挙の時期、すなわち私たちが空中に携え挙げられキリストにお会いする時期と、キリストのアポカリュプスとエピファニーの時期との間に、かなりの隔たりがあるとしたら、これはまことに奇妙なことばとなってしまう。
というのは、患難期前再臨説によれば、患難期の終わりのキリストの来臨は、聖徒に対する報酬とか義なる者の救いとかは無関係なものとになってしまうからである。死んだ者はすでによみがえらされ、生きている者はすでに復活のからだに変えられている。行ないに対する審判評価もすでに過去のものとなり、忠実なしもべたちに対するキリストの報酬はすでに与えられている。患難期の終わりにおけるキリストのアポカリュプスとエピファニーは救いではなく、審判を目的とするものとなってしまう。
しかし、神のことばによれば、このエピファニーは私たちの祝福された望みである。それは私たちが報いを受けるときであり、すべての不法から贖い出され、神の全き所有物となるべくきよめられるときであり、キリストとの交わりにおいて完全にひとつとされる祝福された望みである。このようなわけで、教会の携挙はエピファニーの七年前ではなく、エピファニーのときに起こると結論できる。たとえどのようなことばを作り出せるとしても、主のパルーシア、アポカリュプス、エピファニーの間にはどのような区別もない。それらはひとつの、同一の出来事である。
さらに、すでに明確に示してきたように、パルーシアが「臨在」を意味し、それゆえ教会を携挙するための主の来臨によって導入される全期間を覆うとの主張がある。しかし、キリストの顕現は、審判のみに関連した出来事ではない。そのことは、聖書における「アポカリュプス」と「エピファニー」ということばの使い方から明らかである。それはまた、信仰者の望みがその上に置かれている日であり、その日に、信仰者はキリストの再臨時に救いの完全な祝福に入れられる。教会の携挙とキリストの顕現との区別は、神のことばによって、どこにおいても主張されていないし、キリストの再臨に関係する用語によっても要請されていない、と結論を出せるだけである。
むしろ反対に、どのような推論ができるとしても、それらの用語は、キリストの顕現が携挙と同様、主との全き交わりに入るときであり、主の手から報酬を受け取るとき、つまり信仰者の救いの日であるということを示唆している。
パルーシア、アポカリュプス、エピファニーは単一の出来事である。キリストの再臨を二つの部分に分割することは、立証されえない推測にすぎない。さらに、キリストの再臨を二つの出来事に分けようとすること、あるいはさらに二つの別々の部分に分けようとすることに、患難期前再臨主義者すら幾分当惑しているという事実がある。
この学派のきわめて最近の著者たちのひとりは、教会のためのキリストの来臨はキリストの再臨ではないと主張している。この見解は、キリストの来臨と再臨とを区別する。このような区別はまったく立証されていない。キリストの再臨を描写するために使用されていることばのうちにそのことを支持するものを見出すことはできない。
「来臨(リターン)」と「再臨(セカンド・カミング)」の二つのことばは、聖書の中にそれに相当するギリシヤ語がないという点において、正確に聖書のことばを伝えていない。言い換えると、それは不自然、かつとてもありえない区別である。キリストのパルーシアはキリストの来臨であり、キリストの来臨はキリストの到来であり、キリストの到来はキリストの再臨である。主の来臨について使用されている語彙は、キリストの二つの到来または到来の二つの局面があるという見解に、いかなる支持も与えていない。反対に、キリストの来臨が単一、かつ不可分な栄光に満ちた出来事であると言う見解を立証している。*21
スコフィールドの聖書解釈
ディスペンセーション主義者は、一般に「字義的(“literal”)解釈をする人々」として特徴づけられています。しかし、ことスコフィールドに関して言いますと、それは半面の真理にしか過ぎません。スコフィールドの聖書解釈アプローチにおける、より根本的要素は、イスラエル/教会間の区分にあります。ダービーを思わせるやり方で、スコフィールドは、神の二つの民というこの分岐(bifurcation)から、聖書解釈における分岐を演繹しています。「イスラエルは地上的であり、教会は天的です。前者は、自然的であり、後者は霊的です。」
スコフィールドによると、イスラエルに関するものは「字義的(literalistic)」な仕方で解釈されなければなりません。しかし教会に関するものは、そのように解釈される必要はありません。そして聖書のいくつかの箇所――おそらく数多くの箇所――は、同時に両方のレベルで解釈されなければなりません。「Scofield Bible Correspondence School」 (1907, 45-46)の中で、スコフィールド自身、次のように言っています。
「こういった〔歴史的聖句〕は、
(1)文字通り真である(literally true)。記録されている出来事は実際に起った。しかしながら
(2)それらは(おそらく私たちが考える以上に)寓喩的(allegorical)ないしは霊的重要性を持っている。例:イサクとイシュマエルの歴史。ガラ4:23-31」
「従って――歴史的真実性を堅く保持しながらも――崇敬に歴史的聖句に霊的な意味を付与すること(" spiritualize")が許されている。」
「〔預言的聖句において〕、、私たちは絶対的字義性("absolute literalness")という土台に達する。預言書の中で喩(影:figures)はしばし見い出されるが、喩は常にかならず字義的成就をみるのである。預言の「霊的」ないしは喩的成就という事例は存在しない、、、」
「、、、エルサレムは常にエルサレムであり、イスラエルは常にイスラエルであり、シオンは常にシオンである、、、」
「預言は決して霊化(spiritualized)されず、常に字義的である。」
従って、スコフィールドは純然たる字義解釈者(literalist)ではなく、イスラエルに関する事についての字義解釈者であるといえます。「イスラエルと教会」というこの二元論は、実際には、①いつ、②どこで、「字義的」/「霊的」解釈二元論がそれぞれ適用されるべきかを決定する、より深い二元論です。*22
「歴史的聖句も預言的聖句も共に、字義的(literal)側面を持っている」とスコフィールドははっきりと主張しています。そして、歴史的聖句は、過去に文字通り(literally)起こった事を描写しており、それに対し、預言的聖句は、将来的に文字通り(literally)起こることを描写していると述べています。彼は、この字義的側面を損なわせるようないかなる試みをも拒絶しています。しかし字義的側面に加え、彼は霊的側面も許しているのでしょうか?
もしもそうなら、おそらく彼は次のように言うはずです。「描写されている実際の出来事に関し、私たちは歴史的聖句・預言的聖句共に、字義的に解釈しなければなりません。そして教会に対する適用に関してはそれを霊的に解釈しなければなりません」と。しかしながら、実際、彼はそうは言っていないのです。そしてそう言う代わりに、彼は、預言と歴史の区分を導入しています。
しかし、事実、これでさえも話の全容ではありません。スコフィールドは、ゼカリヤ10:1の注釈において、預言の「絶対的字義性(“absolute literalness”)」に関する彼自身の原則から逸脱してしまっています。この節には次のように書いてあります。「後の雨の時に、主に雨を求めよ。主はいなびかりを造り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人に下さる」(ゼカ10:1)。そしてこの箇所の注釈は次のようになっています。「参:ホセア6:3、ゼカ12:10.ここには肉的、霊的両方の意味がある。古の雨はパレスティナにやがて回復される。しかしそれと同時に、回復されたイスラエルの上にはやがて力強い御霊の注ぎがあるだろう。」
従って、預言におけるスコフィールドのこの「絶対的字義性の土台」というものは、私たちが考えるほどそう絶対的なものではないと言えるでしょう。このように実際、スコフィールドは自ら進んで喩(figures)を認めているだけでなく、その二重の意味についても言及しています。ですから、彼にとってどうしても排除されなければならない肝要点というのは、いわゆる「霊的な」意味自体ではなく、この預言の成就に「教会が参与する」ということを暗示するような解釈――これこそが排除されなければならないとされているのでしょう。非ディスペンセーション主義者にとって、こういった手順はかなり恣意的なものに見えるでしょう。しかしスコフィールド本人にとってはそうではなかったようです。実際、この手順は、彼のエペソ3:3-6の理解が基盤になっています。
古典的ディスペンセーション主義者は普通、この箇所を以下のように理解しています。
――旧約聖書のどこにも新約の教会に対する知識の啓示はない。にもかかわらず、エペソ3章の「奥義」という思想は、予型(typology)として、教会のこともひそかに言及され得るという余地を与えている。しかしここで許されていないのは、教会に対するあからさまな(overt)言及である。もしも未来預言としての旧約預言が、教会のことを言及しているのなら、それはあからさまな予言的事項であったはず。他方、旧約の歴史的記述は、新約の読者たちにも有効な、二次的レベルの「奥義」の意味を持っているだろう。
エペソ3:3-6に対する上記のような理解によって、スコフィールドのような解釈学的アプローチは正当化されます。しかし、もちろん、これだけが唯一可能なエペソ3:3-6解釈ではありません。エペソ3:3-6は、――ユダヤ人と同じ基盤の上にキリストにつながれることによって(6節)――異邦人もやがて祝福を受けるようになるその「方法」は旧約の中では決して明瞭に明かされていなかったという事を言っています。
スコフィールドの聖書解釈は、字義主義が行き詰まりを覚えるような、まさにそのようなケースを念頭に、見事に解説がなされています。新約聖書のあちこちで、表面的には、旧約聖書の御約束や預言の成就について述べているような箇所がみられます。しかも、そういった成就の箇所のいくつかは「非字義的」なのです。しかしスコフィールドは、この困難を、「意味を二つのレベルに区分する」というやり方で切り抜けています。二つのレベルの意味とは、つまり、①肉的・物質的(イスラエル的:Israelitish)意味、そして②霊的(教会的:churchly)意味です。
最初の例として、アブラハムの子孫に関する創世記の御約束のことを考察してみましょう。ガラテヤ3:8-9、16-19、29を読むと、これらの箇所は〔預言〕成就を、キリストの内に、そしてキリストの(霊的)子孫の内に置いているようにみえます。そうではあるのですが、創15:18の注釈で、スコフィールドは、「子孫にはパラレルな二種類あって、一つは肉体的・地上的、もう一つは霊的・天的である」と述べることによってこの問題をうまく打開しています。ゆえに、彼によれば、霊的子孫における成就というのは、イスラエルの待望している「成就」ではないわけです。
次に、マタイ5-7章を見てみましょう。山上の垂訓は、律法の成就を語っています(マタイ5:17)。この成就は、キリストの御説教においてだけでなく、キリストの弟子たち(彼らの義は律法学者やパリサイ人の義にまさるものでなければならないとされました。マタイ3:20、参5:48)にも関与しているようにみえます。これらの弟子たち――特に12使徒たち――は、世界の塩であり光として(マタイ5:13-16)、教会の核を形成しました(マタイ16:18)。それゆえ、天の御国の御約束を含めたマタイ5-7章は、教会に関するものです。しかしこの点でもスコフィールドは、上記と同じような経路での説明が可能であることを見い出しました。マタイ5:2の注釈で彼は次のように言っています。
「山上の垂訓には二重の適用がある。
(1)字義的には御国への適用。この意味においては、山上の垂訓は、地上の義なる政府のための神聖なる憲法を与えるものである、、
(2)しかし、クリスチャンにとっては、ここには美しい倫理的適用が存在する。心の高慢な者ではなく、貧しい者が幸いであるという事実はいつでも真である、、、」
また、使徒2:17では、ペテロが(イスラエルに関する預言である)ヨエル2:28-32が、ペンテコステという教会の出来事の中で成就したという事を言っているようにみえます。しかし、使徒2:17のスコフィールド注釈では、ここにおいても大胆な区分がなされています。
「イスラエルに関する予言としての『終わりの日』と、教会に関する予言としての『終わりの日』の間には区別がなされなけれならない。(1テモテ4:1-3、2テモテ3:1-8、ヘブル1:1-2、1ペテロ1:4,5、2ペテロ3:1-9、1ヨハネ2:18-19、ユダ17-19)、、、教会に関しての「終わりの日」は、キリストの降臨をもって始まった(ヘブル1:2)が、この世の終りの堕落と背教に関する特別な言及がなされている(2テモテ3:1、4:4)。それに対し、イスラエルに関しての「終わりの日」は、イスラエルの高揚と祝福の日々であり、それは『御国の時代』と同義語である。(イザヤ2:2-4、ミカ4:1-7)」
預言的解釈に関する「絶対的字義性」というスコフィールドの一般原則から考えると、「ヨエルはこの箇所はあくまでイスラエルのことを言及しているのであって、教会のことを言及しているのではない」という結論が自然であるように思われます。しかし、この箇所では何といってもペテロ自身が、「教会への言及」としてヨエルの聖句を引用しているため、スコフィールドもやはり、これに対しては譲歩する必要がありました。そして彼は、意味を二つに分割することでそれに対応しました。
そして、「一つのレベルでは、この箇所はイスラエルのことを言及しているけれども、二次的なレベルでは、それは依然として教会の『終わりの日』のことを言及しているとも言える」と彼は述べています。そしてそれが、次に挙げる、ヨエル2:28のスコフィールド注釈です。
「ヨエル2:28の『その後』の意味は、『終わりの日に』(ギ:eschatos)であり、それは、キリストの最初の降臨と共に始まった『終わりの日』の間、部分的にそして継続した成就を成しつつあるが(ヘブル1:2)、より偉大なる成就は、イスラエルに適用される『終わりの日』を待たねばならない。」
従って、幾つかの場合において、スコフィールドは、同一の聖句に二つの別々の意味を前提しており、一つはイスラエル的(Israelitish)、もう一つは教会的(churchly)なものです。そして、イスラエル的「字義的」成就の最重要性を保持するため、教会的な言及は、「適用」(マタイ5:2の注釈)あるいは「部分的、、成就」(ヨエル2:28の注釈)とされています。この方法論は要約しますと以下の図表のようになります。

スコフィールド区分法の精巧さ
こういった区分の導入は、解釈上の困難を解決する方法として、古典的ディスペンセーション主義者の間で現在でも好んで用いられている方法論です。例えば、スコフィールドは、5つ余りの点において「神の御国(kingdom of God)」と「天の御国(kingdom of heaven)」を区別しています。(マタイ6:33のスコフィールド注釈)
それとは対照的に、大半の非ディスペンセーション主義解釈者たちは、この二つの語を、malkut shamainの単なる翻訳異形(translation variants)とみています(参Ridderbos 1962, 19)。ここでも、スコフィールドは、一般的な前千年王国説支持者と共に、二つの最後の裁きの間における区別(マタイ25:22の注釈)、そして二つ別々のゴグ・マゴグの戦いの間における区別(エゼ38:2)を導入しています。イスラエル/教会の区別を無傷のまま保持するべく、スコフィールドは下に挙げるように、「エホバの妻」と「小羊の花嫁」の間にも区別を設けています(ホセア2:1の注釈)。
「そこで、イスラエルは、回復され赦されたエホバの妻となり、教会は汚れのない小羊の妻となる(ヨハネ3:29、黙19:6-8)。イスラエルはエホバの地上的妻であり(ホセア2:23)、教会は小羊の天的妻となる。(黙19:7)」
単一の聖句に二次元の意味を仮定するというやり方(例:スコフィールドのマタイ5:2、ヨエル2:28注釈)は、他のディスペンセーション主義者の間でもみられます。例えば、タン(1974、185)は、マラキ4:5に関しての「エリヤ」の二回到来に区別を設けています。バプテスマのヨハネは、マラキ4:5で預言されているエリヤの到来を「予表し」「予型」しています。しかし「字義性の原則」が守られなければならないのだとしたら、ヨハネは実際には「成就」ではあり得ないことになってしまいます。ティシュベのエリヤが将来の字義的成就として来なければなりません。タンは、こういった区別を設けることに関わる解釈学的原則について非常に明確に次のように言っています。
「もちろん、未来に関する預言に現行の予表(foreshadowings)をみたり、キリスト教会への適用としたりすることは可能です。しかしここで私たちは『拡大された予型』という領域にいるのです。前千年王国説的解釈者は、旧約の出来事に多くの予表を見い出すかもしれませんが、彼らはそれを――実際の成就としてではなく――あくまで適用、予表として見ているのです。(Tan 1974, 180)」
「字義的預言解釈者たちは、新約記者によってなされた旧約の引用句は、実際の成就を指し示すと同時に、真理や諸原則を描写しそれらを適用させる目的をもってなされていると信じています。(Tan 1974, 194)」
ですから、ここにおいて、多くの旧約預言は、いわゆる「適用」という用語で教会に関連づけられ得るのだということを私たちは留意すべきだと思います。しかしながら、この事に関する取り扱いにはディスペンセーション主義者の間で差異があります。この論争の中では、旧約預言の「教会」に対する関係がキーポイントですので、次章では、ディスペンセーション主義内に見られるそのヴァリエーションについて見ていきたいと思います。
ディスペンセーション主義のヴァリエーション
ジョン・N・ダービーおよびC・I・スコフィールド双方にとって、律法と預言の解釈――つまり実質上、旧約聖書全般の解釈――が、ディスペンセーション主義体系の中での鍵となるものでした。
「山上の垂訓の中に出て来る律法は、直接的にはクリスチャンに関係し得ない。もし関係し得るのなら、恵みによる救いという真理が妥協にさらされてしまう。」「預言というのは、将来の地上的イスラエルにおける字義的成就として読まれなければならず、それは教会を成就と読み取ってはならない。」
こういった要素は今も尚、一部のディスペンセーション主義の人々のアプローチにおける肝要ファクターとして存続しています。しかし旧約の律法や預言に対するすべての人のアプローチが全く同様であると考えてはいけません。
今日への適用としての旧約聖書使用
まず一つ目に申しあげたいことは、「クリスチャン生活への聖書の適用」という点で、さまざまなディスペンセーション主義者の間に多様性があることを認めることの大切さです。今日、多くのディスペンセーション主義者は、「直接自分に語りかける書」として聖書を読んでおられます。また、これらの人々は預言的約束(例:イザヤ65:24、エレ31:12-13、エゼ34:24-31、ヨエル2:23、ミカ4:9-10)を自分たちに適用し得るものと捉えています。また彼らは山上の垂訓も自分たちに適用され得ると考えています。
そして彼らは、たとい、そういった預言や掟の「第一義的」言及が千年王国期の人々のために出されているということを信じてはいても、それでも尚、自分たちにも適用され得ると信じています。こういったグループの中には多くの古典的ディスペンセーション主義者だけでなく、かなり修正した型のディスペンセーション神学を信奉している人々も含まれます。しかし中にはそうすることを拒んでおられる人々もいます。これらの人々は「真理のみことばを正しく分割する(“rightly dividing the word of truth”)」ことに勉励しています*23。つまり、彼らは注意深く、それぞれ異なるディスペンセーション(経綸)に対して語られている聖書箇所を分離・分類しているのです。そしてこの経路をたどっている人々は、山上の垂訓が「法的根拠(“legal ground”)」(参:マタイ6:12のスコフィールド注釈)である、従って、これはあくまで(千年王国期の)御国の倫理であって、クリスチャンに対して適用されるべき倫理ではないと解釈しています。
また、クリスチャンは「主の祈り」(マタイ6:9-13)を祈るべきではないし、仮に祈るとしても手本として用いるべきだ。なぜなら、マタイ6:12は恵みのアンチテーゼだから、と解釈しています。一応、このようなスタンスのディスペンセーション主義者を「硬派(“hardline”)」ディスペンセーション主義者と呼ぶことにいたしましょう。そしてそれとは反対のグループを「適用派(“applicatory”)」ディスペンセーション主義者とお呼びすることにしましょう。なぜなら、これらの「適用派」の人々は平素、自分たちクリスチャンに対しても旧約の適用をしているからです。尚、「硬派」「適用派」そのどちらのグループ内にも古典的ディスペンセーション主義者は存在します。
また「硬派」ディスペンセーション主義者の中には、スコフィールドがマタイ5:2注釈で留意していた程度の適用さえも拒むような原則を保持している人々もいます。(スコフィールドは、マタイ5-7章が第一義的には千年王国への言及であるということを述べた後、「この箇所はクリスチャンにとっての美しい倫理的適用がある」という事は記述しています。)さらに、これら「硬派」の人々が預言を読む際、彼らは聖句を、「千年王国期のもの」と「キリストの最初の降臨によって成就されたもの」とに「分割」します。そのプロセスを通し、そうとは気付かないうちに、彼らは教会の一員としての自分たちがそういった聖書箇所を適用することを注意深く回避してしまっています。
もちろん、聖書適用におけるディスペンセーション主義者の間の相違というのはそれぞれ各自の度合の問題です。そうではあるのですが、今私がなしている分類作業というのはそれなりに有益なものではないかと思います。なぜなら、それによってそういった相違の深刻度を私たちはより正確に把握することができると思うからです。
ディスペンセーション主義者も、非ディスペンセーション主義者もどちらも、「相手の方こそ間違っている」と考えています。しかしながら、すべてのことにおいて片方だけが全部正しい/間違っているということはないでしょう。しかしその中に含まれている誤謬はどの位の深刻さを持つものなのでしょうか?そしてそういった誤謬はどれくらい教会にダメージを与え得るのでしょうか?
教会への実際的影響という点でみた時、①「適用派」ディスペンセーション主義者と、②大半の非ディスペンセーション主義者は、(それぞれが③「硬派」ディスペンセーション主義者との間に持っている距離で比べた場合)、むしろ、①と②の人々は、互いにより近い関係にあるのではないかと思います。それではこの事を具体的に考えてみましょう。まず最初に、「適用派」ディスペンセーション主義者のAさんと、非ディスペンセーション主義者のBさんが一緒に話しているとします。

この二つのグループの内の一方が、終末論の詳細において幾つか誤った考えを持っています。そしてこの誤見解はこのグループの生活に多少なりとも影響を及ぼしています。すべてのクリスチャンは、キリストの再臨に対する希望の光の下で毎日の生活を送るよう召されています。そして私たちの希望はいつもある程度において私たちが頭に描いている詳細像によって彩られています。
しかしそうではあっても、私たちが皆共有している中心的希望――つまり、イエス・キリストの再臨自体――に比べたら、そういった詳細の影響はより小さいといえます。詳細内容の多くは、私たちの精神的書棚に収められている詳細にすぎず、私たちの実生活にはさほど影響を及ぼしていないというのが現実です。また実際に一連の終末の出来事が起こり、その結果、自分の終末論的見解が間違っていたことが判明したにしても、それはさして大悲劇とはなりません。ただ、そういった事に一つ問題があるとしたら、それは終末論的見解の詳細というよりはむしろ、そういった見解から引き出される誤った形での実際的諸結論ではないかと思います。
例えば、イスラエルという政治国家が大患難期にvindicate(正当性の立証)されることを信じている人々の中には、「現在」、自分の国の政府があらゆる状況において政治的に親イスラエル路線を取らなければならないと誤って結論づけるようになるかもしれません。もしくは、「主の再臨が近づいているので、もう一般の仕事をやめよう」と、当時のテサロニケの信者の幾人かが取っていたような行動をとるかもしれません(2テサ3:6-13)。しかしこういった事は、成熟したディスペンセーション主義者・非ディスペンセーション主義者なら皆一様に避けようとしています。
では今度は、聖書のかなりの部分を「自分には適用されない」としている「硬派」ディスペンセーション主義者のことを考えてみましょう。この場合、これらの人々の見解が誤っているのだとしたら、彼らが及ぼしているダメージは非常に深刻だといえるでしょう。彼らは、クリスチャンが聖書の多くの箇所から受け取るべき霊的糧を自ら遠ざけてしまっています。またこういった人々が教会の指導的位置にある場合、彼らは他の人々にもダメージを与えることになります。
彼らは真剣に受け取るべき聖書の御約束や掟から自らを遠ざけ、人々の人生の中に神の御言葉が生きて働く余地をはく奪しています。もちろん、すべての御約束や掟が、当時の聞き手に適用されていたのと全く同じ方法で私たちにも適用されるわけではありませんし、私たちはいかにして神の言葉を自分たちに関連づければいいのかという問いにしばし取り組まねばなりません。しかしその努力を初めから除き去ってしまうというのは、そのプロセスを短絡化させることです。
それでは、私たちはディスペンセーション主義内のこういったヴァリエーションから何を学ぶことができるでしょうか?まず、私たち非ディスペンセーション主義者は、ディスペンセーション主義の人々を無差別に非難したり反動を起こしたりすることをしてはいけないと思います。事実、ディスペンセーション主義者の中には、他の人々以上に霊的に私たちに近い人々もいます。ある人々は破壊的な教えをしていますが、また別の人々はそのような教えはしておられません。特に、ディスペンセーション主義の教えから引き出される実際的な成果や、そこに集う人々がいかに聖書から霊的滋養を得ているかを見る時、私たちは短絡的な判断を慎まねばならないことを悟るでしょう。
またディスペンセーション主義者の中には多くの良い働きをしている方々もおられます。そこに残存する相互の相違点というのは、実際レベルでは、理論上見える差異よりも、よりマイナーなものなのかもしれません。それから「適用派」ディスペンセーション主義のみなさんにとっておそらく重要なのは、ディスペンセーション主義者の間に存在する実際的な主要相違点に向き合うことではないかと思います。「適用派」ディスペンセーション主義のみなさんは、実際的にも牧会的にも、旧約預言の適用という点ですでによい働きをしておられると私は思います。
しかしみなさんは、他のディスペンセーション主義者がこの部分においての誤謬に陥らないように周りの人を助けてあげる必要があると思います。また、みなさんに知っていただきたいのは、非ディスペンセーション主義者の中には、聖書の実際的使用という点で、「硬派」ディスペンセーション主義者以上に、むしろみなさんと霊的に近いところにいる人々がいるということです。
その後、いくつかの興味深い進展がディスペンセーション主義内部で起こっており、それはかなりの度合いにおいてスコフィールド自身の見解を越えるものです。「新スコフィールド注釈聖書(New Scofield Reference Bible)」は大方、スコフィールドの伝統を引き継いでいます。しかし少なくとも二、三の点で、スコフィールドのいくつかの「尖ったへり部分」はすでに注釈から削除されています。
例えば、「アブラハムへの約束」や「御国の律法」に関する彼の二重解釈(創15:18およびマタイ5:2の注釈)の部分は新版では消えています。しかし使徒2:17の二重解釈は依然として残っており、むしろ新版では、ここの解釈はさらに強化されたようです。それから創1:28には注釈加筆があり、救いにはただ一つの道しかない、それは信仰をとした恵みによるキリストの内にある救いである、と記されています。
また同じ編注は、啓示の累積的性質について強調しています。もちろん、ディスペンセーションは依然としてそこに存在しますが、それらはそれ以前の神の御働きに「取って代わる/破棄する:supersede」というよりもむしろ、そういった御働きに「付け加わるもの」として捉えられています。こういった新しい強調は、歓迎されるべきものではないかと思われます(参:Fuller, 1980, 18-46)。
それに加え、よりインフォーマルな所においても、ある重要な発展や動きが出てきています。何人かの指導的立場にいるディスペンセーション主義者たちの間で、「少なくとも教会における旧約預言の二次的適用、場合によっては『成就』も言及しよう」といった積極的な意志がみられるのです。また多くの方々は「新約の信者たちは、アブラハムのまことの子孫であるキリストとの一致により、成就に参与している」と言い始めています。
前の章でご一緒に見てきましたように、スコフィールドは旧約預言に対する「絶対的字義性(“absolute literalness”)」という彼の一般的言明により、上記のようなタイプの動きを断固として拒絶していました(Scofield 1907, 45-46)。しかしこういった原則により、スコフィールド自身の内で、自分の「解釈学的原則」と、「実際の読み方」(例:アブラハムへの約束、ヨエル預言、マタイの御国の倫理といったものに、霊的・教会的次元をも許すという読み方)との間に非常な摩擦を生じさせていました。
さらに、預言においての字義性のみの主張は、旧約聖書の歴史の中に寓喩的要素を見い出そうとしていたスコフィールド自身の意思とも軋轢を生じさせる結果をもたらしました。なぜ歴史の部分には〔寓喩的要素に関する〕いくらか余分な範囲を許しているのに(表面的には、でも、歴史の中には寓喩的要素はより少ない。。。)、預言の部分にはそれが許されていないのだろう(表面的にはむしろこちらの方に寓喩的要素がより多く含まれているのに。。)?そういう訳で、スコフィールドの後継者たちの内何人かが、彼が(「歴史」と「預言」との間に設定していた)厳格にして人工的にみえる二分法アプローチを除去しようと試みたのはむしろ不可避なことだったと言っていいでしょう。
その方法はシンプルです。彼らはこう考えました。〈スコフィールド解釈法に加え、預言というのはもしかしたら、――旧約の歴史の中に見いださる付加的次元(extra dimension)と平行し――あちこちでそういった付加的意味を持っているのかもしれない。〉
〈それでは、その付加的次元とは一体どのようなものだろう?うん、そうだ。「歴史」の読みにおいて、私たちは生粋の歴史的出来事の価値を保持しつつ、それと同時に、ある場合においては、そこに「キリストおよび教会を指し示すような予型的次元(typological dimension)」を読み加えている。〉
〈一方、「預言」の読みにおいて、私たちはイスラエルの千年王国の内に字義的成就を保持しつつ、それと同時に、ある場合においては、そこに「キリストおよび教会を指し示すような霊的適用の次元」を読み加える。。。〉
ある人々はさらにここから進んで、〔預言〕成就における教会の参与についても言及するようになっています。例えば、ディスペンセーション主義者のタンは、預言の完璧に「字義的な」成就を主張することにおいてきわめて律儀でありながらも、それと同時に、教会への適用という領域でも彼はきわめて積極的にそれを認め、預言成就における「現在の予表」について次のように言っています。
「もちろん、未来に関する預言に「現在の予表("present foreshadowings")をみたり、キリスト教会への適用としたりすることは可能です。しかしここで私たちは『拡大された予型』という領域にいるのです。前千年王国説的解釈者は、旧約の出来事に多くの予表を見い出すかもしれませんが、彼らはそれを――実際の成就としてではなく――あくまで適用、予表として見ているのです。(Tan 1974, 180)」
スコフィールドは、もちろん、旧約の歴史的記述の中の「予型」や、さらには「寓喩(“allegory”)」の存在でさえも認めていました。しかし、原則のレベルにおいて、彼は、「預言」の領域ではこれを認めることを拒みました。一方、タンはそのような差し控えを全くしていません。しかしタンは、自分の使用する術語(用語)の中で注意深く、重要な区別を保とうと努めています。彼は「成就(“fulfillment”)」という言葉を使う際、いつも一貫して、最も字義的な形態における預言の実現を指し示しています。(多くの場合、そこには千年王国的成就が彼の視野にあります。)
そして、教会に対して関連づけることができるかもしれない預言、といった意味合いを帯びさせたい時には、タンは「予表(“Foreshadowing”)」や「適用(“application”)」といった用語を好んで用いています。しかし他のディスペンセーション主義注解者たちは、ここからさらに進んでいます。例えば、エイリッヒ・ザウアー(Erich Sauer , 1954, 162-78)は、数多くの旧約預言における「四重の成就の可能性」を述べています。

Erich Sauer
1)旧約預言はバビロンからの回復において予備的な仕方で成就している。
2)霊的には教会時代に成就している。
3)千年王国期に字義通り成就する。
4)そして(千年王国に続く永遠の状態である)万物の完成の際、さらなる成就をみる。
ザウアーはこのように自分の立場を明確に打ち出しています。「しかしその他の多くの人々は、複合的成就の可能性を前提とするような(ザウアーと似た)見解に対し、どのくらい議論の可能性を残しているのでしょうか。」とお尋ねになる方がいらっしゃるかもしれません。アーヴィング・ジェンセン(1981, 132)は、一般に広く受け入れられている型のディスペンセーション主義の立場を代弁して次のように言っています。

Irving L. Jensen
「多くの場合、一つの預言には複合的適用がなされます。例えば、イスラエルの患難に対する預言は、バビロン捕囚と同時に、終わりの時の大患難期を言及し得るでしょう、、預言者は、あたかもそれらの出来事の間に何らの時間的介入がないかのように、次から次へと未来の出来事を預言しています。そういった介在的な出来事は彼には啓示されていなかったのです。」
私たちが「旧約の預言」と、「キリストの初臨および再臨に関するいくつかの出来事」の間に存在する明らかなパラレル関係に取り組もうとするなら、こういった複合的適用という考え方は容易に生じてくるでしょう。さらに、新約聖書自体が旧約聖書をクリスチャンに適用させている事例から、私たちは教会とクリスチャンというものが多くの場合、適用に関する一つの重要なポイントであるという認識に導かれます。
仮にあるディスペンセーション主義の方々が、「旧約預言にはしばし一通りではない複合的な適用がある」という認識をもって預言の箇所を読んでいると仮定してみてください。説教者としてこれらの人々は、会衆のみなさんのためにも、教会に対する適用について注意を払う特別な責務を負っています。もちろん、彼らは究極的な成就が何であるのか、そして自分たち以外の状況にいる人々に対する適用がどのようなものであるか調べることはできるでしょう。しかしもしこの方々が牧者としての心を持っているのなら、現在への適用という点に多くの時間とエネルギーを注ぐことだろうと思います。そうしていく過程で、預言の解釈に対するこれらの人々自身のアプローチが次第に、非ディスペンセーション主義者のそれに近づいていきます。実際、私たちは、可能性として考えられる広範なスペクトルを次の図表のように描くことができるかもしれません。

さて、ディスペンセーション主義の方々がまず「適用」一般について話し始めました。そうして、「預言」と「教会」との間の関連性について次第に違和感を覚えなくなるにつれ、これらの人々は、次第にこういった適用を、「予備的(preliminary)」とか「部分的成就(partial fulfillments)」と呼び始めました。一面において、これは単なる用語の違いです。しかし「成就」という語は、「教会によるこれらの聖句の使用」が一義的意味からそれほど隔たってはいないという事を含意する傾向にあります。そしてそれが示唆するのは、神が最初に預言をお与えになった時、教会というのは単なる後の思い付きではなく、主の御意図に統合されたものだったということです。
実際、ディスペンセーション主義の方々は時としてここからさらに進みます。そして、これまで以上により一層、預言を、①教会時代(予備的な方法で)、②千年王国時代(最終的な方法で)その両方において成就するものであるとみなすようになります。しかしそうであったとしても、教会はイスラエルの預言的地位からそれほどかけ離れてはいない、むしろ、教会はそれに(予備的な方法で)参与しているのだと、これらの人々は考えています。
〈クリスチャンは今、アブラハムの御約束の成就に参与している。なぜなら、クリスチャンは――成就の核心である――キリストと結ばれているから。でも、御約束の完全な実現は、やがて将来的に果たされる。〉
〈ということは、一つはイスラエルに、もう一つは教会に、という二つのパラレルな御約束は存在しないということ?そして一つはイスラエルに、もう一つは教会に、という二つのパラレルな宿命というのも存在しないということになる?!〉
〈むしろ、そこに有るのは、一式の御約束や目的に対する(予備的&最終的)異なる歴史的段階なのかもしれない。〉
〈そうなると、やはり存在するのは、ただ一種類の神の民なのだろうか?――終わりの日に、キリストの復活の後、ユダヤ人も異邦人も一つのからだにつらなったという一つの神の民に。。(参:ローマ11:16-32の単一のオリーブの木)〉
この地点で、これらのディスペンセーション主義の方々は、ジョージ・E・ラッドのようないわゆる「古典的」前千年王国説に近い立場に近づきます。古典的前千年王国説は、キリストの(肉体を伴う)再臨の後、キリストの統治の下、偉大なる地上的繁栄という特定の時期があることを信じており、この時期の後、一般的復活と新天新地の創造(万物の成就ないしは永遠の状態)が続くと信じています。しかしこの立場は、二つの神の民ないしは二つのパラレルな宿命といった区別はしていません。ディスペンセーション主義者の中にはこれに同意する方々もいます。しかしこれらの人々は、国家的、民族的イスラエルの継続する重要性を重視したいという願いから(ローマ11:28-29)、自らのことをディスペンセーション主義者と呼んでいます。
そして、これらの人々は、パレスティナの地に関わるアブラハムの御約束は、やがて千年王国期に民族的イスラエルの地において字義的成就を見ることになると信じています。また、ここからさらに無千年王国説の立場にシフトする人々がいるかもしれません。次の事を仮定してみてください。古典的前千年王国説を信じる人々が、時の経過と共に段々と、教会時代における旧約預言の、より多くのより深い成就を見るようになりました。彼らが見ているもの以上に深い成就というのは、そうそう簡単に絶対的で完璧な成就、という風に理解がいきません。彼らはこれまでずっと、より偉大な成就は千年王国期に実現すると見てきたからです。
しかしある人々は、この「千年王国の」平和と繁栄というのはあまりにもすばらしく、これは永遠に続くものであると信じ始めました。これは事実上、万事の完成なのです。でもそうなると、もちろん、彼らは黙20:1-10の自見解を修正しなければならなくなります。これが仮に起るとして、そこにはいくつかの選択肢があります。が、そういった選択肢は私たちを懸念させるには及びません。肝要な点は、旧約預言についての認識は、非常に広範囲な連続体(continuum)をなし得るということです。別の体系を受容すべく、一気にそして意識的に自らのこれまでの体系を放棄することに困難を覚え、そのため、決して別の地点には行かない方もおられるかもしれません。しかしそうではあっても、この連続体に沿って、他の兄弟姉妹が将来的に私たちに近づいてきてくれるかもしれないということに私たちは希望を持つことができると思います。
ディスペンセーション主義者は今後自らの立場を、例えば、古典的前千年王国説や、あるいは無千年王国説に改訂するかもしれませんし、逆に、無千年王国説支持者は、彼らが――「永遠の状態」と定義する状態の初めに――付加的「開始点段階(“threshhold stage”)」というのを導入することによって前千年王国説支持者になることもあるいは可能でしょう。私たちは自らの体系を段階的に改訂していき、それでも尚かつ、最終的には、今自分のいる場所に辿り着くことも可能です。(もしくは、逆のバージョンとして、私たちは自らの見解を改訂していきながら、やがて彼らがいる場所に辿り着くこともまた可能です。)
この地上に生きている限り、クリスチャンの間にはいくらかの教理的意見の不一致があることでしょう。しかしキリストゆえに、そして真理ゆえに、私たちはそれらを克服する方向で共に働いていかなければなりません(エペソ4:11-16)。そしてこの事に関し、たとい、人々がすぐに完全なる意見の一致に達しなくても私たちは気落ちしたり、失望したりする必要はありません!
契約主義神学の中でのいくつかの進展
それでは本章では、ディスペンセーション主義の外側でなされている進展――特に契約主義神学内の進展状況――についてご一緒にみていきたいと思います。契約主義神学は長い間、ディスペンセーション主義の主要競合相手とみなされてきました。確かに歴史的に、契約主義神学はディスペンセーション主義のライバルでしたが、それは必ずしも、古典的ディスペンセーション主義の〈対極双子〉ではありません。また、オールターナティブな立場というものが、預言解釈について、「自分も古典的ディスペンセーション主義と同じだけの数の、詳細にして特定の回答を持っている!」と主張しているかというと必ずしもそうではありません。
また、預言に関するすべての見解が、成就についての正確な予測に等しく役立っているかというと、これもまた常にそうであるとは限りません。預言的言語のあるものは、その含意をことごとく明示するというよりはむしろ、引喩的ないしは暗示的であるでしょう。それゆえ、いかにして成就がなされるかという事の詳細に関し、私たちはかなり時間をかけて取り組まねばならない時が往々にしてあると思います。とはいえ、純粋なオールターナティブな立場というのは――それがどのような立場であれ――福音主義教理の真理についての堅い確信を共有しています。例えば、聖書の無誤性、キリストの神性、処女降誕、キリストの代償的贖罪、キリストのからだのよみがえり等です。
これまでの章で、私は非ディスペンセーション主義のみなさんに、「どうかご自分とは異なる立場にいる人々を理解するよう努めてください」とお願いしてきました。そして今度はディスペンセーション主義のみなさんにも同じ事をお願いしたいと思います。みなさんは同意されないかもしれません。しかしどうか分かっていただきたいのは、ここにも一つのまごうことなきオールターナティブが存在するということ、そして、それは同情心を持って「内側から」見た時、たしかに「理に適っており」――それはちょうどあなたご自身の体系が、同情心を持って「内側から」見た時、たしかに「理に適っている」のとちょうど同じなのです。この章では契約主義神学の掘り下げはせず、主要な特徴点に的を絞って論を進めていきたいと思います。
契約主義神学内でのいくつかの修正

契約主義神学は、その起源をプロテスタント宗教改革に持ち、ヘルマン・ウィトスィウスおよびヨハネス・コケイウスによって体系化されました。本書の目的のため、この神学の起源についての長い歴史は省略し、ウェストミンスター信仰告白によって代表される、古典的契約主義神学のところから話を進めていくことにしましょう。契約主義神学というのは、世界の歴史を「契約」という語で捉えています。それによると、全歴史を通じた神と人間の交流は、二つの契約によって理解されるとされています。
① 行ないの契約(堕落前にアダムと結ばれた。)
② 恵みの契約(キリストを通し、主を信じるすべての人と結ばれる。)
そして恵みの契約は、異なるディスペンセーション(経綸)の中で異なる形で施行(administered)されますが*、実質的には(substantially)全経綸の内にあってそれは同じです。
*ウェストミンスター信仰告白7.4 「この恵みの契約は、聖書で、しばしば遺言という名で表わされている。それは遺言者イエス・キリストの死と、それによって譲渡される永遠の遺産とに、それに属するすべてのものも含めて関連している。ヘブル9:15-17、ヘブル7:22、ルカ22:20、Ⅰコリント11:25」
契約主義神学は常に、一つの恵みの契約の内にあって、施行(administration)の多様性を認めています。これは大部分において、聖書歴史の中における異なる時代の多様性のゆえだと説明できます。しかし力点は紛れもなく、一つの恵みの契約の一致(unity;単一性)にありました。それとは対照的に、古典的ディスペンセーション主義は、さまざまな時代の中における神の施行の多様性「から」スタートし、「イエス・キリストにあるただ一つの救い」という点での一致に対する是認が、あくまで従属的に導入されています。
さて、契約主義神学にはどのような進展があったのでしょう?契約主義神学者たちは、ウェストミンスター信仰告白の形成後、ただ黙って何もしていなかったわけではありません。ゲルハルダス・ヴォス([1903] 1972; [1926] 1954; [1930] 1961; [1948] 1966)は、神の啓示の漸進的性格および、歴史の中における神の贖罪的行為としての漸進的性格についての考察・研究を始めました。

Geerhardus Vos, 1862-1949
そしてこれをもって、「聖書神学(Biblical Theology)」という一連の運動が誕生したのです。この聖書神学では、旧約と新約の間に存在する非連続性や前進という点だけでなく、旧約内のそれぞれの時代間における非連続性や前進にも重きを置いています。*24
この陣営内の代表者として挙げられるのは、ヘルマン・リダーボス(Herman Ridderbos , 1958; 1962; 1975)、リチャード・B・ガフィン(Richard B. Gaffin, 1976; 1978; 1979)、メレディス・G・クライン(Meredith G. Kline, 1963; 1972; 1980; 1981)それから、O・パルマー・ロバートソン(Palmer Robertson,1980)などです。聖書神学という取り組みの中では、旧約内のそれぞれ特定の聖契約を、①他の諸契約との関連性という点で、そして②その唯一性という両方の点で考察することができます。この枠組みの中にいる契約主義神学者たちは、依然として「唯一なる恵みの契約」というものの一致(unity; 合一、統一性、単一性)を信じています。
でも、そういう一連の事は結局何を意味しているのでしょうか?そうです、唯一の「恵みの契約」は、多様な形態の中によってなされる、救いの唯一の道に対する宣言なのです。ディスペンセーション主義のみなさんも、これには同意できると思うのですが、どうでしょうか?それに加え、別の前線においてもいろいろな動きがあります!例えば、アンソニー・A・ホエケマの著書「聖書と未来(The Bible and the Future)」(1979)です。

Anthony A. Hoekema(1913-1988)
ホエケマの、「新しい地」に対する聖書的御約束への着眼により、終末論の領域においても活性化がなされました。

彼は無千年王国説の支持者ですが、(万物の成就としての)永遠の状態の地上的(“earthy”)性格にも力点を置くことで、前千年王国説の千年王国からも、そう隔たったところにはない像を描き出したのです。また、ウィレム・ヴァン・ゲメレン(Willem Van Gemeren,1983; 1984)は、ローマ11章と旧約預言を基盤に、イスラエルの特別な役割に着眼しています。

Willem Van Gemeren
民族的イスラエルに対する神の将来的目的という部分に考慮の余地を入れることで、彼は、ディスペンセーション主義の方々が重荷を持っておられるいくつかの部分を共有し、そこに接近しています。
贖罪的時代ないしは「ディスペンセーション(経綸)」
それではこういった一連の働きがもたらした結果について――特にディスペンセーション主義のみなさんにとって有益になるような部分について――少しまとめてみたいと思います。まず第一に、歴史の中で神のご計画が為される上での特定の諸時代ないしは「ディスペンセーション」が存在します。そしてこれらの諸時代は有機的に互いに関連し合っています。種から新芽が芽生え、新芽が成長した植物となり、そしてその植物が果実を結びます。各時代がそれぞれに対して持っている有機的関係もそのようなものだといえます。

そして各時代の間には、連続性(一本の樹木があらゆる段階を経ながら発育していくように)と、非連続性(種は、新芽とはとても違って見えます。そして新芽は果実とはとても違ったもののように見えます)、その両方があります。具体的にそういった時代がいくつあるのかという事はさほど重要ではありません。大切なのは、それが有機的な型の関係性を持っているということです。例えば、私たちは旧約聖書の中の寓意的(figurative)な「復活」に注意を払うべきでしょう。
――ノアは洪水から救われました(水は、死の象徴です。参:ヨナ2:2-6)、イサクは雄羊の代替により死から救われました。そして乳児のモーセは水から救われ、イスラエルの民は過越および紅海にて救われ、イスラエルの、死からの予備的「復活」の型としてバビロンからの回復がありました(エゼキエル37)。
こういった全ての事は、贖罪の偉大な行為(キリストの復活)との間に、ある種の「連続性」があることを示しています。しかしここにはまた「非連続性」も示されています。こういった事例の大部分はある意味、寓意的ないしは「影(“shadowy”)」的です。エリヤが死んだ子どもを蘇生させるような親近性のあるパラレルであっても、それは完全なパラレルではありません。結局、この男の子は地上的な存在に戻り、やがて再び死ぬことになりました。それに対し、キリストは復活の体で永遠に生きておられます(1コリ15:46-49)。
非連続性は非常に重要です。肉においてキリストが実際に顕現される前には、贖いというのは、必然的に、部分的で影の含みを持ち("shadowy")、「不十分(“inadequate”)」な性格を帯びざるを得ませんでした。なぜなら、それは、それ自体の内に究極的な十全性を据えるのではなく、あくまでもその究極的十全性(つまりキリスト)を「指し示す」ものでなければならなかったからです。さらに、復活モチーフが表現される特定の方法というのは、有機的に開かれつつある過程における「成長」の特定段階と、常に調和しているのです。
例えば、ノアの時代、人類はまだ国々に分化されていませんでした。ですから、適切にも、ノアの家族の「復活」は宇宙的作用域(cosmic scope)を表しています(2ペテロ3:5-7)。イサクの時代には、約束の子孫とアブラハムの相続人が、一人の人間の内に存在していました。ですから適切にも、犠牲と「復活」は、全約束およびその最終的成就を代表するものとして、これに関わっているわけです(参:ガラ3:16)。その他の事例にも同様のことが言えます。それぞれが、クライマックスとしてのキリストの御業の特定の側面を浮き彫りにし際立たせています。そしてそれは、それぞれの出来事が起こる特定の時代および特定の状況にまさしく適合する形で為されているのです。
代表的かしら性(REPRESENTATIVE HEADSHIP)
この歴史的発展の中における統一性(一致;unity)は、人類および宇宙を回復し、再び新しくする神の御働きに内在している統一性です。人類は、かしらとしてのアダムによって代表される統一体(unity)であることを私たちは知っています。(ローマ5:12-21)アダムが堕落したことで、全人類がその影響を受けました。そして被造物それ自体が虚無に服しました(ローマ8:18-25)。それゆえ、贖罪と再創造もまた、代表的かしらであり、新しい人間のかしら、つまり受肉したキリストによって為されます(1コリント15:45-49)。
肉によるアダムの下、一つの人類が存在するように、御霊によるキリストの下に結ばれ一つの新しい人類が存在します。他の被造物がアダムの堕落によって影響を受けたように(ローマ8:20)、それらはキリストの復活によって変えられます(ローマ8:21)。すべての贖われた者のかしらであり代表者としてのキリストご自身が、贖罪と再創造という神の御業における求心力ある統一的中心(unifying center)なのです。特に、キリストの贖いは、人間を神と和解させるだけでなく、人間同士をも互いに和解させます。私たちが神と和解する時、私たちはまた、神と和解の関係にある他の人間と和解します。
例えば、私たちは互いに赦し合うことを学びます(コロ3:13、エペソ4:32)。またキリストがもたらす贖いは人間個人だけでなく、人間の集団に対しても変化を及ぼします。私たちは神の子となり、家族の一員のように互いにつながり合っています(1テモテ5:1)。キリストは私たちを再創造し(エペソ4:24)、神の民である新しい人間共同体へと私たちを導き入れます(エペソ2:19)。そして神に属する民はただ一つでしかあり得ません。なぜなら、キリストは唯一(only one Christ)だからです。そして勿論、キリストの受肉と復活以前には、この唯一性(単一性;oneness)は異なる方法で働いていました。それはキリストの御業が実際に為されるまでは、単に予備的、影のような(shadowy)かたちしか持ち得ませんでした。
しかし私たちは、旧約聖書の神の民のことを、新約聖書の神の民と平行して存在する二番目の神の民と捉えることはできません。それらは――キリストの代表的かしら性を表す公同体の顕現としての――「二つの連続する歴史的段階」です。ディスペンセーション主義者の中には、次のように言う方々もいます。「もしも神が御使いたちにそれぞれ異なる目的を持っていらっしゃるのなら、主はイスラエルと教会に対しても、それぞれ別個の目的をお持ちになっているかもしれないではないですか?」
しかし御使いはこれまで決してアダムのかしら性の下に結ばれたことはありません。そして御使いたちはアダムと共に堕落もしませんでしたし、信仰によってキリストと結ばれることにより罪から贖われたことも決してありません。それゆえに、御使いたちの宿命は、上記のような種類の問いを私たちに突きつけてくるような性質のものではないのです。人間の贖罪問題に関して言いますと、ローマ5:12-21には、私たちがそれに対してどのように考えなければならないのかが示されています。そして、これらの聖句は、原則として、「二つのパラレルな神の民」という思想を排除しています。なぜなら、神の民としての公同の統一体(corporate unity)は、彼らにとっての共通の「代表としてのかしら」から生み出されるものだからです。
キリストの十字架における二分法

歴史的諸時代の間に存在する「多様性」と「非連続性」に対するディスペンセーション主義者の関心について考慮した場合、キリストの生涯の中で起こった事――中でも主の死、復活、昇天――で生じた、歴史におけるラディカルな断絶、この事が特に考察すべき肝要点になってきます。ここに二分法(dichotomy)――すなわち、「以前」と「以後」という二分法が存在します。実にキリストの御業は、真実にして永続する変化をもたらしたのです。神と人間との関係は、それ以後、もはや二度と同じものではあり得なくなりました。なぜなら、今や贖罪が成し遂げられたからです。
それゆえ、イスラエルと教会の間には確かに非常に大きな区別が存在します。しかしその区別は基本的に歴史的なものであって、形而上学的なものではありません。それはキリストの復活「以前」/「以後」を分離する区別であって、「天的」/「地上的」を分離する区別ではありません。
もちろん、キリストは天よりの人です(1コリ15:47-49)。また私たちの国籍も天にあります(ピリピ3:20)。しかしそれは天が神の御座であり、そして全宇宙の刷新のための出発点であり型であるからです。私たちは天を単なる静的《他者》としてではなく、全体を変化させる力源と捉える必要があります。さらに「天」vs「地」のコントラストは、今や「無形で蒸気質なもの」vs「物質的で固形のもの」との間のコントラストではありません。キリストご自身の復活された御体は、まことにリアルであり、まことに有形のものです(ルカ24:39)。
そしてこの方こそ真なる実在です(the really real)。なぜなら、その他すべての肉体的な事物は変化するものであるのに対し(2ペテロ3:10-12)、キリストは永久にそのままに存続されるからです。また、私たちはイエス・キリストとの一致の中で体験している旧約の御約束の成就の内容を気化したり、度を越して個人化すべきではないでしょう。キリストはわたしたちのからだ(our bodies)、そして神の民という共同体の主でもあり、ただ単に個的魂の主だけではないからです。
しかし幾つかの問題がまだ残っています。「ということは、例えば、ユダヤ人のような人々は、ペンテコステの出来事以降、異邦人との間に存在していたあらゆる特異性を失ってしまったのでしょうか?」いいえ、そうではありません。もしもあなたがかつて神の民に属する一員であったのなら、あなたは「命に選び出されている(“marked for life”)」のです。(参:ローマ11:29)神と一度もそのような関係になかった頃とは違う立場に現在あなたは置かれています。ですからそのようなあなたが主に背を向けた場合、あなたの罪責はより深刻なものになります(2ペテロ2:21-22)。
ローマ11章はその事を大変効果的に語っています。何人かのディスペンセーション主義者は、ローマ11章の「オリーブの木」を、「霊的機会や特権に与ることができる場にいるということの象徴」と捉え、そのように解釈しています。確かにそのような意味も含まれていることでしょう。しかしそれはまた「聖いこと」も含意しています(ローマ11:16)。ですから、オリーブの木の一部になることは、1ペテロ2:9で言及されている「聖なる国民」の一員になることと類似しています。またそれはペテロの言う「選ばれた種族、神の所有とされた民」(1ペテロ2:9)であることとも類似しています。
異邦人がつぎ合わされるために、ユダヤ人の中にはオリーブの木から切り落とされてしまった人々もいました。しかし切り取られたユダヤ人はその後も栽培されたオリーブの枝であり続け、そして彼らは再びつぎ合わされることができるのです。これは、そこにただ一つの聖なる(栽培された)オリーブの木――ゆえに、ただ一つの神の民、そして一つの根だけが存在するという事実とまことに整合しています。切り落とされたユダヤ人たちには救いが来ます。――彼らがオリーブの木に再びつぎ合わされ、神の民の一部として彼らの立場が刷新され、再び神との交わりを享受し、根から栄養を摂取するようになる時に。
それではどうして、新約聖書の中には、「イスラエル」と「教会」という二つ別箇の用語があるのでしょうか。一見したところ、これは、「二つのパラレルな神の民」という思想を暗示しているようにみえます。しかし神学というのは、語彙ストックから直接演繹してはならないということを私たちは覚えておかなければなりません(参:Barr 1961; Silva 1982)。実際、新約でのこれらの語の用法はかなり複雑です。といいますのも、「イスラエル」の語使用の多くは、キリストの復活およびペンテコステで起こされた変化「以前の」神の民のことを言及しているからです。また、他の語用法のいくつかは旧約からの引用です。
しかしそれ以上に、旧約の神の民の内、ある人々が神との交わりから切り落とされてしまったという複雑な状況において、幾つかの用語が必要です(ローマ11章)。大概の場合、ユダヤ人のことを指し示すべく「イスラエル」および「ユダヤ人(hoi Ioudaioi)」という語を用いる明瞭な決断がそのまま、「一つの神の民」という――旧約と新約の諸段階の間に存在する――より深遠な概念的・神学的統一性への否定を伴うということにはなりません(参:1ペテロ2:9-10)。
より一般的に言って、聖書というのは、日常語(そして時には文芸語)で書かれたのであって、後代の組織神学者たちの用いるような技術的に厳密な言葉で書かれたのではないということを、すべての聖書解釈者たちは認識する必要があると思います。そして個々の単語の意味は無限に正確であるわけではなく、ある単語が持っている特定の意味というのはその直接的文脈と共に判断されなければなりません(参:Barr 1961, Silva 1982)。
旧約聖書の聞き手による理解

次に、預言を読んだ当時の旧約聖書の受信者はどうだったのでしょう?彼らは語られたことをしっかり理解できていたのでしょうか?そしてどのようにして彼らはそれを理解していたのでしょうか?これらの問いについては第9章で詳説したいと思います。しかし差し当たり申し上げますと、私の考えでは旧約の聞き手たちは預言メッセージを理解していたはずです。しかし私たちがイエス・キリストにある成就を見る光の中で理解するようには、正確に、もしくは完全に理解するには至っていなかったかもしれません。しかし当時、それらのメッセージによって霊的に養われ、励ましを受けるに十分な理解はしていたでしょう。
例えば、新しい出エジプトに関するイザヤの預言(例:イザヤ51:9-11)に耳を傾けながら、彼らはそれが寓意的(figurative)であることに気づいていたでしょう。――つまり、新しい「出エジプト体験」をするべく、自分たちはエジプトに戻ったり、紅海を再度奇蹟的に渡ったり、荒野をさまよったりする必要はないのだ、ということを彼らは自覚していたはずです。そしてこの預言が正確に一体どれくらい「字義的な」形を取ることができるのか結論を出しかねていたかもしれません。どの詳細記述が寓意的なのか、そしてどういう点が寓意的なのか正確には把握できなかったかもしれません。しかし彼らはその預言の本質は知っていました。――それは、最初の出エジプトと同じように力強く包括的な「解放」です。
しかし、このように時として内容が不明瞭である時、私たちはどのようにしてそういった聖句を――特に預言を――理解していくことができるのでしょうか。こういった問いはそうそう簡単に回答を出せないような性質のものです。しかしながら、基本的には、以下のような回答にまとめられるかもしれません。
(1)文法的・歴史的解釈法を用いる。つまり、「その聖句が記述された当時の歴史的・言語学的状況の中で、それが何を意味していたのか?」と問うのです。
(2)「聖書が聖書を解釈する。」明瞭な聖句は時として、より不明瞭な聖句理解を助けます。成就が実際になされる時、それらにより、私たちは預言の箇所をより完全に理解することができます。
(3)主要なポイントは詳細よりも、より明瞭。たとい全ての詳細を理解できているのかはっきり分からなくても、私たちは主要点について確信を持つことができます。聖書が多くの箇所で説いていたり、あるいは強調している内容に対しては、たった一度きりないしは通過的にしか説かれていない内容よりも、その理解により確信を持つことができます。(なぜなら私たちはその詳細を正確に理解できているのかそこまで確かではないからです。)
(4)私たちは、はるか先の御約束や脅威を描いている数多くの預言の「累積的成就」を正当にも期待することができます。
ウィリス・J・ビーチャー(Willis J. Beecher)は、この事について次のように巧みに解説しています。
「事の性質上、――時間に制限されることなく有効な――御約束は、一時(いちどき)に成就され始める場合もありますし、将来複数回に渡って、成就され続けることもあります。」(Beecher 1905, 129)
「ある考証によると、包括的預言(generic prediction)というのは、
①時空的隔たりによって分離され、複数の部分部分から成る出来事の中で起こるものとして、ある出来事を捉える事であり、またこれは
②最も近い部分/より隔たった諸部分/全体、とは無関係に適用されることもあります。――換言すると、一つの複雑な出来事の《全体》に適用される預言というのは、同時に、《部分の中の諸要素》にも適用されるということです。」(Beecher 1905, 130)
「他の人々は、預言の連続的ないしは漸進的成就について述べています。やがて起こるべき出来事は、それ以前の諸出来事(その中のある詳細はそれに類似している)を通して、前もって語られます。」(Beecher 1905, 130)
千年王国と万物の成就を巡っての意見の一致と相違について
千年王国と万物の成就
では、千年王国のことはどうでしょうか?私たちはこれから起こるべき事をどのように見ていけばよいのでしょうか。まず第一に、私たちはキリストの再臨を待ち望んでいます。神の約束はことごとく、イエス・キリストにおいて「しかり。」となり「アーメン。」となります(2コリ1:20)。さらに、すべての御約束は教会に関係しています。――つまり、直接的であれ間接的であれ、すべては何らかの形で私たちに適用することができるという事です。
しかし教会それ自体の中ですべてが成就するわけではありません。その中のあるものは、目下、教会においては全く成就されていません。またあるものはただ部分的に成就されているだけです。預言を学ぶ中で、私たちはそれらの完全なる実現はまだ先のことであるという認識に導かれます。
原則として、この「より完全な実現」というのは、①黙21:1-22:5に描写されている万物の成就としての最終的な「黄金時代」、もしくは②万物の成就とも現在の時とも区分された「白眼時代」(一般には「千年王国期」と呼ばれています)に実現すると考えられます。その中のある預言はその成就を白銀時代にみるかもしれませんし、黄金時代に成就をみるものもあるでしょう。あるいは両方の時代に成就をみる預言もあるかもしれません。
私見ですが、黙示録21:1-22:51の言語が指し示しているのは、万物の成就が、旧約預言の大部分における最大規模の成就となる、という事ではないかと思います。それは無形で触知できないような種類の御国ではなく、新しい天と新しい地であり、その新地は、キリストご自身のよみがえりの御体と同じように物理的(physical)かつ固体的なものでしょう(Hoekema 1979, 274-87; 詳しくは第12章を参)。このように「新しい地」に対する力点は、従来の異なる千年王国見解の立場を互いに近づけることになりました。もしも私たち皆が、「新しい地は最も集約的な成就を表している」という事で意見の一致をみることができるのなら、それよりも小規模な領域に属する幾つかの成就に関する議論は、以前ほど重大なものではなくなるでしょう。
さらに、新しい地に対する強調は、従来のすべての千年王国諸説に、ある決定的にして有益な前進を施しています。大半の無千年王国説論者、前千年王国説論者、後千年王国説論者は三者共々に、千年王国期における預言成就に重点を置いています。その上で、彼らはそれぞれ、千年王国の性質や時期のことを巡ってこれまで意見を違わせてきました。そしてこれは特に、無千年王国説論者側にとっては不利な状況でした。なぜなら、成就に関しての「地的(“earthy”)」性格に彼らはほとんど重点を置いてこなかったからです。
そしてディスペンセーション主義者はこれまで正当にも、彼らのそういった「霊的解釈(spiritualization)」傾向を批判してきました。(Hoekema 1979, 205, 275; quoting Walvoord 1959, 100-102, 298)そのため、黙示録21:1-22:5の「新しい地」を私たちの考察の対象に含めるという事は非常に大切です。しかしながら、たとい私たちがそうしても、「聖書がはたして未来における特定の白銀時代(「千年王国」)の存在を教えているのか否か」を巡り人々は依然として意見の不一致をみるでしょう。
ある人々は「特定の旧約預言の成就のためにはそのような時代は不可欠であり、黙20:1-10はそのような時代の存在を教えている」と考えています。他方、別の人々は、「キリストの再臨によって、罪や罪のもたらす結果に圧倒的な勝利がもたらされるため、その再臨以後、地上における肉体的・可視的キリストの統治は永遠に続き、もうそこでは罪の問題に囚われる必要はなくなる」と考えています。
ここで焦点となっている問題は、再臨のもたらす結果がどれほど圧倒的なものなのかでもなく、どのくらいその預言成就が強烈なものなのかでもなく、「将来の『かの時』に為される成就というのが、キリストが現段階で為してこられた事の有機的継続であるか否か」を巡る問題です。現段階(「この時」)において、キリストは十字架を通し、異邦人とユダヤ人を共に、一つのみからだに統合しておられます(エペソ2:16)。それでは将来的な「かの時」、そこには一種類の神の民が存在するのでしょうか、それともしないのでしょうか?私は一種類の神の民が存在するだろうと申し上げます。なぜなら、彼らをご自身に結び合わせることにより彼らに救いをもたらすのは、ただひとりの「代表的かしら」だからです。
また千年王国を巡る議論に関し、もう一つ申し上げておきたいことがあります。「結局彼らは~~だから~~なのだ」と、相手の見解を批判しようとする際、私たちには思慮深さによる分別力と繊細さが是非とも必要とされるということです。後千年王国説論者は、前千年王国説論者のことを「彼らは悲観主義に陥っている」と批判しています。一方、前千年王国説論者は、後千年王国説論者のことを「今後起こるであろう世界大戦を前に、彼らは救いようがないほどお気楽な楽観主義者である」と批判しています。また往々にして、非難を受けている対岸にいる陣営の人々は、そういった発言を聞いて「自分たちはパロディー化されている」と感じます。
しかし、ライバル体系の観点という《外側から》見たところ、いかにも欠陥あるように見える相手の見解が、その体系自体の観点によって《内側から》観察される時、それはかえって「長所」のようにも見えるのです。そして全ての千年王国説見解がこの種の問題を抱えています。なぜなら、それらは皆残らず、教会史の経路に関し全体的な「ムード(印象)」というものを背負っているからです。そして人々は往々にして、対岸にいる陣営の体系の「ムード」を、全体としての《相手の》体系の枠によってではなく、《自分自身の》体系の枠で読み取ろうとする傾向にあります。ですから、それそのものの実態以上に、相手の見解が、より弱々しいものであるかのように見えます。
現在、私たちはディスペンセーション主義者のことに焦点を当てていますから、私は一つこれらの人々に関わる事例を挙げたいと思います。ディスペンセーション主義者であるチャールズ・L・フェインバーグ(Charles L. Feinberg, 1980, 77; quoting Ryrie 1963, 44)は、彼自身の歴史観について次のように述べています。

「歴史の目指す目標に関し、ディスペンセーション主義者たちは、この地上に建てられる千年王国にそれを見い出している。それに対し、契約神学者たちは、それを永遠の状態に見い出している。だからと言って、ディスペンセーション主義者たちが永遠の状態の栄光を軽視しているわけではなく、私たちが主張しているのは、人間の歴史における主権者なる神の栄光の顕示は、新しい天と地においてだけでなく、現在の天と地においても見られなければならないという点である。こういった歴史目標に対する認識観は、楽観主義的であり、且つ、その定義の要求にも適合している。他方、契約神学側の見方では、歴史を『善悪の間に生じる連続した現行の闘争』とみており、それらは永遠の状態の開始の時点で終結させられるまで続く、、という風に彼らはみているわけだから、それは明らかに現在の歴史の中において何ら目標を持っておらず、ゆえに、悲観主義的である。」
私たちはこれをどう受け止めたらいいのでしょうか。前千年王国説論者は一般に、後千年王国説論者によって「悲観主義的」と非難されています。「なぜなら、彼ら前千年王国説論者は、主の再臨まで、キリストの王国の可視的勝利を後回しにしているからです。」
しかし前千年王国説論者たち自身は、そのようには捉えていません。フェインバーグやライリーなどは特に、自分たちは真に楽観的であると主張しています。フェインバーグやライリーが「主の再臨」を考える時、それに関して彼らが持っている観念は、後千年王国説論者のそれとは異なっています。彼らは主の再臨後の時代を、現行の歴史との基本的「連続関係」を持つものであると捉えています。そして彼らは、歴史を、ただ単に自分たちの時代の彼岸にあるものであり、それゆえ希望無きものであると捉えるのではなく、「いやむしろそれは歴史の絶頂期である」と考えています。
しかし、現在の時間の枠組みにおいて、後千年王国説論者が見ようとしている「勝利」を、前千年王国説論者は目に見える形では持っていないため、後千年王国説論者たちの枠組みの《内側から》見た時、前千年王国説論者たちは悲観主義的に見えるのです。
それでは今度は、他の人々に対する、フェインバーグとライリーの批判に注目してみましょう。冒頭の引用で、フェインバーグは、「他方、契約神学側の見方では、、明らかに現在の歴史の中において何ら目標を持っておらず、ゆえに、悲観主義的である。」と評しています。もちろん、フェインバーグやライリーが言っている事は、契約神学のすべての見解に当てはまるわけではありません。それは、契約神学的な前千年王国説や後千年王国説に当てはまるのではなく、ただ無千年王国説だけに該当するものです。しかしその無千年王国説に限っても、彼らの批判は歪んだものだと言えます。
実際、彼らのこの無千年王国説批判は、後千年王国説が前千年王国説に関して犯しやすい種類の誤りと同一のものです。ライリーの枠組みの《内側から》見ると、歴史の目標そして歴史の絶頂は、新しい天と新しい地が到来する前に、現行の歴史のただ中に到来しなければなりません。もしそうでなければ、私たちの現時代は(古い地の終焉までにも拡大されるものとして今や捉えられた上で)希望無きものになる。。――そのように彼には見えているわけです。
しかしこれは少なくとも「何人かの」無千年王国説論者の捉え方とは一致していません。例えば、上述のアンソニー・ホエケマ(無千年王国説論者)は、新しい地に関し、特別な力点を置いています(1979, 274-287)。彼は言います。「新しい天と新しい地における万物の成就は、全くの新しい開始ではなく、今あるもののトランスフォーメーション(変化、変容)である。キリストの復活のからだと、復活前のからだの間に連続性があるように、そこには依然として連続性がある。」それゆえ、ホエケマのような無千年王国説論者は、「歴史」を、天地の刷新を「通し」それを「越え」続いていくものであると捉えています。
そして彼らは、最終的な万物の刷新を(あたかも万物の刷新以降は、まったく時間感覚が存在しないかのように)「時間」と「永遠」の間の区分としては考えていません。彼らはそれを「ゼロからの再出発」としてではなく、「新しい創造」(2コリ5:17)としての信者の刷新に類似した刷新だと考えています。ですから万物の成就に対しての彼らの見解は、――罪が完全に無くなるという点を除くと――古典的(歴史的)前千年王国説の「千年王国観」に非常に似ています。そして彼らは言います。「キリスト再臨の時にいかなる勝利がもたらされるかに関し、私たちはむしろ前千年王国説論者たち以上に楽観的なのです」と。それに対し、フェインバーグやライリーはもちろん、「いや、勝利は『現行の歴史(“temporal history”)』の中にもたらされなければならない」と言うでしょう。
しかし「現行/一時的(“temporal”)」、「歴史」といった用語は、ディスペンセーション主義者の体系の中では、上述のホエケマ型の無千年王国説の体系とは異なる機能を持っています。フェインバーグやライリーは、新天新地の到来前に、勝利が成し遂げられなければならないと主張していますが、彼らの意味する「新天新地」というのは、無千年王国説論者にとっての「新天新地」とは異なる意味合いを帯びているのです。ライリーは、ディスペンセーション主義は楽観主義的で、無千年王国説は悲観主義的だと言います。しかしそのような批判は、彼が意図的に、――無千年王国説論者たちが最も深大に楽観しているところの――その一つの時代を除外して後、初めて為し得るものです。その意味で、ホエケマのような無千年王国説論者にとって、ライリーの批判は、誤解や疑問を生じさせるような種類のものであるに違いありません。
一つの譬えを出しましょう。これはあたかもライリーが、自分の自家用車(セダン)と、無千年王国説論者の小型トラック(pickup-truck)との間で「一つ、競争をしようではないか」と提案しているような感じです。

セダン

荷台付き小型トラック(pickup-truck)
ライリーは言います。「さあ、どっちの車がもっと荷物を積めるか見てみようじゃないか。」そうした上でライリーは言うのです。「セダンの方がもっとたくさんの荷を積める。なぜかと言うと、車体の外側にあるゾーンは一切競争ゲームの《対象外》だから!」ライリーにとって、「万物の成就」を加え入れることは、車の上部に、網棚を据え置くような行為に他ならないのです。そういうのは競争の《対象外》とされます。しかし「地的」(“earthy”)無千年王国説論者にとっては、「万物の成就」というのは小型トラックの「後部荷台」に相当します。それに、そもそもピックアップ・トラックというのは、この後部荷台の機能性ために存在するようなものです!
でももし「後ろの荷台使うのはルール違反だぞぉ~」とあなたが彼に言うなら、もちろん、彼は負けます。そういった意味で、ライリーの展開している議論は、恣意的判断による無意味な勝利をもたらしている感が拭えません。
関係改善の可能性
この章で私は、契約神学の中での進展について述べてきました。そしておそらくディスペンセーション神学の中でも進展があったと言って差し支えないのではないでしょうか。第3章で見てきました修正ディスペンセーション主義者の中には、一種類の神の民しか存在しないという見解に立っている方々もいます。この是認一つをとっても、両陣営間にかなりの同意と意見の一致がもたらされているのではないかと思います。
実際、この章で取り上げた点すべてに同意してくださっている修正ディスペンセーション主義の方々もいます。ですから、仮に、千年王国期におけるイスラエルの特異性の問題をマイナーな問題だとして取り扱うことが可能だとするなら、もはや意見の不一致をもたらす実質的領域は残っていないことになります。しかし、この問題に関し、すべてのディスペンセーション主義者/契約神学者が、平和的な立場に立っているわけではありません。ですから一致を妨げているそういった諸問題について私たちは次の章以降、取り組まざるを得ないようです。
単純な反論ではほぼ不可能
「とにかくディスペンセーション主義は間違っている」と考える福音主義クリスチャンがいます。しかし「なぜ/どこが」間違っているのかを示すのは決して容易なことではありません。もちろん、多くの人は自分として満足する形ではその誤りを指摘できるかもしれません。しかし彼らは、ディスペンセーション主義を信奉している誰かを納得させるに足りるだけの説得力を持ってそれを示すことに苦戦しています。なぜでしょうか?
ここには幾つかの重要な問題が絡んでいます。まず第一に、古典的ディスペンセーション主義は、一つの神学体系だからです。そしてこの神学は大いに内的一貫性を持っています。そして、正誤は別としても、入念に精巧に作り上げられた体系というのは、常にかならず「一般的反論に対する回答」というものを持っているのです。そしてその体系のある部分が挑戦を受けようものなら、別の諸部分がすぐさま「応援に駈けつけ」ます。ある程度において、これはどの神学体系にも当てはまることです。
しかしながら、一般的に言って、それは《修正版》ディスペンセーション主義にはそれほど当てはまらないように思われます。第3章でさまざまな修正版ディスペンセーション主義の形態をみてきましたが、こういった修正型は(古典型に比べ)より「緩和な "loose"」諸体系を産出しており、そのため、こういった修正体系は、全体と容易に調和しないような何かであってもそれを各聖句解釈に許す、といった傾向を持っています。それゆえに、本章において私は考察の焦点を古典的な形態におけるディスペンセーション主義に絞ろうと思います。
「生け垣」作り
古典的ディスペンセーション主義における最大の論争点の一つが、旧約預言の本質――特に、預言成就の本質――に関するものです。こういった成就は常に「字義的」なのでしょうか?そして、そもそも「字義的」とはどういう意味なのでしょうか?古典的ディスペンセーション主義者は、「過去におけるすべての預言成就は、純粋に全く『字義的である』」と主張しています。「だから、まだ未成就の諸預言に対しても同じことを期待すべきなのです。それ以外の受け取り方には何ら根拠がありません」と。
スコフィールド(1907, 45-46)は次のように言っています。「比喩(象徴、表象;Figures)はしばしば預言の中に見いだされるが、そういった比喩は常に字義的成就を伴う。そして『霊的』ないしは比喩的預言成就の事例は一つだに存在しない。」
この主張に対し、非ディスペンセーション主義者が効果的に反論するのは非常に困難です。なぜなら、古典的ディスペンセーション主義者は、預言成就という思想の周囲に、「生け垣」を作って自己を防衛しているからです。これらの人々は「預言成就」に関するある思想を持っており、「字義性」という観念は、原則として、反対者が反例を挙げることをほぼ不可能にしているからです。もちろん、新約聖書の中にも「字義的」成就を示す明瞭な事例が存在します。そしてディスペンセーション主義の人々はこういった諸事例を彼らの論拠としています。
しかし非ディスペンセーション主義者が「非字義的」成就を表す、明瞭なその他の事例を持ち出してきたら、その場合はどうなるのでしょうか。(例えば、ルカ3:5、使徒2:17-21、ガラ3:29、ヘブル8:8-12)これに対し、ディスペンセーション主義者はいくつかの供給源を持っています。
まず一つ目に、彼らは、(スコフィールドが言うように)「元々の預言には『比喩』があった」と主張することができます。それゆえ、イザヤ40:1は、バプテスマのヨハネの比喩的預言であり、地形学的な変化を期待するようには私たちに約束しません。しかし「比喩」と「非比喩的な表現」との違いを私たちはどのように識別できるのでしょうか?この違いはいつも誰にでも完全に明瞭なものでしょうか?
ディスペンセーション主義者はこの点に関し、便利な《防衛演習場》を持っています。つまり、時として、彼らはすでに起こった事実に「即して」どれが比喩的で、どれが非比喩的なのかを決定することが可能なのです。彼らは、全聖書がすでに完成し、多くの預言がすでに成就し、「どの預言が自分の体系にフィットし得るのかし得ないのか」を述べ、そのようにして彼らの基本システムの環境が万全に整った後に、都合よく、どれが比喩的であるかについての決定を下しているといえます。
従って、「どれが比喩的で、どのようにそれが比喩的なのか?」といった諸決定は、帰納的基盤というよりはむしろ全体としての「体系」それ自体のもたらす産物だと言えるのではないかと思います。もしくは、それは循環プロセスと言ってよいかもしれません。つまり、体系との整合性に対するニーズが、「何が比喩的であるのか」の決定を補佐するわけです。さらに、そういった諸決定を下す事は、体系の整合性をサポートする特的の諸聖句の聖書解釈を生み出すことを補助します。それゆえ、この「字義性」というものが何を意味するのかについて後章で詳しく取り扱う必要があるでしょう。
ディスペンセーション主義者にはまた、もう一つ別のルートがあります。それは、「明らかに《非》字義的な預言成就は、新約での『成就』というよりはむしろ『適用』である」という主張です。それゆえ、タン(1974, 193-94)は次のように述べています。
「『成就』に対してこれほど広義な定義を付与することにより、〔新約の中での全ての旧約引用において〕非字義的な解釈者たちは、明らかに自分の都合に合わせ偏見をもって事例を解釈しています。なぜなら、そういった定義は確実に霊的な意味を付与した形の成就(spiritualized fulfillments)を示唆しているからです。このテクニックは暴露されるか、もしくは無千年王国説や後千年王国説の立証への論駁は、各書ごと(book-for-book basis)になされるべきです。、、、字義的な預言解釈者たちは、新約記者による旧約引用は、実際の成就を指し示すと同時に、諸真理や原則を描写し、適用させる目的でなされたと信じています。」
もちろん、「旧約の諸原則における新約の『適用』という諸事例」を指摘するタンの言明は正しいと言えましょう。しかし、ここから彼はかなり大胆な結論に飛んでいます。彼は、成就に関する「彼らの」立証は、「各書ごとに(“on a book-for-book basis”)」に検証され論駁されねばならない、しかし、こと自分の立場の立証に関しては、「各書ごとに」取り扱う必要はないと考えているのです。
ここから見て取れるのは、彼自身が、純粋に帰納的な基盤というよりはむしろ、ア・プリオリに自らの立場を決めてしまっていることです。つまり、彼は、もう片方の極端に行き、そして「字義主義」を擁護すべく、事実を偏見眼で見ています。どのようにしてでしょうか?彼は「新約聖書の中における実際的成就を示す事例は、多くの場合、ινα πληρωθη(ギ:‘that it might be fulfilled’ ~が成就するためであった)というギリシャ語の慣例表現と共に導入されている」と主張しています。タン自身はおそらく気づいていないかもしれませんが、これは事実上、解釈者をしてほとんど排他的にマタイの福音書のみに制限させてしまう結果をもたらしています。
なぜなら、マタイの福音書だけが旧約を引用するに当たり、「成就 “fulfill”」という語を通常用いているからです。一方、他の新約記者たちは――彼らの頭の中に「成就」という概念がある時でさえ――他の慣用表現を特徴的に用いています。それゆえ、タンは「非字義主義者」たちに反論の余地を与える際、非常に狭義の基盤(マタイ)しか許していないわけです。一方、タンは、こと自分自身に対しては、自らの立場の弁証手段として、聖書中にでてくるあらゆる「字義的」成就の事例を用いることを自らに許しています。それゆえ、ここに、弁証プロセスにおける深刻な歪みが存在します。それによると、明らかな「《非》字義的」成就は、
①元々の預言における「比喩(象徴;“figures”)」に訴えることで「字義的」とみなされるか、あるいは、
②(「成就」ではなく)「適用」だと言及されています。
そして、明らかな「字義的」はもちろん「字義的」とみなされます。するとどうでしょう?このプロセスが完了した暁には、驚くなかれ、すべての成就が「字義的だ」ということになるのです!それゆえ、(新約期に非字義的な方法で「適用された」諸聖句も含め)未だに未成就の諸聖句もまた、やがて「字義的」成就をみることになる、と結論づけがなされています。そしてこのような議論手法が、いわば、反証を排除する上での「組み込み式内蔵メソッド」となっているわけです。
しかしながら、マタイの福音書における成就を巡ってでさえも、タンは依然として諸問題を抱えていると言えましょう。これらは、彼の手法によっては除去されません。なぜなら、マタイは、(引用する上での)慣用表現の中で「成就」という語を頻用しているからです。そうなると、マタイの福音書の諸成就は一体どうなるのでしょうか?私たちが、旧約の文脈におけるマタイの引用を理解し、マタイの福音書全体の文脈におけるマタイ自身の、成就に関する彼の神学を理解する時、上記のような厳格な字義主義思想にはやはり支障が生じてくるのをみます。そういう意味でも、マタイの福音書というのは、古典的ディスペンセーション主義者との対話の出発点としては適切な書ではないと思います。
というのも、ディスペンセーション主義者であれ、非ディスペンセーション主義者であれ、マタイの福音書における特定の諸聖句を解釈する人々は、自分の奉じる体系からの大域的支配(コントロール)をすでに受け過ぎているからです。また、ディスペンセーション主義者には、(新約における明らかな《非》字義的成就について釈明する上で)さらに、もう一つ別のルートもあります。つまり、彼らは、「イスラエルに適用すべき『字義的』レベルとは反対に、新約聖書は、成就の『霊的』レベルを表象しているのです」と言うことができるわけです。
そしてこれが、教会における、(アブラハムの)子孫の約束の「成就」についてスコフィールドが行なった事でした(ガラ3:29)。そして、このような手法により、イスラエルへの「字義的」成就のレベルが無傷のままで保存されます。そしてもしもこのような手続きが用いられるなら、新約のどのような立証聖句が、ディスペンセーション主義的預言解釈に不利に働くのか見分けが困難になります。もちろん、こういった一連の事があるからといって、それがそのままディスペンセーション主義誤謬を意味するわけではありません。しかし成就の性質に関する彼らの議論の大部分がいわば「循環的になっている;circular」ということは確かに言えます。
そして反論者に対しディスペンセーション主義者の用いている手段は、「自身の陣営での真理の打ち立て」というよりはむしろ、「反証の人工的除去作業」に因るものが大であると言えます。ディスペンセーション主義の反論者たちはここから一つ教訓を得ることができるでしょう。つまり、成就のことを言及している新約諸聖句にフォーカスを置くことは、あなたにとって通常、賢明な事ではないということです。そこに焦点を置いてしまうと、結局、自分自身にも、対話相手のディスペンセーション主義者の論客にも、歯がゆい思いをさせるだけです。それ以上により基本的な問題は、
①何をもって成就の立証とみなすか?
②どのようにその成就が理解されているのか?
にあります。そして、この先行諸問題が、〔ディスペンセーション主義者/非ディスペンセーション主義者両陣営の〕聖句釈義、および体系全般との統合性への各自の取り組み――こういったものを大部分決定づけています。
それゆえ、上記の先行問題が正面から問われない限り、預言成就に関する新約諸聖句は、誰をも説得させるものにはならないでしょう。ですから対話のためには、より良い別の基盤を探すべきだと思います。
ディスペンセーション主義の調和
論客たちはまた、ディスペンセーション主義というのが、かなりの度合いにおいて、調和のとれた統一体であるということを評価すべきでしょう。この体系では、各部位が、ほとんど全ての別の部位と調和しています。論客が、弁証のため、ある聖句を再解釈しようとするなら、ディスペンセーション主義回答者は、自らの解釈を支持するような、二つないしはそれ以上の諸聖句を引用できるでしょう。そうすると、論客はまたすぐさま、数多くの諸聖句を再解釈する必要に迫られます。それではディスペンセーション主義のどんな要素が、このような印象的調和を可能にさせているのでしょうか?そこには、二つの「相補的解釈手順」という合同の働きがあります。
解釈手順1.区別の増産化(multiplying of distinctions)
ディスペンセーション主義者は進んで、――これまで誰もそこに区分を見たことのないような場所に――ある鋭利にしてきめの細かい区分を導入しようとしています。
例えば、「携挙」は「キリストの再臨」と区別されています。(しかし、多くのディスペンセーション主義の方々が認めておられるように、新約聖書の中にはこの二つを区別するような、一貫性ある術語上の相違というものはどこにも存在していません。)また、「神の国(kingdom of God)」は「天の御国(kingdom of heaven)」と区別されており、そのような事例が他にも続きます。(しかし、修正ディスペンセーション主義者の多くは、上述のような多くの鋭利な区別をもはやしていません。この点において人によって違いがあることを私たちは覚えておく必要があります。)
解釈手順2 適用の倍加(doubling the application)
解釈手順1を補完する形で、単一の聖句の中における、単一の表現の適用を2倍にするという二番目の手順が存在します。この手順に従い、多くの預言的諸聖句は、イスラエルにおいて地上的成就を果たし、教会に対しては「霊的」適用ができるとの解釈がなされています。(参:図表2.2)〔手順1〕が、言葉の上では類似の諸聖句を細裂(さいれつ)させるのに対し、〔手順2〕は、単一の聖句を、二つの異なるレベルの成就につないでいます。
さて、原則としては、聖書の中に、これまで認識されていなかったようなある種の区分を見い出すことは可能です(手順1)。また、一つ以上の成就ないし「適用」を含む聖句も存在し得ます(手順2)。しかし、こういった手順による適用に付随する危険性についても私たちは認識すべきです。もし私たちが1)&2)両方の解釈手順を頻用し始めるなら、聖書の異なる諸聖句を調和させるための選択肢の数が急増します。
こうしてある聖句を解釈するに当たっての、私たちの持つ柔軟性は非常に増します。それゆえ、「正しくはない包括的体系という傘下においてでさえも」、調和や整合化は比較的容易になります。ディスペンセーション主義者は正当にも、「ディスペンセーション主義は、その大部分において、調和がとれ、安定し、一貫性をもった体系だ」と感じておられます。しかしそういった整合性は、ある解釈学的企図の産物である場合が多々あります。そしてそういった解釈は、
(1)区分の増産化、および
(2)関係性の倍加作業
によって、人為的に生み出された整合性になり得ます。それゆえ、ディスペンセーション主義の場合で言いますと、整合性や調和は、真理の裏付けとはならないのです。
また、私たちは、ディスペンセーション主義の背景が、この調和を促進させるのに貢献したという事実にも留意すべきでしょう。ダービーもスコフィールドも法曹界で働く弁護士でした。そして両者とも、数多くのテクストを、論理的に調和させ、かつ単一の整合する体系に整えることにおいて、かなりのスキルを持っていました。もしも彼らの聖書的・解釈学的土台が正しいのなら、もちろん、それに越したことはありません。ですが、仮にそうでなく、誤った諸前提を基盤にしてでさえも、それでもやはり彼らは、かなりの調和性を持つ体系を構築することができていたでしょう。
さらに、彼らの強みが、文法的・歴史的解釈よりもむしろ、論理的調和および現代への適用の内にあったことは覚えておくべきです。既存教会に対する非常に否定的な態度により、ダービーは、実質上、歴代のキリスト教会が生み出してきた学術的省察や解釈の果実を使うことから、自らを切り離してしまっていました。もちろん、現代のディスペンセーション主義者は、この体系内における文法的・歴史的解釈を洗練させるべく努めてこられました。
しかし、私の判断では、古典的ディスペンセーション主義内部でのそのような解釈の試みは、依然としてやはり、この包括体系の持つ諸前提や固定された考え方に支配される傾向が強く、この体系は、――ディスペンセーション主義者が特定の諸聖句を検証しようとする際にすでに先行的な形で作用しています。後の章でみていきますが、文法的・歴史的解釈は、古典的ディスペンセーション主義においては、今も脆弱点として残っています。
いろいろな社会的要因
次に、ディスペンセーション主義のグループ内に存在する心理学的・社会的諸要因について触れておきたいと思います。心理学的・社会的諸要因というのは一般に、これまで私たちがずっと慣れ親しんできた解釈体系を後にすることを困難なものにします。共有された世界観や諸教理を持つどんな文化/サブカルチャーにおいても、ある程度において、結束性(粘着性)を持つ社会的要因が働いています。(参:Berger and Luckmann 1967)
確かに社会的諸要因それ自体は、ある特定の世界観や教理の真理を擁護・反証する価値を持っていません。しかしながら、ある社会集団の構成員にとって「明瞭」「当たり前」「常識的」と思われている事がらが、《外側にいる人々》にとっても同じように「明瞭」であるかというとそうではありません。
ダーウィニズムへの対抗

ディスペンセーション主義者の間に働いている一つの特別な因子というのは、ダーウィニズムに関しての破壊的諸勢力に対する、彼らの反動です。諸科学の発展と共にダーウィニズムは、――キリスト者個人ないしは、少なくとも《準》キリスト教価値観に対する――従来の広範な西洋文化的コミットメントを抜本的に弱体化させました。こういった風潮の中で、ディスペンセーション主義は、聖書の諸真理の持つ厳密さに重点を置くことにより、科学の主張する、いわゆる「正確な諸真理」という挑戦に答えようとしてきました。
また、聖書の用いる比喩・象徴的な、そして「完全に明瞭ではなく、完全に正確でもない言語」は、なにかマイナスのものであるかのように見えるきらいがありました。それゆえ、「聖書の言語には高度の正確さがあるという事を信じる必要性」および「聖書の言語をできる限り、比喩・象徴的な方法では解釈しないようにしなければならない」という事に対するプレッシャーがディスペンセーション主義者の内にありました。ですから、ある方々は次のように考えておられます。「ディスペンセーション主義を離れることは、すなわち、聖書が現代科学の諸基準にも立派に対峙することのできる書であるという主張を捨て去ることであり、また、正確で明瞭な聖書言語を取り扱うことによって得られる確実性を捨て去ることにつながる」と。
主観性への恐れ
第二番目の要因として挙げられるのは、主観性に囚われることに対する恐れ(the fear of subjectivity)です。ディスペンセーション主義者はこれまで、聖書の意味が、主観的偏見を基に、近代主義者たちによって歪曲されているのを目の当たりにしてきました。そして往々にしてこういった偏見は、本格的な宗教「体系」や世界観による影響を受けています。ですから、当然のことながら、ディスペンセーション主義者たちは、そういった偏見に裏打ちされたものを拒絶しようとしてきました。主観性に統治された聖書解釈というのは非常に間違っています。しかしながら、主観性そのものに対する恐れというのは、ややもすれば、解釈における明白な省察(explicit reflection)を拒絶する方向へと私たちを導きやすいのです。
ある人は、ただ聖句テクストの「平易な(“plain”)」意味に訴えようとします。そういった聖句は、すでに「平易な」意味を持つものとしてそこに存在しているため、解釈者の考え(input)をほとんど必要としません。そういうわけで、この人が、このレベルで聖句に取り組み続けるなら、彼は、最大限の客観性に裏付けされた確信を持つことができるとされます。一方、別のある人が今度は明示的に、他の多くの解釈諸原則を検証していると仮定してみてください。この人は物事をそうそう当たり前には受け取りませんし、それに間もなく彼はこう気づくのです。
――確かにここには、他にも可能な選択肢というものが存在する。そして選択肢の存在というのは、個々の特定の聖句テクストの解釈に対してだけでなく、解釈諸原則の形成や構築に対しても当てはまるのだ、と。
諸原則それ自体は(部分的には諸聖句に訴えることによって)正当化されなければなりません。しかしその際、このプロセスが循環的になってしまう恐れがあります。そうすると、その人の中で、自分の純粋な客観性についての確信がかなりぐらつきます。*25
解釈学的省察
さらに、解釈学的省察というのは、「聖書解釈に及ぼす全体的諸体系の影響」についての省察も含み得ます。実際、ディスペンセーション主義者であれ、契約主義者であれ、カルヴィニストであれ、アルミニウス主義者であれ、近代主義者であれ、とにかく神学体系というのは、私たちが所定の聖句に接する方法に対し、深遠な影響を及ぼしています。世界観や社会的文脈というのは、私たちが知覚する内容、「明瞭なもの」として前提する内容、強調を置く内容に影響を与えているのです。
もちろん、ディスペンセーション主義者の中には、聖書解釈について省察し、それについて著述しておられる方々もいます。しかしそういった省察にあってでさえも、こういった方々はご自分の解釈諸原則を最初から前提しておられるように私には思えますし、実際、非ディスペンセーション主義者はまさにその前提部分について、ディスペンセーション主義の方々ともっと議論や話し合いを深めたいと願っているのです。特に、幾人かのディスペンセーション主義者は、聖句の『平易な意味』という、あくまで未分析な考えをベースに聖書研究に取り組んでおられるように外部者の目には映っています。
「気づいていないこと」に対する気づき
三番目の影響領域として挙げられるのは、大半のディスペンセーション主義の人々が、聖句に対する「統一されたディスペンセーション主義読み方」に寄与している一連の社会的要因に気づいていないという事実そのものに存しています。ディスペンセーション主義者は、聖書が平易であり、解釈者はこの「平易な」意味に忠実でなければならないと力説しています。しかし不幸なことに、私たちと聖書記者との間を隔てる歴史的距離ゆえに、そういった従来の聖書記者たちの意図は、必ずしも常に平易であるとは限りません。私たちが一般信徒の方々に聖書の意味は「平易だ」と勧める時、彼らはそれをどのように受け取るでしょうか。傾向的にみられるのは、彼らは私たちのそういった勧告を、元々の歴史的文脈の中ではなく、21世紀の文脈、それも自分たち自身のサブカルチャー文脈で読むよう奨励されているのだと受け取ってしまうことです。
こうして聖書は、元々の読者たちだけでなく、私たちのためにも直接的に書かれた書となります。「それでは、聖書の指し示す『私たち』とは誰のことを指しているのだろう?」――それはやはり、ディスペンセーション主義的に聖書を読むクリスチャンの集まりに違いありません。一般信徒であるディスペンセーション主義者にとって、「平易な」意味というのは、仲間のクリスチャンたち(その仲間たち自身もまたディスペンセーション主義者です)から日頃、見聞きする教えや規範の背景を基に自動的にそれらを聖句に読み込むところの「意味」です。
それゆえに、彼らにとっての「平易な意味」というのは往々にして、ディスペンセーション主義体系の枠組みを通して見た時の聖句の意味となることが多いのです。ここから次のような反応が生み出されます。時々(ええ、残念ながら、「しばしば」と言わねばならないかもしれません)、非ディスペンセーション主義者は、「えっ、なぜあなたは私たちとは違う聖書の読み方をしているのですか?」と驚愕するディスペンセーション主義者に遭遇することがあります。彼らの最初の反応は、「この《非》ディスペンセーション主義者ははたして真のクリスチャンなのだろうか?」です。こういった反応が無理からぬのは、平易性に対しての解釈学的説明が次の2点に置かれ、強調される時です。
(1)(ディスペンセーション主義を信奉する)その教会の牧師が、会衆に、「福音主義クリスチャンの間でも、いろいろな解釈の相違がある」という事実を説明しようとしない。
(2)その教会(集会)のメンバーたちが、「自グループのその解釈から脱線すること」と、「聖書そのものを拒絶すること」とを同一視し始める時。
それと同じような社会的傾向により、学究的な古典的ディスペンセーション主義者の間であってさえも、1世紀の教会の神学的環境についての、幅のある省察が比較的乏しいと言えます。〈非〉ディスペンセーション主義の新約学者たちにとっては少なくとも、古典的ディスペンセーション主義者による新約解釈というのは、「各書を1世紀の記者たちの1世紀の聴衆者に向けられた諸書として読もうとする純粋な試み」というよりは、むしろ、「すでに完了したディスペンセーション主義体系という背景をバックになされた解釈である」とみなされています。
しかしディスペンセーション主義の方々はおそらくそうは考えていないことだろうと察します。そのため、これは話し合いの起点としてはあまりふさわしくないでしょう。新約学者たちはしばしば、聖書の記者たちの著述の「内側に」入り込んで、聖書を読もうと奮闘します。それにより、彼らは聖書記者たちが言った内容だけでなく、「なぜ」そのような仕方で記者たちが言ったのかを理解しようと努めているのです。どのような種類の懸念が彼ら記者たちの生涯や説教に命の息吹を与えていたのでしょうか?このような懸念を背後に、次のような中心的問いがもたらされます。
「もしも新約聖書が――《自覚的》古典的ディスペンセーション主義者である――当時の人々によって書かれたのだとしたら、はたして新約各書は、現在私たちが目にするような書であり得るでしょうか?」〈非〉ディスペンセーション主義の新約学者たちはこの問いに関して「否」と答えています。
ここで一つ譬えを出したいと思います。全体としての新約の教えは、――教会がそれ以降、三位一体およびキリストの二つのご性質についての信条を形成していった――その基盤を形作っています。こういった信条形成は、新約聖書に固く基づいており、聖書の教えと完全に調和しています。しかし新約記者たちは、後に統合された省察の中で自覚的に得られたこれらすべての教義を、必ずしも保持していたわけではありません。
例えば、使徒たちは私たちの救いに関し、純粋にして最終的な真理を記述しました。しかしこういった使徒たちが、三位一体教義について、後のアウグスティヌスやナジアンゾスのグレゴリオスと同じような、自覚的・技術的洗練性なるものを必ず持っていたに違いないと想像するのは時代錯誤的といえましょう。私はここで、アウグスティヌスがパウロよりも「良い頭脳」(もしくは劣った頭脳)を持っていたと言っているのではありません。そうではなくただ、アウグスティヌスの意識的省察が、使徒パウロのそれとは異なる方向に焦点を向けていたということなのです。
それでは、これをディスペンセーション主義に関する状況と比べて考えてみましょう。私が申し上げたいのは、「使徒たちは洗練された《自覚的》ディスペンセーション主義者であった」と考えるのは時代錯誤的だということです。そのように主張するのではなく、ディスペンセーション主義者はむしろ、ただシンプルに、「私たちは正当にも、自らの教理の全体性から、後に形成されたディスペンセーション主義体系を演繹し、統合したのです」と述べるべきではないでしょうか?そしてもしそうであるなら、新約の歴史的理解は、精神面における、私たちと使徒たちの間の距離をも考慮に入れることでしょう。
ですから、私たちは、マタイやパウロやヨハネやヘブル書の記者を、できる限り、彼ら自身の言葉で、つまり、「内側から」理解しようと努めます。そういう意味でも、やはり、使徒たちは《自覚的》古典的ディスペンセーション主義者のようには考えていなかった。――これが〈非〉ディスペンセーション主義学者たちの大体の所感です。そして、〈非〉ディスペンセーション主義者は、「預言成就に関する聖書解釈という点で、新約記者たちの神学は、古典的ディスペンセーション主義の基本原則と相いれない」と考えています(on this hermeneutics, cf., e.g., Dodd 1953; Longenecker 1975)。
新約記者たちは皆、前千年王国説論者であったかもしれませんし、皆、無千年王国論者であったかもしれませんし、中には特にこれといった確信を持っていなかった人もいたかもしれません。しかし全ての人は、キリストの初臨・再臨その両方において、キリスト及びキリストの民の内で為される成就という考えを中心に置いていました。そして(千年王国ではない)この中心的主題こそが、未来に関する1世紀のクリスチャンの教えを支配していたのです。
しかし、こういった事を議論する際、私は皆さんに1世紀の教会に訴え出ないことを勧告したいと思います。1世紀の教会の神学的環境および、新約理解に関する教会の立場の評価に関しては多くの要因が関与しているからです。また、ここまでの考察により、ハル・リンゼイの『地球最後の日(The Late Great Planet Earth)』を初めとする「センセーショナルなタイプ」のディスペンセーション主義についても、より良く理解することができるでしょう。

一度ある人が、「聖書は21世紀の文脈で直接的に書かれているのだ」と前提し始めるなら、聖書と、最新の政治的・社会的ニュース事件の間を細かく関連づけようという試みは、何といっても魅力的なものになります。そして、このような重大な前提が一旦受容されるなら、そこからもたらされる結果は決して馬鹿々々しいものではなくなります。
恵みのみによる救い
最後のポイントになりますが、ディスペンセーション主義者は、恵みのみによる救いの純粋性を保ち、この恵みに基づく確信を保持したいと心を配っています。救いの確信は御約束に対しての神の誠実さに深くかかわっています。しかしどのようにそれらの御約束は解釈されるのでしょうか?もしも御約束が「平易」でなかったとしたら、私たちの確信は脅威にさらされます。さらに、ディスペンセーション主義者はこれまで熱心に、「神の多くの御約束は無条件である」という考えを擁護してきました。そして御約束の無条件性は、それらが言及されたまさにその形態において、成就することを保証します。
こういった「無条件性への願望」も、科学的に正確な言語という理想に彼らが惹かれている一つのほのかな要因なのかもしれません。家庭や職場においての日常言語の中で、言明ないし約束は暗示的資格や諸条件を含んでいます。例えば、「5時にはあそこにいるから。」というフレーズには、しばし、暗示的な理解――つまり、「もしも急用がなければ/もしもあなたが約束をキャンセルしなければ」といった含み――と共に発言されることが多くあるのです。一方、科学的領域において、諸資格ないし諸条件は、略さず詳細に説明されなければならないものとされています。ですから、聖書を科学的言語になぞらえようとする行為は、そこに多くの無条件的約束が存在することに対する強調を促します。
もっとも、この点においてもヴァリエーションが存在します。大半の修正ディスペンセーション主義者は、子孫および土地に関するアブラハムへの約束は無条件であるけれども、預言成就に関わる私たちの参与は、信仰によって条件づけられていると考えています。そして私はこの立場に同意します。
社会的諸要因に対する評価
さて、ディスペンセーション主義の安定性や魅力に貢献している社会的諸要因についてはこれ位にしておきましょう。それぞれの要因の背後には、「良い」動機や「良い」原則の要素があることに私たちは留意すべきです。しかしそれぞれの要因において、その「良いもの」は歪曲され得ます。
まず「私たちは精巧な科学に対し回答しなければならない」という懸念について考えてみましょう。ディスペンセーション主義者のこういった反応の背後にある良い原則は、神聖な権威および聖書の信頼性についての原則でしょう。しかし、ここにはまた危険性も存在します。つまり、この原則をなんとか尊守したいと熱望する余り、正確性のための人為的現代基準や技術的言語を押し付けることによって歪みが生じるかもしれない危険性です。
次に、主観性に対する恐れ、そして聖書の「平易性」に対する主張についてはどうでしょうか。ここでもまた、背後には、聖書の明瞭さについての原則という「良い原則」が存在します。救いのために必要な事柄は聖書の数カ所ではっきり言及されていますので、学ぶ事に遅い人でもそれらの十分な理解に達することができるでしょう。しかしそうだからと言って、聖書のあらゆる箇所が等しく明瞭であるわけではなく、また明瞭な聖句も、すべての点において明瞭であるというわけではありません。それゆえ、それは、「全て(あるいはほとんど全ての)聖書箇所の意味は非常に明確なので、平均的な読者はすぐにその意味を把握することができる」という見解には相当しません。明瞭性の原則というのも、無誤性の原則と同様、過度に単純化され過ぎたり歪曲されたりする危険性があります。
次に、聖書解釈に及ぼす「伝統からの影響問題」についてはどうでしょうか?聖書解釈の最終決定を行使するローマ・カトリック教会の主張に反対し、宗教改革者たちは、「教会の伝統は聖書に並ぶもう一つの権威ではない。そして、教会の伝統は絶えず、聖書の批判の支配下になければならない」ということを強調しました。そして、この要素、つまり、教会の伝統に関わる一切を排除するというのが、ディスペンセーション主義者の内にみられる真理の要素としての傾向であると思います。しかしながら、宗教改革の原則は、「教会の伝統は存在しない」「私たちは、聖書を解釈する方法において、完全に教会の伝統の影響を排除できる」ということと同一ではありません。
それでは、恵みによる救いおよび無条件の御約束に対するディスペンセーション主義の愛好についてはどうでしょうか?この懸念の内に存在する真理の要素は、明白であり重要なものです。キリストは完全に私たちの救いを成し遂げ、私たちに代わって完全に神の義を満足させてくださいました。それゆえに、救いは保証されているのです。またそれは、キリストがすべての条件を満たしてくださっているという意味で無条件です。旧約聖書のアブラハムへの御約束は究極的に、キリストの来臨を通して与えられる恵みに依っています。しかしその事実は、私たちクリスチャン側の従順や訓練の必要性を除去するものではありません。キリストの救いおよび救いの保証は、信仰の行使における、キリストとの一致の中でのみキリスト者たちに可能とされます。そして真の信仰は死んだ信仰ではなく、愛によって働く信仰です(ガラ5:6、参:ヤコブ2章)。
純粋な恵み(ガラ5:4)と純粋な信仰(ガラ3:2-14)のためにあれほど力強く戦っていたパウロは、これまた同じ手紙の中で、邪悪さの中に生き続けながらも肉的〔救いの〕確信にうつつを抜かしている者に対し、警告の言葉を容赦なく発しています(ガラ5:13ー6:10、特に6:8)。パウロは「もしも。。。なら。。」という"if" の言葉を用いることを躊躇せず、悪しき行いの者たちには永遠の滅びを警告しました。生活にも忠実さにおいても全く変化の伴わない、単なる口先だけの信仰は、人を永遠の救いへ導きません。なぜならそのような信仰は偽善的だからです。その他の聖句の中の無条件的言語は、こういったタイプの資格(適格性)から独立したところで作用はしません。
私たちは、恵みに関する新約の教説を過度に単純化し、それをアンチノミアニズム(無律法主義)に変質させてはなりません。それゆえ、従順に関するあらゆる旧約聖句そして、「条件」について述べているあらゆる聖句を、恵みに対するアンチテーゼ的対立の内にある単なる「律法」だとレッテルを貼ることは、事を単純化し過ぎています。今日、多くのディスペンセーション主義指導者の方々が、この危険性に気づき、自らをアンチノミアンの極端から切り離そうとしていられることに私たちは感謝すべきだと思います。*26
本章で皆さんとご一緒に見てきました社会的諸要因その一つ一つは、ある意味、そのどれもが「確実性への願望」に関連することに留意すべきです。確実性に関するもっとも基本的形態は、救いの確実性を含めた、聖書の基本的諸真理に関する確実性です。律法および、人間の責任に対するその強調/警告が導入されることにより、救いの確実性は容易に脅かされます。そういう意味でも、「律法」と「恵み」の間の鋭利な区別、そして無条件の御約束に対する強調は、ディスペンセーション主義の魅力を形作るものとなっています。実際、ダービー自身、キリストの内にある自分の天的位置についての確実性へ「解放された」文脈の中でディスペンセーション主義を開始したことも注目に値します。
変遷する世の中で
次に、移り変わる世の中での私たち自身の役割に関し、ディスペンセーション主義は確実性への願望に訴えています。それでは科学による諸変化についてはどうでしょうか。科学の発展は、人類の種の起源についてのダーウィニズム見解および「世界は巨大な自治メカニズムである」という科学による前提ゆえに、聖書の内に存在する私たちの確信を揺らがせ弱体化させているのでしょうか。こういった脅威に対抗し、ディスペンセーション主義は、聖書の信頼性に確証を与えようとしています。しかしこのプロセスの中で、聖書をあまりにも現代科学の規準に合わせようとする危険に陥ることにもなりかねません。特に、「字義性」に対する強調は、時として、聖書を現代科学に同化させてしまう危険性を持っています。
政治情勢の変化
では、政治的そして社会的世界における変化についてはどうでしょうか。ディスペンセーション主義は、「預言」と「私たちの時代」との間に、ある種の関連性を見い出すことを奨励しています。こういった関連性の確立は、信奉者たちに、一見恐ろしく不穏にみえる世界情勢の出来事に対する深い志向と理解を提供し得ます。基準点として現代の出来事を聖書と統合させることにより、それを聞く人たちは、自分自身の立っている立場に関する正当性を再確認することができます。つまり、彼らはさまざまな出来事に関しての一貫した解釈を持っているわけです。「センセーショナル版」ディスペンセーション主義は、まさにこういった理由で非常に人々の心を掴みやすいのです。

解釈における確実性
ディスペンセーション主義は、「聖書解釈」の面においても、一般信徒の方々に確実性を提供しています。現代のこの世は、ノン・クリスチャンの非合理主義および自律という主観性が非常に強勢を誇っています。こういった潮流に抗し、ディスペンセーション主義は平易性を主張しています。そして社会学的相対主義化ないしは、真摯な神学論争のさなかに突如として現れてくる懐疑の問題に対し、一般に広く受け入れられているヴァージョンのディスペンセーション主義は、聖書解釈においての影響力ある要因としての「教会伝統」――これに対する基本的非認識を打ち出しています。また、学術的諸問題や周到な文法的・歴史的解釈に関わる多くの未回答の問いに対し、ディスペンセーション主義は、一般読者に対する聖書の有効性を保証しています。
ある体系の中にいることでもたらされる確実性
そして、もちろん、ある「体系」を持ち、それに関わることで確実性がもたらされます。(この点・あの点でそれが正しいか間違っているかは別として)およそ「体系」と名の付く物は、多くの回答を提供してくれます。ですからその体系を離れ去ることは、何か空虚の中に迷い込んでいくもののように感じられます。それゆえに、人々は、その体系を離れるよりは、体系の中に存在する数多くの「困難点」ないしは明らかな矛盾をむしろ我慢する道を選ぼうとするのです。しかしこういった種類の問題を抱えているのはディスペンセーション主義だけだと考えてはいけません。ディスペンセーション主義者ではないあなたや私はどうでしょうか?私たちには確信があるでしょうか。それとも私たちは心もとなさに不安な思いをしているでしょうか。そうです、私たちにもまた、確実性に対する願望があるのです。
そして神は、イエス・キリストとの一致を通してたしかに私たちに確実性と安定感を提供してくださっているのです。しかしここで私たちは自分自身に自問する必要があるでしょう。――果たして私は、キリストの羊の一人であることの他に、何か別の安定感を求めてはいないだろうか?
羊であることは、安全であることを意味します。そしてそれはあなたが全ての回答を得ているからではなく、あなたがキリストのご配慮の内にいるからなのです。
誤った方法での安全性追及
私たちが誤った方法で安全性を求めるなら、それは他の人々を助ける私たちの能力に支障をきたらせます。例えば、私たちは自らを正当化させるべく、論敵たちを激しく非難する習慣を身に着け、それによって、「自分は正しい位置にいる」という感覚の内に安定感を補強しようとするようになるかもしれません。
ですから、ここまでの私たちのディスペンセーション主義分析は、「ディスペンセーション主義が誤っている」という事を示すためのものではありません。そうではなくむしろ、(ディスペンセーション主義者も、〈非〉ディスペンセーション主義者も共に)私たち皆が、一度立ち止まって、自らの歩みを振り返るための意図をもって書かれています。自信過剰気味の方に対し、このメッセージは次のように言います。
「あなた自身気づいていないかもしれませんが、あなたの信じている信仰内容に及ぼしている諸影響というものが存在します。 そして、あなた自身もしくは他の人々の抱いている悪い動機(混在した動機)が、秘かな方法であなたの信条の純粋性にダメージを与えている可能性は実際あるのです。あなたが他の人から教えられ、無批判に受け入れてきた隠れた前提(思い込み)はもしかしたらあなたの聖書理解に影響を及ぼしているかもしれません。あなたの信条はことごとく神から来たものであることに、あなたは本当に確信を持っていますか?それは本当に確かですか?それとも、あなたがそれらの教えの幾つかを鵜呑みにしたのは、あなたの尊敬するあの牧師がそれをあなたに説いたからではないでしょうか?そのことを深く考えてみたことはありますか。そして、あなたとは違う解釈をしている人々の弁証にまともに耳を傾けることもしないままに、どうしてあなたは自らの信じる教えの詳細にそこまで自信満々になれるのでしょうか。」
一方、弱気になり自信を失いかけている人々にはこう語りかけます。
「あなたは教師たちからこれまで受けてきた教育上の恩恵を含め、あなたに与えられている賜物を使うべきです。あなたは自分の持っている知識を教会の中で大いに役立てるべきです。そして聖書が言っていることを大胆に説き明かすべきです。しかしあなたはそれを教会の中で他の方々からの助言や矯正を受けながら行なうべきです。(あなたの信仰体系に属する陣営の外側にいるクリスチャンも含め)他のクリスチャンの見解に耳を傾けることは、それによって神が私たちを真理に導き入れる上で主が私たちに賜った道の一つなのです。」
ディスペンセーション主義の朋友との対話のために
ディスペンセーション主義の是非をめぐって人々が議論を始めた場合、何が起こるのでしょうか。最初の小競り合いは、たいがいの場合、神学的なものです。人々は、教理問題に関し、終末の出来事に関し、クリスチャンと旧約律法の関係などに関し、互いに意見の食い違いをみます。しかしそういった議論はすぐに特定の聖句に関わるものへと移行していきます。人々は釈義(exegesis;ある特定の聖句に帰する意味)のことで意見を違わせます。しかし釈義だけでは十分ではないのです。なぜなら、相違の本質は、解釈(hermeneutics;聖書解釈のための一般諸原則)を巡ってのものだからです。ですから、解釈学的問題に真っ正面から向き合わない限り、対話はその実をみることが少ないでしょう。
釈義の適切性
それでは、私たちは議論を、解釈学的原則のレベルに絞るべきでしょうか?いいえ、そうはすべきではないでしょう。大半のディスペンセーション主義の方々は(取り扱う諸原則が解釈学的なものであれ神学的なものであれ)ただ一般諸原則だけを基に議論を進めることに懐疑的ですし、そのように感じるのは正当なことだと思います。
彼らは特定の諸聖句をベースに議論したいと望んでいます。それゆえ、聖書解釈に関する省察は、釈義と結び付いていない限りあまり有益なものとはならないでしょう。しかし釈義は、議論の中で取り扱う聖句の数が増えるに従って脱線しやすいというのもまた事実です。熟練したディスペンセーション主義者/〈非〉ディスペンセーション主義者は両者共々、自由自在に数多くの聖句を駆使することができます。
一つの聖句の解釈で困難に直面させられるや、彼らはすぐさま他の聖句に訴えます。というのも(彼らの考えの中では)、そうすることによって、最初の聖句の解釈が正しいということが明示されるからです。そうすると対戦する論客は、ムッとなります。なぜなら、彼は相手の示すそういった聖句の一つでさえも、その解釈に同意できないからです。そのため、彼はさらに多くの聖句を持ち出してきてそれらを解釈し直す必要に迫られます。
聖書聖句というのは、一度に一か所のみを取り扱ってはじめて効果的・徹底的に議論可能なものですから、上記のような議論の仕方では、それぞれの側がただ、自陣営の正当性および、相手陣営の愚鈍さを確認した、と思うだけに終始するでしょう。それぞれの側がただ単に聖句を、ゲシュタルト(形態)に照らし、そして自分の体系に照らしつつ見ています。そして「体系」それ自体がその他数多くの立証聖句を用いつつ、構築されているのです。そしてそういった数多くの聖句は、外部者に自分の体系をとことん釈明すべく用いられます。
ディスペンセーション主義の方々になんとか納得していただきたいと願っている非ディスペンセーション主義者の一人として、私は次に挙げる二つの箇所が特に有益ではないかと思いました。一つはヘブル人への手紙12:22-24、そしてもう一つは1コリント15:51-53です。この二か所を選んだのは、これが古典的ディスペンセーション主義者が自らの見解を再び考え直す良いきっかけとなる箇所ではないかと思ったからです。そして古典的ディスペンセーション主義者自身が、反対方角へ持っていく議論のベースとして、自身が選ぶであろう諸聖句に関しての、最良の判定者になるのではないかと思います。どちら側の議論も、お互いから学ぶという意味で歓迎されるべきです。ですが、私はディスペンセーション主義の方々がご自分の見解を表明するようには、この方々の見解を表明することはできませんし、それができるようなフリをするつもりもありません。
それではこれから、ヘブル12:22-24と1コリント15:51-53およびそれに関連する解釈学上の問題に焦点を絞っていきたいと思います。私は、古典的ディスペンセーション主義の皆さんができるだけ理解しやすいような形で、これらの聖句と解釈学的諸原則を注視していくつもりです。尚、〈修正〉ディスペンセーション主義の皆さんにとっても、古典的ディスペンセーション主義の方々との対話の中で、これらの聖句は有用かもしれません。
それから、〈修正〉ディスペンセーション主義者と、〈非〉ディスペンセーション主義者との間の対話ですが、そうですね、どの聖句箇所がみなさんの対話にベストなのか正直、定かではありません。〈修正〉ディスペンセーション主義者と〈非〉ディスペンセーション主義者は、それぞれの陣営の内にかなりの多様性を持っています。さらに、第3章と4章で見てきましたように、多くの点で両者の見解は近いのです。その意味で、ヘブル12:22-24および1コリント15:51-53も、依然としてみなさんにとって、かなり興味深いものかもしれません。しかしすでに両者の間に存在するかなりの度合いの同意と一致ゆえ、こういった聖句を巡っての対話は、異なる外観を帯びることになるでしょう。
では、古典的ディスペンセーション主義者との対話の場合はどうなるのでしょうか?この場合、聖句テクストそれ自体に訴えるだけでは十分ではありません。みなさんは交互に「解釈学的諸原則」にも、そして「釈義」にも訴えることができるようなやり方で議論を進めていかなければなりません。
そうした時初めて、根柢部分に横たわっている解釈学的諸原則が表面に浮かび上がってくるでしょう。鍵となる諸聖句を用いることで、解釈者は具体的な方法で、解釈学的諸原則を取り上げることができます。そしてそれにより、古典的ディスペンセーション主義の解釈学的実践は、その理論自身に従っておらず、また従い得ないことが示されるでしょう。上記の二つの聖句テクストを用いた議論に加え、対話のために大切なことは、「この聖句においては少なくとも二通りの解釈が可能である」ということを率直に認めることではないかと思います。一つは、古典的ディスペンセーション主義体系の中で作用させた時に理に適う解釈。そしてもう一つは対話相手の奉じる体系の中で作用させた時に理に適う解釈です。
この方法により、論客たちは二つの積極的目的を果たすことができます。一つは、彼らが、相手の立場に立って物事を考察し、いたわりの心を持って相手の見解に耳を傾けることで対話相手のディスペンセーション主義者と友情を築くことができることです。また彼らはこういった対話を通し、より良く聖書を学ぶことができます。そしてディスペンセーション主義の聖書解釈者であることが一体どのようなものなのかをより良く知り、学ぶことができます。彼らは言うでしょう。「ああ、なるほど!こういった諸原則を用いるなら、確かに『この聖句の意味は~~だ』という主張は理に適ったものであることが分かる!」と。
そして彼らは、古典的ディスペンセーション主義の枠組みの《外側から》見た時にはクレージーに思えるような事柄であっても、それをヤジったりするようなことをもはやしなくなるでしょう。それと同時に、彼らはディスペンセーション主義者に対し、「全体としてのこの体系自体が、釈義をする上での重要なinput(投入)になっているという事実」――これに対するより良い認識を対話相手に提供することができるかもしれません。その際に、みなさんは二つの包括的フレームワーク(枠組み)を相手の前に広げ、それを提示します。(一つはディスペンセーション主義の枠組み、もう一つは相手の非ディスペンセーション主義の枠組みです。)
そうした上でみなさんは言います。「さあ、それぞれの枠組みが特定の聖句に適用される際、どのように働くのか見てみることにしましょう」と。それにより、これが一つの聖句の意味を巡っての愚鈍さの問題でもなく、他の立証聖句の存在に関する知識の不足といった問題でもないことがより明らかにされるでしょう。
特定の神学的諸問題
ディスペンセーション主義の福音主義クリスチャンと、非ディスペンセーション主義の福音主義クリスチャンを隔てている神学的諸問題は、短時間で口頭で話すことが難しい種類の問題です。なぜなら、多くの場合、それらは数多くの聖書テクストの内容統合にかかわっているからです。一般に、神学的統合に関する真剣な取り組みというのは、聖書精読や黙想の時が最良でしょう。しかしそれでも、論客は口頭で手短にこういった神学的諸問題のことを述べることで、相手のディスペンセーション主義の方が後にそのことを熟考する機会を提供することができるでしょう。以下に挙げる三つの領域における省察がもっとも有意義なものだと思います。
第一番目に、旧約の御約束についての教会の相続に関する事柄があります。1
ここでの神学的問題のエッセンスは、とてもシンプルに提示することができます。旧約の御約束の中のどれが、キリスト相続人(Christ heir)に向けられているのでしょう。キリストはイスラエル人なのでしょうか。キリストはアブラハムの子孫なのでしょうか。そしてキリストはダビデの相続人(跡継ぎ)なのでしょうか。これらの問いに対する回答は、「どれほど多くの神の約束があろうとも、それらはことごとく、キリストにおいて『しかり。』となります」(2コリ1:20参照)。
それでは、こういった御約束の内どれが、キリストと結ばれたクリスチャン相続人に向けられているのでしょうか。神学的に言えば、この問いに関して「その全てです」と回答することに抵抗するのは困難です。と言いますのも、「キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなたがたは、キリストにあって、満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威のかしらです」(コロサイ2:9-10)。また人は「天的な」祝福と、「地上的な」祝福を、手際よく小ぎれいに分割することもできません。なぜなら、そこに存在するのはただひとりのキリストであり、私たちはそのキリスト全体を受け取っているからです。からだのよみがえりとキリストにある万物の更新はまた、存在の物質的側面にも及んでいます(ローマ8:22-23参照)。
パウロが言うように、「私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして、御子といっしょにすべてのものを、私たちに恵んでくださらないことがありましょう」(ローマ8:32)。そしてパウロが「世界」(“world,” κόσμος)は私たちのものと言った時、それは決して誇張ではなかったのです(1コリント3:21-23)。このテーマに関しては第12章、13章で再びご一緒にみていきたいと思います。
それから第二番目の神学的問題は、旧約のシンボリズムの性質に関することです。旧約の中での神の啓示に漂う雰囲気は、終末論的希望で満ち溢れています。そしてこの希望は終わりの日に焦点を置いており、天的な神の住まいを目指すものです。故に、そのような文脈においては、終末論的預言の最も「字義主義的(“literalistic”)」な読み方はベストなものではないと言えましょう。この問題に関しては、第8-11章で「字義性(“literalness”)」の意味を考察する際に、詳しくみていきたいと思います。
第三番目に、論争の中で聖書自体がどのように使われているのかといった問題があります。つまり、こういう事です。:ディスペンセーション主義者を、〈非〉ディスペンセーション主義者から最も違わせている問題の一つ(いや、おそらく最も肝心かなめとなる問題)は、旧約聖書の解釈問題であるということに、皆さん同意してくださると思います。そしてこの問題はそれ自体の内に、①「ディスペンセーション(経綸)」ないしは天啓史に関する問題、②「イスラエル」と「教会」の問題、③聖書解釈における「字義主義(“literalism”)」に関する問題を内包しています。さらに、「旧約預言の解釈問題」はこの問題の鍵となる下位区分(subdivision)に相当します。ですから、私は、以上のことが考察すべき神学上の中心課題だと考えています。
それではどのようにして、この主題に関する聖書自身の教えを見い出すことができるのでしょうか?――それはもちろん聖書を読むことによって、です。ええ、その通りです。しかしこれは壮大なプロジェクトです。では、聖書のどこか特定の箇所で、この主題についてより直接的に言及し、聖書の中の他のどの書よりも詳細にその事を述べている書は存在するのでしょうか?ええ、私は存在すると思います。それはずばり「ヘブル人への手紙」です。そしてもしそれがそうならば、私たちは旧約聖書解釈に関する私たち自身の教理を「主として」この書をベースに考察していくべきだと思います。
例えば、信仰義認の教理の場合、私たちはローマ3-4章、ガラテヤ3章という二大聖句から始めます。その後私たちは、その教理とヤコブ2章のようなよりマイナーな聖句を統合します。しかしその際、もしも私たちがその手順を逆さまにし、逆向きにしてしまったらどうなるでしょうか?仮に私たちがある主要聖句箇所を、一つの「構想」にフィットさせよう、適合させようとしているとします。しかしその「構想」たるや、わずかな数聖句からほとんど全面的に引き出されたものであり、しかもそういった聖句の意味も、それ自体においては絶対的に明確というわけではないのです。
このような手順を取る時、私たちはかなり誤謬や歪曲の道に陥りやすくなってしまいます。そこで私は、自分自身にも、そしてディスペンセーション主義の朋友たちにも、次のことを提案したいと思います。皆さん、これからご一緒に、ヘブル書を読み、学び、黙想することに心を注いでみませんか?そして共に祈ろうではありませんか。主よ、どのようにして正しく旧約聖書を解釈し、正しく新約と旧約の関係を理解することができるのか、どうか私たちを教え導いてください。
そしてどうか「自分の見解をバックアップしてくれるようなヘブル書理解の方法があるのか、ひとつ見てみることにしよう」といった態度で聖句に臨む人が一人もいませんように。どうか私たちがただ単に自分たちの既存見解を裏付けることにひたすら固執するような態度を取ることがありませんように。そうではなく、できる限り純粋に、そういった既存見解を一旦脇に置きましょう。そして――もしもヘブル書の内容のどこかが私たちに指摘するのなら――、御言葉によるそういった批判に進んで自らを従わせましょう。そしてヘブル書が導く所はどこであれ、その場所において、私たちが、謙遜な御言葉の聞き手であることができますように。
こういった訓練にリスクはないと思います。聖書は私たちを逸脱から守ることができます。ですから、自分の安全ゾーンをなんとか確保しようと、これまでの既存信条に堅くしがみつく必要はないと思います。実際、私たちがこれまで大事にしてきた諸見解に対して聖書が何らかの挑戦をすることを許さず心を開かないなら、そのような状態こそかえって私たちにとって安全でない状況になり得ます。さらに、こういった共なる学びは、おそらく自分自身の立場に関して迷いがある方、どちらの見解を従ったらいいのか今も優柔不断の状態にある方にとっては、最良の学びの時になるのではないかと思います。
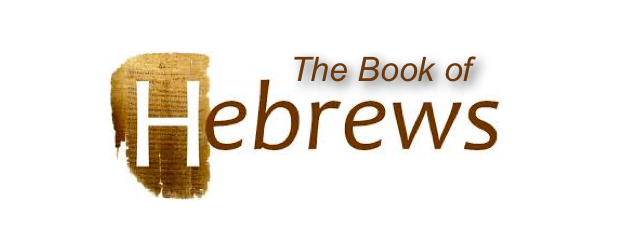
そして、おそらく神が私たちにヘブル書を提供してくださった理由の一つは、私たちが安全で確実な出発点を見い出し、そうして後、旧約の解釈という複雑なプロセスに私たちを導き入れてくださるためではないかと思います。実際、これは自分自身の人生の中でも実証されました。私にとっても、ヘブル人への手紙を用いたこの聖書の学びは決定打の一つとなったのです。ですからきっと他の多くの方々の人生の中でもそのような事が起こるのではないかと私は思っています。しかしヘブル書自体、壮大なテクストですので、他に取り扱わなければならない諸テーマのこともあり、本書ではその全てについてお話することはできません。しかし第12章で、私たちはヘブル書の一つの鍵となる聖句、つまり12章22節から24節までをご一緒にみていきたいと思います。
患難期前携挙説にとっての問題聖句 1コリント15:51-53
終わりのラッパ(THE LAST TRUMPET)
「字義的(“literal”)」解釈原則という極めて重要な課題に取り組む前に、いくつかの問題を例証している特定聖句をご一緒に見ていきたいと思います。今、念頭にあるのは、1コリント15:51-53です。これはディスペンセーション主義についての議題における、最も有益な二つの聖書箇所の一つです。なぜなら、これは根柢にある解釈学的諸原則を表面に浮かび上がらせる聖句だからです。ディスペンセーション主義検証においてこの箇所は必ずしも決定的な聖句ではないかもしれませんが、それでも対話相手との肯定的なコミュニケーションを築く上での最初のアイスブレーカー的な感じで用いることができるのではないかと思います。

患難期前携挙説(情報源)
1コリント15:51-53は、患難期前携挙説にとっての問題聖句です。なぜなら、この箇所は「終わりのラッパ」(=「最後のラッパ」〔新共同訳/岩波訳〕、“the last trumpet,” τη εσχατη σαλπιγγι)のことが言及されてあるからです。さて、古典的ディスペンセーション主義理論では、1コリ15:51-53は、携挙のことを言及した箇所だと解釈されています。携挙の7年後、(選ばれたユダヤ人たちが集められるマタイ24:31の出来事と関連して)、目に見える形でのキリスト再臨がある際に、今度はまた別のラッパが鳴ります。そうなりますと明らかに、1コリ15:52で描写されているラッパの音は、本当のところ「最後の」ラッパの音ではないということになりそうです。
一方、(古典的ディスペンセーション主義理論に反してですが)仮に、1コリ15:51-53の「携挙」と、マタイ24:31の「可視的再臨」が実質的に同時に起こるとしますと、二つのラッパはおそらく同一のものとなり、そこに解釈上の問題は何もありません。それゆえに、この二か所(1コリ15:51-53とマタイ24:31)を調和させるに当たり、ディスペンセーション主義理論には、明らかなる困難があります。さて、この困難点に対し、ディスペンセーション主義者は標準的回答を持っています。実際、この回答は、ディスペンセーション主義体系の内部においては、きわめて「明白な “obvious”」ものです。
おそらくこの体系の一般諸原則に、ある程度通じていらっしゃる方なら、その回答がどのようなものか察しが付くだろうと思います。そしてこの点における私の懸念は、そこに回答が有るか無いかの問題ではなく、解釈学的問い――つまり、その回答が『いかにして』得られたのか?――という懸念です。私たちは絶えず、解釈学的問いをし続けなければなりません。――〈私が1コリント15:51-53を理解し、それをマタイ24:31と調和させようとする際の「諸原則」はいったい何だろう?〉
古典的ディスペンセーション主義者がこれらの諸原則について話す際、私たちにこう言います。「私たちは聖句を『字義的 “literally”』ないしは『平易に “plainly”』解釈しなければなりません。」それでは1コリ15:51-53の「字義的」解釈とは一体何なのでしょうか?ここでいう「字義的」とは、特定聖句の解明を助けるあらゆる文法的・文脈的・歴史的手がかりをフルに考慮に入れるということを意味すると思われます。それは時に大変な努力を要します。しかしそれはやはり健全なものでしょう。また、「字義的」であることは、私たちにとって、もっとも「平易 “plain”」ないしは「明らかな “obvious”」ものに固持することを含意し得ます。さて、この原則に同意した場合、私たちは次のような議論を展開することになるでしょう。
「えーと、1コリ15:52の『平易な』意味は、これが最後のラッパ(終わりのラッパ)だということになると思います。つまり、それ以後は、もうラッパは無いということです。あなたは私に、『私たちは聖句を《字義的に》解釈しなければならない』とおっしゃいますし、確かに、私たちが《字義的》であろうとするなら、ここの聖句があたかもそれ以外の何か他の事を言っているかのように主張することはできない話です。そこでマタイ24:31をみますと、そこにラッパのことが言及されているのですが、マタイの福音書のこのラッパは、
①1コリ15:52と同じラッパか、もしくは、
②それ以前に鳴り響いたラッパか
という二択になりますよね?というのも、1コリ15:52のラッパは、何と言っても「最後の」ラッパですから。(つまり字義通り、文字通りに「最後」という意味です。)そしてマタイ24:30ではすでに、目に見える形での再臨のことが述べられています。そうなると、目に見える形での再臨は、『携挙』で信者のからだが変えられるのと同時期に起こっているようにみえます。繰り返しになりますが、『1コリ15:51-53を解釈する際、それを《字義的に》解釈しなければならない』とあなたは私におっしゃっていますので、従って、『携挙』と『再臨』の間に7年間の隔たりがあるということを私は信じることができないのです。」
こういった結論を避けるため、幾通りかの提案がなされるかもしれません。まず第一に、ある人は、「ラッパは一つしかないけど、そのラッパから複数の音響(blasts)がでている」と提言するかもしれません。しかしこの説明は立ちゆきません。なぜかといいますと、1コリ15:52はラッパの「音(sound)」のことを言及しているからです。これは、「長く続く一連の最後の出来事に関連した音響(blasts)のために使われる、単一の固定したラッパがある」というよりは、やはり、「神のラッパの最後の音(sounding)であること」を明らかに含意していると言っていいでしょう。
二番目に、「ラッパの音はおそらく7年間続く」と提言する方がおられるかもしれません。しかしこの説明もまた立ちゆきません。なぜなら、1コリ15:52は、そこでの動きの迅速性を強調しているからです。死者のよみがえりは、――ラッパがずーっと鳴り響くある長い長い時間のスパンの中で行なわれるというよりは――、連続的に終わりのラッパの音に続いて行われるものです。ええ、それが少なくとも、この聖句の「もっとも平易な(“plainest”)」理解の仕方のように思われます。
それから三番目に、「マタイ24:31は目に見える形でのキリストの再臨のことではなく、携挙について述べているのです」と言われる方がいるかもしれません。しかし一節前にあるマタイ24:30の「字義的」解釈は、否応なく確実に、それが目に見える再臨のことを言及しているという結論に私たちを導きます。もちろん、上記のような議論は、私たちが「ごつごつした」意味において「字義的」であろうとする中で生じて来るものです。しかしたとい私たちが健全な文法的・歴史的釈義によって1コリント15章とマタイ24章を理解しようと努めたにしても、やはり、これらの聖句は、「携挙」と「再臨」を同時期のものとしてみることによって、もっとも容易に調和されると言っていいかと思います。
ディスペンセーション主義者の標準的回答
それではJ・ドワイト・ペンテコステ(1958, 189-191)によって提示されている標準的回答に耳を傾けてみることにしましょう。

J. Dwight Pentecost
「最後の("last")という語は、ある計画を完了させるという事を意味しているかもしれませんが、それは必ずしも、いつまでも存続するような『最後』ではありません。教会に対する計画がイスラエルに対する計画と異なっているように、〔教会とイスラエルの〕それぞれが、――二つの終りのラッパを同一のもの/同時期のものとすることなく――「終わりのラッパ」と呼ばれるラッパの音によって完結すると考えられます。、、、(3)教会のためのラッパは、単一です。それはどんなラッパにも先行したことはないので、それは『一連の複数のラッパのうちの最後のものです』とは言えません。患難期を締めくくるラッパは明らかに、一連の七つのラッパの最後のものです、、、(7)1テサロニケのラッパは明らかに教会のためのものです。というのも、神は特別にイスラエルを扱い、一般的に異邦人を扱っておられますので、患難期のこの七番目のラッパは、教会のことを言及し得ません。そうするなら、教会とイスラエルの区別が失われてしまいます。」
ペンテコステは他にも多くのことを言及していますが、その大半は、患難期中携挙説や黙示録11:15で言及されている第七のラッパに関する特定の諸見解という文脈の中で論じられています。次の点でペンテコステは確かに正しい事を言っています。それは、文脈によっては、「最後の」という言葉が絶対的な意味で受け取られてはならないということです。しかしながら、具体的に、いつ「最後の」という言葉が《限定された意味で》理解されるべきで、いつそう理解されるべきではないのか、、、それらを私たちはいかにして決定することができるのでしょうか?その際に、どのような解釈学的原則を使っているのでしょうか。
そして、「最後の」という言葉を《字義的に》解釈するというのは、一体どういう意味なのでしょうか。たしかに時々、「最後の」という語は、限定的属格(qualifying genitive)を伴うことがあります。例:「祭りの終わりの大いなる日に、、、」(ヨハネ7:37)。また「最後の」という語は、明らかな文脈から限定を受ける場合もあります。例:マタイ20:8の「最後に」は雇われた人たちの最後の者と意味しているに違いありません。
しかし、1コリント15:51-53にそのような明瞭限定はまったくありません。その反対に、全体としての聖句は、1世紀のユダヤ人環境が全世界の終わりに関連していたところの出来事に関するものです。そして、そのパースペクティブ(大局観)は、限定されたいくつかの出来事といったものではなく、宇宙的なものです。結局、「最後に」という語を非限定的に理解しないペンテコステの主張は、ただ一つの解釈学的議論に依拠しています。その一つとは、「それは教会にとっての最後であって、イスラエルにとっての最後ではない」という主張です。
しかし1コリントの手紙のどこに、「『終局性(“lastness”)』は教会に関する事柄に限定して理解されなければならない」という言及や暗示があるのでしょうか?1コリント15:20-28の視野は、万物の成就に至るまでの千年王国期全体を含んでいるということにディスペンセーション主義の方々は同意しておられます。そして1コリ15:45-57は明らかに15:20-28での多くのテーマを取り上げています。ディスペンセーション主義者は聖句を「文字通り」「字義的に」取らなければならないと言います。それは、「聖書テクストの中で何ら根拠の見い出されない内容を、聖句の中に勝手に読み込まない」という事を本来、意味しているのではないでしょうか?
それでは、1コリント15:51-53の「字義的」解釈とは何なのでしょうか?これはディスペンセーション主義者が1コリ15:52の解釈で格闘している時、忍耐強くそして繰り返し問われ続けなければならない問いです。最終的に、J・ドワイト・ペンテコステにとっての「字義性」とは、1コリ15:51-53を、すでに彼の頭の中にある「イスラエル/教会の区別」という思想で読むことを意味しているように思われます。つまり、「この聖句はイスラエルの宿命について言及している箇所なのだろうか?それとも教会の宿命についてなのだろうか?」と問いながら聖句に臨むという事です。
しかしそうなると、「字義的」という語には、ディスペンセーション主義二分法という含意があまりにも詰め込まれ過ぎていて、そのため、もはや肯定的で公平な対話のための価値が失われてしまうことになります。確かに、聖書の教理的統一性について高い見方を保持している解釈者であるなら誰でも、ある聖句を理解する際に、聖書の他の諸聖句と調和させるような仕方でそれを理解するよう努めなければならないことを認めています。聖句は、直接的な文芸・歴史的文脈といった観点だけでなく、その他の聖書の包括的全体としての文脈の観点でも読まれ、理解されなければなりません。さらに、解釈者というのは、自分が、聖書教理の総合的形態についての、ある種の諸結論をすでに形成しているということも認識しておく必要があると思います。
彼らは多くの教理的確信を保持していることでしょう。そして、幾つかの聖句からの明瞭な教えを基盤に築かれたそういった確信を、彼らは、――ただ単に新しい一つの聖句が解釈上の困難を起こしているからといって――、そうやすやすと棄てるようなことはしません。それゆえ、ディスペンセーション主義者が1コリ15:51-53の聖句に関し、やっていることは、〈非〉ディスペンセーション主義者がやっていることとそう大差ありません。両者共に、先行する諸判断や確信からの影響の下、聖句を読んでいます。しかしこういったプロセスが、「人々が誤謬を捨て去ることを困難にする要因となっている」という事実は認識すべきだと思います。
ですから、1コリント15:51-53のこの簡略分析それ自体は、ディスペンセーション主義が間違っていることを示してはいません。しかしディスペンセーション主義体系が所定の聖句の解釈に影響を及ぼしているという事実に、より気づくことができたのではと思います。その意味で、体系というのは確かに聖書解釈に影響を及ぼしているのです。そして前述しましたように、これはディスペンセーション主義体系だけに限った話ではなく、他のどんな解釈体系内においても、さまざまな点で類似の現象が起こり得るのです。すべての問題を回避できる人は誰もいません。しかし、鋭利な「神の二つの民」という区別を設けている古典的ディスペンセーション主義内部では、上記のような問題はさらに深刻化します。
正誤は別として、古典的ディスペンセーション主義というのは、聖句に訴えるだけでは論駁ほぼ不可能な体系です。たといそこに解釈上問題となる諸聖句があったとしても、ディスペンセーション主義体系の援助により、ほとんど自動的にそこからの脱出の道が提供されます。「字義的」という言葉がそういった諸問題を隠し覆ってくれます。なぜなら、「字義的」という語の許容範囲がいったいどこまでなのか明瞭ではないからです。ここでいう「字義主義」というのは、自らの体系が窮地に陥った時にはいつでも「イスラエルと教会の区別」という概念を輸入することを許可するような、そのような主義なのでしょうか?
そしてもしも実際に「字義主義」がこういった輸入措置を許しているのだとしたら、それは最も重要な解釈学的問い――それこそ〈非〉ディスペンセーション主義者たちにとっては死活問題であるところの問い――を棚上げしていることに他ならないのではないかと思います。それでは「ある体系がいかにして反論され得るのか?」という事について、ディスペンセーション主義者自身は、どのように言っているのでしょうか。チャールズ・フェインバーグ(1980, 39)は、前千年王国説を検証することに関し次のように述べています。

「第一に、聖書的だとされるある教理が、何らかの困難に遭遇した場合、その人はただ、〔申し立てられた〕その問題の解決は可能であることを示しさえすればいい。そしてある聖書箇所が前千年王国説に相反するという主張がなされた場合には、『釈義の諸規則に従えば、調和は可能である』ということを示すだけで十分である。」
まず初めに、後千年王国説も無千年王国説も、修正ディスペンセーション主義も歴史的前千年王国説も皆、ここでフェインバーグが提言しているものと同じ基盤の上にそれぞれ自分自身の見解を保持することができると私は考えています。それぞれの論者は、自分自身の体系内において「調和は可能である」という事を示しさえすればよいのです。もちろん、堅固な前千年王国説論者、後千年王国説論者、無千年王国説論者であるなら皆、そのことをしっかり主張できるでしょう。ですから、それぞれに異なる千年王国の立場を仲裁・調停するためには、フェインバーグの基準は本当にあまりにも脆弱なものと言わなければなりません。
しかし問題はさらに深刻化します。なぜなら、ここでフェインバーグは、「釈義の諸規則」とは一体何であるかについて未だにうやむやなままだからです。彼の言うこういった諸規則は、1コリ15:51-53のような聖句を取り扱う際に、「イスラエル/教会」の区分を発動させる権利をも含んだところの諸規則なのでしょうか?もしそうなら、私たちは循環的議論に入り込むことになります。この円は次のように循環していきます。
①前千年王国説ディスペンセーション主義は、「イスラエル/教会」の区別の妥当性を明示している。
↓
②この区別は、解釈学的規則に統合される。
↓
③そしてこの規則は、ディスペンセーション主義体系を構築し、調和させるために用いられる。
↺
フェインバーグは続けて次のような事を書いていますが、あまり気強い内容ではありません。(1980, 40)
「すべての預言は、啓示のすばらしい計画の一部である。預言の真の重要性が認識されるためには、全ての預言的計画のこと、そしてご計画の部分部分の間に存在する相互関係の事が念頭になければならない。」
ここでフェインバーグは、ある人が預言を解釈する際、ディスペンセーション主義全体のことが念頭になければならないと言っているように思われます。そして「ディスペンセーション主義の本質的要素は、釈義の諸規則に総合されている」と言っているかのように聞こえますが、みなさんはどう思いますか?もしかしたらフェインバーグは、狭義の意味で、釈義の間に区別を置こうとしているのかもしれません(つまり、最初の引用文)。そして広義の意味で、預言の「重要性」についての評価を下しているのかもしれません(二番目の引用文)。しかしながら、狭義の意味における釈義は当然のことながら、ディスペンセーション主義者が1コリ15:51-53を処置するようには処置しないでしょう。
ここに一つの大きな問題が残されます。「字義的」解釈とは一体何なのでしょう?そして聖句の解釈において、私たちは何を考慮に入れることを許容しても差し支えないのでしょうか。さらに、私たちはいかにして対話の中で不毛な堂々巡り(循環性;circularity)を回避することができるのでしょうか。この種の循環に陥ってしまいがちなのは、何もフェインバーグ一人に限ったことではありません。
古典的ディスペンセーション主義者であれ、修正ディスペンセーション主義者であれ、無千年王国説論者であれ、後千年王国説論者であれ、皆が皆、自分自身の体系で諸聖句を調和させることは「可能」ということを示しつつ、結局ぐるぐる堂々巡りをしている、という事はあり得るわけです。しばし起こることですが、この「釈義の諸原則」というのが、それぞれの体系内で微妙に違った傾斜(見方、観点;slant)で理解された上で、それぞれが自分の立場をますます立派に力強く構築しようとします。往々にして、「字義主義」に訴えることは、聖書解釈における主観性を避けるための一部分だと考えられています。
しかしただ単に、「字義主義」という旗を振りかざしているだけでは、主観性への可能性を本当には回避できません。私たちは自分が「字義的」という言葉を用いる時、それをどのような意味で用いているのか検証する必要があります。そしてそれが含意していること/していないことを明確にするよう努めなければなりません。そうでなければ、結局その人は、外からの知的挑戦や洞察を避け、自らの諸前提や欠陥の内に逃避するだけになってしまいかねません。もちろん、すべてのディスペンセーション主義者が逃避していると言っているのではありません。しかし、逃避していない方々は、そうしている人々がいるということを十分に考慮に入れるべきでしょう。
「字義的“LITERAL”」解釈とは何でしょうか?
それでは「字義的」聖書解釈についてご一緒に省察していきましょう。ある意味、ほとんど全ての問題が、この問いの下に埋(うず)もれていると言っても過言ではないと思います。私たちはこれまで、「字義性」に対するダービーやスコフィールドのアプローチを概観してきましたが、もうすでに、こういった問題の存在に気づかれた方もおられると思います。
彼らのアプローチの中では、厳格な字義性が、「イスラエルと教会の二元的宿命」という、より根本的な原則に従属しているように見受けられます。例えば、スコフィールドは旧約歴史に関しては、その非字義的で、「寓意的(“allegorical”)」な意味を用いることを惜しみなく奨励しています。そして、「絶対的字義性(“Absolute literalness”)」は預言解釈の内のみに見いだされます。しかし、そうではありつつも、スコフィールドによれば、この「字義性」は、預言的言明における多くの「比喩(“figures”)」の存在と両立が十分に可能とされています(Scofield 1907, 45-46)。
そうなると、スコフィールドの意味する「字義的」とは一体何なのでしょうか?あまり明瞭ではありません。おそらく無意識的にでしょうが、この語にはすでに、この神学体系に属する諸前提のいくつかが積み込まれているのかもしれません。しかし全てのディスペンセーション主義者が「字義的」という語を同じ方法で使っている訳ではありません。例えば、修正ディスペンセーション主義者は「字義的」という語をただ文法的・歴史的解釈のことを言及する際に用いているかもしれません。そういう方々にとってこの語は特に何か特別な意味合いはないわけです。その場合、私は彼らに同意します。
しかしディスペンセーション主義関係の著作の大部分において、この語にはなにかしら付加された内包的意味があります。それゆえに私たちはこのキー・ワードをより詳細に検証する必要があります。
「字義的」という語の意味の持つ困難点

「字義的」解釈というものを定義し、より正確にそれを特定する試みは、もちろん望ましいものです。しかし、これは見かけほどそう容易な作業ではありません。チャールズ・ライリー(1965, 86-87)は、自身の用いる「字義性」という語の意味を詳説すべく、「普通の(“normal”)」「プレーンな/平易な(“plain”)」といった関連用語を提示しました。しかし、それ自体では、これもまた不十分です。
正常性(normality)に対する私たちの感覚は、(全体的な世界観をも含めた)私たちの文脈感覚に抜本的に依拠しています*27。スタンリー・フィッシュの論文の内容はここで繰り返さず、私は平行した経路でこの問題を検証していきたいと思います。この問題の一つの主要な側面として挙げられるのは、多くの場合において、文ではなく単語に、「字義的」ないし「普通の」意味があるということです。
さらに、単語にとっても文にとっても、そしてコミュニケーション行為の中のどの点における意味の決定においても、文脈というのが極めて重要です。「どの文脈が考察されるべきで、そういった文脈がいかに考察されるべきか」という点は、意味決定のプロセスにおいて非常に大切です。しかし文脈についてのこういった諸課題は、非常に多くの場合、古典的ディスペンセーション主義者の「字義性」議論の場において、論拠なしに前提されているように思います。ですから私たちはこういった問題をより精密にみていく必要があります。
言葉の意味
それではいくつかの具体例と共に、中心的課題にアプローチしていきたいと思います。ある文章から抽出した次のサンプルをみてください。
"battle"
この語の意味は何でしょう?"battle"という語のグラフィックな象徴は、名詞形の「戦い “a battle”」もしくは動詞形の「戦う “to battle”」となり得ます。
"battle”という一単語を除いて他に何ら文脈が与えられていない場合、私たちはおそらくこれを名詞形の「バトル」として捉えるだろうと思います。実際、名詞形が動詞形からというよりはむしろ、動詞形がその意味を名詞から導き出しています。もし街角で大勢の人に「"battle"というこの言葉を定義してください」とアンケートをとったとしたら、おそらく大多数の人が、「戦闘で従軍すること」(動詞)よりも、「バトル、戦争、戦い」という名詞形で定義づけをすることでしょう。そこから示され得るのは、彼らは動詞形よりも名詞形の方を考えているということです。
大半の単語には、「まず最初に頭に浮かぶ意味」("first-thought meaning")といったようなものが存在します。つまり、「この語はどういう意味ですか?」と訊かれた時に人が自然に答える、そういう意味のことです。もちろん、全ての人が全く同じ事を言うわけではありませんが、それでもある種類の答えがたいがいの場合、支配的です。しかし、ほんの少しであっても何かそこに文脈が与えられるや、語の意味についての私たちの推測には劇的な変化がもたらされます。次の例をみてください。
"to battle"
さあ、これで“battle”が動詞であることがほぼ確実になりました。(ただし、“to battle”が、“Off to battle we go”のように前置詞句である可能性はあります。)そして今も、《最初に頭に浮かぶ意味》として「戦闘に従軍する、戦う」という意味が私たちの脳裏にはあります。それではもう少しだけ文脈を増やしてみましょう。
"I had thorns and briers to battle"
(茨とおどろが、私と戦った。)
さあ、困ったことになりました!この節の「字義的な」意味は何でしょうか。もし私たちが、是が非でも各単語が、「最初に頭に浮かぶ意味」で構成されなければならないと主張するなら、もはやつじつまの合った解釈はできなくなってしまいます。“battle”という動詞が示唆するのは、そこに生命を持った敵がいるということです。一方、敵として描かれている「茨とおどろ」は生命体ではありません。そうなると、この文はおそらく隠喩的なものではないかと推測されます。

茨やおどろ
しかしもちろん、最小限の「比喩度」をもつ解釈も可能ではあります。例えば、一人の庭師さんがいて、彼は近頃悩まされている、庭の「茨とおどろ問題」のことを上のように鮮やかに表現した――そう捉えることはできるでしょう。つまり、この場合、庭師さんは、「雑草を抜く(“keep out”)」に相当するものとして、比喩的な意味で“battle”という語を用いたのだと分析できます。しかしもちろん、隠喩的文は、それ以上のことを暗示しています。それは軍事的状況と、農業の状況との間のアナロジー(類推)を私たちに提供します。
軍事的武器に相当する農業上の何かは存在するでしょうか?ある陣営が「敗北」したかのように見える、そういう農業的「戦い」の諸段階というものが存在するでしょうか?「戦う」という語の使用は、「雑草を抜き取る」という語の使用よりも、もう少し含意するものがあると思います。しかしその度合いがどれくらいであるかは、文脈を見、はたしてその文脈が「戦争」と「農業」の間にさらなる比較を置いているのかを確かめて初めて判断が可能になります。
"Would that I had thorns and briers to battle"
「もしも、茨とおどろが、私と戦えば」
さあ、文頭に付いている「もしも(“would that”)」という表現により、私たちの意味理解に大域的な変化が起こされます。それ以前には、私たちはこの場面が一人の庭師の、実際の経験であるという推測をせざるを得なかったのに対し、今や私たちはその経験がただ単に仮想上の、想像に基づくものに過ぎないことを知ったのです。それではさらに文脈をみてみましょう。
"Would that I had thorns and briers to battle! I would set out against them, I would burn them up together"
「わたしはもう怒らない。もしも、茨とおどろが、わたしと戦えば、わたしはそれを踏みつぶし、それをみな焼き払う。」
これだけの文脈が与えられた今、私たちは「戦い」と「農業」との間にさらに拡大されたアナロジーを見ることができます。「わたしはそれを踏みつぶし」「それをみな焼き払う」という行為は、他の諸都市に対して仕掛ける戦争の中で人が行なうことのできるものです。しかし「最小限に抑えられた比喩度の(“minimally figurative”)」解釈は、こういった全ての「戦争アナロジー(例え)」が、茨やおどろに対する農夫のスキルを表すべくもたらされたと捉えています。
A pleasant vineyard, sing of it!
I, the LORD, am its keeper;
every moment I water it.
Lest any one harm it,
I guard it night and day;
I have no wrath.
Would that I had thorns and briers to battle!
I would set out against them,
I would burn them up together.
「その日、麗しいぶどう畑、これについて歌え。
わたし、主は、それを見守る者。
絶えずこれに水を注ぎ、
だれも、それをそこなわないように、
夜も昼もこれを見守っている。
わたしはもう怒らない。
もしも、茨とおどろが、わたしと戦えば、
わたしをそれを踏みつぶし、
それをみな焼き払う。」
これは何かエデンの園を思い起こさせるような情景ではないでしょうか?――古のエデンもしくは未来の新しいエデンの園を。主の言及が聖書啓示の文脈を示唆しているため尚さらのこと、私たちはその可能性を考えます。この文脈では、エデンの園に関する創世記物語が明らかな背景となっています。それゆえ、私たちはエデンの園のことが暗示されているのではないかと考えるわけです。にもかかわらず、そう考えさせるに絶対的に必要な明白なる言明というのはどこにもありません。もし私たちに全く想像力がなかったとするならば、その場合、私たちは次のように言うことができるかもしれません。「この箇所で主はただ、自分には手入れをしているぶどう畑がある、と言っておられるに過ぎない。これが新しいエデンだとかかつてのエデンの園だとか、そういう事は言っていない。」
実際、これはイザヤ書27:2-4からの引用句です。そして今私がみなさんにこの事をお伝えした際、私は事実上、みなさんにそれ以上にずっと広範囲な文脈を考慮に入れることができるような機会をも提供したのです。つまり、差し上げたこの情報により、みなさんは、イザヤ27章の文脈、イザヤ書全体の文脈、イザヤという人物およびその時代文脈、イザヤ書前後に執筆された聖書の他の部分という文脈などを今や考慮に入れることができるわけです。
そしてこういった文脈の中で、イザヤ27:6は、「イスラエルは芽を出し、花を咲かせ」と言っています。この聖句およびイザヤ5章のぶどう畑のアナロジー(例え)を踏まえると、イザヤ27:2-4の箇所が実際、庭師(<畑を手入れする農夫)およびぶどう畑の全図を隠喩的に用いているということに皆さん同意されるはずです。そしてイザヤ27:4での「戦う」は、「主がご自身の敵に対し戦いをする」という仮定上の戦争のことを考慮に入れています。全体図は隠喩的ですが、「戦う」というこの語自体は、最初私たちが想像していたよりは「より隠喩度の低い(“less metaphorically”)」用いられ方をしているということが明らかになりました。非人格的な茨やおどろとの問題(→非字義的戦い)よりも、個人的な敵に対する戦い(→おおむね "字義的戦い")が視野に入っているのです。
さらに、「戦う」という語の効力は、①戦争の雰囲気に対し私たちがその感覚を保持しているか否か、②庭師の茨とおどろとの葛藤がどのような仕方で戦争になぞられているかに依拠しています。それに加え、全体の文脈を考慮に入れた時、エデンの園への引喩(ほのめかし)は実際に現存しているように私には思われます。エデンにおける平和の型は、イスラエルが将来的に経験するようになるであろう包括的平和を想起させるために用いられています。この平和はもちろん主として、霊的そして社会的方法で自身を顕示しています。しかし、ここで視野に入っている実りの豊かさはまた、字義的な農耕的豊作をも包含しているように思われます。それゆえ、これは申命記的な祝福(申28:1-4)および植物に関連する預言的な予測に関連しています。
しかし留意しなければならないのは、こういった一連の考えは、多くの言葉によって言及されているというよりはむしろ暗示され、遠まわしにほのめかされているものです。ですから、「『確実な』証拠が提示されない限り、自分は散文的で、限定され、『統制された』聖書解釈を捨てない」と言い張る人たちに、こういった遠まわしの言及が実際のものであることを「証明」することはできないでしょう。
字義性を定義する
この例から鑑みますと、「字義的な」意味について語る際に、少なくとも三つの妥当な方法がある言えます。まず一つ目に、単語の「字義的な」意味とは、ネイティブ・スピーカーが、孤立したある単語(つまり、特定の文ないし談話といった文脈から切り離されたところにある語)について訊かれた際に、一番初めに思いつく意味だと言うことができるかもしれません。そしてこれが上述した、いわゆる「最初に頭に浮かぶ」意味です。
それゆえ、battleの「最初に頭に浮かぶ」意味は、「戦い、戦闘」です。「最初に頭に浮かぶ」意味は多くの場合、もっとも一般的な意味です。そしてこれは(常にというわけではありませんが)他の可能な辞書的意味よりも性格において、より「物質的」ないし「具体的」である場合があります。(*他の可能な辞書的意味の中のいくつかは「比喩的」と分類されるかもしれません。)
例えば、burnの「最初に頭に浮かぶ」意味は、「火が燃える」です。これは、燃えるような(=激しい)怒りという時のburnの隠喩的な使い方よりも、より「物質的」ないし「具体的」です。最初に頭に浮かぶ意味、ないしこの意味合いにおける「字義的」意味は、あらゆる「比喩的・象徴的」意味に相反しています。曖昧さを避けるため、私は単語におけるこういった意味を「最初に頭に浮かぶ意味」と呼びます。覚えておいていただきたいのは、これは孤立した環境にある単語の意味です。
しかし、もしそういった単語が文を形成したらどうなるのでしょうか。もちろん、想像の上では、機械的にそれぞれの単語に「最初に頭に浮かぶ意味」をあてがっていき、そうやって文全体ないしはパラグラフ全体を解釈するプロセスを進めることは可能かもしれません。

チョコレートミルクシェイク;(shake=握手する)(情報源)
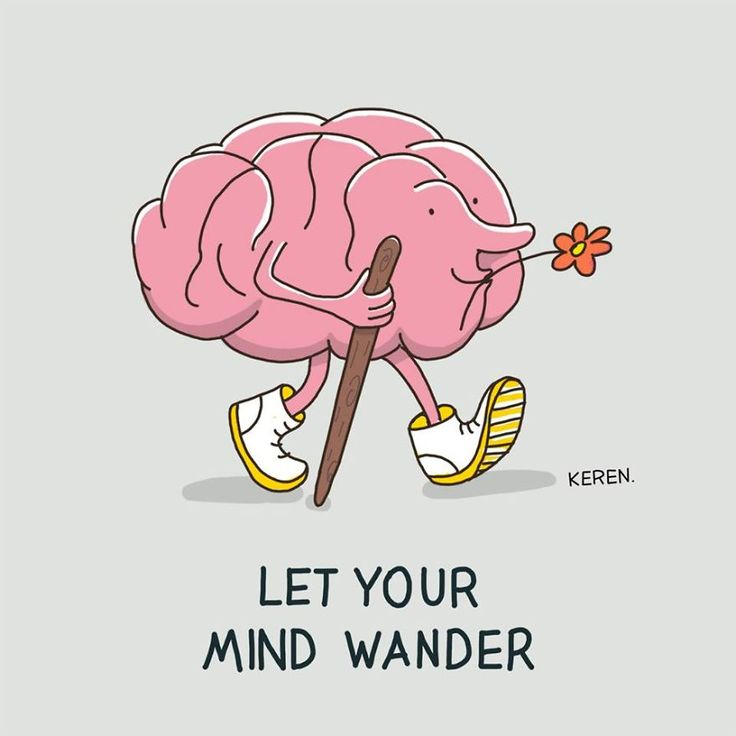
...one's mind(精神) wander(ぶらぶら歩く)=思いがさまよう(情報源)
しかしその結果は往々にして、人工的で、時には馬鹿げてさえいます。なぜなら、これは、単語のどの意味(sense/senses)が実際に「作動するか」という決定の上に及ぼす文脈の影響を考慮に入れていない解釈方法だからです。こういった解釈を、《最初に頭に浮かぶ型解釈》(“first-thought interpretation”)と呼ぶことにしましょう。
それでは、「もしも、茨とおどろが、わたしと戦えば」を例にとってみましょう。この句を《最初に頭に浮かぶ型》で解釈するならどうなるでしょうか?まず、(孤立環境にある)「茨」の《最初に頭に浮かぶ》意味は、「とげのある植物」です。「おどろ」の《最初に頭に浮かぶ》意味もそれに似ています。それから「battle」の《最初に頭に浮かぶ》意味は、「敵軍に対する軍事行為」です。純粋に機械的な方法でこれらの単語をつじつまの合うように結合させることは困難です。あるいは、
―話し手は、次の軍事作戦において茨とおどろを武器として用いたいと思っているのだ。
―茨とおどろが(サイエンス・フィクション的)突然変異を起こし、彼らは意識的に軍隊を組織しているのだ。
と結論づけることもまあ、できない事はありませんが、《最初に頭に浮かぶ型解釈》が、時として奇妙で馬鹿げているのは確かです。
《平べったい解釈》
次に、私たちは、聖句を有機的全体と読みつつも尚、それらをできる限り最も散文的な方法で読んでいくメソッドを考えてみましょう。この場合、私たちは明白なる比喩表現だけはかろうじて認めますが、それ以上の表現は頑として認めません。また、詩的ニュアンス、皮肉、語呂合わせ、それから、その箇所全体が可能性として持ち得る比喩的・引喩的性格なども無視します。少なくとも、そういった表現が完全に明瞭でない時にはいつでも無視するのです。
こういったやり方を、《平べったい解釈》(“flat interpretation”)と呼ぶことにしましょう。これは「可能であれば字義的(“literal if possible”)」式の解釈です。それではここで再び、イザヤ27:2-4を例にとってみましょう。平べったい解釈は、この箇所が残りのイザヤ27章の中に組み込まれている事、それからこの章がイザヤ書全巻の内部に組み込まれていることを認識しています。
しかしこの解釈法においては、イザヤ27:2-5というのはあくまで、「主がやがて、ぶどう畑という形をとる完璧な園芸活動をなすようになることに対する預言」として理解されるに過ぎません。それでも尚、イザヤ27:6の「イスラエルは花を咲かせ」というのは、イスラエルの民の霊的繁栄のことを表す比喩ではないかと認めざるを得ないでしょう。ですからイザヤ27:2-5を、霊的繁栄に対する間接的な言及(暗示・ほのめかし)と受け取るのは自然なことです。しかし、それが確かにそうだという事を「立証する」手立てはどこにもありません。ですから結局のところ、イザヤ27:2-5は、単に農業のことを言っている箇所かもしれないわけです。
その結果、それは、繁栄の一般的主題という観点からのみ、イザヤ27:6と関連づけられることになります。さらに言えば、純粋に農業的な意味における読み方こそが、最も「字義的」です。これは、荒唐無稽に陥ることはなく、尚且つ《最初に頭に浮かぶ型解釈》に限りなく近い解釈です。もしこれがあまりに極端なケースだとお感じになるのでしたら、私たちは、より穏健な事例を取り上げることもできます。仮にある人が、イザヤ27:2-5は、イスラエルに対する神の霊的ご愛護を表す比喩的な描写であることを認めているとしてください。でも、この人は、「いや、でも、エデンの園に対する暗示などというのは存在しない」と今も主張しています。
さて、「エデンの園に対する暗示はない」と言っているこの人が間違っていることを「立証」できる人は誰もいません。なぜなら、たしかにエデンは、ここの箇所で明確に言及されているわけではないからです。これもまた、平べったい解釈です。しかし《最初に頭に浮かぶ型》ほどは平べったくありません。この「平べったい解釈」という用語は、最も極端な事例を指し示すものとして捉えると便利かと思います。そして、そうした上でですが、さまざまな度合でこの極端にアプローチする、複数の他の解釈が存在し得るということを覚えておかれるといいでしょう。
最後に、三番目の解釈法をみてみましょう。この解釈では、私たちは聖句を、有機的全体として読み、各聖句が、元来の聖書記者や当時の状況の事をどのように述べているのかを理解しようと努めます。そして私たちは自問します。「この聖句が書かれた当時、いったいどのような理解や推測が正当だとされていたのだろう?」と。この解釈法は、聖書記者が伝達している意味を伝達しようと努めます。またこれは、きめの細かい暗示や、オープン・エンドな言語を進んで認めようとします。そして、聖書記者たちが、「どこまで暗示表現が拡大されるのか」に関し、一定の両義性やあいまいさの度合いを許している際には、それを認めるよう努めます。これを「文法的・歴史的解釈」と呼ぶことにしましょう。
もし書き手が、非常に想像力に欠けている(ないしは散文的タイプの)人であり、あるいは、その箇所が完全に散文調の書き物のジャンルの一部であった場合、文法的・歴史的解釈は、平べったい解釈と一致します。しかしその他の場合においては、平べったい解釈と文法的・歴史的解釈は、必ずしも常に一致をみるとは限りません。書き手が、より想像力に富むような書き方をしようとしている場合、文法的・歴史的解釈は、――たといそれが、誰も看過できないほど誰の目にも完全に明瞭なものでなくても――私たちが、そういった聖句の中に、暗示、語呂合わせ、その他の間接的伝達方法を探し求めようとすることを許してくれます。
それでは、ディスペンセーション主義の方々が言うところの「字義的」とは一体何を意味しているのでしょうか?彼らが意味しているのは、上に挙げたいくつかの類型の内の一つなのでしょうか?それとも、それとは別のなにかなのでしょうか?ディスペンセーション主義の方々は繰り返し、自分たちは聖書の中の修辞(figures of speech)の存在を認めると言ってこられました。ですから、①その発言を基盤に、そして②解釈学的諸原則についての彼らの言明のもっとも明確にして最良なものを基盤として鑑みるなら、私たちは、彼らがおそらく文法的・歴史的解釈を推進していると理解すべきだろうと思います。
さらに、これまでの解釈学理論の歴史の中で、sensus literalis(「字義的な意味」)という用語は、文法的・歴史的解釈と関連づけられてきました。それゆえ、ただ単に文法的・歴史的解釈を目指すということで、(テクニカルな意味で)「字義的」という言葉を使うことに関しては、そこに歴史的根拠があるわけです。しかしながら、現代の私たちの文脈において、ディスペンセーション主義者による「字義的」という語の度重なる使用は、有益なものではありません。
といいますのも、「字義的」という語が、「比喩的」の対立概念として理解される傾向があるからです。それゆえに、「字義的」という語は、非常に往々にして、上の二つのタイプの解釈法(《最初に頭に浮かぶ型解釈》or《平べったい解釈》)を指しうる状況にあります。
「平易な」解釈(“PLAIN” INTERPRETATION)
「平易な(“plain”)」という語も上記の語に代わる言葉として用いられています。ですが、この語にしても、たいした状況改善にはつながっていません。なぜでしょうか?聖書が書かれた当初に生きていた聞き手たちにはすでに、十分な文脈状況に関する暗黙の了解(気づき)があったのです。彼らは当時の歴史的状況という文脈、文法知識の文脈、彼らがすでに聞き知っていたコミュニケーションの部分に関する文脈といったものを知っていました。
彼らは次の文を聞く前にすでに、こういった豊かな諸文脈を熟知していたため、その文章は普通、彼らにとって「平易な」意味であったわけです。しかし、21世紀の聞き手である私たちが同じ文を読んだ上で、この「平易な」意味とはいったい何だろうと自問する際、私たちが得るのは、21世紀文脈(つまり、私たちの暗黙の知識と切り離せない部分である文脈)の中の文(orパラグラフ)の意味です。
時に、文法的・歴史的な意味は、私たちにとって「平易」とはほど遠い難解さを持っています。なぜなら、私たちは、その当時と現在との間に存在する相違を認識するよう奮闘し、尽力しなければならないからです。さらに一般信徒のディスペンセーション主義者にとっての「平易な」意味とは、――ディスペンセーション主義の預言体系という――すでに彼らの内に存在している既存知識の文脈の中で彼らの心に浮かぶ意味であることが多いのです。
以上の事から、もしや四番目の解釈法が存在するのではないかという可能性に私たちは導かれます。つまり、「平易解釈法」です。これは、解釈する人自身の世界観や歴史的状況という、その人の暗黙の知識の文脈によって、聖句テクストを解釈する方法です。そしてこれは元々の歴史的・文化的文脈の持つ役割を極小化させます。文法的・歴史的解釈が、「平易解釈」と違う点はまさにこの、解釈のための主要な歴史的・文化的文脈に関する論点にあります。
「平易解釈」は、すべてを、あたかもそれがダイレクトに、現代文化に生きる自分自身に向けて書かれているかのように読んでいくことです。それに対し、文法的・歴史的解釈は、すべてを、それが元々の聖書記者の時代・文化の中で書かれたものであるとしつつ読んでいくことです。もちろん、私たちが、現代文化・サブカルチャーの中で書かれた現代文学を共に解釈していくなら、その際には、両者は同じです。こうしてみてきますと、どうやら「字義的」とか「平易」という語にはある種のマイナスな障害があるようです。
もしも、ディスペンセーション主義者が、《最初に頭に浮かぶ型解釈》、《平べったい解釈》、《平易解釈》などとは一線を画しつつ、真剣真摯に文法的・歴史的解釈を促進しようとしておられるのなら、これらの人々は、「字義的解釈」というフレーズを取り下げることによってその真剣さ・忠実さを示すことができると私は信じます。
現状をみますと、いわゆる「文法的・歴史的解釈」が、あいまいさを残さず一義的に、彼らの望むものを指し示している一方、「字義的」という語はあいまいで多義的であり、その結果、元来の文法的・歴史的解釈に、上記のような別種の解釈法の一部ないしは全部が示唆され持ち込まれてしまうという遺憾な傾向があります。もちろん、「字義的」という語は依然として、〈非〉比喩的な意味で個々の単語を表す際に用いることはできます。
例えば、「ぶどう畑」という語は字義的には、ぶどうを栽培する畑のことを意味します。イザヤ27:2ではこの語は、イスラエルを指すものとして、非字義的・比喩的に用いられています。それとは対照的に、創世記9:20では、この語は字義的・非比喩的に用いられています。この場合、「字義的」という語は、「比喩的」という語と相反しています。しかし、広範囲にわたる聖書箇所はどこであっても、そこに比喩表現が含まれているかもしれませんし、含まれていないかもしれませんので、「字義的」という語は、そういった「解釈に対する大局的アプローチを表すもの」としては、もはや使われません。
しかしながら、「字義的解釈」というフレーズを取り下げることは、幾人かのディスペンセーション主義者にとってはかなり困難を要する事ではないかと察します。なぜなら、「字義的」という語は、彼にとっての標語(モットー)であり、横断幕となっているからです。これはある意味、便利な看板用語ではあると思います。なぜなら、まさしくこの用語は、自分にとって都合のいい時に、《平べったい解釈》や《平易解釈》にすっと滑り込むことのできる媒介物になり得るからです。
ではこれから、ディスペンセーション主義の人々によって提示された「字義的」解釈についてのより正確な言明をご一緒にみていきたいと思います。彼らは本章で取り扱ったさまざまな困難点を回避しているのでしょうか。どうでしょうか。それでは次の章でそのことをみていきましょう。それでは、「字義的」解釈における諸原則についての、ディスペンセーション主義者の説明をみなさんとご一緒にみていきたいと思います。
字義性についてのライリーの説明
字義的解釈についての包括的説明の一つは、チャールズ・C・ライリー(1965, 86-87)によってなされました。

Charles.C.Ryrle
ライリーの説明における最も重要なパラグラフは長いです。そこで、便宜上、私たちはそれらを数行ごとに区切りながらみていきたいと思います。導入的な概説をした後、ライリーは次のように始めています(1965, 86)。
「ディスペンセーション主義者は次のように主張します。つまり、自らの解釈原則は、字義的解釈の原則であると。これは何を意味するかといいますと、――著述の中であれ、会話や思考の中においてであれ――標準的用法の中に存在するものと同じ意味を各単語に付与するという解釈のことです。」
ライリーは間違いなく自分が文法的・歴史的解釈の定義に向かっていると考えていたはずです。しかし上記の文をみる限り、彼が《最初に頭に浮かぶ型解釈》("first-thought interpretation")を推奨していると受け取られても仕方がない感じはします。つまり、「各単語には、――文脈のいかんに関わらず――辞書に載っている最も有名・顕著な意味(まず最初に頭に浮かぶ意味)が付与されるべきである」と主張していると受け取られかねないという事です。
ある単語の意味として、(辞書の中に見いだされる広範囲な意味の中の)一体どの意味が、与えられた文脈の中で作用するのかという問いがあります。そしてその問いに対する「歴史的文脈、談話文脈、文文脈の決定的な影響」をライリーが述べなければならなかったのだとしたら、やはり彼は、もっとずっと複雑で高質な説明をする必要があったと思います。しかしまだ最初の数行しか読んでいないのですし、ライリーに対してあまり辛く当たることのないようにしましょう。さあ、続きの文です。
「これは時折、文法的・歴史的解釈の原則と呼ばれています。なぜなら、各単語の意味は、文法的そして歴史的考慮によって決定されるからです。」
これは適切な言明ではないかと思います。ですがライリーは依然として、単語の意味に焦点を置いています。これでは十分ではありませんし、彼の言明は今も尚、いかにして文の意味や談話の意味が生じるのかについての不適切な見解を前提しているといっていいでしょう。文の意味というのは、その構成諸単語の意味のたんなる機械的総計ではありません。そこには文法・段落の文脈・歴史的文脈が存在し、それらが、読み手に対し、
①いかにして個々の単語が組み合わされているのか、
②それらが(言明、命令、話し手の態度、声の調子、暗示等のコミュニケーションをもたらすような)複雑な相互作用の中で、いかにして相互に修飾し合っているのか、
を語っているのです。ライリーは続けて言います。
「この原則はまた、標準解釈(normal interpretation)とも呼ばれています。なぜなら、言葉の字義的意味は、すべての言語における彼らの理解へと至る標準的なアプローチだからです。」
不幸なことに、ライリーはここで《最初に頭に浮かぶ型解釈》について言及しているように見受けられます。一節の中の各単語に「字義的」意味、つまり、――単語が孤立した環境で作られている状況下――まず最初に思い浮かぶ意味を付与しなければならないとライリーは言っているのでしょうか?控え目に言っても、ライリーはやはり、単語の域から出ておらず、文やコミュニケーション行為には言及がいっていません。
しかし彼に対して思い遣りの心を持ち、(たしかに彼の文章からはそのような傾向はみられるけれども)それでももしかしたらライリーは本当には《最初に頭に浮かぶ型解釈》を推進してはいなかった、と仮定することにしましょう。もしかしたら彼は次のように言いたかったのかもしれません。
「辞書に出てくる単語は、多くの場合、いくつかの可能な意味を持っており、隠喩的に用いられ得る潜在性を持っています。しかし、ある単語がある特定の節/特定の全的文脈の中に現れる時、私たちはほとんど自動的に、その単語に、文脈と一致する意味を付与します。ネイティブスピーカーの視点から見たこの「ほとんど自動的な」付与行為――これが、私の意味するところの『字義的意味』なのです。これはまた、手続きにおける標準的や方法ですから、『標準解釈』の一側面とも呼ばれ得るでしょう。」
不幸なことに、ライリーは「言葉の字義的意味」という彼自身のフレーズの中に付随するいくつかの特別な意味を定義するという点で心を配ることができなかったようです。それゆえに、彼が意味しているのは、《最初に頭に浮かぶ型解釈》であるかのようにどうしても思えてしまいます。それではもう少しそういった点を明らかにすべく、次のパラグラフを読んでみましょう。
「これはまた、平易解釈とも呼ばれます。――『字義的な原則は修辞(figures of speech)を排除する』などという誤った印象を誰も持つことのないためです。」
修辞に対するこういった言及は有益なものです。ですがここでの懸念は、――修辞表現を「排除しない」のは良しとして――、では一体ライリーは《平べったい解釈》に対しどのような捉え方をしているのかという点です。《平べったい解釈》は「明らかな」修辞表現だけは認めますが、それを越える一切のものを頑として拒みます。ですから、「平易な」という言葉には、最も明白な次元を越えるものに対する拒絶といった含みがもたされやすいのです。もしくは、現代人としての私たちにとって「平易」であればそれで十分という含みがあるのかもしれません。もしそうでしたら、ライリーの言う「平易」は、前章で私が説明し定義したところの「平易解釈」に類似しているでしょう。
この解釈によれば、私たちの時代と聖書の時代の相違は比較的わずかなので、私たち自身の知識や文化の背景をもって聖書を解釈することで十分だということになります。しかし「文法的および歴史的考慮」に関してライリーが前に言った事を考慮するなら、彼としては、私が意味する《平べったい解釈》について述べる意図はなかったはずです。でも、彼がもしそうしたかったのなら、〔定義をするに当たって〕ライリーはもう少し必要条件や説明を導入すべきだったと思います。それでは、ライリーが《平べったい解釈》という選択肢を排除するような言及をしているのか、それともむしろその選択肢を強化するようなことを言及しているのか、さらに詳しくみていきましょう。
「象徴、修辞、予型といったものは、この方法により全て、平易に解釈し、それらは決して字義的解釈と相反していません。結局のところ、修辞表現に付与する意味の存在それ自体が、用語に関わる字義的意味のリアリティーに依拠しているのです。修辞はしばしば意味をより平易にしますが、それらを読み手に届けるのはあくまで字義的、標準的、平易な意味に他ならないのです。」
この説明はみなさんにとって助けになりましたか?ええと残念ながら、少なくとも私にとっては助けになっていません。といいますのも、これを読むだけでは、ライリーがはたして文法的・歴史的解釈の事を言っているのか、それともいわゆる《平べったい解釈》の事を言っているのか定かではないからです。上のパラグラフでは「字義的」という言葉が三回連続して使われています。一番目の「字義的」に関してですが、それが「文法的・歴史的」であることを私たちは願います。
それから二番目の「字義的」ですが、これは「最初に頭に浮かぶ意味」を意味しています。(つまり「比喩的」に対立するところの「字義的」です。)それから三番目の「字義的」は、かなりの確率で、《平べったい解釈》だと考えられます。ここからますます明らかにされる事実があります。それは、「字義的」という言葉のいわゆる「有用性」の一つが、この用語が、いくつかの異なる意味の間を移動することができるという事です。
さらに、上記の説明の中では、「開口」テクスト(“open-ended” texts)に関連する可能性が考慮されていません。あるテクストでは意味の中心的アスペクトが明らかかもしれませんが、どの位まである種の暗示表現やその意味が考慮されるべきなのか不明瞭なケースもあります。そして、《平べったい解釈》がしくじるのは、まさにこの点においてです。この解釈は、曖昧で両義的な表現や、(積極的効果を出すべく用いられる)「可能だけど完全に明瞭ではない暗示表現」といったものの可能性を過小評価します。
しかしこれに対する応答もあります。そしてこういった《平べったい解釈》の支持者たちは、次のように議論を展開するかもしれません。
「私たちは、聖書記者たちが(ある箇所で)『開口』聖句を書いたかもしれないということは認めます。そしてそういった聖句を『平べったく』解釈するのは適切ではないということも認めています。しかし聖書というのは『開口』でオープンエンドなテクストではないと私たちは信じています。神は、聖書を執筆された際、それを隠そうとせず、むしろ真理を伝達することを意図されました。それゆえ、神は曖昧で両義的な表現やあまり明確でない暗示表現などを使うことはないと私たちは考えています。そして神はオープンエンドな隠喩の中で(つまり、どこまでその隠喩的比較が拡張され得るのか、私たちにとって明瞭でないような箇所で)詩的な可能性につけ込むような、そのようなことはなさらないのです。」
これは骨のある議論でありしっかりした立場ではありますが、ただ単に受容し前提するのではなく、しっかりと検証を受ける必要のある立場です。解釈学的諸原則について言明する上で注意を怠るなら、私たちはいとも簡単に論拠なくそれらを前提してしまいがちです。さらに、この立場の信憑性を問うているのはただ単に私だけではありません。イエスの譬え話(参:マルコ4:11-13)や旧約の予型をみるだけでも、そこに十分な議論の余地があることが明らかです。そしてもちろん、ライリーは私が引用しているこの論考の中で明確に予型のことについて言及しています。しかし予型のことを彼はどのように捉えていたのでしょうか。特に、旧約予型の重要性は、元来の旧約文脈の中に見い出され得るものを越える可能性があると彼は考えていたのでしょうか。この問いに対し、聖書の霊感に関する正統見解をもっている大半の解釈者たちは「然り」と答えています。さて彼の議論は次のようになります。
「神は創造のはじめから終わりを知っておられる。それゆえ、聖書の神聖なる執筆者として、主は《予型》とその《対型 antitypical》的成就の間の関係を築くことがおできになる。預言成就は後になって実現されるものなので、予型は、旧約時代の一般的方法によって得られるものよりも、より豊かになる。換言すると、ある場合においては、予型に対する神のご意図は、文法的・歴史的解釈によって私たちが得ることのできるもの以上に豊かである。そういった豊かさは、それが正当に認識されるなら、文法的・歴史的意味を侵害せず、それに相反するようなこともない。それは、預言成就と比較される際、予型に対する付加的重要性より生じてくるのである。」
もしこれが真なら、文法的・歴史的解釈は予型解釈にあたっての全てを成すものではない、ということになると思います。そして文法的・歴史的解釈は、解釈の全的行為の中における重要な一地点であるに過ぎないということになるのかもしれません。それゆえ、ライリーは文法的・歴史的解釈のことについてだけを語っていたのではないと考えられます。予型のことに言及する上で、彼は文法的・歴史的解釈以上に豊かな諸原則をなにか考慮に入れていたのかもしれません。
他方、《平べったい解釈》を明確に排除しないことで、彼は、文法的・歴史的解釈よりも豊かでないなにかを支持すべく、ある偏倚を導入しているのかもしれません。(なぜならそれは、明瞭ではない暗示や比喩表現を考慮に入れようとしないからです。)概して言いますと、ライリーの意味する「字義的」解釈における彼自身の説明には、まだまだかなりの議論の余地が残されていると思います。ライリーはE・R・クレイヴェン(E.R. Craven)を引用しつつ、次のように続けています。
「いわゆる字義主義者は、比喩的言語、象徴が預言の中で使われているということを否定しませんし、偉大なる霊的真理がその中で表明されているということを否定してもいません。字義主義者のとるべき立場というのは、簡単に言いますと、預言は、――明白に比喩的だと捉えられている――その他の発話と同様、標準的に(normally)解釈されなければならないということです。」
この引用は、基本的に良いと思います。ただ不幸なことに、ライリー(もしくはこの文の中で引用されているクレイヴェン)は、何かが明白には比喩的でない場合どうすればいいのかについて私たちに語っていません。つまり、こういうことです。仮に何かが「明瞭に、平易に、まぎれもなく比喩的」というわけではないけれど、一応、比喩的である可能性があるとします。この場合、私たちはどうすればいいのでしょうか?ここに、《平べったい or 平易解釈》と、文法的・歴史的解釈の間に存在する、多大なる潜在的相違が横たわっています。
《平べったい解釈》が、明瞭な比喩だけしか認めないのに対し、文法的・歴史的解釈は、あらゆる比喩・暗示を認めようとします。ライリーとしては、文法的・歴史的解釈のことを述べようとしていたのかもしれませんが、もしもそうなら、彼はこの文の冒頭を「字義主義者」ではなく、「文法的・歴史的解釈者」とした方が良かったのではないかと思います。
字義性についてのその他の言明
上記のライリーとは対照的に、タン(1974, 29-30)は、以下に引用しますように、文法的・歴史的解釈をずっと明確に定義しています。

Paul Lee Tan
「『解釈する』というのは、発話者ないしは書き手の元々の意味を説明することです。そして『字義的に』解釈するというのは、標準的、慣習的、そして言葉や言語の妥当な使用法に従い、発話者ないしは書き手の元々の意味を説明することです。聖書の字義的解釈というのはただ、標準的、慣習的言語の使用法に従い、聖書の元々の意味を説明することです。」
「、、、ある単語がさまざまな意味を持つのは普通のことです。しかし、単語がある状況下で使われる時、それは通常、ただ一つの意図された意味を持っています。」
「、、、発話者や書き手を『理解する』ためには、私たちはその発話者/書き手が言葉を、標準的に、かつ、多数の意味を含ませることなく使っているということを前提する必要があります。そしてこれが解釈学における字義的メソッドが、聖書啓示の中の神について前提していることなのです。このメソッドは聖書を謎かけではなく、啓示とみなしています。」
しかしタンは、《平べったい解釈》の方向へと、事を深刻に偏向させています。また単語についてタンが言っている内容においては、「最初に頭に浮かぶ意味」の方向へ向かう、同一の傾向が依然としてみられます。二段落目では、タンはむしろ、次のように言った方が良かったと思います。「あるテクスト内のどんな単語の存在においても、その単語は、――文脈が一つ以上の意味を持たせるべく作動しない限りにおいて――ただ一つの意図された意味を持ち得ます」と。
イザヤ27:2-4の分析でみなさんと一緒にみてきました通り、ある文脈は同時に一つ以上の意味を作動させることができるのです。例えば、イザヤ27:4の「戦い」という語は、
①主がイスラエルに代わって遂行しようとしておられる個人的敵に対する戦い(こちらが主要点)、
②庭師の、茨やおどろに対しての隠喩的戦い、
という二つの考えを同時に呼び起こしています。そしてこの箇所のフルな効果はそれら二つ両方の可能性に依拠しています。
「茨」や「おどろ」というのは、個人的敵のことを表すべく、ぶどう園に関連した拡張比喩の中で用いられています。しかしそれらはまた、(字義的/文字通りの)茨やおどろの存在なしに、エデンの園の記憶を想起させる力も持っているのです。それゆえ、「茨」や「おどろ」の全的効果は、――隠喩的&字義的関連性という――これら二つが同時に存在するということに依拠しています。
実際、大部分のメタファー(隠喩)の効果は、そのような二面(orそれ以上の)意味の同時存在に依拠しているのです(参:Max Black 1962, 25-47)。それゆえに、タンの第三段落目は、事実上、メタファーの存在の可能性自体を排除してしまっています。おそらくタン自身にはその意図はなかったと思います。しかしながら実際、彼は非常に一方的で片寄った議論に落ち込んでしまっています。そしてタンはさらに明確に次のように記しています。

「通常の人間コミュニケーションは、次のことを要求します。つまり、話される内容/書かれる内容は圧倒的に非比喩的であるという根本的原則を要求するのです。A・B・デイヴィッドソンは正当にも次のように言っています。『預言の解釈において私は次のことを第一原則にしています。
☆預言者の言葉を字義的に読む。
☆字義的な意味が彼〔預言者〕の意味である。
☆彼は現実の間を動いているのであって、象徴の間を動いているのではない。そして人々(people)のような具体的なものの間を動いているのであって、我々の教会とか世界などという抽象物の間を動いているのではない。」(Tan 1974, 132)
タンは、コミュニケーションは「圧倒的に非比喩的」と言っています。もちろん、比喩的使用が起こる背景と対照する、非比喩的な語用というものは存在するに違いありません。また、一般的に言語学習者は、さまざまな文脈の中における語用を観察することによって、言葉の意味を習得していく場合が多いです。その意味において、たしかに、言葉の非比喩的使用というのは「圧倒的/支配的」でしょう。
しかし結局、そういった非比喩的言語の「圧倒的優勢」は何を意味するのでしょうか。それは、平均的な言語使用者がこれまで耳にしてきた発話の総数内における圧倒的優勢です。そしてこういった種類の優勢は、「かなり長い談話でさえも完全に比喩的であるかもしれない」という可能性と十分両立し得ます。例えば、イエスの譬え話やジョン・バニヤンの寓話などは、徹頭徹尾、比喩的です。
聖書解釈における全域的要因について
さらに、ある話全体が、特別に比喩的な単語の存在なしに、全域的に比喩的であるかもしれない可能性について、残念ながらタンは考慮していないように思われます。イエスの譬え話のいくつかがその例として挙げられます。例えば、失われた羊の譬え(ルカ15:4-6)は、それ自体においてストーリーとして受け取られていますが、よく見ますと、そこにはほとんど比喩的な言語は含まれていません。個々の単語のいくつかは明らかに比喩的な方法で使われています。しかしルカのその文脈の中において、全体としてのこのストーリーが、意味の二面性に関連した拡張メタファーとして機能していることは明白です。つまり、それは、羊飼いと彼の羊という「牧畜的」面と、神の民の指導者と人々に関する「救済的」面に関連しているのです。
それでは、聖書の預言が退屈な歴史小説家のようなものなのか、ジョン・バニヤンのようなものなのか、たとえ話やそういったものなのか否か、私たちはどのようにして知ることができるのでしょう?聖書預言が、圧倒的・排他的に比喩的なのか、それとも非比喩的なのかという問題は、コミュニケーションにおけるいわゆる「根本的原則」をベースに「前提」されてよいものではありません。それは、預言を、その口頭文脈(verbal content)および歴史的文脈の両方において見ていく中で決定されるべきものです(文法的・歴史的解釈)。
その意味で、――タンやデイヴィッドソンがしているように――それらを先行的に宣言してしまうことは、《平べったい解釈》ないし《プレーン解釈》ないし、その両方の方向へと、問われるべき課題にバイアスをかけていく事に他なりません。デイヴィッドソンの言明にはまた別の問題があります。今回は、イスラエル/教会の区別に関しての問題です。彼は上述の文の中で、「現実」と「象徴」、「具体的なもの」と「抽象物」をそれぞれ対立概念として捉えています。
また「人々」が具体的なものとして捉えられる一方、「私たちの教会」および「世界」は抽象物と見なされています。おお、あたかも私たちの教会が「人々」ではないと言っているかのように!そしてあたかも、「天」と「地」との間に存在するという、いわゆる根本的区別がここにおいて作動しているとでも言っているかのように!教会は天的なものと捉えられており、それゆえに、教会はなにかリアルでないもの、「具体的でないもの」として扱われています。それに対し、他の人々は地上的であり、それゆえに具体的だとされています。
このような論点回避の対照法は、いったいどこからやって来るのでしょうか?字義性という用語は事実上、(「地」と「天」の間の区別と同様、「イスラエル」と「教会」の間に区別を置く解釈をする)古典的ディスペンセーション主義教義のための暗語(cord-word)と化してしまっている感があります。
ある人々は私があまりにもライリーやタンやデイヴィッドソンに厳しいとお感じになっているかもしれません。彼らは本当に重要な論点をはぐらかそうとしているのでしょうか?彼らは本当に、《平べったい解釈》を有利にもっていきたいがために、事を歪曲しているのでしょうか?それとも、彼らはただ単に不正確なだけなのでしょうか?おそらくですが、彼らは単に不正確なだけなのかもしれません。しかし彼らが不正確であるところの、その特定の《方法論》は、ディスペンセーション主義者と〈非〉ディスペンセーション主義者との間を現在隔てている諸問題の所在を示す助けにはなりません。
いや、その反対に、それは、彼らや私たちを混乱させています。しかもこの事態が発生しているのは、事もあろうに、彼らが、――(他のアプローチと比較した場合の)聖書解釈におけるディスペンセーション主義アプローチの特徴点を明記しようとしている――まさにそういった文脈のただ中で起こっているのです!
私たちはまた別の方法でこの問題を描写することができるかもしれません。みなさん、ぜひ自問してみてください。私たちが特定の旧約の歴史ないしは法に関する聖句に取り組んでいる際に、「いつ/どのようにして」予型的な意味を見い出すことができるのか、はたしてライリーやタンの説明は、それに対する回答を与えているでしょうか?
ライリーは明白に、予型の存在を許しています。一方、タンは推定上、一応は認めると思いますが、言葉の中に存在する複数の意味を否定している彼の言明から鑑みるに、もしかしたら彼は予型の存在を排除しているのかもしれません。そして両者とも、①象徴的/引喩的意味があるのかないのかの決定において、また②そういった意味に付随している暗示がどこまで拡大されるのかの決定において、文脈の持つ極めて重要な役割についてあまり語ることをしていません。そしてこれは、「予型的方法を、歴史と同様、預言にも適用することがはたして妥当なことか?」についての問いへと私たちを導きます。
この問いに対し、スコフィールドは「否、妥当ではない」と答えました。しかしライリーとタンは直接的には「歴史」と「預言」を区別していません。それゆえ、原則的に言って、彼らは「歴史」にも「預言」にも予型的方法を許しているようにも受け取れますし、あるいは逆にそのどちらにも許可を与えていないようにも見えます。といいますのも、A・B・デイヴィッドソン論考からのタンの引用文(1974, 132)は、――教会に対してのその辛辣な排除言及と共に――、預言解釈に対する予型的方法の使用を禁じていることが明らかにうかがえます。タンはあまりにも不明瞭な一般原則を使っているために、
①(歴史的聖句という)点においては、かなりの引喩性(ほのめかし)を許した上で解釈可能とする一方、
②(預言的聖句という)別の点においては、そのような引喩性をもったものをことごとく極小化した上で解釈を施しているのです。
そしてその場合、彼の一般原則は、文法的・歴史的解釈/《平べったい解釈》/《プレーン解釈》/そしておそらくはその他の諸解釈の間をも行き来する、不明瞭であいまいな性質のものです。
それから最後にもう一つだけ例を挙げたいと思います。フェインバーグ(1980, 46)のM・J・ウィンガーデン(M. J. Wyngaarden)に対する批判です。ウィンガーデンは、「旧約の時代においてでさえ、上述したような旧約諸聖句は、潜在的・初期的な霊的解釈(spiritualization)を具象化していたと理解すべきだ」と書いているのですが、それに対し、フェインバーグ(1980, 46)は次のように反論しています。
「旧約時代に上記のような諸聖句がどのように理解されていたのかということに関しては、説明の必要はありません。というのも、それは常識の問題であり、慎重な検証に開かれているからです。そうです。それらは徹頭徹尾(only and solely)字義的に取られていたのです。」
ここでのフェインバーグが意味している「字義的」とは何でしょうか?他のディスペンセーション主義者と共に、フェインバーグもまた、「聖書には比喩的言語がある」ということを明白に認めています。ということは、「字義的」という語は、「修辞表現を全く持たない」ということを意味し得ません。つまり、「徹頭徹尾、字義的」とフェインバーグは強い表現こそしているものの、実際のところ、彼は「修辞は無い」とは言っていないわけです。それゆえに、「字義的」は《最初に頭に浮かぶ型解釈》を意味してはいません。それでは、それはただ単に《文法的・歴史的解釈》のことを含意しているのでしょうか?
この文脈においては、明らかにそれを含意していません。というのも、もしここで含意されているのが文法的・歴史的解釈だったとしたら、フェインバーグの言明自体が、ほとんど瑣末(さまつ)主義に陥ってしまうからです。フェインバーグもウィンガーデンも両者共々、文法的・歴史的解釈の重要性を認めています。ですからここで争点となっている問いは、「はたして文法的・歴史的解釈の中に、いくらかの霊的解釈(“spiritualization”)は含まれているのか、それとも含まれていないのか?」です。
この問いに関し、ウィンガーデンは、「然り。含まれている」と答え、フェインバーグは、「否。含まれていない」と答えています。そうした上で、フェインバーグは自分の立場が、ウィンガーデンとは違うことを表すべく、「字義的」という言葉を使っているのです。ですから、ここでの「字義的」というのは、いわゆる《平べったい解釈》にかなり近いと考えられます。もし私が彼の言っていることを正しく理解しているのなら、フェインバーグは、「旧約著述の中の特定の事例において、文法的・歴史的解釈というのは、結果的に《平べったい解釈》と一致している」ということをまさに主張すべく、彼はここで「字義的」という語を使っています。
元々の聞き手は、平べったい方法で聖句を理解していた。ゆえに、文法的・歴史的解釈は、この平べったさを再生産しているのだ、と。さて、それでは私たちがフェインバーグの言っていることを一応理解できたとしましょう。ここでの彼の主張は非常に重要なものです。これは解釈学的論争のまさに心臓部分に近いと言っても過言ではないかもしれません。しかしフェインバーグは自分のその見解を弁明していません。そうする代わりに彼はただ、自分の見解は「常識の問題」と言っているだけです。残念なことに、これは少なくとも私にとっては「常識」ではありません。私はそれを「常識」だとして前提してしまうのではなく、この問題を詳細に検証したいと望んでいます。それゆえ、本書の第10章と11章でこの問題を取り上げることにしたいと思います。
さて、「字義的」解釈とは何なのでしょうか?これは混乱を生じさせる用語であり、聖書解釈における死活問題の多くをはぐらかし避けるために使用され得る用語でもあります。ですからできるなら、私たちはこのフレーズを使わない方が賢明だと思います。そしてむしろ文法的・歴史的解釈のことを言及すべきだと思います。但し、「字義的」という語は、特定の単語や文の意味を論じる際には、依然として用いることができます。その場合の「字義性」とは、比喩的であることの反意語です。そしてそれは、私の言う《最初に頭に浮かぶ》意味とおおよそ同じような働きを成しているといっていいかと思います。
旧約聖書のイスラエルにおける解釈学的見地
本章では、旧約への適用――特に旧約預言への適用――という点で、文法的・歴史的解釈がどのように進行していくのか、みなさんとご一緒に考察していきたいと思います。文法的・歴史的解釈は、そのもっとも狭義な焦点として、聖書記者はその著述によって何を意味(意図)していたのかを問います。しかしそれは、「記者は頭の中で何を考えていたのか?」という事に関する単なる心理学的憶測ではありませんし、元々の聞き手はなんら手がかりがないにも拘らず、こちら側が勝手に、「聖書記者の意図は~~であったに違いない」と決めつける、そのような根拠なき推測でもありません。
そうではなく、文法的・歴史的解釈は、記者が実際に言及した内容に焦点を置きます。それはまた、記者の対象とする読者たちが、聖句の意味せんことを理解する上で何をもってjustifiedされるのか(正当化される、正しいとされる、正当だと理由づけられる)に関心をもつ解釈法であると特徴づけられましょう。読み手に関する後者の特徴には、それによって、私たちが聖書記者の考えについての憶測や推測的読みを強いて回避させ、記者が実際に書いた内容に私たちを強いて局限するという長所があります。
しかしながら、人間の読み手は完全無欠ではありません。特に、私たちは、主観的に聖句の中にある意味を読み込ませるというような事を避け、どの意味が私たち読者が〔聖句を〕読み取る上で正しいとされる意味なのか――その部分を知ろうと努めます。いずれにせよ、文法的・歴史的解釈は、聖書記者の持っていた諸目的を念頭におきながら、その当時の時代や文化の背景を基に聖句が何といっているのかを取り扱います。
前キリスト教時代の聞き手による実際の諸解釈

預言者ミカ
ですから、文法的・歴史的解釈は、聖書が書かれた当初に焦点を置きます。しかし(例えば)預言者ミカの時代のイスラエルの民がミカの言う意味を理解していた事(と私たちの捉えるその内容)に訴えるだけで、それがそのままミカ書の解釈に厳密なる回答が与えたことになる、と考えることはできません。当時の民の中には、罪や頑なな心によって、理解を誤る者がいたかもしれません。さらに、こういった旧約聖句が書かれた当時のイスラエルの民の聖句理解についての情報さえあまりないのが現状です。それゆえに、私たちは下記のようなフェインバーグの言及の真意を理解しかねます(1980, 46)。

「旧約時代に上記のような諸聖句がどのように理解されていたのかということに関しては、説明の必要はありません。というのも、それは常識の問題であり、慎重な検証に開かれているからです。そうです。それらは徹頭徹尾(only and solely)字義的に取られていたのです。」
もちろん、口頭での神の御言葉に対するいくつかの民の応答や、書かれた御言葉に対する応答という旧約それ自身の記録から、私たちはそういった回答者たちが神の御言葉をどのように理解していたのか、断片的な知識は得ることが可能です。例えば、神が民に掟を与えた時、どのような事が起こったのでしょうか。掟を聞くやいなや迅速に直接的にそれらに従った人々は、その掟が直接的な意味を持っていると理解したわけです。そしておそらく従順なイスラエルの民たちは、神の掟を平べったく(flatly)解釈していたと思われます。
しかしまたおそらく、彼らはそういった直接的な応答に加え、それを越えたところにある付加的含意や暗示の類をみていた可能性もあります。ですが、この事に関しては、私たちが「すべてのイスラエルの民は、多かれ少なかれ、《平べったい解釈》をする傾向にあった」と前提しない限り、特になにを立証する手立てもないというのが現状ではないかと思います。前キリスト教時代における一般読み手の解釈について、私たちが得ることのできる最も精巧な資料は、旧約新約間の中間期(intertestamental period;旧約聖書の最後の書が書かれてから新約聖書の最初の書が書かれるまでの間の約400年)に存在します。

中間期
フェインバーグはそのことを考慮していたのでしょうか。おそらくそうしていなかっただろうと思います。それはともかくとして、旧約新約間の時代の資料は、フェインバーグの諸結論を裏付けるものにはなっていません。実際、この時代の解釈学的応答は非常に多様性に富んでいます。ある解釈者たちは「平べったく」解釈しています。そうかと思うと、ある人々はかなり空想的な解釈をしています。ユダヤ人のフィロン(Philo Judaeus, bc13-ad45/50)やクムラン共同体、ユダヤの黙示(Jewish apocalyptic)などを参照するだけでもそれは一目瞭然です。(例:Philo, Legum allegoriarum; 1QpHab, 1QpMic; 1 Enoch; Longenecker 1975, 19-50; Patte 1975)
イスラエルの希望
それでは本題に戻りましょう。――旧約の聞き手たちによる実際の解釈ではなく、「正当/正しいとみなされている(justified or warranted)」解釈についてです。聖書記者は実際には、旧約本文の中で何を述べたのでしょう。元々の聞き手が旧約聖句を理解する上で何が正当なもの(justified or warranted)とされていたのでしょうか。特に預言聖句の中で何が述べられていたのでしょうか。イスラエルの自己理解および、イスラエルの神理解におけるいくつかの要因は、「彼らの預言理解は《平べったいもの》ではなかった」という見解に私たちを導かざるを得ないと思います。
もちろん、時折、特定の預言聖句は、主として(or全く)非隠喩的な予言として理解されてきたことでしょう。しかしその他の場合、イスラエル自身の態度は、いわゆるオープンエンド型の予想(期待・待望)だったはずです。イスラエルは、どのようにしてその預言が成就に至るのか厳密には知らない状態のまま、そういったいくつかの預言の成就を待望しなければなりませんでした。また彼らは、一体どの程度まで、真理の隠喩的表現が作用するのかについても厳密には把握していなかったはずです。例えば、その一例をイザヤ40:4-5に見ることができるでしょう。
4もろもろの谷は高くせられ、もろもろの山と丘とは低くせられ、高低のある地は平らになり、険しい所は平地となる。
5 こうして主の栄光があらわれ、人は皆ともにこれを見る。これは主の口が語られたのである。
この直接的・遠隔的文脈をみる限り、元々の読み手が、4節の預言を、「単なる地形学的な変化(地の表面の形が変わること)についての描写だ」と理解することを絶対的に妨げるものは何もありません。それゆえに、《平べったい解釈》は、「この節は地形学上の変化を言っているのだ」と捉えます。また、(「もし可能なら字義的」という原則を基盤にした)オリジナルな歴史的文脈の中における解釈法も、同様のことを言うでしょう。しかし実際の状況は、《平べったい解釈》が思うほど、そう単純なものではありません。確かに、イスラエルの民は、これを、地形学上の変化以外の(あるいはそれ以上の)なにかであると見るよう強いられてはいません。しかしまた同時に、彼らは、「これは単なる地形上の変化です!」、もしくは「これこそが主要点です!」と捉えるように強制されてもいません。
まず第一番目に、直接的文脈(例:イザヤ40章~66章の大半)は、第二回目の出エジプトについてのテーマを提示しています。(イザヤ43:16-21、51:9-11、52:12、63:7-19等をご参照ください。)荒野の中の道(40章3節)というのは、捕囚(以前にはエジプト;今はバビロン)から約束の地に至る道を描写する言葉です。そうであるならば、地形学上の変化を表す言葉は、神ご自身が民のただ中にいらしてくださる時に関連した備えの完全性を示唆する隠喩的表現であるかもしれません。
第二番目に、イザヤ2:1-18ではすでに、「神の至高性」および「人間高慢が低められるさま」を示唆すべく、そういった平らにするプロセスに関する類似の言語が使われています。スコフィールド・レファレンス・バイブルは、イザヤ2:2の注釈として、「山というのは、聖書のシンボリズムにおいて、王国を意味する(ダニエル2:35、黙13:1、黙17:9-11)」と記されています。スコフィールドのこの言及はもちろん《平べったい解釈》ではありません。また、厳密に言って文法的・歴史的解釈でもありません。なぜなら、彼の言及は、イザヤ書が書かれたその当時には未だ書かれていなかった聖書の各聖句にその拠り所を求めているからです。
しかしながら、("平べったい"ではなく)繊細な読者なら、イザヤ2:12-18の主要点は、高慢と謙遜、栄誉と不名誉、至高と屈辱にあるのであって、地形上の変化にあるのではないということを理解しておられるでしょう。さあ、またイザヤ40:3-5に戻りましょう。イザヤ40:3-5は、隠喩的言語というその選択により、未来に関する散文的、年代記的描写よりは、確かに、より正確さの低い聖句といえます。しかしそれは「人間の高慢が低くされること」「二回目の出エジプト」「神の最終的贖いの宇宙的視野」といったテーマを互いに関連させつつ記述することに成功しています。敬虔なイスラエルの読み手はここの聖句の主要点を押さえていたはずです。主はやがて壮大な《新》出エジプトにおいてご自身を顕現され、人間の高慢を取り扱ってくださるだろうと。そこに地形上の変化があるのか、そして、どれくらい、この《新》出エジプトが最初の出エジプトに類似しているのかといったことは、ここの聖句には明瞭に書かれていません。
こういった希望の表現は膨らみ、実際に預言が成就する時により明確になります。例えば、バプテスマのヨハネに関する預言成就の光に照らし、今や私たちは、悔い改めというのが、(イザヤ40:4で暗示されている)人間の高慢に対する主の取り扱いの主要な側面であったことをより明瞭に知るに至っています。
後の日
それでは再度、預言解釈という一般課題に戻ることにしましょう。「後の日(“latter days”)」のための旧約預言は、純粋にシンプルに言って、イスラエルの民にその中心を見い出していません。また、純粋にシンプルに言って、パレスティナの土地の刷新にその中心を見い出してもいません。そうです。むしろ彼らの待望のもっとも深い根源は、「主の来臨」の内に見い出されます。
「荒地で、主のために道を整えよ」(イザヤ40:3)。「主の栄光が現わされる」(イザヤ40:5)。「ユダの町々に言え。『見よ。あなたがたの神を。』」(イザヤ40:9)。「見よ。神である主は力をもって来られ、その御腕で統べ治める」(40:10)。「シオンに向かって『あなたの神は王となられた』と言う者の足は山の上にあって、なんと麗しいことだろう」(52:7)。
このような聖句は他にも枚挙にいとまがありません。神の来臨、栄光の中での神の顕現は、神の民の刷新をも含意せざるを得ません。出エジプトやシナイにおいてそうであったように、未来においても、神の来臨は、裁きと救い、その両方を意味します。そして神の来臨は土地の刷新を含みます。なぜなら、主が顕現される所はどこでも聖なる地となるからです(参:出エ3:5)。
それゆえに、預言は神の民および彼らの地の刷新についてこれほど多くを語っているのです。そしてこれらの事は神の来臨から隔絶したところにあるものではありません。目を見張るような壮麗な万物の刷新は、圧倒的に偉大な神ご自身の人格および後の日におけるご自身に関する啓示を顕示し、反映しています。
しかしたとい、民と土地の刷新が神ご自身の来臨によって決定されるとしても、依然として、神ご自身が、預言的待望のもっとも深い中心におられます。イスラエルの民は神の来臨が何を意味するのかを詳細に予測できていたでしょうか。そうです、それは平べったい解釈を意味しません。そうではなく、それは神ご自身が究極的な解釈者であるということに対する解釈を意味しているのです。モーセでさえもただ神の「後姿」しか見ることができませんでした。全世界に対して全き栄光の内に啓示される神を持つということは(イザヤ40:5)、あまりにも壮観であるため、イスラエルの民は、隠喩的であるもの、そしてそれがどんな方法で隠喩的であるかについて控え目(reserved)でならなければなりませんでした。
祭司の王国としてのイスラエル(ISRAEL AS A KINGDOM OF PRIESTS)
特に、イスラエルの自己理解というのが、イスラエルの将来に関する彼らの預言の読み方に影響を与えました。それでは、イスラエルはどのような自己理解をしていたのでしょうか?国として民としてのイスラエルに対し、神は、イスラエル自身の重要性の中軸は単なる生物学的/民族的境界にあるのではなく、ご自身との関係性の内にあるのだと言われました。イスラエルは神の御名を帯びることにより(民6:24-27)、彼らのただ中に神が住まわれるということにより(民14:14)特異な存在として特徴づけられた民でした。そして国民全体が、「祭司の王国であり聖なる国民」(出エ19:6)でした。
祭司として、彼らは聖の中で神に仕え(レビ19:2)、神を知る知識を全世界の国々にもたらすという、特別にして優れた役割を遂行しなければなりませんでした(創12:3、申4:6-8)。それでは、イスラエルは祭司としての自分自身の役割をどのように理解していたのでしょうか?それは、アロンの祭司制の枠組みの中でイスラエルに与えられた非常に具体的な型を遵守することによって、でした。アロン系の祭司たち(そしてそれに従属するレビ人たち)はもちろん、非常に特別な意味における祭司でした。全体としてのイスラエルはアロンの子孫たちとは同じ地位にはありませんでした。確かに共同体全体は、聖に関するより低い意味において(出エ31:13)、聖なるものでした。しかし、そうだからといって、祭司と民との間の区別を亡きものにしようとのコラの企ては正当化されませんでした(民16-17)。
アロン系の祭司たちは特別な意味で聖なるものでした。しかし、そういった特別性ゆえにこそ、アロン系の祭司たちは、民が――より緩和な次元において――いかにあるべきかということに関する一つのパターンを定めたのです。ですからアロンは、イスラエルのための一つのパターンとしての存在していました。しかしアロン自身はそれ以上に深いなにかにまねて型どられていました。天幕のための指示は、「よく注意して、あなたが山で示される型どおりに作れ」(出エ25:40)でした。天幕は聖なる場所であり、至高に聖い神の宿り場としての天に模(かたど)って造られました(1列8:27、30、34、36、39)。
天幕の務めもまた天的な務めに型どられたものであったと考えられます。神の絶えざる臨在の内になされる御使いの務め、そして神が「顔と顔とを合わせて」(民12:8)語りかけてくださったモーセの務めなども髣髴されます。そしてアロンはもちろん、そのままでは神の前に立つことができませんでした。彼は特別な装束を着なければなりませんでした。さもなくば彼は息絶えていたのです(出エ28:38、43)。
さらに、アロンの装束のいくつかの装具や配置にしても、少なくとも漠然と、天幕それ自体に相当しています。青服、金、指輪、「主への聖なるもの」と刻まれた純金の板などは皆、天幕の各側面を連想させるものです(参:Kline 1980, 42-47)。祭司であるアロンは天にある型に型どられていました。それゆえに、イスラエルの祭司制の全き型には深さにおける諸レベルがありました。全体としてのイスラエルは祭司でした。アロンは祭司でした。そして神の天的な原型には、究極的な祭司制がありました。(下の図表10.1をご覧ください。)

ですから、祭司の国としてのイスラエルの存在には、象徴的な重要性がありました。しかしそうだからと言って、イスラエルの祭司制が「ただ単に」象徴的であったに過ぎないとか、「ただ単に」説明に役立つ教育的価値しか持たないとか、そういう事は全くありません。それに、イスラエルの祭司制が「ただ単に」天にある「本物の」祭司的リアリティーを映し出す幻影にすぎないとか、そういうことも全くありません。いいえ、それは確かに実在するものであり、「本物」でした。――イスラエルの民がそれを受け取ることができる次元において、そしてその時点における神の解放を表す予備的(preliminary)性格および主の啓示にふさわしい次元において、それは「本物」だったのです。
神のための代理人だけでなく、まことの神ご自身が、真にイスラエルと共におられました。そして主の臨在は、祭司としての彼らの聖別を意味していました。にもかかわらず、イエス・キリストの到来により神が臨在しておられるようなあり方および強度(intensity)ではその当時、神は臨在しておられませんでした。ですから、その意味において、イスラエルにおける神の臨在は、予備的であり、「影的(“shadowy”)」であったのです。
預言書の中で言及されている後の日(the latter days)は、神の栄光がこの地に顕現する、かの広範な終末論的時代です(イザヤ40:5、60:2-3、ゼカ2:5)。以前には神の栄光は天に限定されており、天幕および神殿の中の至聖所を満たすために従属的に顕れていました。しかし、終末論的に言えば、神はその威厳をもってこの地に来られるのです。後の日には天的なリアリティーが地上的で象徴的な映しに取って代わります。そして天的な原型が、影であったものを満たしそれを変えます。
それゆえに後の日というのは、アロンの祭司制における改訂(revision;詩110:4)、および祭司制と密接な関係を持つ律法の改訂を暗示しています(ヘブ7:12)。しかしそれ以上に、それは、イスラエルそれ自体の存在における改訂を暗示しています。なぜならイスラエル自体、祭司の王国として選ばれているからです(参:イザヤ66:18-24)。イスラエルの存在自体が初めより、象徴的かつ天的な含みを持っていましたので、預言成就にもそれらと同じニュアンスが包含されています。終末論的「時」というのは、イスラエルの性質それ自体における象徴的含みがリアリティーに変化する時です。
それでは、これが、パレスティナの土地の性質に関するイスラエルの認識にとって何を意味していたのか考えてみることにしましょう。地は神に属するものでした(レビ25:23)。そしてそれは汚れた慣習により汚されてはならないものでした(申21:23、レビ20:22-24)。また拡大された意味において、土地そのものが聖く、神の宿る場所でした。聖なる土地として、それは天的な宿り場に対する神のご統治に型どられていました。しかしそれは、神が後の日に、全地になそうとしておられることをも明示していました。神の王国は、――(旧約時代において)それが天であったように――、今度は地に到来するのです。
パレスティナの地はエデンにもなぞられていました(イザヤ51:3)。それはアダムが落伍(失敗)した地点を指し示していました。エデンに対するアダムの統治(全地に対する統治の出発点)は堕落によって損なわれてしまったのです。イスラエルは「新しいエデン」に対する統治権を授けられました。パレスティナに対するこの統治は「最後のアダム」(1コリ15:45)としてお生まれになるべき「女の子孫」によって回復されるべき完全なる統治を待望しました。これら全てが意味するのは、聖書預言を「平べったく」読むことは、文法的・歴史的解釈の侵害であるということです。そしてイスラエルの歴史を「平べったく」読むこともそれと同様、侵害となります。
イスラエルの歴史には、祭司の国としてのイスラエル自身の存在における、象徴的次元に由来するいくつかの象徴的含みがあります。しかし終末論的預言は、そういった象徴的な含みが強調され、表面化してくるポイントなのです。なぜなら、それが予備的段階から最終段階への移行期だからです。そしてそういった象徴的含みは、従来、「予型(typology)」として分類されてきたほとんど全てのものを含みます。実際、イスラエルの存在は、初期予型で満ち満ちているため、成就の光の下に生きる私たちには、イスラエルのそういった状況を評価することは容易ではありません。本当にそれは不可能です。なぜなら私たちは自分たちがキリストから学んだことを忘れることなどできないからです。
しかしこれだけは言えましょう。イスラエルは象徴的含みのおぼろげな感覚を通して実に多くのことを知ることはできていたでしょうと。そしてそれと同時に、影は、本体が提供するあらゆる深さや豊かさを提供しなかったため、少ししか知り得なかった――ということもあり得ます。多くの内容は、明確にして、理性的に言明された手段によってではなく、むしろ暗に(tacitly)知られていたのでしょう*28。旧約イスラエルの終末論的待望についてもう一点だけご一緒に考察したいと思います。それ以前ではない「後の日」というのは、天的な神の現実が、その栄光の中で地に顕現する決定的な時期だからです。
それゆえに、近い(差し迫った)未来に関する預言的言明は、「後の日」についての言明とは異なる性質を持っています。近い未来においては、組織されたイスラエルの政治的・社会的共同体が多かれ少なかれ、直線状に続きます。そこでの預言的言明は、それらが象徴的・暗示的言語を用いている時でも、依然として象徴的な次元での成就を見い出すことが期待できます。
それに対し、「後の日」における成就(終末論の広義的意味における終末論的成就)は異なっています。ここでは象徴がリアリティーに取って代わり、それゆえ、成就に関する直線状の捉え方はもはや可能ではありません。つまり、解釈学的に言って、《前》終末論的預言成就(Pre-eschatological prophetic fulfillments)は、終末論的成就とは異なる性質を持っているのです。
そのシンプルな例としてマラキ3:3-4の預言を見てみましょう。マラキはここで、未来のある時点で、レビの子たちが主に受け入れられる義のささげ物を捧げるようになると預言しています。もしも考慮に入れているこの時期が《前》終末論的時であったのなら、ここでいう回復とは、レビ記で説明されている時系列に沿ったところの、義なる礼拝の回復のことだと思うのが自然でしょう。
しかしマラキ3:1-2の文脈をみますと、「後の日」という特別なフレーズこそ使っていないものの、これが、圧倒的な神の裁き及び、圧倒的な神の来臨に関する文脈であるだろうことが見て取れます。つまり、ここは「後の日」に関する文脈なのです。その場合、「ささげ物」の形態が絶対的に同じものであり続ける、と見なすことができるのか、そう明確ではありません。継続した〔動物による〕血のささげ物が尚も捧げられることになるのでしょうか。もしくは(場合によっては)ささげ物は賛美とあわれみのささげ物に限定されるのでしょうか(ヘブル13:15、ピリピ4:18、ローマ12:1、15:16と同様)。継続したささげ物の性質は、聖めのための最終的、決定的犠牲がなされた時に変化が起こされたのかもしれません(マラキ3:2、4:1ー3、参:ヘブル10:1-3)。
幾人かのディスペンセーション主義の方々はもちろん、エゼキエル44-46章を基盤に、「千年王国期に〔動物による〕血のささげ物が再開する」と考えておられます。しかし、本章で私たちはエゼキエル書に関するさまざまな議題を取り上げることはしません。なぜなら、そこには、さらなる解釈学的議論が関与してくるからです。
要点は次の点です。「後の日」に関するほとんどどんな預言聖句であっても、私たちは「これは、千年王国期における、完璧に『直線状』にして『明白な』種類の成就のことを言っている」と主張することができます。ええ。それは実際、可能です。しかし、あらゆる場合において、それがかならず必然的に、その聖句の意図する純粋なる意味なのでしょうか?ここで問われているのは、はたして旧約聖書の聞き手たちが、「この聖句は最も明確な方法で成就しなければならない」と言うことを余儀なくされていたのか否か、という点です。
第二番目の例として、エレミヤの預言を取り上げてみることにしましょう。差し迫った未来におけるエレミヤの災いに関する預言(参:エレ24:1-10)と捕囚からの回復(参:エレ29:10-14)は、明白な仕方で成就します。しかしながら、エレミヤはまたより遠隔的展望をも持っていました。エレミヤはさらに絶頂ともいうべき成就のことを言っており、その時、モーセ的秩序の全体は、より力強く、親しく、有効性をもつ契約――新契約――に取って代わります(エレ31:31-34)。ここでエレミヤが終末論的リアリティーに触れていることは明らかです。そしてこの場合の成就解釈は、そう明白にというわけにはいきません。もちろん、この聖句に関して、現在、意見の不一致があります。ある方々は、成就を千年王国期におけるユダヤ人だけに関連づけて解釈しておられます。しかしどうでしょう。その他にも可能な解釈というのはもしやあり得るでしょうか?千年王国期の成就を否定することなく、さらに、新約聖書期における成就が存在する、ということを言うことはできるでしょうか?
イエスが来られると、「後の日」が開始します。特に、イエスはその死の際、ご自身の血潮によって新しい契約をお立てになりました(マタイ26:28)。しかし確かに最後の晩餐の記述の中に「新しい」という語が出てきているのか否かについての本文テキスト問題はたしかにあります。ですが、とにもかくにも、①契約についての言及、②罪の赦し(参:エレ31:34)、③モーセ契約の開始との並行ゆえ(参:エレ31:32)、そこに関連性があるのは確かです。
クリスチャンは聖餐に与ることによってこの契約への参与を祝います(ルカ22:19、1コリ11:24-26)。ですから、すべてのクリスチャンは、生物学的・社会的にユダヤ人であろうとなかろうと、それに拘りなく皆、新契約の参与者であるという結論を避けることは難しいと言えましょう(参:ヘブル10:11-22)。なぜならキリストはイスラエル人であり、クリスチャンはキリストに結ばれていますから、クリスチャンはエレミヤ書の中でイスラエルとユダに約束されている諸恩恵に与ります。
それでは、誰と新しい契約が結ばれたのでしょうか?そうです、それはイスラエルおよびユダと結ばれました。それゆえ、それはイスラエル人であるキリストの恩恵により、キリストゆえにクリスチャンと結ばれています。それゆえ、「イスラエルとユダ自身が、キリストの初臨の際、変化を経験した。なぜなら、キリストこそが最後にして、至高に忠実なるイスラエル人だから。こうしてキリストの周りにすべてのまことのイスラエルは集まるようになる」という方もおられることでしょう。とは言いましても、おそらく多くのディスペンセーション主義の方々は、新契約に関するエレミヤの約束に対するこうした解釈のことで、完全には私に同意できないと感じておられるかもしれません。ここでは詳細にこの問題に立ち入りません。ただここで肝要とされている問題は、ある特定の聖句に関することではなく、原則――預言解釈の原則――に関することです。
終末論的預言成就を解釈するに当たり、――それを《前》終末論的成就とは異なる基盤で解釈することに対しての――健全にして堅固な文法的・歴史的土台が存在するという事と私は申し上げたいと思います。エレミヤの時代のイスラエルの民は、(多くの場合、無意識的ではあったかもしれませんが)終末論的神の来臨の、世界を揺るがすような刷新的性格のことを理解していたはずです。
それゆえ、(例えばですが)「エレミヤ31:31の『イスラエルの家』および『ユダの家』は教義的確実性をもって、最も散文的、生物学的意味で解釈されなければならない」という風に主張するのは、文法的・歴史的解釈から逸れてしまっています。実際、そういった散文的、生物学的意味というのはむしろ、イスラエル人が経験上、短期的な預言として適用していたのではないかと思われます。
今、私が提唱しているのは、「元々の(文法的・歴史的)文脈において、終末論的指向性のある預言は、その中に付加的な可能性を組み込んでいる」という事に関してです。終末論に関する旧約の人々の立場は、短期的預言に対する彼らの立場とは異なっていました。つまり終末論的預言にはオープンエンドな示唆性があったのです。ですから成就の厳密なる詳細は、往々にして、――その成就が実際に起こるまでは――特定できないものでした。
偉大なる王の臣下としてのイスラエル
次に、王のしもべとしてのイスラエルを考察してみることにしましょう。神ご自身がイスラエルを治める王でした(申33:5、1サム8:7)。またイスラエルは特別な祭司の「王国」であり、神はその王国をご自身の律法で治めておられました(出エ19:6)。神がイスラエルと結んだ契約は、ヒッタイトの諸王が自分の臣下と結んだ宗主権条約にも似ていました(参;Kline 1963; 1972)。
イスラエルの存在と自己理解という《編み物》は、実際、神とイスラエルの契約および、王である神としもべであるイスラエルの関係という《生地》によって織りなされていました。地上的(人間である)イスラエルの王は、神の正義および神の統治の反映でなければなりませんでした(申17:14-20、1サム8:7)。そして彼は偉大な王である神の息子のようでした(2サム7:14)。このようにして、彼はまた、究極的な王であり御子を待望していたのです(詩2:7)。
その意味で、終末論ないし「後の日」は、神が、ご自身のしもべの救いのため、そして地に正義をもたらすため、絶頂なる方法でご自身の王としての御力を行使させる時に他なりません(イザヤ52:7)。神は全地を統べ治める王になられます(ゼカ14:9)。主の力強い御腕は、出エジプトの時と同様、すばらしく統べ治めるでしょう(イザヤ40:10)。そして神の王制の顕現は、その内に、人間としてのダビデの王制を内抱しています。
神はご自身の民の牧者となられ、ダビデは牧者になります(エゼ34:11、23-24)。一方の行動はもう片方の行動となります。「ダビデの家は神のようになる」(ゼカ12:8)。事実、ダビデの子が、「力ある神、永遠の父、平和の君」(イザヤ9:6)です。それゆえ、イスラエルに対する神の王制は、終末論的時において、決定的刷新・変化および完全な実現をみます。ダビデの系列にある(人間の)諸王とイスラエルの関係もまた変わります。そしてイスラエルそれ自体が変わります。なぜならそれは、王に対するしもべの関係によって成り立っているからです。
終末論的時に、しもべとしてのイスラエルは、唯一のまことのしもべ――神の救いそして神の統治を、イスラエルの諸部族だけでなく、全世界にもたらすお方――と神秘的に同定されます(イザヤ49:3,6、参:使徒13:47)。イスラエルは王の民であり、聖なる地は王の統治下にある地です。そしてその両者共、神の統治が到来する時に、象徴から現実へと移行します。
預言的御言葉の受け取り手としてのイスラエル:真の預言のジャンル
最後に、預言の背質および様態についてのイスラエルの理解について考察していきたいと思います。イスラエルの存在の中にあって、預言者たちのすべての預言は、モーセの務めを背景に読むよう意図されていました。預言者たちは主のための代弁者でした。
そしてモーセ自身は主のための代弁者の最高の模範として存在していました。またモーセを通し、主は後の預言の受容に関連した、イスラエルに対しての特定の諸指示を与えました。(特に民12:6-8、申13:1-5、申18:14-22において。)イスラエルは、①預言者たちが固く主だけを礼拝しているのか、そして②彼らの預言する内容がはたして成就するのか否か、によって預言者としての彼らの信憑性を試すことになっていました。そして①②の内容共に、預言者の使信に対する基本的了解度を前提としていました。
他方、民数記12:6-8は明らかにその他の預言者たちをモーセの下位に置いています。モーセは、自身の役割とメッセージの基礎的資質においてだけなく、啓示の様態においても、他の預言者たちを凌いでいました。モーセとは神は「顔と顔を合わせて」語りました(12:8)。そしてこれは幻や夢の中での、より遠隔的で間接的な現れの形態とは対照的です(12:6)。モーセに対して神は、「なぞで」話すことはせず、「明らかに」語りました。そしてモーセは、「主の姿を仰ぎ見て」いました(8節)。
それゆえに、モーセは、享受していた神との親密性の度合において、他の預言者たちを凌駕していました。彼は神の天的臨在の内的リアリティーに、より近くありました。「顔と顔を合わせて」「主の姿を仰ぎ見ていた」等の節は、モーセの、ダイレクトにして親密な神との出会いを特徴づけていると言っていいでしょう。
しかし、そういった明らかに強烈で絶対的な表現であっても、それら自身は相対的に理解されなければならないことを私たちは知っています。モーセでさえも、その最も深い意味において、ただ神の「うしろ」を見ることができただけであり(出エ33:23)、それも彼の生涯の中の絶頂ともいうべき一つの経験の中においてのみでした。
しかしもしも民12:8の表現が相対的だとしたら、後の預言者たちの〔神の〕臨在体験もまたモーセのそういった体験に関連していることがより容易に理解できます。イザヤ(イザ6:1-8)、エゼキエル(エゼ1等)、ダニエル(ダニ7:9-10)は主の栄光の啓示を見、強烈な種類の啓示を見ました。しかしそういった経験でさえも、民12:6-8を鑑みると、モーセの体験の下位に置かれなければなりませんでした。
「預言メッセージの明瞭性と直接性」は、「神の天的臨在に対する預言者の関係における明瞭性および直接性」に関連しています。モーセに対し、神は「明らかに語って、なぞで話すことはしない」(12:8)と仰せられました。そこから含意されるのは、モーセの下位に位置するその他の預言者たちは、夢や幻といったもので特徴づけられる(12:6)、よりなぞを帯びた形で語っていたということです。
もちろん、神はここで(後期のあらゆる預言的啓示のジャンルの)狭義にして技術的に正確なる特性を明言しておられるわけではありません。その中のいくらかは確かに夢や幻の中で与えられましたが(ゼカ10:2、ダニ7:1、8:1等)、その他の多くははっきりこの形態に入るわけではありません。むしろ、民数記12:6-8の箇所で神は少なくとも、解釈のゆとりという点での、広義で包括的な特性をお与えになっていると考えるのが妥当でしょう。
それゆえ、ただ表面的に民12:6-8を考慮するだけでも、古典的ディスペンセーション主義者は深刻な諸問題に直面することになります。ある人は、スコフィールドの次の格言を大切にしておられるかもしれません。――つまり、歴史的聖句は多くの場合、「霊的重要性」を持っている。しかし預言の聖句に見いだされるのは「絶対的字義性」であると(1907, 45-46)。
が実際、スコフィールドは危険なまでに、民12:6-8の秩序を反転させてしまう瀬戸際まで行っています。何といっても民12:6-8は、全聖書の中にあって、預言の様態および相対的字義性について明確に述べている数少ない箇所の一つだからです!しかしながら民12:6-8の挑戦は、これよりも深刻なものです。なぜなら民12:6-8は、より広範囲な文脈でみるなら、「天的なリアリティー」と「地上的な象徴」との間の関係についての問題を再び浮かび上がらせているからです。
イスラエルは地上にいました。堕落以来、彼らは神の臨在から離されていました。神の「御顔」、神の栄光、あらゆる属性の中にある神ご自身の現実といったものは、天の中心であり心臓部に当たります。地上におけるイスラエルと、この究極的中心との関係はどのようなものだったのでしょうか?出エジプト記33:23と民数記12:6-8はどちらも、イスラエルがこの究極的リアリティーに接近するに当たっての間接性および仲介的資質を強調しています。モーセの時代、モーセ自身が仲介者として仕えていました(参:申18:16、出エ20:18-21)。
預言者たちは、――ある点においてモーセには及んでいませんでしたが――モーセの型にならう仲介者たちでした。このように、預言者がsubordinate(従属的、副次的、補助的)である限りにおいて、イスラエルはその預言者のメッセージ自体がヴェールで覆われた/象徴的な性質をもっているのだろうと考えていたことでしょう。そうです。終末(eschaton)は、ヴェールの覆いが取り外される時です。――国々を覆っていたヴェールが外され(イザヤ25:7、イザヤ40:5)、またそれだけでなく、イスラエルの覆いが外される時です(エレ31:33-34、例えばイザヤ6:9-10との対照として)。
終末の時までは、イスラエル自身の存在は、モーセ立法の構造によって秩序づけられていました。それゆえ、モーセの体制に一致している短期的預言は、より「直接的」もしくは直列形の成就がもたらされることが眺望されていたのかもしれません。そして究極的な預言者――モーセ以上に偉大なるお方――が興る時、成就はその性質変更を余儀なくされます(使徒3:22-23)。預言の性質や預言的啓示の様態についての以上のような考察は、――祭司の王国および偉大なる王の臣下としてのイスラエルの存在についての省察により――イスラエルが到ることのできる諸結論と符合していると考えられます。
予型(よけい)について
予型(よけい:ギリシア語: τύπος, ラテン語: Typus, 英語: Type)は、聖書の解釈法のひとつである予型論的解釈で用いられる概念。旧約聖書における数々の事象(主な例:青銅の蛇)が、新約聖書におけるイエス・キリストおよび教会の予型(予兆・前兆)として記述されていると考える*29
予型の挑戦
前の章で、私たちはイスラエルの社会的・政治的構造、そしてその存在自体が象徴的な重要性を持っていたことを考察してきました。特に、モーセ時代、イスラエルが一つの国として構成された際、その社会的構造や性質は、神ご自身・主の御約束・天における主の栄光に満ちた住まいへの言及によって特徴づけられていました。それゆえに、モーセ立法制定の中の要素が持つ象徴的重要性には、「垂直的な」重要性があります。そしてその中のさまざまな要素が神とそのご人格、ご計画、天を指し示しています。
しかしこの重要性は同時に、水平的でもあり得ます。垂直的な方向に象徴が指し示している霊的諸現実は、栄光の内になされる、終末論的神の「来臨」の際に、この地において完全な形で顕示されます。それゆえに、象徴は時に、明瞭・不明瞭に前方を指し示す性質を持っています。それでは、古典的ディスペンセーション主義の方々が旧約啓示のこの象徴的側面をどのように取り扱っているのか、ご一緒にみていきたいと思います。
予型に対するディスペンセーション主義者のアプローチ(DISPENSATIONALIST APPROACHES TO TYPOLOGY)
もちろん、ディスペンセーション主義者も予型について知っており、それを研究しておられます。彼らは予型を、「新約のクリスチャンである私たちが旧約の中に見いだすことのできるなにかである」と受け取っています。しかしこれまで、ディスペンセーション主義者は、新約それ自体が残りの聖句を予型している(typologizing)という文法的・歴史的基盤についてほとんど語ってきませんでした。それはあたかも、旧約それ自身の内には、象徴的な省察を奨励するような箇所はどこにもなかったと言っているかのようです。それゆえ、彼らの内で、新約の予型は、――旧約時代にすでにそこに存在していた――旧約の象徴的含みから隔離されています。
さて、過去に用いられていたこういったアプローチは、スコフィールドの二分法聖書解釈のアプローチと非常に良く調和していました。この点のロジカルな関係性について、どなたか詳細に分析した方がおられるのか分かりません。ですが、この解釈法でいくと、旧約聖書は二つのレベルで読まれなければならないとされています。
レベルその1:
イスラエルに向けて言及されている旧約箇所は、非常に散文的(prosaic)に捉えるべく意図されていた。一方、天幕、さまざまな犠牲、族長たちの生活、王制、ダビデの生活などに対する象徴的意味については、イスラエル人によって、看過され得る――否、おそらくは看過されるべきものとされた。
レベルその2:
旧約聖書は、それらが教会に関連する時には、豊かな象徴的意味を生み出すべく意図されていた。
しかし「字義的」解釈のことで討論が進み、発展していくにつれ、上記のようなアプローチはますます困難になってきました。スコフィールドのような二重アプローチというのはどれも、まず先行的に、「イスラエルと教会に対する二つのパラレルな目的の間に存在する鋭利な区別」という前提からスタートしなければなりません。しかしそれ自身だけを論拠にしようとするなら、それはあまりにも恣意的と言わなければならないと思います。それでは、私たちはいかにして、より良い形で「字義的」解釈を定義すればよいのでしょうか?
それに対する最も確実な道は、この「字義的」解釈を、文法的・歴史的解釈と同一のものにすることだと思います。しかし、文法的・歴史的解釈が予型(typology)に直面する際に、興味深いことが起こります。さあ、文法的・歴史的解釈は、旧約の天幕、イサクの犠牲、ダビデの生涯などについてどのような取り扱いをするのでしょうか?これに対し少なくとも二つの回答が考えられます。
回答1.
「文法的・歴史的解釈は、上記のような聖句の中で、何ら象徴的含みを見い出さない、もしくは、見い出したとしてもほんの最小限に過ぎない。」とする立場。
しかしこの結論は、①新約それ自体とも、それから②ディスペンセーション主義者が旧約の歴史的啓示に関する多くの側面でこれまで解釈してきた内容とも衝突を起こしてしまうでしょう。
回答2.
文法的・歴史的解釈は、旧約の中にある多くの象徴的重要性を明らかにし、それらは、後に新約聖書の中で用いられているものに正しく従っている。
*そしてこちらの回答②の立場に私自身の見解は近いです。
しかし、もしもこれが真だとすると、象徴的・予型的重要性は、私たちが旧約預言に取り組む際にも消えることはない、ということになります。旧約預言は、モーセの啓示を背景として書かれています。もしも犠牲、神殿、土地、祭司制、王制などがモーセ時代に象徴的重要性を持っていたのだとしたら、――預言聖句の中で〔犠牲、神殿、土地といった・・〕同じものが言及され、暗示されている際には――その重要性は引き続き存在するということになります。
いや実際、預言者たちの後期啓示が、それ以前には比較的不明瞭であったある種のものに光を照らすにつれ、それはむしろより一層、増し加わり、より豊満になっていくと言えるでしょう。それゆえ、文法的・歴史的解釈はそれ自体として、預言者たちに対し、モーセを背景に解釈する事を強い、そしてそこから進み、象徴的・予型的要素を、未来に関する預言的言明にダイレクトに導入していくことになります。そしてこれは旧約の「歴史」と「預言」の間に厳密な区別を置くスコフィールドの解釈法と相反しています。
そうではあっても多くの現代ディスペンセーション主義者はなんとかここに自らを調和させようと努めておられるかもしれません。そして彼らは次のように言うでしょう。「旧約の歴史は、実際の(『字義的』)出来事や制度を指し示しています。象徴的含みは、出来事のリアリティーを無効にはしません。そして、同じ事が預言についても言えます。未来のことに関する預言は、象徴的な含みと、ストレート(『字義的』)な成就の両方を持しているのです。」ディスペンセーション主義者によるこのような承認は、重要な前進となります。なぜなら、これによって、「教会時代に対する二次的適用として、旧約預言を積極的に用いていく」という道が開かれるからです。
ディスペンセーション主義者は、今後も多かれ少なかれ、以前のような形態の「字義的」成就という捉え方を保持することが依然としてできます。しかし、旧約歴史の象徴的含みは、教会としての私たちに対する予型的教訓を含んでいます。そしてそれと同様、預言の象徴的含みは、――たといそれらがいわゆる「成就」に該当はしなくても――私たちに対する意味を持つことになります。さて、ここまで来ますと、ディスペンセーション主義者は再度、自らに問うことになるでしょう。「預言の成就とは本当に一体何を意味しているのだろう?」と。
前述しましたように、多くの旧約預言は、差し迫った未来において部分的成就を見たかもしれませんが――それでも今も尚、「後の日」の偉大なる成就の絶頂の時を待望しています。その時、主の栄光がはっきりと顕れ、旧約啓示の部分的で影的だったものは究極的・実体的なものに取って代わられます。そして、そのような諸預言は、最も広義な意味において「終末論的」です。
それでは、終末論的預言は、旧約歴史や旧約の諸制度(institutions)とまったく同じような仕方で作用するようになるのだと私たちは期待することができるのでしょうか?旧約の歴史は、象徴的な予型としての含みを持つ時、二つの次元を持っています。
①シンボル(symbol)それ自体としての次元、それから
②そのシンボルが象徴するもの、としてのもう一つの次元です。
さらに、シンボルというのは、ただ単に、時代を超越したいくつかの霊的真理を象徴しているわけではありません。つまり、それらはただ単に垂直的な指向性をもっているわけではないのです。シンボルはまた「時間」の中で、――少なくとも間接的に――終末論的預言の懸念である、まさにそれと同じ時期を指し示しています。こうした二つの次元性は、「旧約の啓示がその性質において、予備的であり影的である」という事実と密接な関係を持っています。終末論的預言は実に、これと同じ二つの次元を持っているのかもしれません。
①シンボル(symbol)それ自体としての次元、それから
②そのシンボルが象徴するもの、としてのもう一つの次元です。
しかし終末論的預言の成就の時は、クライマックスとしての啓示の時です。それゆえに、未来のその時、象徴(symbol)はリアリティーに取って代わられ、もはやリアリティーと平行した別々の歴史的認識を必要としなくなるのかもしれません。
予型としての神殿(THE TEMPLE AS A TYPE)
それでは神殿のことを例に取り上げてみましょう。聖書の中には、ソロモンの神殿、バビロン捕囚後にゼルバベルによって建てられた神殿、エゼキエル書40-48章で描かれている神殿、神殿を建てる者としてのメシア預言(ゼカ6:12-13)等が記されています。
神殿というのが旧約の領域における象徴的・予型的なものであることは皆同意しています。それは、人と共に宿る神の住まいを象徴する神の家です。またそれは天にある神の御住まいを型どって造られています(1列8:29-30、出エ25:40)。それは天にあるものの「写しと影」です(ヘブ8:5)。また神殿は、天にある神の御住まいを「垂直的に」指し示していますが、それと同時に、――やがて神と人との共生が全き実現をみる――終末論的「時」に向け、前方をも指し示しています。
またキリストのみからだが神の神殿であることにも皆さん、同意してくださると思います(ヨハネ2:21、参:ヨハネ1:14)。そして教会は公同的に、そしてクリスチャンたちは個々に、聖霊の宮です(1コリ3:16、エペソ2:21、1コリ6:19)。そしてここでの問いは、「はたして教会とクリスチャンは、ゼカリヤ6:12-13の中にあるような預言に関連しているのか否か?」です。
まず留意したいのが、キリストご自身がゼカリヤ6:12-13に関連しておられるということです。ヨハネ2:12で暗示されているキリストの復活は、明らかにゼカ6:12-13の成就の一部です。なぜなら、神のすべての約束は、キリストの内にあって成就するからです(2コリ1:20)。では、クリスチャンはどうでしょうか?クリスチャンはキリストと共によみがえり(エペソ2:6)、そして神の神殿であるキリストご自身が、彼らの中に宿っておられます(ローマ8:10)。そういう意味においてクリスチャンは神殿なのです。
そうであるならば、クリスチャンもまた、ゼカリヤ6:12-13にある神殿建設の預言成就の一部であると言うことを、なぜに回避することなどできましょう?それでは今、新約の中でなされている成就の型について見てみることにしましょう。新約時代、私たちはシンボリズムの第二番目の次元――つまり、物質的な石で作られた神殿――を必要としているでしょうか?旧約の中では、そこに二次元ありました。一つは「字義的」(石でできた神殿)、そしてもう一つは予型的・霊的なもの(神と人間の交わりにおける霊的リアリティー。現在、キリストの復活および聖霊の降臨により、それは実現している)です。
「もしも二つの次元があるのだとしたら、今もやっぱり二次元あるべきではないのでしょうか?」しかしそう反応してしまうと、私たちはヘブル人への手紙の主題を見落としてしまうことになります。ヘブル人への手紙によると、影なるもの(石でできた神殿)は、完全なものによって取って代わられる時、「廃止」され得るのです(ヘブル10:9)。
もちろん、新約時代それ自体は、神の御約束における最も完全にして豊かな実現を未だ含んでいません。そういった完全さが訪れるのは、新しいエルサレム、新天新地においてです。そしてその時にも、物質的、「地上的」な要素は残ります。私たち救われた者はその時、体外離脱の霊ではなく、復活のからだをもち、都に住む者となります。そしてその都は同時に、至聖所である神殿なのです。この事については次章でくわしくみていきたいと思います。差し当たり、旧約聖書における象徴的・予型的含みに関する解釈によっていくつかの挑戦がもたらされていることを受け止めたいと思います。
ディスペンセーション主義者は、こういった予型が、新約におけるキリストおよび信者たちに関する真理を予表(foreshadow)していることを躊躇なく認めておられます。ですから、ディスペンセーション主義者と対話をするにあたって、予型というのは話の自然な出発点になるでしょう。文法的・歴史的解釈は預言の中にそれと同じ象徴的・予型的重要性をみていますので、それは、「いかに預言が、新約の信者たちと有機的に一致した関係を持っているのか」を表しています。ですから、予型的関係は単なる二次的適用だとして片づけてしまうことはできない、ということになります。
この点における、古典的ディスペンセーション主義理論の主要な弱さは、この理論が、これまで「予型的解釈」と「文法的・歴史的解釈」との間の統合をなおざりにしてきた事にあります。
文法的・歴史的解釈への制限(A LIMIT TO GRAMMATICAL-HISTORICAL INTERPRETATION)
予型に関してですが、もう一つ困難な事が生じてきます。それは次のようなことです。前章で述べましたように、予型は、それが実際に成就されるまではフルに認識し得ないものです。予型はそれが語られたその時にはかなりの意味を持ちます。しかしそれはオープンエンドです。ですから私たちは漠然とした一般的な仕方では、いかにして預言成就がくるのかを予測することはできません。その詳細は依然として不明瞭です。しかし一旦成就がなされるや、それは元々のシンボリズムの重要性の上に、付加的な光を照らすのです。
換言すると、すべてを理解するためには、人は、後に書かれた聖句を、初期の聖句と比較検討しなければならないということです。しかしそういう比較検討の仕方ですと――本来、文法的・歴史的解釈を崩したり、矛盾させたりしてはならないのですが――それは文法的・歴史的解釈の境界線を超えてしまうことになります。なぜなら、その方法は、元々の歴史的・文化的文脈の中では入手不可能な情報を考慮に入れているからです。それゆえ、文法的・歴史的解釈では十分ではないということになります。もちろん、文法的・歴史的解釈は、私たちが特定の諸聖句を理解するに当たり、それらに統制や精錬をもたらす上での重要な役割を果たしています。
しかし私たちはそれと同時に、(そういった聖句が待望し、備えているところの)さらなる啓示に諸聖句を関連づけていく作業にも取り組む必要があります。この部分は大切です。なぜなら、聖書解釈に関するディスペンセーション主義者の言明にはこれまでほとんど常に、この部分が省かれてきたからです。実際、ディスペンセーション主義者の多くは、「非ディスペンセーション主義的な読み方では、『新約を旧約の中に読み直す(“reading the NT back into the OT”)』という風になってしまうから」という理由で、非ディスペンセーション主義的な聖書解釈を拒絶してこられました。
そうですね、そういう風に表現するなら、たしかにこりゃダメだという感じはしますよね。そして、これではまるで旧約が「読み直す」ことを支持していないかのように聞こえてしまいますよね?それに時折、ディスペンセーション主義者の主張は間違いなく的を射ています。実際、ある人々の「読み直し」行為は、旧約の文法的・歴史的解釈の影響を消し去ってしまっているのも同然だからです。
しかしここでの困難点からそう簡単に目を逸らすことのないようにしましょう。といいますのも、ディスペンセーション主義者自身もまた、予型を用いる際に、上で述べたこととかなり似たようなこと事をしてしまっているからです。また、多くの異なる聖書箇所からの聖句の統合解釈に依拠している「預言的体系(“prophetic system”)」を形成する際にもまた、ディスペンセーション主義者は同様のことをしてしまっています。
なぜでしょう?「聖書には一人の神的執筆者がおられる。だから、私たちははじめから終わりまで統一され首尾一貫した使信を期待することができる」という事実を鑑みる時、すべての解釈者は上記のようなことをせざるを得なくなるからです。それゆえ、私はディスペンセーション主義のみなさんに、次の二つのことを提案したいと思います。
(a)旧約歴史/旧約預言の両方における象徴的・予型的含みを真剣に視野に入れた文法的・歴史的解釈の理解にいっそう深め、その観念を発達させていってください。
(b)前期の聖句と後期の聖句を《一緒に》検討することによってのみ引き出される洞察と共に、文法的・歴史的解釈から得られる諸成果を豊かにしていくようなさってください。
*それから、(b)の際、みなさんは、旧約の歴史聖句の中における予型の時だけでなく、旧約の預言聖句の中における予型的・引喩的箇所においても、そのことを実践するよう努めていってください。
おそらく修正ディスペンセーション主義者の中には、すでにこの事をしている方々がおられると思います。そして、こうしながら尚且つ、将来的な千年王国期には、終末論的預言の大部分における比較的「ストレートな」形での成就があるということを信じることも可能です。私にとっては、そこは最も重要な問いではありません。むしろそれ以上に大切なのは、ここそこで、クリスチャンおよび教会における預言の成就がある、ということを認めることができるのかどうかという点です。そしてこの点が過去における論争の骨髄の一つでした。それゆえに、こうした〔予型の問題に関する〕一歩進んだ省察は、今後私たちを互いに結び合わせ、一致に向かわせる助けとなっていくことでしょう。
ヘブル人への手紙12:22-24
前章にて私は、ディスペンセーション主義について話し合いをする上で、ヘブル人への手紙が最も重要な聖句テクストであるということを申し上げました。聖書のどの箇所以上に、ヘブル書は、旧約の《新約への関わり方》に関する重要な問いを明確かつ詳細に述べています。さらに、この書簡の中には、前章で取り扱った予型に関する見解も明快に語られています。残念なことに、紙面の関係上、ヘブル人への手紙全部を検討することにはできないでしょう。そして本章で私はヘブル12:22-24に着目しようと思っています。
ここの聖句は、ディスペンセーション主義者の議論の中でこれまであまり注目を受けてこなかった箇所です。また、この聖句だけでは一連の議題解決には至らないとは思います。しかしこの箇所が、「シオンの山」および「エルサレム」の相続におけるクリスチャンの参与について語っている、その言及方法ゆえに、かなりの価値を持っているのではないかと思います。それゆえ、これらの聖句は、ディスペンセーション主義の方々が(「教会とイスラエルという別々のパラレルな宿命」、「教会における預言の非成就」に関する是認で特徴づけられている)固い部分をほぐす際にも助けになる箇所なのではないかと思います。
おそらく、ここの箇所がこれまであまり注目されてこなかったがゆえに、いや、まさにそうだからこそ、今後の新鮮な発展に向け、私たちの対話は実り多い出発点になるのではないかと思います。
シオンの山およびエルサレムの成就(FULFILLMENT OF MOUNT ZION AND JERUSALEM)
ここで中軸となる私たちの関心は、ヘブル12:22における「シオンの山」および「天にあるエルサレム」についての言及の意義にあります。一体何が、ヘブル書の記者をして、キリスト者の諸恩恵についてこのように語らしめたのでしょうか?特に、ここでヘブル書は、(ミカ4:1-2やイザヤ60:14のような旧約の預言聖句の成就として)クリスチャンがシオンの山に来ると言うことができる――それを含意しているのでしょうか。
シオンの山およびエルサレムは旧約の中で重要な意味を持っています。なぜなら、そこが、神ご自身の指示により神の神殿が建てられた場所だからです。そしてシオンの山およびエルサレムが持つ神殿との深い関係性ゆえに、これらは私たちが神殿と関連づけている予型の中で共有されているのです。ヘブル人への手紙の中で、地上の天幕(or 神殿)は神の天的住まいの写しであり影であるという事実がかなり述べられています。キリストが来られた時、主は、天にある実体にきよめをもたらす「さらにすぐれたいけにえ」を導入されました(ヘブル9:23、13-14)。
そしてキリストは、天にある神のまことの聖所に入る道を設けてくださいました(ヘブル10:19-20)。ヘブル12:22のシオンの山および天にあるエルサレムもまた同様に、――旧約聖書のシオンの山およびエルサレムが「写しであり影である」ところの、それの――天にある実体であるにちがいないということになります。
多くのディスペンセーション主義の方々(古典的ディスペンセーション主義者&修正ディスペンセーション主義者)は、この地点までは皆さん、私に同意してくださっているはずです。これまで、ディスペンセーション主義のみなさんは、シオンの山およびエルサレムについての旧約歴史の聖句における予型的意義を認めることに何ら困難を感じてこられませんでした。しかしディスペンセーション主義者は、次に私が提言する内容に対してはためらいを覚えるかもしれません。まず申し上げたいのが、予型に対する《対型(antitype)》の顕れは、預言成就にかなり等しいものであるということです。

《予型》=像、象徴。
《対型》=本体、表象されているもの。
例えば、ヘブル書全体を鑑みる時、キリストのいけにえは、旧約における動物のいけにえの《対型》であるということです。そしてこの動物のいけにえは、キリストのいけにえを指し示す予型であったわけです。キリストのいけにえは、――イザヤ53章だけでなく、ダニエル9:24の「咎を贖い “atone for iniquity”」をも含めた――旧約歴史のいけにえが指し示していたものの終点であり、完成した産物です。キリストのいけにえはまた、完全ないけにえについての諸預言の成就でもあります。

それでは、こうした「いけにえに関する状況」と、「エルサレムに関する状況」との間にアナロジー(類比)を見ることはできるでしょうか。ヘブル12章の、天にあるエルサレムは、注ぎかけられた血の付いた大祭司としてのキリストの臨在によるものです(ヘブル12:24)。それゆえ、天にあるエルサレムは、《予型》としての旧約の歴史的聖都であるエルサレムに対する《対型》であるように思われます。それゆえ、これが同時に、完全に回復されたエルサレムについての、諸預言の成就であると見ることもできるかもしれません(ミカ4:1-2、イザヤ60:14)。
前章で考究しましたように、これは決して文法的・歴史的解釈に対する侵害ではありません。旧約の中のいけにえ、神殿、聖都の象徴的意義のいくつかを認識する文法的・歴史的解釈は、エルサレムに関する預言的資料の中における象徴的(予型的)意義をも認めています。
アブラハムの希望
私たちは、ディスペンセーション主義者にとって、より受け入れやすい経路で同様の結果にたどり着くこともできます。とりあえず今、「新約時代がはたして『成就』であるか否か」の議題を脇に置くことにします。それでも尚、シオンの山、エルサレム、そしてパレスティナ全体に対しての高揚された栄光、富、聖めに関する旧約預言が存在します。こういった預言は、土地の相続に関するアブラハムに与えられた根本的諸約束を膨らませ、深化させています。
それではアブラハムは神の御約束を基盤に何を待ち望んでいたのでしょうか。ヘブル書は、アブラハムが「堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいた」そして「その都を設計し建設されたのは神です」(ヘブル11:10)と言及しています。そしてそこから数節後にヘブル書はさらに説明を加え、アブラハムが、生前、約束された国を相続することのなかった寄留者であることを記しています。
「しかし、事実、彼ら〔アブラハムおよび彼の子孫たち〕は、さらにすぐれた故郷(a better country)、すなわち天の故郷にあこがれていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました」(ヘブル11:16)。*30
それゆえ、アブラハム自身、天にあるcountry(πατρίς; 故郷、ふるさと)の所有に関与する御約束を理解していたのです。そして天にあるこの故郷は、――ヘブル12:22にある天にあるエルサレムである――「都」を中心としています。さらに、アブラハムは今すでにこの都に属しています。なぜなら、彼はヘブル12:23で言及されている「全うされた義人たちの霊」の中に含まれているからです。それゆえ、ヘブル12章は、この時代の内に、アブラハムに対する約束の成就があるということを示しています。しかしこれは究極的終点ではなく、成就のもっとも拡張された実現形でもありません。それはこれからの後に起こることです。しかしそれが依然として成就であることには変わりがありません。この成就はアブラハムや族長たち自身に訪れました("The fulfillment has come to Abraham...")。
しかしそれではユダヤ人クリスチャンはどうなのでしょうか。彼らは現在、アブラハムの相続を共有しているのでしょうか。ええ、彼らは「シオンの山、天にあるエルサレムに近づいているのです」(ヘブル12:22)。つまり、彼らはアブラハムが約束の成就の中で待ち望んでいたまさにその都に住むべくそこに近づいているのです。ユダヤ人クリスチャンは、キリストを信じたことにより、以前より劣ったアブラハムの子になったわけではありません。また彼らはアブラハムの信仰に倣ったために、そのために相続権を奪われたとか、そういうわけでもありません!それゆえに、彼らの存在もまた、アブラハムへの約束成就の一側面なのです。
次に、異邦人クリスチャンはどうでしょうか?彼らはシオンの山に近づくことができるでしょうか。もちろん、できます。なぜなら、福音により、彼らは、ユダヤ人クリスチャンと共に等しく御父に近づくことができるからです(エペソ2:18-19)。彼らはアブラハムへの祝福を共有しています。そしてこれは「地上のすべての民族は、あなたによって祝福される」(創12:3)というアブラハムへの御約束と完全に調和しています。そして使徒パウロはまさにこの論点をガラテヤ3:7-9、3:26-4:7の中で展開しているのです。それゆえ、シオンの山へ異邦人クリスチャンが近づくこと(ヘブル12:22)は、アブラハムへの約束の成就でした。
ディスペンセーション主義者のある方々は次のように言うかもしれません。「それは美しい適用ではあるけれども、本当のところの成就というわけではないです」と。これまでご一緒に見てきました通り、その答えは、ディスペンセーション主義体系の《内側》では、常に通用します。しかしヘブル書で言及されているこの祝福が成就でないとするなら、それが一体何であるのか私には見当がつきかねます。ヘブル書はアブラハムがこの都を待ち望んでいたと言っており、アブラハムへの約束は、「異邦人たちがこの祝福に内包される」ということを言っています。このように、アブラハム自身がそれを成就とみなしているわけですから、私たちとしてはそれに対して何をどう反論していいのか分かりません。
しかしディスペンセーション主義者はここで一つの重要な点を指摘してくださっています。それはヘブル12:22における成就は、あくまでも成就の一つであり(“a” fulfillment)、アブラハムへの約束の最も偉大・壮大・クライマックスとしての実現ではないという点です。そうです、それは未だ起こっていません。そしてこの事実を過少評価するなら、私たちは過ちを犯してしまいます。その一方、幾人かの(幸い、全員ではありません)ディスペンセーション主義者は、異邦人クリスチャンにおける成就に対する露骨な否定によって、対極側にある誤謬を犯しています。
黙示録における新しいエルサレム
〔ディスペンセーション主義〈前〉千年王国説論者および歴史的〈前〉千年王国論者の別に関わりなく〕すべての前千年王国説論者は、「アブラハムへの約束は、キリスト再臨に続く、千年王国期に、より完全な形での成就を見る」ということを信じています。さて議論を進めるために、まずここで、前千年王国説が正しいと仮定することにしましょう。
しかしそう仮定したにしても、これだけで一件落着というわけにはいきません。といいますのも、黙示録21:1-22:5における新天新地にて成就されるべき諸約束が未だ残っているからです。そしてそれがヘブル12:22と関連しているがゆえに、この最終的成就は重要なポイントです。ここにすでに困難点があります。黙示録21:1-22:5における事象の性質に関し、ディスペンセーション主義者たちの間で意見の不一致があります。
確かにほとんどの方は黙21:1-7が「永遠の状態」を描写しているということに同意しています。しかし黙21:9-22:5はさまざまな解釈のされ方をしています(Pentecost 1958, 563-83)。あるディスペンセーション主義者たちは、ここの箇所は永遠の状態を表していると考え、別のある人々は「いや、ここの箇所は千年王国を表している」と考えています。J・ドワイト・ペンテコステはここの解釈として、「これは両者の組み合わせである」という見解を好んでいます。①黙21:9-22:5における天にあるエルサレムは、すべての聖徒の永遠なる住まいとなる、②しかしそれは千年王国期に存在するものとして描写されている。
さて、黙21:9-22:5と、黙21:1-7の間に密接な関係があることに皆、同意しています。それゆえ、それ以外のあり方を示唆する諸要因がない限り、文法的・歴史的解釈は、「その両方の箇所が、同じ状況のことを描写している」と結論づけることになります。もし私たちが、永遠の状態は新しい地を含むのだということをしっかり念頭に置き続けるなら、黙21:9-22:5のいくつかの側面における明らかに「地的(“earthy”)」な性質は、永遠の状態と実に調和していることに気づかされます。
黙示録22:2にある諸国の民の癒しに関する言及でさえも、黙21:4の「彼らの目の涙をすっかりぬぐい取ってくださる」からほとんど離れていません。両者とも、黙示録の主要部分にみられる苦しみや不完全性と対比をなしています。実際、私たちが、――「永遠の状態というのは、千年王国と共通するいくつかの特徴点を持っているはずだ」という独断的前提でスタートするのでない限り、――黙21:9-22:5が永遠の状態であるという事に対しての反論内容はどこにもありません。
しかし、黙21:9-22:5が、永遠の状態において天から下ってくるエルサレムの初期段階であるということを少なくとも認めるならば、黙21:9-22:5が永遠の状態を描写しているということを立証する必要さえありません。そしてこれは全ての人が認めなければならないものです。なぜなら、天にあるエルサレムは揺り動かされないものであるからです(ヘブル12:28;参 Pentecost 1958, 580)。黙21:9-22:5を解釈する上でどちらの選択肢を採ろうとも、黙21:1-7および21:9-22:5その両方の中で記されている新しいエルサレムは、ヘブル書の「天にあるエルサレム」との根本的連続性の内にあります。
もちろん、黙示録21章の新しいエルサレムは、ヘブル書が書かれた時点よりも後期の状況を描写しています。ですから、今(ヘブル書)と、かの時(黙示録)の間には、啓示において、そして神の御目的の働きという点において前進があります。しかし、それにも拘らず、両者の間には連続性があります。それを支持する根拠として下に何点か挙げます。
(a)「エルサレム」という名称が両者の密接な関係を示しています。
(b) 黙示録21章の新しいエルサレムは、「天から下って来」、それはヘブル12:22のエルサレムの位置です。
(c) ヘブル12:22のエルサレムは、「揺り動かされない御国」(ヘブル12:28)として描写されているものの様相です。そしてこれは、たとい天と地が揺り動かされても消え去ることのないものです。
(d) アブラハムは天にあるエルサレムを待ち望んでいたとヘブル書は言っています(ヘブル11:10、16)。そして黙示録の中において、アブラハムの行き先は新しいエルサレムでなければなりません。よって、この両者は同一のものです。
(e) ディスペンセーション主義の注解者たち自身が、何の苦も無く、この両者を同一のものとして認めています(Kent 1972, 272; Newell 1947, 426; Pentecost 1958, 579; Walvoord 1959, 326)。
そしてもしもこれら全てが真なら、クリスチャンは今、天にある都の、アブラハムの相続に共に与っています。それゆえ、彼らはまた、それを将来も共有することになります。ユダヤ人と異邦人を、二つ別々の起源を持つ民として区別するのは正当なことです。しかしながら、(もしも彼らが神の御約束を信じるようになった場合)彼らの行き先(destiny;宿命)は同じです。両者共に、天から下ってくる新しいエルサレムの相続に与ります。それゆえ、「二つのパラレルな宿命」、一つは天的で、もう一つは地上的という考えは消え去ります。
新しい地(THE NEW EARTH)
ディスペンセーション主義者の中には、「あなたがたは、天と地の間に存在する適切な区別という部分に焦点を当てていない」と反論される方々がおられるかもしれません。「クリスチャンは天にあるエルサレムに参与します。しかし、イスラエルは、千年王国期に、地上的エルサレムにおいて、地上的成就をみなければなりません」と。
しかし黙示録21章において、新しいエルサレムは天から地に下って来ます。そして旧約預言の地上的成就はそのクライマックスを黙示録21-22章の内に見いだします。アブラハムは確実に、この地上的成就に参与します。そして他のユダヤ人たちも参与します。またユダヤ人クリスチャンは、彼らがアブラハムの信仰に倣ったからといって、それでユダヤ人の相続を奪われるということにはなりません。ゆえに、彼らも参与します。
しかしさらに、異邦人クリスチャンもまた参与しなければなりません。なぜなら、彼らはユダヤ人であるキリストと結ばれているその恩恵によって共同の相続人とされているからです(エペソ3:6)。それゆえ、黙示録21-22章において、天的/地上的それぞれの「宿命」の間の厳密な分離性は不可能です。新しい地で、クリスチャンはアブラハムの約束の地上的実現に関係しています。さて、彼らは天にあるエルサレムの一員であることを享受していますから、アブラハムの約束における最初の一コマ(first installment)を経験しているのです。
もし私たちの中のある方々が、成就におけるクリスチャンの参与という点を拒絶されるのなら、それはその方々が「字義的」成就をあくまで強く主張しているからではないのです。実際、黙示録21:1-22:5におけるエルサレムは、各自好きなだけ字義的に解釈することも可能ですし、それはクリスチャンの参与に反対するようなことは何も言っていません。そして、もし私たちがクリスチャンの参与を拒むのだとしたら、それは(いわゆる「字義的」解釈に対するこだわりというよりは)むしろ、「天的な宿命」と「地上的な宿命」との間にどうしても厳密なる区別を保持し続けたいという、その方々の要望が原因です。
そして、二つ別々の宿命という主張は、「人々が別々の起源を持っている」という(まっとうな)主張以上のなにか、そしてそういったまっとうな主張とは異なるなにかを言っています。そして事実、「別々の宿命」というこの考えは、全く聖書聖句からの根拠なしに、体系化された諸理論の中に組み込まれています。一部のディスペンセーション主義者は、天と地の間に設定するこういった厳密な区分化(compartmentalization)は間違いであるということを認知するようになってきています。ケネス・バーカー(1982, 12)は次のように言っています。

Kenneth Barker
「厳密に言って、イスラエルを地上的な民、教会を天的な民と呼ぶことも間違っています。なぜなら、永遠の状態において、私たちは皆、新しいエルサレムそして新しい地の祝福を共有するようになるからです、、、」
ですから、多くのディスペンセーション主義者が認めようとしている程度以上に、この地とその民に対する、神の壮大な企図、そして主の総合的目的および包括的計画の中における、より壮大なる一致ないしは統合性が存在しているのです。過去、私たちの中のある人々は、「木を見て森を見ず」の状態にありました。私たちは区分化・区画化をし過ぎていたからです。
ヘブル11:16と12:22の重要性
それではまとめてみましょう。黙示録21-22章は、私たちが話し合いをする上で貴重な聖句です。なぜなら、新しい地に対するこの聖書箇所の強調は、クリスチャンとイスラエルそれぞれの最終的行き先(destiny)が同様であるということを示しているからです。そしてこれは――天と地ほども違う「二つの別箇の宿命」という考えを強調する――最も厳格な形態のディスペンセーション主義にとってはすでに挑戦です。
またヘブル12章は、①クリスチャンがすでに黙示録21-22章の成就の前触れを経験している、②それゆえ、彼らは旧約の「ユダヤ人の(“Jewish”)」約束に関与している、ということを示しているという点で重要です。
最後に、ヘブル12章は、それが天と地に関連する仕方において注目に値します。古典的ディスペンセーション主義は、天と地を単に、――教会とイスラエルという二つ別々の宿命が実現するという――二つ別々の領域として解釈していました。しかしヘブル12章は、その二つを「影」と「本体」、「歴史的待望」と「成就」という観点で、互いに相関性を持ったものとして捉えています。それゆえ、この事実は否応なしに、ディスペンセーション主義者を、「パラレルな軌道を走る教会とイスラエルという垂直的配置」から引き離し、彼らを、連続した歴史的諸段階に属している、教会およびイスラエルの歴史的・予型的な配置へと導いていきます。
しかしことわっておきますが、ヘブル12:22-24をベースにしたこれらの議論は、「旧約預言のどの部分も絶対にクリスチャンや教会において成就していない」と主張する、より厳格な形態のディスペンセーション主義に対し、より一層の重要性があるということです。エリック・ザウアーやその他の人々は、千年王国期における最も字義的なる成就をみているものの、教会における成就はしっかりと認識しておられます。そしてこういった立場の人々は、ヘブル12:22-23における主要な含意のいくつかを会得しています。千年王国期におけるアブラハムおよびクリスチャンに対する成就の、統合された性質についてのさらなる考察により、――あらゆる世代を通した歴代の神の民の宿命や相続における根本的一致を見る方向へと――私たちはさらに進んでいきます。
キリストにあるイスラエルの成就
古典的ディスペンセーション主義を特徴づける中心的原則は、イスラエルと教会の「パラレルにして別々な宿命」という原則です。それによると、イスラエルと教会は神の二つの民であり、一つは地上的、もう一つは天的です。この章では、この原則を組織神学の観点からご一緒にみていきたいと思います。しかし覚えていただきたいのは、現在、多くのディスペンセーション主義者はパラレルな二つの宿命というこの原則を修正しています。それゆえ、本章の考究はそういった方々には当てはまらないかもしれません。
一方、この「二宿命原則」を保持しておられる方々にとって、その原則への最も鋭利にしてダイレクトな挑戦は、キリストにある成就に関する聖書的教えの省察より生じてきます。
旧約の約束の相続人になる
すでに前の章で私は、旧約の預言的御約束と教会との関連性について述べました。「教会はイスラエルの直線的連続だ」などと私たちが露骨で短絡的な主張をしないのでしたら、この主張は強固なものになります。私たちは、諸約束の成就の中心点としてのキリストご自身のやり方に従うべきです。そして、キリストは完全なる意味においてイスラエル人です。実際、すべてのイスラエルが不忠実さゆえに拒絶されても(ホセア1:9)、キリストは究極的に忠実なるイスラエル人――究極的「残された者」としてとどまります(参:イザヤ6:11-13、11:1)。
それゆえ、2コリント1:20は、「神のお立てになった御約束がどんなに多くても、それらはことごとくキリストにおいて『しかり。』となる」と言っています。そうなると次のような問いが残ります。「イエス・キリストとの合一は、クリスチャンに何をもたらしているのでしょうか?」教会は、キリストとの共同相続人にされた(ローマ8:17)ということも含め、キリストを通した神の祝福の全き満たしを受容しています(エペソ1:23、コロ2:10)。
つまり、私たちは主が相続されたものを相続しているのです。そしてキリストがアブラハムの子孫であるゆえ、私たちはアブラハムの子孫です(ガラ3:29)。さらに主と一つにされていることにより、私たちは全世界を所有しています(1コリ3:21-23)。そしてこれは、キリストとの合一の性質についての考察によってさらに強化され得ます。
キリストと一つに結ばれることは、親密にして、個人的で、経験的なものです。しかしそれだけではありません。キリストとの合一は、それに公同的次元(corporate dimension)をも加えるものです。教会は、それぞれのメンバーのキリストとの合一、および互いの間の合一によって形成される公同的有機体です。しかしパウロはキリストとアダムとの間のアナロジー(類比)を指摘することにより、私たちの視野をさらに拡げています(ローマ5:12-21、参:1コリ15:45-49)。
アダムの堕落は、完全に人であるお方――新しい人類のかしらとして立っておられる人――によって克服され、覆されました。古い人類(アダムに結ばれていたすべての人)は、ひとりの人アダムを通して罪と破滅と相続権・交わりのはく奪状態へと落ち込みました。それに対し新しい人類は、「最後のアダム」であるイエス・キリストを通して義、救い、相続、神との交わりを得ました。
神の民とは、イエス・キリストが彼らのかしらとして代表し、仕える人々です。先に私たちは御約束の相続について考察してきました。しかし、相続というのは、より壮大な鳥瞰図の一部分に過ぎません。そしてこの壮大な鳥瞰図というのが新しい人類のことなのです。新しい人類は、アダムの堕落とは対照的に、義、救い、相続、交わりを受けます。神の民の合一は、イエス・キリストというひとつのかしらの合一によって保証されています。私はこれについて前の章で述べました。しかし今、この事実が、古典的形態のディスペンセーション主義者にジレンマを与えています。幾人かのディスペンセーション主義者は無防備な発言をしていますが、彼らは救いには一つの道しかないということを保持しようとしています。
すべての経綸において、救われる人は誰でも、神の御約束にある信仰により、主の恵みによって救われます。しかし仮に私たちがこの救いの道についてさらに深くさらに詳細に述べようとしているとしましょう。それは神の恵みによります。しかしその「恵み」とはどういう意味でしょうか?義なる神が不義なる者を救うことが一体どのようにして可能なのでしょうか?神の恵みは、イエス・キリストの代理的贖罪と密接な関係があります。また恵みは、キリストがご自身の使命を完了される前にすでに与えられていましたが、それはその御働きを予知する中で与えられました(ローマ3:25)。
それでは信仰とはどういう意味なのでしょうか?信仰とは信仰のための信仰でもなく、空虚なものへの信仰でもありません。それは神の御約束に対する信仰であり、イエス・キリストによって完全に成し遂げられる救いの日を指し示す、ご自身の契約的公約(commitments)に対する信仰です。
そしてこの御業が成し遂げられる時、私たちは、イエス・キリストの御業は最後のアダムの御業であることを見ます。そして、救いに関わるひとつの働きの合一は、キリストにあって救われた新しい人類の合一を含意していることを見い出します。ゆえに、そこから導き出される結論は、神の一つの民ということになるでしょう。この点に関し、ダニエル・P・フラー(1957, 178)は、このジレンマのことを次のように明確に表現しています。

Daniel. P Fuller
「、、、彼ら〔ディスペンセーション主義者〕は、救いは〔神の御言葉への信仰そして血潮により〕いつも同一の方法で施行されると考えたいと望んでいます。その一方、彼らはこの考えから導き出されるロジカルな結論、つまり、救われた人皆が、〔イスラエルも教会も差異なく〕同じ立場にある、ということは受け入れようとしたがっていません。」
救いからイエス・キリストの公同的合一へ
このジレンマは――救いの側面から始まり、公同的合一で終わる――、一連の漸進的諸段階を提示することでより一層明らかにされるでしょう。その各段階において、私たちはキリストとの合一がひとつにして唯一の祝福の手段であることを強調します。
さて最初の地点において、私たちが救いの側面を考える際、ディスペンセーション主義者は、救いの方法における統一性を保持すべく、合一に対する強調に進んで同意しようとします。そして終点において、私たちが公同的合一の側面を考える際、ディスペンセーション主義者は「神の二つの民」という自らの思想を取り壊さなければならないという状態に気づきます。
ではまず初めに、救いの側面としての義認について考えることにしましょう。救われる者は信仰によって義とされます。さらに義認は究極的に代償的行為です。キリストの義が私たちにとって肝要であり、私たちの罪はキリストの上に置かれました。私たちは「キリストにあって義と認められ」ています(ガラ2:17)。次に、変えられたいのちの力もまたキリストより来ます。私たちは「キリストにあって聖なるものとされ」ています(1コリ1:2)。また霊的な実はキリストの内に宿ることによって流れ出てきます(ヨハネ15章)。ここでのキリストとの合一の言語は、ガラテヤ3章のそれと非常に類似しています。
この義認に関する文脈の中で、パウロは私たちが「キリスト・イエスに対する信仰によって、神の子どもです」(ガラ3:26)と言っています。そしてパウロは続けて私たちは「みな、キリスト・イエスにあって、一つ」(ガラ3:28)と言っています。そしてさらに鋭く公同的強調をもった表現を見い出すことができます。私たちは「一つのからだとして」和解し(エペソ2:16)、「キリストにあって」「一つのからだ」(ローマ12:5)、「キリストのからだ」(1コリ12:27、エペソ1:23)となりました。
キリストとの合一は、(義認、子とされること、聖化を含めた)「救い」と、「公同的合一」その両方がしっかりと織りなされる形の、有機的な関係です。人はキリストとの合一なしには救われ得ず、キリストとの合一は、神のひとつの民の一部になることを意味します。しかしディスペンセーション主義者は、旧約の神の民は現代の私たちと同じような仕方ではキリストとの合一を享受していなかったということにすぐに気が付きます。
――キリストはその時はまだ受肉されておらず、死んだ後に復活もされておらず、聖霊のお遣わしになっていなかった。それらは全てその通りです。
しかし旧約においては人々はどのようにして救われていたのでしょうか?彼らはそういった事柄への待望により、またそれらの効力の一種の予備的「後方作用(“working backward”)」によって救われていました。そしてディスペンセーション主義者であれ非ディスペンセーション主義者であれ、救いの道の統一性(unity)を主張する人は、何らかの形でそのことを認めなければなりません。
しかしそれはまた私たちを次の結論にも導きます。つまり、イスラエルと教会の間の相違というのは根本的に、救いを完遂すべくキリストが来臨される「前」と「後」における神の民の間の相違であるということです。それはユダヤの血統の人々の将来についての問いによっても、別の方法でその含意が見い出されるでしょう。こういった人々はどのようにして救われ、そして彼らの相続に与るのでしょうか?今やキリストがご自身の業を成し遂げてくださり、救いはもはや予型や影、予測や予兆といった事柄ではなくなりました。
救いはキリストとの合一によるものであり、それ以外の方法はありません。そしてその救いは、現在であれ千年王国期であれ、ユダヤ人および異邦人をして、キリストの「構成員」と成さしめます。彼らは新しい人類として公同的にひとつです。それゆえに、キリストというひとつのかしらの下にあるこういった新しい人類を二つに引き裂くということはもはや考えられないという事になります。そして、私たちは千年王国を眺望する時、そこにおける救いが――最後のアダムであるイエス・キリストというひとりの人との合一であるにもかかわらず、その合一が、「一つは地上に、もう一つは天にあるという《二つの相続》、《二つの宿命》をそれぞれ持つ、《神の二つの民》」という区別によって弱体化される、というような事をもはや考えることができなくなります。
将来的な探求のための他の領域
これまでディスペンセーション主義者との実り多い対話の場を作り出す上でもっとも大切だと思われるポイントに触れてきました。この章ではさらなる探求のための、その他のポイントを提示したいと思います(その中のいくつかはすでに少し言及しています。)ある場合には、少なくとも、こういった論点は、アプローチのための相補的方法を提供するものとなるかもしれません。
今後話し合いを深めたいテーマ
―前述しましたように、ヘブル人への手紙は、旧約解釈について、他のどの書にまさって克明な取り扱いがなされています。旧約理解に影響を与えている解釈学的諸原則を明らかにすべく、ヘブル書全体の学ぶがなされるといいかもしれません。
―旧約からのマタイの引用は、議論の余地のない預言成就の事例です。なぜなら、マタイはしばしば、「~と言われた事が成就するためであった」という引用句を用いているからです。これもまた、旧約預言の解釈学的諸原則の検証のための、一つの出発点となるかもしれません。
―黙示録21:1-22:5は、直接的に旧約から引用しているわけではありませんが、それでも旧約言語に溢れ、また旧約諸聖句への含みで溢れています。旧約の預言が黙21:1-22:5の中で提示されている像の中で成就されている仕方に焦点を当てて、話し合いをすることも可能でしょう。そしてこれは、次の二つの方法でディスペンセーション主義者に影響を与えると思います。
(1)少なくとも何人かのディスペンセーション主義者は、千年王国期における預言成就に注目し過ぎてしまっていて、より完全なる成就としての万物の成就(consummation)に殆ど注意が向けられていない傾向がみられます。そういった方々にとって私たちの話し合いは良い挑戦を与えるものになると思います。
(2)黙21:1-22:5は、天と地を統合しています。またこの箇所は、教会に適用される像(ガラ4:26)およびイスラエルに向けられている旧約預言(参:エゼキエル47、イザヤ60:19-22)を統合しています。神のひとつの民の合一と、「字義的」成就の性質についての問いは、この文脈の中で実り豊かに提示され得ると思います。
―以上が、1986年初版の完訳です。―
ジョージ・ラッド著『終末論』(第2章 イスラエルについてはどうか。)
第1章において、旧約聖書はイエス・キリストにおいて与えられた新しい啓示の視点に立って解釈されなければならないという聖書解釈の原則を確立した。では新約聖書は、イスラエルについて何を教えているのだろうか。
旧約聖書は、イスラエルの未来における救いを見ているが、新約聖書はその預言を大幅に再解釈して、それらが教会において霊的に成就されるべきであるとしているのか?すなわち、教会は新しい真のイスラエルなのか?あるいは、神はまだご自身の民イスラエルのための未来を用意しておられるのか?
幸いなことに、霊感された聖書の中には、この主題についての詳細な議論が記されている。それがローマ人への手紙9-11章である。パウロは最初に、イスラエル民族がメシヤとしてのイエスを拒絶したことに対し、「私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります」(ローマ9:2)と、肉における同胞に対する心底からの関心と愛を吐露している。
パウロの最初の論点は、「イスラエル」つまり真の霊的イスラエル――神の民――はアブラハムの肉的子孫と同一ではないということである。「イスラエルから出る者〔本来の血縁の子孫〕がみな、イスラエル〔霊的な子孫〕なのではなく、アブラハムから出たからといって、すべてが子どもなのではなく・・・・」(ローマ9:6-7)。
パウロはこのことを証明するために旧約聖書の歴史を思い起こさせる。アブラハムには二人の息子、イサクとイシュマエルがいた。しかしイシュマエルの家族とその子孫は、アブラハムの本来の血縁の子孫であるが、霊的子孫には含まれない。
「イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれる」(ローマ9:7)、「すなわち、肉の子どもがそのまま神の子どもではなく、約束の子どもが子孫とみなされる」(ローマ9:8)。
神はイサクを選び、イシュマエルを拒絶された。それゆえアブラハムの真の子孫――真のイスラル――は、生来の肉的な血統において決定されるのはなく、神の選びと約束によって決定される。その意味は明らかである。パウロのいた当時のすべてのユダヤ人が、神の民「イスラエル」を名乗ることができるわけではない、神の民「イスラエル」を名乗ることができるのは、アブラハムの信仰に倣う人、約束の子であると自己証明する人だけである。
この原則は、すでにローマ人への手紙の始めの部分に系統立てて述べられている。ローマ人への手紙2:28-29でパウロは、「外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上のからだの割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による、心の割礼こそ割礼です。その誉れは、人からではなく、神から来るものです」と書いてある。
この《霊的割礼》対《肉的割礼》の原則は、パウロを起源とするものではない。この主題はすでに、旧約聖書に見い出されるものであり、パウロはそれを繰り返している。「ユダの人とエルサレムの住民よ。主のために割礼を受け、心の包皮を取り除け。さもないと、あなたがたの悪い行いのため、わたしの憤りが火のように出て燃え上がり、消す者もいないだろう」(エレミヤ4:4)。
モーセの律法への外側だけの従順のみでは、神の愛顧を確かに受けているアブラハムの真の子孫であるとは言えない。そこには、それにふさわしい心――そして生活――がなければならない。さもなければ、神の怒りと直面することになる。
この原則は、ヨハネの黙示録の二つの節にも適用されている。ヨハネはある人々について、「ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの会衆である」(黙示録2:9.3:9も参照)と言っている。ここには、ユダヤ人であると(正当に)主張できる人々がいる。確かに彼らは肉において、また宗教的にユダヤ人ではあるが、ヨハネは彼らのことを、霊的にユダヤ人ではなく、実際はサタンの会衆であると言う。メシヤとしてのイエスを拒絶して、イエスの弟子たちを迫害していたからである。
次にパウロは、もしそれが事実であるとしたら、神の身勝手さを反映しているのではないかという反論を取り扱う。この反論に対し、厳しいことばで答えている。
「しかし、人よ。神に言い逆らうあなたは、いったい何ですか。形造られた者が形造った者に対して、『あなたはなぜ、私をこのようなものにしたのですか』と言えるでしょうか。陶器を作る者は、同じ土のかたまりから、尊いことに用いる器でも、また、つまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか」(ローマ9:20-21)。
この箇所は、神の選びと個人の救いに対する拒絶という視点から解釈されることが多い。しかし個々人にどのような適用がなされるにせよパウロの論点は、第一義的には贖罪の歴史と、アブラハムに与えられた約束を受け継ぐ者として神がヤコブを選ばれたことである。
神は字義上のイスラエルの反逆や背教に多大な忍耐をもって耐えた。「それも、神が栄光のためにあらかじめ用意しておられたあわれみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためなのです」(ローマ9:23)。
神は字義上のイスラエルの不信仰に忍耐してこられた。それは、その忍耐を通して、真のイスラエルにあわれみを示すためだった。パウロは同じことを、同じ箇所の後ろのほうで取り上げている。
「では、尋ねましょう。彼らがつまずいたのは〔最終的に、回復不可能あ状態に〕倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって、彼らの違反によって、救いが異邦人に及んだのです」(ローマ11:11)。イスラエルはつまずき、不信仰となったが、そこに神はある目的を持っておられる。
神が忍耐をなくしたわけではない。イスラエルのつまずきもイスラエル自身のために起こったわけではない。むしろ、神はイスラエルのつまずきを、異邦人に救いをもたらすために用いたのである。パウロは前のほうの箇所で、この主張を発展させて述べている。「神は、このあわれみの器として、私たちを、ユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです」(ローマ9:24)。
神が怒りの器――神の裁きの下に立つ不信仰なユダヤ人――に取って代わるものとして選ばれた「あわれみの器」は、ユダヤ人と異邦人から成る混成体である。続いて、パウロは驚くべきことをする。旧約聖書の文脈ではイスラエルに言及している二つの箇所をホセア書から引用し、大部分が異邦人から成るキリスト教会に当てはめているのである。それによって、旧約聖書が異邦人の教会を予見していたことを証明しようとする。
「それは、ホセアの書でも言っておられるとおりです。『わたしは、わが民でない者をわが民と呼び、愛さなかった者を愛する者と呼ぶ』」(ローマ9:25)。
ホセアは姦淫の女をめとるように主から命じられた。その女は、イスラエルの霊的姦淫を象徴している。二番目に生まれたのは女の子で、ホセアは「その子をロ・ルハマ〔訳注・新改訳欄外注「愛されない」)と名づけよ。わたしはもう二度とイスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを赦さないからだ」(ホセア1:6)と告げられた。しかし、イスラエルに対するこの拒絶は最終的なものでも、回復不可能なものでもない。事実は、ホセアは続いて、神の国におけるイスラエルの未来の救いを主張する。ホセアは、弱肉強食が動物界から取り除かれる日を見ている。神は野の獣、空の鳥、地を這うものとの契約を結ぶ。暴力と戦争の武器、弓と剣、戦争そのものをもなくしてくださる。
イスラエルは地に安全に住み、安らかに伏す。「わたしはあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と、恵みとあわれみをもって、契りを結ぶ」(ホセア2:19)。それから、ホセアは言う。「わたしは・・・・『愛されない者』を愛し、『わたしの民でない者』を、『あなたはわたしの民』と言う。彼は『あなたは私の神』と言おう」(ホセア2:23)と。
さて私たちは今、キリスト論で見た同じ現象を終末論の領域でも見ている。旧約聖書の諸概念が根本的に再解釈され、予見されていなかった適用を与えられている。旧約聖書においては字義どおりのイスラエルに適用されているものが、ローマ人への手紙9章25節ではユダヤ人も異邦人をも含む教会に適用されているのである(ローマ9:24)。事実、新約聖書時代の教会で構成上優勢であったのは異邦人であった。
パウロは、再びホセア書から引用する。「『あなたがたは、わたしの民ではない』と、わたしが言ったその場所で、彼らは『生ける神の子ども』と呼ばれる」(ローマ9:26)。ホセアは、息子である第三の子を持った。そして、こう告げられた。「その子をロ・アミ〔訳注・新改訳欄外注「わたしの民でない」)と名づけよ。あなたがたはわたしの民ではなく、わたしはあなたがたの神ではないからだ」(ホセア1:9)。
ここではホセアは、すぐに続けてイスラエルの未来の救いを知らせている。「イスラエル人の数は、海の砂のようになり、量ることも数えることもできなくなる。彼らは、『あなたがたはわたしの民ではない』と言われた所で、『あなたがたは生ける神の子らだ』と言われるようになる」(ホセア1:10)。この二箇所で、旧約聖書の文脈では字義どおりのイスラエルに言及している預言が、新約聖書において(異邦人)教会に適用されている。言い換えると、パウロは、ホセア書1:10と2:23の預言が教会において霊的に成就されたと見ているのである。
したがって必然的に、異邦人教会における救いの出来事は、イスラエルになされた預言の成就であるということになる。このような事実があるからこそ、筆者を含む聖書を学ぶ者たちは、教会は新しいイスラエル、真のイスラエル、霊的イスラエルであると言わざるをえないのである。この結論は、パウロがクリスチャンを(霊的な)アブラハムの子孫と言っている箇所によって支持される。「彼は、割礼を受けていないとき、信仰によって義と認められたことの証印として、割礼というしるしを受けたのです。それは、彼が、割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。
すなわち、割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼のときに持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです」(ローマ4:11-12)。ここでアブラハムは、ユダヤ人信仰者と異邦人信仰者の父と言われている。したがって不可避の結論として、ユダヤ人であるかギリシヤ人であるかとは関係なく、信仰者こそがアブラハムの真の子ども、真の霊的イスラエルであるということになる。再び、ローマ人への手紙2:28-29を思い起させられる。すなわち真のイスラエルは、心の内で割礼を受けた人々であるということである。
ローマ人への手紙4:16において、パウロは再び「アブラハムは私たちすべての者の父なのです」と繰り返している。ガラテヤ人に書いたとき、パウロはすでにこの真理を明言している。「ですから、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい」(ガラテヤ3:7)。ディスペンセーション主義者は、《霊的》解釈を、旧約聖書を解釈するうえで最も危険な方法とみなしている。ジョン・ワルブード教授は、これは現代のローマ・カトリック、現代のリベラル派、現代の非ディスペンセーション系保守の立場の著者たちを特徴づけている解釈であると書いている(The Millennial Kingdom, Dunham, 1959, p.71)。しかし筆者は霊的解釈を採用しなければならないと思っている。
なぜなら筆者には、旧約聖書において字義どおりのイスラエルに言及されている約束を、新約聖書が霊的教会に適用していることがわかっているからである。筆者が霊的解釈を採用するのは、契約神学の立場を採っているからではなく、神のことばに縛られているがゆえである。それでは、教会が真に霊的イスラエルであるのなら、「神はご自分の民〔字義どおりのイスラエル〕を退けてしまわれた」(ローマ11:1)のだろうか。パウロはこの問いに続けて、長めの回答を記している。パウロはローマ人への手紙11章5節で、イスラエルの未来の救いを暗示している。
「もし彼ら〔字義どおりのイスラエル〕の捨てられることが世界の和解〔異邦人の救い〕であるとしたら、彼らの受け入れられることは、死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。」
パウロは、このことを有名なオリーブの木のたとえで例証している。オリーブの木は全体として見れば、神の民である。栽培種の枝(ユダヤ人)が栽培種の木から切り取られ、野生種のオリーブの枝(異邦人)が栽培種のオリーブの木に接ぎ木された。しかし、栽培種の木に野生種の枝を接ぎ木するなどという話は聞いたことがない。パウロはその疑問にも気づいていたので、「もとの性質に反して」(ローマ11:2)と語っている。パウロはイスラエルに取って代わった異邦人に、イスラエルに対して誇ってはならないと警告する。神には再び、異邦人を切り取ることもできるからである。
逆に、「彼ら〔ユダヤ人〕であっても、もし不信仰を続けなければ、つぎ合わされるのです。神は、彼らを再びつぎ合わすことができるのです。もしあなたが、野生種であるオリーブの木から切り取られ、もとの性質に反して、栽培されたオリーブの木につがれたのであれば、これらの栽培種のものは、もっとたやすく自分の台木につがれるはずです」(ローマ11:23-24)。
その後、パウロはすばらしい論述によって、全体の状況を要約している。「兄弟たち。私はあなたがたに、ぜひこの奥義を知っていていただきたい。それは、あなたがたが自分で自分を賢いを思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部がかたくなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうして、イスラエルはみな救われる、ということです。こう書かれているとおりです。
『救う者がシオンから出て、
ヤコブから不敬虔を取り払う。
これこそ、彼らに与えたわたしの契約である。
それは、わたしが彼らの罪を取り除く時である』」(ローマ11:25-27)
ここに贖罪の歴史における聖定――栽培種のオリーブの木に生えた栽培種の枝、不信仰ゆえに切り落とされた栽培種の枝、もとの性質に反して接ぎ木された野生種の枝、まだオリーブの木に再接ぎ木されていない栽培種の枝――がある。
イスラエルはつまずきの岩――キリスト――につまずいた。しかしいつまでも倒れたままではない(ローマ11:11)。パウロは、「イスラエルはみな救われる」と語っているが、明らかに、かつて生きていたすべてのユダヤ人についてそう言っているわけではない。パウロは贖罪の歴史について語っている。しかし、生きているユダヤ人の大多数、すなわち「イスラエルはみな」救われる日が訪れるということである。
イスラエルがどのように救われるのかについて、パウロがもっと詳しく書いてくれていたらと思われるかもしれない。「救う者がシオンから出て」ということばは、おそらくキリストの再臨に言及していると思われる。再臨の目的の一つとして、キリストのもとに教会を集めることとともに、イスラエルを贖うことがあるのだろう。
ただし、二つの事柄は明白である。一つは、イスラエルは教会と同じ方法で――つまり、信仰によってメシヤであるイエスに向かうことによって――救われなければならないということ(ローマ11:23)。もう一つは、イスラエルが経験する祝福は、教会が経験している同じ祝福――キリストにある祝福であるということである。それでは、神殿再興についての旧約聖書の詳細な約束についてはどうなるのか。ヘブル人への手紙は、律法には「後に来るすばらしいものは影であっても、その実物はない」(ヘブル10:1)と語り、この問いにはっきりと答えている。
神殿といけにえの制度を規定する律法は、キリストにおいて私たちにもたらされた祝福――実物――の影にすぎない。影はその目的を達成した。キリストは今、天にある真の幕屋に入り、私たちの大祭司としての務めを行なっておられる。今、神の贖罪の計画が影の時代に逆戻りすることなどありえない。実際に、ヘブル人への手紙が明確にこのことを断言している。「しかし今、キリストはさらにすぐれた務めを得られました。それは彼が、さらにすぐれた約束に基づいて制定された、さらにすぐれた契約の仲介者であるからです。もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、後のものが必要になる余地はなかったでしょう」(ヘブル8:6-7)。
ここで強調すべき点は、ヘブル人への手紙は、モーセの契約とキリストによる新しい契約を対比させているということである。もしモーセの契約が適切なものであったのなら、第二の契約は必要なかったはずである。ヘブル人への手紙は、エレミヤ書31:31-34からの長い引用によって、このことを証明している。
「主が、言われる。見よ。日が来る。わたしが、イスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が。・・・それらの日の後、わたしが、イスラエルの家と結ぶ契約は、これであると、主が言われる。わたしは、わたしの律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。・・・なぜなら、わたしは彼らの不義にあわれみをかけ、もはや、彼らの罪を思い出さないからである。」
ここで、すでに直面した事柄に再び遭遇する。新しい契約が二つあると考えることはきわめて困難である。二つの契約とは、キリストによってキリストの血を通して教会との間で結ばれた契約と、イスラエルとの間で結ばれる未来の新しい契約である。イスラエルとの間で結ばれる契約は、ディスペンセーション主義者によれば、大部分がモーセの契約の更新である。確かにパウロがローマ人への手紙9-11章で、字義どおりのイスラエルはまだ新しい契約の内に入れられていないと教えていることは、すでに見てきたとおりである。
しかしその契約とは、十字架を通して教会と結ばれた新しい契約と同じ契約である。別個の契約ではない。ヘブル人への手紙8章は、エレミヤを通してなされた約束を、キリストを通し教会との間に結ばれた新しい契約に適用している。このことは、第二の箇所でさらに明確にされている。ヘブル人への手紙10章11-17節は、罪のための十字架上のキリストの犠牲、続いて神の右への着座、そして「その敵がご自分の足台となるのを待っておられる」ことについて語っている。それは「キリストは聖なるものをされる人々を、一つのささげ物によって、永遠に全うされた」(ヘブル10:13-14)からであると語っている。
それらのことばは、ヘブル人への手紙がキリストにより教会との間に結ばれた契約について語っていることを明らかにしている。それから、ヘブル人への手紙は、再びエレミヤ書31章を引用する。
「それらの日の後、わたしが、彼らと結ぼうとしている契約は、これであると、主は言われる。わたしは、わたしの律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。」またこう言われます。「わたしは、もはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。」これらのことが赦されるところでは、罪のためのささげ物はもはや無用です。(ヘブル10:16-18)
エレミヤ31章の新しい契約が、キリストによってキリストの教会との間に結ばれた新しい契約であることは、だれも否定できない事柄である。ヘブル人への手紙から引用した上記の箇所は、赦しのあるところでは、罪のためのささげ物はもはや無用であると語っている。キリストによって成し遂げられた赦しは、モーセの制度を無用、かつ廃止されたものとした。ヘブル人への手紙は、8:13で同じ真理を断言している。「神が新しい契約と言われたときには、初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものは、すぐに消えて行きます」。
それらのことばは、紀元70年のローマ人によるエルサレムの破壊の史実に言及しているのかどうかは別として、少なくとも、贖罪の実体がもたらされたのだから、古いモーセの秩序は消滅したのだと断言している。ここで再び、旧約聖書預言書の根本的な再解釈を手にする。この解釈によれば、モーセの契約は、そこに記された神殿といけにえの制度を含めて一時的なものである。ヘブル人への手紙の議論は、それらがキリストにおいてもたらされた霊的実体を指し示している予型であり影であるということである。予型と影はそれらの目的を達成するやいなや、神の贖罪のご計画から無用のものとして捨てられるというのである。
このことは、現在のイスラエルの問題にどんなかかわりがあるのか。三つのことが指摘される。
第一に、神はご自身の民を保護してこられた。イスラエルは「聖なる」民(ローマ11:16)のままであり、聖別されており、神の目的を遂行することが定められている。
第二に、まだすべてのイスラエルが救われているわけではない。今日のある学者は、千年王国において歴史は、初めて真のキリスト教国を目撃することになるだろうと言っている。
第三に、イスラエルの救いは、モーセのいけにえの制度の再興を伴うユダヤ教神殿の再建を通してではなく、すでに教会との間で制定されているキリストの血による新しい契約を通してなされなければならない。
ヘブル人への手紙は、モーセのすべての制度は廃止され、消え去ったと断言している。それゆえ、イスラエルは「預言の時計」であるという、よく知られたディスペンセーションの見解は間違っている。近代イスラエルがパレスチナに帰還したことが、イスラエルに対する神の目的の一部分であったとしても、新約聖書はこの問題の解明に何の光も投げかけていない。ただ二千年の間、イスラエルが一つの民族として保持されていることは、神がご自身の民イスラエルを見捨ててはおられないことの一つのしるしではある。
ー引用おわりー*31
追記―1993年
1987年の初版以来、私たちは、本書3章でみてきたような、修正ディスペンセーション主義そして「神のひとつの民」型ディスペンセーション主義の、さらなる進展を目の当たりにしています。特に、最新の発展具合を、Craig A. Blaising and Darrell L. Bock, eds., Dispensationalism, Israel and the Church (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1992)*32の著書の中にみることができます。

Darrell L. Bock(ダラス神学校)


(ブライズィング氏とボック氏の立場は、上の図表の右側上方に位置づけられています。漸進的ディスペンセーション主義〔Progressive Dispensationalism〕です。また、ダラス神学校は、グレイス神学校やタルボット神学校と共に、古典的ディスペンセーション主義→修正ディスペンセーション主義→漸進ディスペンセーション主義へと変化していっています。)
こういった発展は、1987年初版の自著 Understanding Dispensationalists が提言し、促進しようとしていた方向性を強化しています。1987年の段階で小規模に起こりつつあった内容を、彼らは調和させようとしています。それゆえ、実質的に私の著書は1987年当時と同様、今も有用性を残していると思います。
物理的な王国(A PHYSICAL KINGDOM)
いくつかディスペンセーション主義の読者の方々から質問を受けましたので、次に挙げる3つの点を明確にし、また補強しようと思います。最初の質問は、ポール・S・カールリーンによって詳説されている将来的「イスラエルのための地上における物理的王国」についてです*33 多くのディスペンセーション主義者は――修正版の方々であっても――物理的王国に対するこの期待こそ、彼らと契約主義神学者たちを仲たがいさせ、いかんともしがたい亀裂を起こす争点だと考えています。
しかしまず、私たちが思い巡らせている「地上における物理的王国」というのがいかなる種類のものなのかを注意深く定義し、理解するようにしましょう。私はアンソニー・A・ホエケマと同様、万物の成就には、新しい天だけでなく新しい地も含まれていることに力点を置いています(黙21:1)*34。さらに――復活の体が、古い体の変貌であるように――この新しい地は、古い地の変貌であり更新であると私は理解しています。この新しい地は、イエスの復活のからだが触知可能かつ肉と骨であったように(ルカ24:39)、物理的であり物質的であると理解しています。
変貌のからだは実際、1コリ15:44-46のように「霊的なもの」であることでしょう。しかし新しいものの「霊的」性質というのは、聖霊によって満たされ、主によって強められている状態を含みます。またここで言う「霊的」とは、「物質的」の対照としての「空気のような」という意味ではなく、終末論的な秩序《以前》の「自然的」秩序と対照をなす「終末論的」という意味です。ですから、新しい地は、その性質において物理的かつ物質的であると言えましょう。そしてこの新しい地で、すべての贖われたイスラエルは王国の統治を享受するでしょう。「彼らは地上を治めるのです」(黙5:10)。「柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです」(マタイ5:5)。
それゆえ、手短に言いますと、私は将来における「地上の物理的王国」を確かに信じており、そのように信じないことは、かなりの誤謬であると思います。しかしディスペンセーション主義の方々は私の見解に今もって満足してはおられないだろうと察します。彼らの頭にあるのは、イスラエルのための千年王国であり、それは新しい地ではなく、古い地上にある王国のことです。全員ではありませんが*35多くの方々は、この地点で、ラディカルな区別がなされなければならないと考えています。なぜなら彼らは、万物の成就の際の新しい地を、現行の地上とは完全に異なり、関連のないものであると想定しているからです。
そして千年王国期の地上だけが、現行の地上と実質的連続性のうちに存続すると考えています。しかしここでの意思疎通の食い違いはかなり危険なものです。彼らの思い描く「新しい地」というのは、私の思い描く「新しい地」と同じではないのです。私のいう新しい地は、実質上、彼らの千年王国期の地上と見分けがつかないのです。いやそれだけでなく、それは彼らが想像する以上により優れたものです。なぜならそこでは全ての悪はすでに消え去っているからです。
未来におけるユダヤ人信者たちの役割
それから二番目の主要点は、将来的なこの王国が「イスラエルのため」のものであるという点です。そしてこの点においては、修正ディスペンセーション主義者や漸進的ディスペンセーション主義者の方々でさえも、自らと、〈非〉ディスペンセーション主義的前千年王国説者(=歴史的前千年王国説者)との間に区別をつけようと努めている点でもあります。王国が「イスラエルのため」というのはどういう意味なのでしょうか。大半の契約主義神学者たちと同様、私も、イエス・キリストを信じるユダヤ人と異邦人が共に、アブラハムおよびダビデへの御約束を相続すると考えています。
他方、ディスペンセーション主義者は、区別された民族的集団およびnationとしての忠実なるユダヤ人たちが、千年王国にて特別な役割を担うと考えています。それでは、キリストの再臨後、どのような種類の特別な役割が王国内の忠実なるユダヤ人に委ねられているのでしょうか?ここでもまた、私たちは、どのような多種多様な人々のことが私たちの念頭にあるのかを注意深く理解する必要があります。
私のような契約主義の立場にいる者といたしましては、神の国の中に多様性に富んだ民族グループの人々がいるということを積極的に肯定しています。今日のキリスト教会内には、さまざまな民族グループの人々がいます。――ユダヤ人、ジプシー、ポーランド人、リトアニア人、ケチュア人、中国人、ミャンマー人、バントゥー人、コマンチェ人等。。。
新約聖書の時代、異邦人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンはそれぞれ独自の慣習や民族的諸風習を保持していました。異邦人はユダヤ人になるよう要求されておらず、ユダヤ人も異邦人のようになるよう要求されていませんでした(彼らは例えば、引き続き子ども達に割礼を施し、モーセ慣習を遵守することが可能でした。使徒21:21)。それゆえ、こういったすばらしい多様性は、キリストのみからだの栄光を表すなにかであると信じることはきわめて妥当だと思います。そして、それは引き続き、キリスト再臨後における変貌した形態の中にあっても表れていくことでしょう(黙21:24)。
民族的、社会的、さらには地理的多様性であってさえも、それらはキリストのからだの霊的一致ときわめて良く調和しているのです。それゆえに、契約主義神学内では、「キリストにある神のひとつの民の合一」に対する強調は、民族的多様性に対する認識と、きわめて良く調和するものと捉えられています。逆に、ほとんど全てのディスペンセーション主義者は今日、「救いはキリストにある道しかない」ということを積極的に認めています。キリストとの合一により、今やユダヤ人も異邦人も共に、キリストにあって等しく霊的恩恵を享受しています。
ですから契約主義神学者と、ディスペンセーション主義者との間の今日における相違点というのは、それほど甚大なものではないと言えます。契約主義神学者たちは、ユダヤ人信者の民族的特異性というもののいくつかを認めることができますし、ディスペンセーション主義者は、すべての民族グループに対しての共通した恩恵といったもののいくつかを認めることができます。にもかかわらず、重要な相違点は依然として残っています。ディスペンセーション主義者は、将来、グループとしての民族的ユダヤ人信者に、特別な宗教的地位や役割があるということを信じています。
一方、契約主義神学者たちはそう信じてはいません。従って、これから先の話し合いでは、この問題に焦点が置かれるべきだということになるでしょう。それから、ここで鍵となっている問題をさらに明確化するために、消去法的にまずは「何が問題とされていないのか」について述べたいと思います。まず第一に、ユダヤ人クリスチャンがはたして民族的、社会的、地理的、もしくは他の特徴点を保持するのか否かといった点は問いの対象にはなっていません。というのも、間違いなくそれは保持されるでしょうし、そういった相違点はむしろ、キリストのからだの中における多様性に肯定的貢献をすると思われます。
二番目に、はたしてユダヤ人信者が旧約聖書の土地や王国に関する御約束を相続するのかどうかといった事もここで問題にはなっていません。もちろん、彼らは相続するでしょう。換言しますと、私たちは将来的な「地上における物理的王国」が「イスラエルのため」であるか否かということを問題にはしていないのです。*36
ここで問題にされているのは、それがはたして異邦人クリスチャンのためでもあるのかどうかという点です。ユダヤ人クリスチャンは未来のある時点で、ある特別な祭司的特権もしくは宗教的祝福を持ち、そして、そこから異邦人クリスチャンは排除されているのでしょうか?「イスラエルのために」というフレーズは実際的には、①「イスラエルのため、そして異邦人のためではない」という意味なのでしょうか?②それとも、「イスラエルのため、そしてキリストとの合一を通して相続人となった異邦人クリスチャンのためでもある」という意味なのでしょうか?
古典的ディスペンセーション主義は、①の意味を主張しています。そして契約主義神学は②の意味を主張しています。それゆえ、ただ単に、「はたしてユダヤ人は将来の王国において、特別な役割を果たすようになるのか否か?」と問うだけでは問題は明確化されません。事の焦点は、私たちがそれぞれ、いかなる種類の特別な役割というのを想定しているのか、、そこに全てがかかっています。民族的特異性のことでしたら、もちろん、Yesです。そして他の人々が排除された上での、特別な宗教的ないしは祭司的特権・祝福ということでしたら、答えはNoです。
ディスペンセーション主義者自身が、この点でジレンマに陥っています(本書13章参照)。彼らは、キリストにある唯一の救いという統一性(unity)を肯定しようと望んでいます。しかし次に彼らはガラテヤ3章で述べられているパウロの言明に衝突してしまいます。というのもこの箇所でパウロは、キリストにある信仰を通した義認のリアリティーは、「異邦人はユダヤ人信者と共に同じ宗教的特権を授かっている」という結論に容赦なく私たちを導くからです。
パウロの主張は、キリストにある救いの道に対する中心的リアリティーを基盤になされていますから、それはキリスト再臨後の未来の王国にも適用されなければなりません。その時には、ユダヤ人信者は実際、ダビデ王国の祭司的・王権的特権を享受するでしょう。しかし、ここで「異邦人信者はそういった諸特権を等しく共有することはない」と言うのは、全く聖書的根拠に欠けています。さらに、異邦人に対するそのような排除は、ガラテヤ3章と矛盾しており、従って、それは反福音(antigospel)です。それゆえ、異邦人たちは、排除されるのではなく、内包されます。
しかしながら、このように異邦人たちが内包される時、「ディスペンセーション主義前千年王国説」と「契約主義プレミレニアリズム(歴史的前千年王国説)」を差異化させていた最も重要な特徴点が消失することになります。そして、そうなりますと、そういった立場を標識化するものとして「ディスペンセーション主義」という用語使用はもはやその意義を失うことになるでしょう。*37この根本的ジレンマを回避するべく道を示すことのできたディスペンセーション主義者は一人もいません。
救いの唯一の道はキリストとの合一を通した救いです。そしてキリストとの合一は――私たちがユダヤ人であろうと異邦人であろうと――すべての祝福の全き享受へと私たちを導きます。未来は、キリストが成し遂げてくださったことを決して無効にはしません。それがガラテヤ3章の意味するところです。それゆえ、ガラテヤ3章は「岩」であり、未来に関するディスペンセーション主義者の諸見解はこうして、この岩の上で粉々にされるでしょう。私は古典的ディスペンセーション主義の持ついくつかの特徴点を越え、そこから進んでさらに研究を続けておられる漸進的ディスペンセーション主義の方々に個人的いたわりと感謝の気持ちを抱いています。
私は、彼らのこういった前進を嬉しく思っております。と言いますのも、これまで以上に聖書の真理を忠実に表現しておられるように見受けられるからです。また彼らの著書の中に表されている平和的・融和的な語調にも感謝しています。しかしながら、彼らのおかれている立場は、本質的に不安定なものです。長期的に見ますと、これらの方々は、今後、神学的に「古典的ディスペンセーション主義」と「契約主義プレミレニアリズム(歴史的前千年王国説)」との狭間に安らぎの港を見い出すことに困難を覚え、その不可能性を感じることだろうと思います。そして現在、これらの方々自身の見解の上に働いている力は、おそらく今後、ジョージ・E・ラッドの型に倣った契約主義プレミレニアリズムへと彼らを導いていくだろうと予測されます。
シンボルの深み(SYMBOLIC DEPTH)
最後になりますが、私は、予型の領域が特に重要であるという点について今でも確信を持っています。旧約聖書の啓示の中に内在する象徴的深みに対する認識は*38、神のなさる伝達の性質に関する、字義主義的(《平べったい》;flat)諸前提を崩壊させます。そして一度、こういった諸前提が処分されるなら、ご自身の約束に対する神の誠実さは、成就の厳密な形態についての柔軟性と調和していることが見えてくるでしょう。そしてこの柔軟性は、「成就の形態にかんする新約聖書の指示」に第一義的な重要性を与えることに関し現在私たちを阻害しているものを取り除きます。
それではそれが意味していることをもう少し特定化してみることにしましょう。理論上、未来の王国において、ユダヤ人クリスチャンがパレスティナの地に大部分住んでおり、それに対し、異邦人クリスチャンはそれ以外の地域に大部分住んでいる、という状況を人々は想定するかもしれません。そういった地理的特異性はそれ自体において、何か問題を生み出すことにはなりません。しかし、ディスペンセーション主義者は、パレスティナの地という一つの特定の土地に対し、他の土地とは差異化させた、特定の宗教的重要性を見い出そうとしています。
旧約聖書の時期、カナンは紛れもなくそのような重要性を持っていました。なぜなら、それはキリストにおける世界の相続地を予型していたからだと私は考えています(ローマ4:13、ヘブル11:16)。しかし、今ここで、将来、ある場所(or 土地)が格別に聖く、あるいは格別に神の御約束の成就となると仮定することにしましょう。そうしますと、異邦人たちも、この相続地の中に等しく参与権をもたなくてはならないということになります。そうでなかったら、私たちはガラテヤ3章を侵害してしまうことになります。
そして、ただ単に古典的ディスペンセーション主義と共に、「異邦人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンが地上とは区別されたところの天を相続する」と主張するだけでは問題があります。なぜなら、この立場だと、私たちはユダヤ人クリスチャンたちを祝福の地上的側面から廃嫡してしまうことになります。そうなると、この人は、ディスペンセーション主義者が最も大切にしている全ての旧約の御約束と真っ向から対立することになります。また、「ガラテヤ書は、ある狭義の意味における『霊的』祝福のことを言っているに過ぎない」と言うことも問題です。なぜなら、(ディスペンセーション主義者の理解によるところの)「異邦人クリスチャンではなく、ユダヤ人クリスチャンが将来的に、祝福の物質的側面を相続する」という事は依然として真だからです。
さて、異邦人たちは、彼らの得ることのできる神のあらゆる祝福を得るべく熱心でなければなりません。もしもそれらを逃してしまうのなら――たといそれらが将来における下位的な「物質的」祝福であったとしても――、その場合、彼ら異邦人たちには、そういった付加的祝福を見逃すことのないよう、自ら割礼を受け、そして本格的なユダヤ人になろうとするまっとうな理由があります。そしてこういった付加的祝福という考えこそ、パウロが渾身の力を込め論駁した内容だったのです。
ですから、真の危険は、「契約主義的統一性(covenantal unity)は自動的にユダヤ人信仰者から相続権を奪ってしまうことになる」という点にはないのです。(それに実際、そんなことはありませんから。)そうではなく、真の危険は、ディスペンセーション主義者が、ユダヤ人が将来キリストを通して受けることになっている完全な諸特権のいくつかを異邦人も受けることに対し、それ〔=異邦人も受けることになっているそういった諸特権〕を不法にも異邦人から排除してしまっている点にあるのです。
―完―
japanesebiblewoman.hatenadiary.com
文献目録(BIBLIOGRAPHY)
For convenience, many of the works are classified according to their millennial position. Disp. = dispensational premillennialist; Classic premil = “classic” or “historical” premillennialist; Amil = amillennialist; Postmil = postmillennialist.Original dates of publication are given in brackets.
Allis, Oswald T. 1945. Prophecy and the Church. Philadelphia: Presbyterian and Reformed. Amil. A classic against dispensationalism.
Barker, Kenneth L. 1982. “False Dichotomies between the Testaments,” Journal of the Evangelical Theological Society 25:3-16. A “moderate dispensationalist” (close to classic premil) calls for rapprochement.
Barr, James. 1961. The Semantics of Biblical Language. London: Oxford University.
Bass, Clarence B. 1960. Backgrounds to Dispensationalism: Its Historical Genesis and Ecclesiastical Implications. Grand Rapids: Eerdmans.
Beecher, Willis Judson. 1905. The Prophets and the Promise. New York: Crowell.
Berger, Peter L. and Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin.
Berkhof, Louis. 1942. The Second Coming of Christ. Grand Rapids: Eerdmans. Amil.
Black, Max. 1962. Models and Metaphors: Studies in Language and Philosophy. Ithaca, N.Y.: Cornell University.
Boettner, Loraine. 1958. The Millennium. Philadelphia: Presbyterian and Reformed. Postmil. A survey of the major options, antagonistic to dispensationalism.
Chafer, Lewis Sperry. 1936. “Dispensationalism,” Bibliotheca Sacra 93:390-449. Disp.
________. 1951. Dispensationalism. Dallas: Dallas Seminary. Disp.
Cox, William E. 1971. An Examination of Dispensationalism. Philadelphia: Presbyterian and Reformed. Amil. Brief, combative.
Darby, John Nelson. [n.d.] 1962. The Collected Writings. Ed. William Kelly. Oak Park, Ill.: Bible Truth Publishers. Disp. Foundational writings of dispensationalism.
________. [n.d.] 1971. Letters of J. N. D. 3 vols. Sunbury, Pa.: Believers Bookshelf. Disp.
Dodd, Charles Harold. 1953. According to the Scriptures: The Substructure of New Testament Theology. London: Nisbet. Dodd is in the end a modernist. But he is good at laying bare the idea of fulfillment presupposed in New Testament use of the Old.
Dollar, George W. 1973. A History of Fundamentalism in America. Greenville, SC: Bob Jones University. The historical of American dispensationalism described from a dispensationalist perspective.
Ehlert, Arnold D. 1965. A Bibliographic History of Dispensationalism. Grand Rapids: Baker. Disp. Marred by a focus on “dispensations” as redemptive epochs rather than on the distinctives of modern dispensationalism.
Fairbairn, Patrick. 1964. The Interpretation of Prophecy. London: Banner of Truth. Amil. An excellent older work, now in reprint.
Feinberg, Charles L. 1980. Millennialism: The Two Major Views. The Premillennial and Amillennial Systems of Biblical Interpretation Analyzed & Compared. Third and Enlarged Edition. Chicago: Moody. 1st and 2d eds. under the title Premillennialism or Amillennialism? Disp. A standard dispensational text.
Fish, Stanley E. 1978. “Normal Circumstances, Literal Language, Direct Speech Acts, the Ordinary, the Everyday, the Obvious, What Goes without Saying, and Other Special Cases,” Critical Inquiry 4:625-44. Reprinted in Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Cambridge: Harvard University, 1980. Pp. 268-292. The role of worldview and interpretive standards in the determination of meaning.
Fuller, Daniel P. 1957. The Hermeneutics of Dispensationalism. A dissertation to Northern Baptist Theological Seminary. Chicago. Classic premil.
________. 1980. Gospel and Law: Contrast or Continuum? The Hermeneutics of Dispensationalism and Covenant Theology. Grand Rapids: Eerdmans.
Gaebelein, A. C. 1911. The Prophet Daniel: A Key to the Visions and Prophecies of the Book of Daniel. New York: Publication Office “Our Hope.” Disp.
Gaffin, Richard B. 1976. “Systematic Theology and Biblical Theology,” in The New Testament Student and Theology. Vol. III. Ed. John H. Skilton. Philadelphia: Presbyterian and Reformed. Pp. 32-50.
________. 1978. The Centrality of the Resurrection: A Study in Paul’s Soteriology. Grand Rapids: Baker. Amil.
________. 1979. Perspectives on Pentecost: Studies in New Testament Teaching on the Gifts of the Holy Spirit. Grand Rapids: Baker.
Grant, James. 1875. The Plymouth Brethren: Their History and Heresies. London: W.H. Guest.
Hendriksen, William. 1974. Israel in Prophecy. Grand Rapids: Baker. Amil.
Hoekema, Anthony A. 1979. The Bible and the Future. Grand Rapids: Eerdmans. Amil.
Hughes, Philip E. 1976. Interpreting Prophecy. Grand Rapids: Eerdmans. A semipopular exposition of covenantal amillennialism.
Jensen, Irving L. 1981. Jensen Bible Study Charts. Chicago: Moody. Disp.
Kent, Homer A., Jr. 1972. The Epistle to the Hebrews: A Commentary. Grand Rapids: Baker. Disp.
Kline, Meredith G. 1963. Treaty of the Great King: The Covenant Structure of Deuteronomy. Grand Rapids: Eerdmans. Amil.
________. 1972. The Structure of Biblical Authority. Grand Rapids: Eerdmans.
________. 1974. “The Covenant of the Seventieth Week,” in The Law and the Prophets, ed. John H. Skilton. Nutley, N.J.: Presbyterian and Reformed. Pp. 452-469. Amil. A discussion of the key text in Daniel 9.
________. 1980. Images of the Spirit. Grand Rapids: Baker. OT biblical theology, including symbolic overtones of OT institutions.
________. 1981. Kingdom Prologue I. South Hamilton, MA: Meredith G. Kline.
Kraus, Clyde Norman. 1958. Dispensationalism in America: Its Rise and Development. Richmond: Knox.
Ladd, George E. 1952. Crucial Questions about the Kingdom of God. Grand Rapids: Eerdmans. Classic premil.
Lindsey, Hal. 1970. The Late Great Planet Earth. Grand Rapids: Zondervan. Disp. Popular dispensationalist rapture theory.
Longenecker, Richard N. 1975. Biblical Exegesis in the Apostolic Period. Grand Rapids: Eerdmans.
McClain, Alva J. 1959. The Greatness of the Kingdom: An Inductive Study of the Kingdom of God. Chicago: Moody. Disp.
Marsden, George M. 1980. Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth-Century Evangelicalism: 1870-1925. New York/Oxford: Oxford University.
Mauro, Philip. 1928. The Gospel of the Kingdom: With an Examination of Modern Dispensationalism. Boston: Hamilton Brothers. Classic premil.
________. 1929. The Hope of Israel. Swengel, PA: Reiner.
________. 1944. The Seventy Weeks and the Great Tribulation: A Study of the Last Two Visions of Daniel, and of the Olivet Discourse of the Lord Jesus Christ. Rev. ed. Swengel, Pa.: Bible Truth Depot.
Newell, William R. 1947. Hebrews Verse by Verse. Chicago: Moody.
Patte, Daniel. 1975. Early Jewish Hermeneutic in Palestine. Missoula, Mont.: Scholars Press.
Pentecost, J. Dwight. 1958. Things to Come: A Study in Biblical Eschatology. Findlay, Ohio: Dynham. Disp. A full working out of details of eschatology.
Pieters. Albertus. 1937. The Seed of Abraham. Grand Rapids: Zondervan.
Radmacher, Earl D. 1979. “The Current Status of Dispensationalism and Its Eschatology,” in Perspectives on Evangelical Theology, ed. Kenneth S. Kantzer and Stanley N. Gundry. Grand Rapids: Baker. Pp. 163-76.
Reese, Alexander. n.d. The Approaching Advent of Christ: An Examination of the Teaching of J. N. Darby and his Followers. London: Marshall Morgan and Scott. Classic premil.
Ridderbos, Herman N. 1958. Paul and Jesus: Origin asnd General Character of Paul’s Preaching of Christ. Philadelphia: Presbyterian and Reformed. Amil.
________. 1962. The Coming of the Kingdom. Philadelphia: Presbyterian and Reformed.
________. 1975. Paul: An Outline of His Theology. Grand Rapids: Eerdmans.
Robertson, O. Palmer. 1980. The Christ of the Covenants. Grand Rapids: Baker. Amil.
Ryrie, Charles C. 1953. The Basis of the Premillennial Faith. New York: Loizeaux Brothers. Disp.
________. 1963. “The Necessity of Dispensationalism,” in Truth for Today, ed. John F. Walvoord. Chicago: Moody. Disp.
________. 1965. Dispensationalism Today. Chicago: Moody. Disp. An introduction to dispensationalism.
Sandeen, Ernest R. 1970. The Roots of Fundamentalism: British and American Millenarianism 1800-1930. Chicago: University of Chicago.
Sauer, Erich. 1953a. The Dawn of World Redemption: A Survey of Historical Revelation in the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans. Disp. A moderate form of dispensationalism allowing multiple fulfillments.
________. 1953b. The Triumph of the Crucified: A Survey of Historical Revelation in the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans. Disp.
________. 1954. From Eternity to Eternity: An Outline of the Divine Purposes. Grand Rapids: eerdmans. Disp.
Scofield, Cyrus I. 1907. The Scofield Bible Correspondence School, Course of Study. 7th ed. 3 vols. [No place and no publisher are given]. Disp. (The title page shows that this edition, unlike some later editions, was actually authored by C. I. Scofield. Moreover, the copy in the library of Westminster Theological Seminary, inherited from the library of C. G. Trumbull, has a handwritten appreciation in the front, “To Charles Gallandet Trumbull … with the love of The Author.” Clearly Scofield claims to be “the author,” not merely a final editor.)
________, ed. [1909] 1917. The Scofield Reference Bible. The Holy Bible containing the Old and New Testaments. Authorized King James Version…. Ed. C. I. Scofield. New York: Oxford. Disp. The most wide-spread source for popular American dispensationalism.
________, ed. 1967. The New Scofield Reference Bible. Holy Bible, Authorized King James Version…. New York: Oxford. Disp.
Silva, Moises. 1983. Biblical Words and Their Meaning: An Introduction to Lexical Semantics. Grand Rapids: Zondervan.
Tan, Paul Lee. 1974. The Interpretation of Prophecy. Winona Lake, Indiana: BMH Books. Disp.
Van Gemeren, Willem A. 1983. “Israel as the Hermeneutical Crux in the Interpretation of Prophecy,” WTJ 45:132-144.
________. 1984. “Israel as the Hermeneutical Crux in the Interpretation of Prophecy (II),” WTJ 46:254-297.
Vos, Geerhardus. [1903] 1972. The Teaching of Jesus concerning the Kingdom of God and the Church. Philadelphia: Presbyterian and Reformed.
________. [1926] 1954. The Self-Disclosure of Jesus: The Modern Debate about the Messianic Consciousness. Grand Rapids: Eerdmans.
________. [1930] 1961. The Pauline Eschatology. Grand Rapids: Eerdmans. Amil.
________. [1948] 1966. Biblical Theology: Old and New Testaments. Grand Rapids: Eerdmans.
Walvoord, John F. 1959. The Millennial Kingdom. Finlay, Ohio: Dynham. Disp.
Walvoord, John F., and Zuch, Roy B. 1983. The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty. Wheaton, IL: Victor.
Wyngaarden, Martin J. 1934. The Future of the Kingdom in Prophecy and Fulfillment: A Study of the Scope of “Spiritualization” in Scripture. Grand Rapids: Zondervan.
*1:I realize that such a description may strike many D-theologians as inaccurate. They would want to characterize their approach to interpreting all parts of the Bible as uniformly “literal.” But, as we shall see, such was not the way that Darby or Scofield described their own approach. While Darby and Scofield affirmed the importance of “literal” interpretation, they also allowed symbolical (nonliteral) interpretation with respect to the church. Of course, in our own modern descriptions we are free to use the word “literal” in a different way than did Darby or Scofield. But then the word “literal” is used in a less familiar way, and such a use has serious problems of its own (see chapters 8 and 9).
*2:参照:Fuller1980, 10
*3:例、ライリー1965、65-74、フェインバーグ1980、67-82
*4:Radmacher 1979, 163-64
*5:関連記事:Dispensational vs. Historic Premillennialism「ディスペンセーション主義前千年王国説と歴史的前千年王国説の9つの違い」by Wick Broomall
*6:It should be noted that Feinberg sees covenant theology as having the “dual hermeneutics” (1980, 79). Since both dispensationalism and covenant theology must deal with the distinctions between epochs of God’s dominion, each is in fact bound to have certain theological distinctions and dualities. Those dualities flow over into the area of hermeneutics. What matters is the kind of dualities that we are talking about. My terminology is intended to capture the distinctive duality of dispensationalist hermeneutics, without being evaluative or prejorative.
*7:詳しくは本書の第3章をご参照ください。
*8:Fuller 1957, Bass 1960, Dollar 1973, Marsden 1980
*9:[n.d.] 1971, 3:298; quoted by Fuller 1957, 37-38; 1980, 14
*10:[n.d.] 1971, 3:298; quoted by Fuller 1957, 38
*11:1875, 5; quoted in Bass 1960, 73
*12:Darby [n.d.] 1962, 20:240-41 [Ecclesiastical Writings, no. 4, “God, Not the Church …”]; quoted by Bass 1960, 106.
*13:Bass 1960, 108-109
*14:Bass 1960, 106
*15:訳注:
*16:[n.d.] 1971, 3:299; quoted by Fuller 1957, 39
*17:[n.d.] 1962, 2:373 [“The Hopes of the Church of God …,” 11th lecture, old ed. p. 567]; quoted in Bass 1960, 130
*18:[n.d.] 1962, 2:35 [“On ‘Days’ Signifying ‘Years’ …,” old ed. pp. 53-54]; quoted in Bass 1960, 129
*19:Darby [n.d.] 1962, 2:376 [“The Hopes of the Church of God …,” 11th lecture, old ed. pp. 571-72]; quoted in Fuller 1957, 45.
*20:Mardden 1980参照
*21:関連記事
*22: For specific examples of Scofield’s “spiritualization” of historical Scriptures, see the notes in The Scofield Reference Bible on Gen 1:16, 24:1, 37:2, 41:45, 43:34, Exod 2:2, 15:25, 25:1, 25:30, 26:15, introduction to Ruth, John 12:24. Ezek 2:1 can also be included, as an instance of spiritualization based on a historical part of a prophetic book. The introductory note to Song of Solomon should also be noted.
*23:I do not intend to criticize the expression itself (it is biblical: 2 Tim. 2:15 KJV). Neither am I criticizing attempts to distinguish addressees of prophecy. I am concerned here for the practice of forbidding applications on the basis of a division.
*24:*訳者注:聖書神学についての記事のご紹介:
*25:訳注:
japanesebiblewoman.hatenadiary.com
*26:訳者注:アンチノミアニズムに関する記事のご紹介:
*27:参:Stanley E. Fish, “Normal Circumstances, Literal Language, Direct Speech Acts, the Ordinary, the Everyday, the Obvious, What Goes without Saying, and Other Special Cases” 1978, 625-44.
*28: Martin J. Wyngaarden (1934, 88-135) speaks in this connection of “latent spiritualization” in the OT. I am not altogether satisfied with the way in which he develops his argument, but I believe that the basic idea is sound.
*30:訳者注:新改訳で「故郷」と訳されているギリシャ語は、πατρίςであり、意味としては、「父(先祖)の土地、故郷、ふるさと、郷里」(織田昭『新約聖書ギリシア語小辞典』)等、記載されています。
*31:関連資料
Seeing Christ in All of Scripture, 2016 (PDF)
目次
1 Biblical Hermeneutics by Vern S. Poythress
2 Old Testament Hermeneutics by Iain M. Duguid
3 New Testament Hermeneutics by G. K. Beale
4 Systematic Theology and Hermeneutics by Richard B. Gaffin Jr.

Palmer Robertson, The Christ of the Covenants
目次
PART ONE:
INTRODUCTION TO THE DIVINE COVENANTS
1. The Nature of the Divine Covenants
2. The Extent of the Divine Covenants
3. The Unity of the Divine Covenants
4. Diversity in the Divine Covenants
PART TWO:
5. The Covenant of Creation
PART THREE:
THE COVENANT OF REDEMPTION
6. Adam: The Covenant of Commencement
7. Noah: The Covenant of Preservation
8. Abraham: The Covenant of Promise
9. The Seal of the Abrahamic Covenant
10. Moses: The Covenant of Law
11. Excursus: Which Structures Scripture―Covenants or Dispensations?
12. David: The Covenant of the Kingdom
13. Christ: The Covenant of Consummation
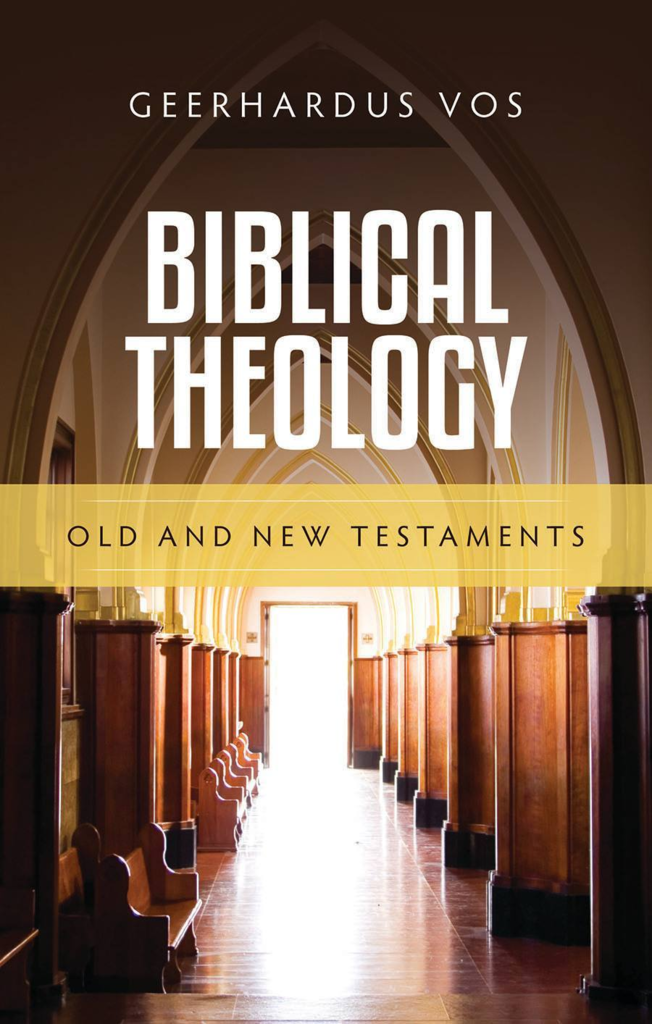
Outline of Geerhardus Vos' Biblical Theology
*32:We should also note the continued discussions under the auspices of the Dispensational Study Group, which meets yearly in connection with the annual national meeting of the Evangelical Theological Society. In November, 1989, the Group focused discussion on my book, and the results were published in Grace Theological Journal 10 (1989) 123-164.In addition, the major material from the Dispensational Study Group in 1990 appears in Grace Theological Journal 11 (1990) 137-169.
*33:The words come from Paul S. Karleen’s review and response, “Understanding Covenant Theologians: A Study in Presuppositions,” Grace Theological Journal 10 (1989) 132. See my comments in Poythress, “Response to Paul S. Karleen’s Paper `Understanding Covenant Theologians,’” Grace Theological Journal 10 (1989) 148-149.
*34:Hoekema, The Bible and the Future.
*35:David L. Turner, “The New Jerusalem in Revelation 21:1-22:5: Consummation of a Biblical Continuum,” in Dispensationalism, Israel and the Church, pp. 264-292, helpfully emphasizes the continuities between the millennium and the consummation.
*36:Though it might better be said that believing Israel comes into the kingdom. See Bruce K. Waltke, “A Response,” in Dispensationalism, Israel and the Church, p. 352.
*37:“If one envisions a Jewish millennium in which the kingdom will be restored to ethnic Israel in the land, the term dispensationalism will still be useful. If ethnic Israel’s role is only its remnant status on a permanent equality with the Gentiles in the one true people of God with no distinctive role in the land beyond the Parousia, then the term dispensationalism is misleading and ought to be dropped” ibid., p. 354.
*38:Note that I do not see typology merely as a product of later commentary on earlier events, but as adumbrated by the significance of events even in their original context. The theocentric character of biblical revelation invites us from the beginning not to take the route of flat reading.