
...トマス・アクィナスは、キリスト教信仰と理性の間には自然な調和があることを示しました。これこそがトマスの偉大な業績です。トマスは、二つの文化が出会った時代に(当時、信仰は理性の前に降服しなければならないように思われていました)、二つの文化がともに歩むことを示しました。彼が示したことはこれです。理性が信仰と相容れないように見えるなら、それは理性ではありません。信仰が真の合理性と対立するように見えるなら、それは信仰ではありません。こうしてトマスは新たな総合を作り上げました。この総合が、その後の時代の文化を築いたのです。(引用元)
目次
神学生たちの証し
①ジョシュア・リム(ウェストミンスター神学校卒業生)
これらの研究を通して私は自分の疑いや懐疑主義の大部分が、ルターの「十字架の神学*1 」を通した神知識および、現実認識に関し自分が無意識的に採用してきた、ある種の哲学的諸前提に由来していたことに気づきました。*2
また、私が抱えていた哲学的諸問題の大部分も、「哲学と神学」の関係に関するこれまでの自分の理解から生じてきていたのだということに気づきました。
こうして哲学と神学の分かち難い結びつきが私の中で確かなものとされていきました。いわゆる「純粋なる神学」というものを人は所持することはできません。それはちょうど、ーー聖書を解釈するという行為なくしてーー単に「聖書を信じる」ということが不可能なのと同じです。人がそれを認めているいないに拘らず、哲学というのは常にそこに現前しています。
そして「神学とは区別されたところの哲学など、私は一切持っていない」と主張している人々は不可避的にある種の疑念を引き出さずにはおれないのです。(それはちょうど、「自分はただ単にまっすぐに聖書を読んでいるのです」と主張しているファンダメンタリストたちによって引き起こされる疑いと同様です。)
この時期、私は聖トマス・アクィナスの著作の中に知的安らぎの資源を見い出しました。すでに溯ること1年前、アクィナスのことを紹介してもらい、神学校でも彼に関する講義を受講していました。その時点で私はすでに彼の『神学大全』の4分の1を読了していましたが、(この学びにより、『アクィナスは存在論神学(ontotheology)をやっていた』という観念は是正されました。)、依然として私は恩寵と律法に関する彼の見解にいくばくかの疑念を持っていました。とはいえ、私は前に進むことにし、『神学大全』を最後まで読み切ることにしました。
聖アクィナスを通し、私は神を信じるに当たってのより説得力のある強靭な根拠を見い出し、またこの天使的博士(Angelic Doctor)による入念な描出ーー自然によって知られ得るもの(例:神の存在)と、恩寵を通してのみ知られ得るものとの間の輪郭ーーにより、自分自身の懐疑主義を見直すことができ、そこから脱出する上でトマスに大いに助けられました。
ちなみにこういった懐疑主義はカントを遥かに溯り、最終的には裸の神(deus nudus)に対するルターのアレルギーに根差しているのではないかと思われます。この考え方によると、すべてのスコラ哲学者たちは、哲学を通し不法に垣間見ようとしていたとされています。ルターは「栄光の神学 theologia gloriae」と「十字架の神学 theologia crucis」を区別しましたが、それに付随する形で、ソラ・フィデ(「信仰のみ」)という概念、そしてソラ・スクリプトゥーラ(「聖書のみ」)の教理が生まれました。*3
私の目には、唯名論的な哲学的レンズを通してのみ、義認は、なにか純粋に外因性のものとして認識され得るように思われました。(その結果として、クリスチャンは「同時に聖徒であり罪びとである(simul iustus et peccator)」という見解が生じることになりました。)
換言しますと、改革派神学者たちが一般に「教父たちは過度にギリシャ哲学から影響を受けていた*4」と非難しているのと同じようなあり方で私は、宗教改革者たちは、さらに無批判的な様で同時代の哲学を受け入れたという責めを負っているのではないかということに気づきました。それどころか彼らは自らの諸前提を無視した上で、自分たちの聖書解釈を聖書と同一視していたのではないでしょうか。中世神学者たちの‟推論”を批判しながらーー。」*5
②アンドリュー・プレスラー(南部福音神学校卒業生)
...南部福音神学校(SES)での学びがいかにしてカトリック教会とのフル・コミュニオンへの道を行く上での助けになったのかについて以下二点を挙げたいと思います。
まず最初の一点は、南部福音神学校における聖トマス・アクィナスの高い位置づけです。教授の何人かは、根本的な哲学的/神学的諸事項においてアクィナスを信頼できる指針として捉えており、そのことを通し、カトリック教会に対する私の従来の偏見が打ち砕かれました。
SESの教授全員がトマス主義者ではありませんでしたが、哲学、キリスト教弁証学、神学緒論、組織神学がトマス主義的視点から教えられていることは確実でした。聖トマスと共に問題に取り組んでいく中で、神の神秘に関し、理性は不十分であり、そういった神の諸神秘は、神的権威を基盤にした上で信仰によって受け取られなければならないということを私たちは発見しました。
しかしそれと同時に学んだのは、信仰は理性を廃棄するわけではなく、むしろ、理性は神的権威に訴えている純正なる諸主張と見せ掛けの諸主張を識別する上で私たちを助けてくれるものになり得るということでした。
もちろんトミズムだけがキリスト教神学の中における唯一の有益な学派というわけではありませんが、それが、聖書的、神学的、哲学的智慧をたたえた深い井戸であることは確かだと思います。そしてその井戸の水を味わい、それがひんやりし且つ清涼なものであることだけは初学者に過ぎない自分にもよく分かりました。*6
聖トマス・アクィナス(ベネディクト十六世)
聖トマスはきわめて重要な神学者です。そのため第二バチカン公会議は二つの文書で聖トマスの思想の研究をはっきりと勧めました*7。すなわち、『司祭の養成に関する教令』(Optatam totius)と『キリスト教的教育に関する宣言』(Gravissimum educationis)です。しかし、トマス研究を大いに重視し、推進した教皇レオ13世(在位1878-1903年)はすでに1880年に聖トマスをカトリック学校・大学の守護聖人と宣言しました。
聖トマスがこのように評価されるおもな理由は、彼の教えの内容だけでなく、彼が用いた方法、とりわけ哲学と神学の新たな総合と区別にあります。教父たちはさまざまなプラトン主義的哲学を目の当たりにしました。
この哲学の中では包括的な世界観と人生観が示されていました。そこには神と宗教に関する問題も含まれました。こうした哲学に対抗して、教父たちも、信仰から出発し、プラトン主義の諸要素を用いながら、包括的な現実理解を構築しました。それは人間の本質的な問いにこたえるためです。
教父たちは、聖書の啓示に基づき、信仰の光に照らして修正したプラトン主義によって構築したこの現実理解を「われわれの哲学」と呼びました。それゆえ、「哲学」ということばは、純粋に理性的で、したがって信仰と区別される体系のことではなく、現実に関する総合的な理解を意味しました。この現実理解は信仰の光に照らして構築されますが、理性によって創造・考案されます。たしかにこの現実理解は理性固有の力を超えていますが、それ自体として理性をも満足させます。
聖トマスにとって、アリストテレス(紀元前322年頃没)によるキリスト教以前の哲学との出会いは、新しい展望を開きました。アリストテレス哲学が旧・新約聖書を知ることなく作られたことは間違いありませんでした。それは啓示によらず、理性のみによって行われた世界の説明でした。そしてこの首尾一貫した合理的説明は説得力をもちました。それゆえ、教父たちの古い形式の「われわれの哲学」はもはや役に立たなくなりました。哲学と神学、信仰と理性の関係を再考しなければなりませんでした。
まず、それ自体として包括的で説得力のある「哲学」が存在しました。これは信仰に先立つ合理的説明です。次いで、信仰によって、信仰のうちに行われる思考としての「神学」が存在しました。ここで次のことをただちに問わなければなりません。
合理性の世界、すなわちキリストと無関係な思考としての哲学は、信仰の世界と両立しうるでしょうか。それとも、両者は相容れないのでしょうか。二つの世界が相容れないことを裏づけるさまざまな要素が存在しました。
しかし、聖トマスは両者が両立することを強く確信しました。そればかりか、キリストを知らずに構築された哲学は、それを完成するために、いわばイエスの光を待ち望んでいると考えました。これは聖トマスにとって大きな「驚き」でした。この「驚き」が聖トマスの思想家としての道を決定づけたのです。
このように哲学と神学が独立したものであること、同時に、両者が関係し合うことを示すことが、この偉大な教師の歴史的使命となりました。それゆえ、19世紀に、近代的理性と信仰は相容れないと強く主張されたとき、なぜ教皇レオ13世が聖トマスを理性と信仰の対話の導きとして示したかが分かります。
聖トマスは神学的著作の中で哲学の合理的思考を前提とし、それを具体化しました。信仰は、人間理性が獲得した真理の遺産を堅固にし、統合し、照らします。*8
聖トマスは認識の二つの手段――すなわち、信仰と理性――を信頼しました。そこから彼は、信仰と理性はともに、あらゆる真理の唯一の源泉である、神の「ロゴス(みことば)」から生まれるという確信へと導かれました。神の「ロゴス」は、創造の領域においても、あがないの領域においても働きます。
理性と信仰は一致しますが、他方で、両者は異なる認識の手続きを用いることも認めなければなりません。理性は、間接的なものであれ直接的なものであれ、現実に内在する証拠の力によって真理を受け入れます。これに対して、信仰は、ご自身を啓示する神のことばの権威に基づいて真理を受け入れます。
聖トマスは『神学大全』の初めにこう述べます。
「学には二つの類のものがあることを知るべきである。すなわち或る学は、たとえば算数や幾何学等のように、知性の自然本性的な光のもとに知られる原理から出発するのであるが、また或る学は、上位の学の光のもとに知られる原理から出発する。たとえば光学は幾何学によって知らされた原理から出発し、音楽は算数によって知られる原理から出発するのである。ところで聖なる教(すなわち神学)は、この第二の意味での学である。なぜならそれは上位の学の光のもとに知られる原理から出発するからである。この場合『上位の学』とは、すなわち神と至福者たちの知にほかならない」*9
この区別は、人間的諸学の自律性と、神学の自律性をともに保証します。しかし、この区別は分離を意味するのではありません。むしろそれは、互いに利益を与え合う協力を意味します。実際、信仰は、理性を、自らの力に疑いを抱くあらゆる誘惑から守り、理性がますます広い地平に自らを開くよう促し、理性における根本的諸原理の探求を生き生きと保ちます。
他方、理性も、神と人間の関係に関する超自然的な領域に自らを適用することによって、自身の考察を豊かにします。たとえば、聖トマスによれば、人間理性は疑いなく唯一の神の存在を肯定することが可能です。しかし、神の啓示を受け入れる信仰のみが、三位一体の神の愛の神秘に達することができます。
他方で、信仰が理性を助けるだけではありません。理性も、自らの手段によって、信仰のために何らかの重要なことをなしえます。理性が信仰に対して行う3種類の奉仕について、聖トマスは『ボエティウス三位一体論注解』(Super Boetium De Trinitate)の序文でこう要約します。「信仰のもろもろの基盤を示すこと、類比を通して信仰の真理を説明すること、信仰に反対する異論を排斥すること」*10
根本的に、神学史全体は、このような知性の努力の遂行だといえます。知性は、信仰の理解可能性、その表現と内的一致、合理的性格、そして人間の善を推進する力を示すからです。
神学的推論の正しさとその真の認識論的な意味は、神学的言語の価値に基づいています。聖トマスによれば、神学的言語は、根本的に、類比的言語です。創造主である神と、被造的存在者のへだたりは無限です。類似性よりも類似していない点のほうがはるかに大きいのです*11。にもかかわらず、創造主と被造物がどれほど違っていても、被造的存在と創造主の存在の間には類比があります。この類比のおかげで、わたしたちは人間のことばで神について語ることができるのです。
聖トマスはこの類比の教えを基礎づけました。しかも優れた哲学的論証によってです。すなわち、啓示により、神ご自身がわたしたちに語りかけたのであれば、神はわたしたちが神について語ることも可能にしたといえます。
わたしはこの教えを思い起こすことは重要だと思います。実際、この教えは現代の無神論のある種の反論を解決する助けとなるからです*12。現代の無神論は、宗教的言語が客観的な意味をもつことを否定します。そして、宗教的言語は主観的意味ないし単なる感情的な意味しかもたないと主張します。この反論は実証主義の思想に由来します。実証主義は、人間は存在を認識せず、むしろ実在の経験的機能だけを認識すると考えるのです。
聖トマスや偉大な哲学的伝統とともに、わたしたちはこう考えます。実際には、人間は自然科学の対象である機能だけを認識するのでなく、存在そのものについても何ごとかを認識します。たとえば人間は、自分の存在の物理的・生物学的側面だけを認識するのでなく、人格、すなわち他者であるあなたを認識するのです。
聖トマスの教えに照らされて、神学はこう主張します。たとえどれほど限界があるにせよ、宗教的言語は、矢がその意味する現実に向かうように、意味をもっています。わたしたちは存在に触れるからです。
人間理性とキリスト教信仰の間のこうした根本的な一致は、トマスの思想の他の基盤となる原理にも見いだされます。すなわち、神の恵みは人間本性を否定せず、かえってそれを支え、完成させるというものです。実際、人間本性は、罪を犯した後も、完全に破壊されたのではなく、傷つき、弱まったにすぎません。
神から与えられ、受肉したみことばの神秘を通じて伝えられた恵みは、まったく無償のたまものです。このたまものにより、本性はいやされ、強められ、助けられます。それは、幸福という、すべての人の心が本来望むことがらを追求するためです。人間のすべての力は、神の恵みによって清められ、造り変えられ、高められるのです。
自然本性と恵みの間のこの関係の重要な適用は、聖トマス・アクィナスの道徳神学において行われました。聖トマス・アクィナスの道徳神学はきわめて現代的な意味をもっています*13。聖トマスはこの分野に関する教えの中心に、新法、すなわち聖霊の法を位置づけます。
深く福音的な展望のもとに、聖トマスは、聖霊の法が、キリストを信じるすべての者に与えられた聖霊の恵みであるといいます。この聖霊の恵みと、教会が伝えてきた、教理的・道徳的真理に関する文書また口承による教えが結びつけられます。
聖トマスは道徳生活における聖霊の働き、すなわち恵みの根本的に重要な役割を強調します。対神徳と人間的徳はこの恵みから生まれます。そして聖トマスは、もしキリストへの信仰の関係を真に生きるなら、すべてのキリスト信者は「山上の説教」の崇高な目標に達することができることを悟らせます。
しかし、聖トマスは付け加えていいます。「恩寵は自然本性よりもより強力・有効であるとはいっても、人間にとってより本質的・・・・なのは自然本性である。」*14
そのため、キリスト教的道徳においては、理性が一つの役割を果たします。理性は道徳的自然法を識別することができるからです。理性は、幸福に至るために、行うほうがよいことと、避けるほうがよいことを考慮することによって、この道徳的自然法を認識できます。幸福はすべての人の心のうちにあります。この幸福が、他者に対する責任を課し、またそこから、共通善を追求させます。
いいかえると、対神徳であれ人間的徳であれ、人間の徳は人間本性に根ざしています。神の恵みは倫理的努力に伴い、それを支え、促します。
しかし、聖トマスによれば、信者と非信者の区別を問わず、すべての人は本来、自然法のうちに表された、人間本性が要求するものを認識し、そして、実定法の法文のうちに自然法へと導かれるよう招かれています。実定法は、人間の共存を規定するために国家的・政治的権力から発布されるものだからです。
自然法と、自然法の表す責任が否定されるとき、個人レベルでは倫理的相対主義*15への、政治的レベルでは全体主義国家への道が悲惨な形で開きます*16。人間の普遍的権利を擁護し、人格の尊厳の絶対的価値を肯定するには、ある基盤が必要です。自然法と、自然法が示す議論の余地のない諸価値こそが、この基盤ではないでしょうか。*17
尊者ヨハネ・パウロ二世は回勅『いのちの福音』の中に、深い現代的意味をもち続けることばを書きました。
「ですから、社会の将来と健全な民主主義の発展のためには、これらの本質的にして人間に本来備わる、道徳的な諸価値を再発見することが急務です。これらの諸価値は人間存在の真理そのものから流出し、人間の尊厳を表し擁護します。いかなる個人、過半数の人々、国家といえども、この価値を造り出すことも修正することも破壊することもできず、ただ容認し尊重し伸張させる義務を負うのみです。」*18
要するにトマスは、広く信頼できる人間理性の概念をわたしたちに示してくれます。「広い」というのは、この理性が、いわゆる経験的・科学的理性の領域に限定されず、むしろ全存在へと、すなわち人生の根本的で放棄することのできない問いかけにも開かれているからです。
「信頼できる」というのは、この理性は(とくにそれがキリスト教信仰の霊感を受け入れるならば)、人格の尊厳と、人格の権利の不可侵性と、人格の義務の強制力を認める文明の推進者となるからです。
人間の権利の不可侵性を認識する上で根本的に重要な、人格の尊厳に関する教えが、聖トマス・アクィナスの遺産を受容した思想界で深まったことは驚くべきことではありません。聖トマスは、被造物である人間に関してきわめて崇高な概念をもっていたからです。聖トマスはこの人間の概念を、厳密に哲学的なことば遣いをもって、こう定義しました。「全自然におけるもっとも完全なもの、すなわち、『理性的本性において自存するところのもの』」*19
聖トマス・アクィナスの深い思想が、彼の生き生きとした信仰と熱心な信心から生まれたことを、わたしたちは忘れてはなりません。この信心を、聖トマスは霊感に満ちた祈りの中に表しました。
たとえば彼は神に次のように祈り求めます。「御身を探す熱心、御身を見いだす知恵、御身のみ心に適う生活、御身を待ち望む毅然たる堅忍、ついには御身に一致し奉る信頼をわれに与え給え。」*20*21
ー終わりー
関連記事
*1:theologia crucis;Kreuzestheologie.訳者注:アウグスブルグ信仰告白、第18条 自由意志について「自由意志について、われらの諸教会は、かく教える。人間の意志は、公民的の正義を行い、理性が把握するような事柄を選ぶいくらかの自由を有する。しかし聖霊なくしては、神の義、すなわち霊的正義を行う力をもたない。引用元」
*2:訳注:
*3:訳注:関連文献 A.E.マクグラス著(鈴木浩翻訳)『ルターの十字架の神学―マルティン・ルターの神学的突破』(2015)
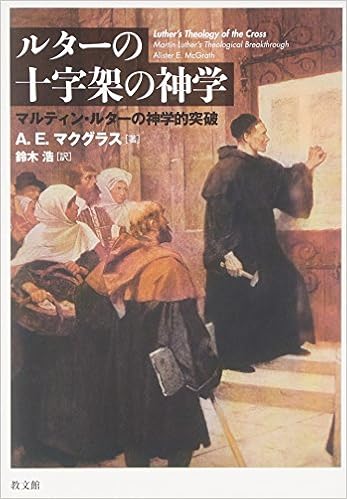
*4:訳注:
*5:私の辿ってきた道ーージョシュア・リム神学生の真理探究記【後篇】
*6:私の辿ってきた道ーーアンドリュー・プレスラー師の信仰行程【その1】
*7:訳注:
*8:訳注:
*9:『神学大全』:Summa theologiae I, q. 1, a. 2〔山田晶訳、『世界の名著続5 トマス・アクィナス』中央公論社、1975年、85頁〕。
*10:同:ibid. q. 2, a. 2。
*11:DS 806参照
*12:訳注:
*13:訳注:関連文献

アラスデア・マッキンタイア著『美徳なき時代』(みすず書房).
*14:『神学大全』:Summa theologiae I-II, q. 94, a. 6〔稲垣良典訳、『神学大全13』創文社、1977/1993年、87頁〕
*15:訳注:
*16:訳注:
*17:訳注:
*18:同71
*19:『神学大全』:Summa theologiae I, q. 29, a. 3〔山田晶訳、『神学大全3』創文社、1961/1987年、52頁。ただし文字遣いを一部改めた〕
*20:『種々の敬虔な祈り』:Piae preces〔竹島幸一訳、上智大学中世思想研究所編訳・監修『中世思想原典集成14 トマス・アクィナス』平凡社、1993年、813頁。ただし文字遣いを一部改めた〕訳注: