
聖マクシモス(Μάξιμος ο Ομολογητής, 580-662)のイコン(出典)
目次
執筆者:袴田玲氏(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程(Ph.D)、日本学術振興会特別研究員)
序
ビザンツ帝国は、ギリシア哲学をときに正面から否定しつつも継承した最大の担い手である。古代には学芸都市として栄えたアテナイを擁し、ギリシア語を公用語とするこの帝国は、ヘレニズム文化を受け継ぐ一方で、キリスト教を国教としたことによって、自らの出自、とりわけギリシア哲学への屈折した対応を迫られることになる。
ビザンツ帝国のキリスト教、すなわち正教会の立場からすれば、唯一の真理とはキリストのことであり、それは形而上学的思弁によって追及されるのではなく、信仰に基づく実践によって体験されるものである。
それゆえ、西欧ラテン教会における神学のような教義の体系を構築するとか、哲学を神学に積極的に取り入れるなどという姿勢は、中世以降、正教会においてはダマスクスのヨアンネス(650-750年頃)のようなわずかな例外を除いては見受けられず、ギリシア哲学は人々を過ちへと導く「異教の哲学」とみなされた。6世紀には伝統あるアカデメイアが閉鎖され、キリスト教の教えに反する哲学書が焚書処分を受けることもしばしばであった。
![]()
ダマスクスのヨアンネス(Ιωάννης Δαμασκήνος)ダマスコのイオアン - Wikipedia
しかし、そのような状況を潜り抜けて、ギリシア哲学はビザンツ文明の中で脈々と保たれつづけた。*1なかでも新プラトン主義は、時間的・思想的近さゆえ、キリスト教との深い結びつきがある。ポルフュリオスは『キリスト教徒駁論』を著して激しい論争を引き起こし、教会当局によって焚書に処せられたが、他方、彼の『イサゴーゲー』は、世俗の教育の場ではアリストテレス哲学の入門書として重用されていた。

ポルフュリオス(Πορφύριος, 234ー305頃.ローマ?)*2
また、プロクロスとの類似関係が指摘されている偽ディオニュシオス・アレオパギテースは、正教会内では「大ディオニュシオス」と呼ばれ、現在に至るまで絶大な権威をもって読み継がれている。
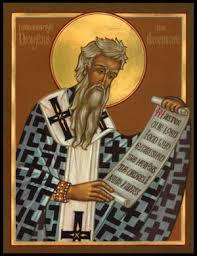
偽ディオニュシオス・アレオパギテース(Ψευδο-Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, Pseudo-Dionysius Areopagita)*3
このように、ビザンツ時代における正教思想と新プラトン主義哲学との間には、一概には語れない複雑な影響関係がある。それゆえここでは、正教会の神秘思想の中心である神化思想と、新プラトン主義哲学における一者への還帰と合一の思想という点に焦点を絞って考察してみたい。
神化とヘシュカスム
聖書には、人間は神の「像と似姿にしたがって」創造されたと記されている(創世記1:26)。ここから、正教会の教父・師父たちは人間神化の思想を築き上げていった。
4世紀のアタナシオスは、「神は人間となった、人間が神とされるために」と述べて人間神化に思想的支柱を与え、7世紀に入ると、証聖者マクシモスが「神の受肉と人間の神化は、神と人間の共働的果実」と述べ、双方向的視点を打ち出すに至る。

聖マクシモスの生涯が周りに描かれた、正教会のイコン(17世紀、ソリヴィチェゴドスク)出典
かくして「人間は創造の瞬間から神の像と似姿を与えられていたにもかかわらず、アダムとエバの堕罪によって似姿を失ってしまった。しかし、神が人間となって罪を贖ったので、人間は再び神の似姿を回復し、神へと導かれる運命を取り戻した」という、ある意味で楽観的な発想が、正教会の根本的な人間理解として共有されてゆく。
そしてこの人間観を基礎として、神と人間が一つになること、人間が神へと導かれることが目指された。10世紀以降、今日でも正教の聖地とされるアトス山の修道士たちの間で盛んになったヘシュカスムとは、身体技法を含む独特の修行によってひたすら神化を追求する運動であった。
そして、14世紀にヘシュカスムをめぐって帝国を二分する論争が起きた際、その正教的正統性を擁護して体系化し、「ヘシュカスムの博士」と言われたのがグレゴリオス・パラマス(1296頃ー1359年)である。次に、彼の言葉を手掛かりとして、正教会における神化思想と新プラトン主義との関連について考察しよう。
パラマスにおける神化とプロティノスにおける合一

グレゴリオス・パラマス(1296年 - 1359年)は小アジア出身のギリシアの神学者、アトス山の修道士、のちにテサロニケの大主教を務めた、正教会の聖人。中世正教神学の主流となった静寂主義(ヘシュカズム)の提唱者であり、かつ静寂主義を代表する理論家である。中世の正教会における理論家として最も重視される。出典
人間の「神による創造から堕落、そして似姿の回復と神との合一」という正教会の神化思想と、新プラトン主義における万物の「一者からの発出と漸衰そして還帰」という思想に、すでに両者の構造的類似を見いだすことができるが、さらに人間の神化を語るパラマスの思想そのものに、神秘的合一を語るプロティノスの哲学を連想させるものが多々ある。
たとえば、パラマスの修行論には「知性(ヌース)の自身への立ち返り」という表現がしばしば出てくる。彼によれば、神化をめざすヘシュカスムの修行において重要なのは、絶えざる祈りと知性(ヌース)の身体への回収・集中である。
そもそも新プラトン主義の文脈において知性(ヌース)という概念は、感覚的形象を次々と捨象していったさきに、直知のうちでとらえるべきものというニュアンスを帯びていたが*4、パラマスにとって知性(ヌース)とは、気をつけていないと感覚器官、とりわけ視覚を通じて外へと四散していってしまうものである*5。
修道者は己れの知性(ヌース)を自身の内へと取り集め、一点に集中させるよう努力しなければならない*6。*7
パラマスは、偽ディオニュシオスを引用しながら、「〔知性が〕自分自身に戻ってきて、迷いなき道を通じて登攀するように、自分自身を通じてさらに神へと戻る*8」よう推奨する。この点でパラマスは、「魂の外から内への向き直りと魂自身への立ち返り」*9を強調するプロティノスの言葉づかいにきわめて接近する。
「無形相の神あるいは一者との一化」という主題への強い関心もまた、プロティノスとパラマスに共通する。パラマスは、人間と神が一つになるという事態を次のように表現している。「光は光の中において見られるのであり、見るものも同じ光の中にある。、、、他のすべてのものから離れ出ながら、見るもの自身もまたすっかり光となり、見られているものに似たものとなり、いやむしろ、混じり気なく一とされるのである。光でありつつ、光を通じて、光を見ながら」*10。
また、次のようにも言う。「人間の水準を超えた状態になるのであるから、恵みによって、すでに神ですらあり、神と一つになって、神を通じて神を見るのである」*11。
パラマスのこれらの言葉づかいからは、プロティノスと同じ「一」への渇望、つまり、修行者があらゆる多様性を脱して自己自身と一つになり、さらに主客を超えて神(一者)と真に一となることへの欲求が感じられるであろう。また、合一の動きに「見る」という動詞が好んで使われる点、神(一者)が光として表現される点も、両者に共通である。
このように、新プラトン主義の文脈において練り上げられた知性(ヌース)概念をさらに発展させることで、正教会の神化思想は、具体的な修行の実践のかたちを生み出したと言えるのであり、また、光と光が溶け合うさまに譬えて神秘的合一を語るパラマスとプロティノスには相通じるところがある。
さらに、パラマスがヘシュカスムを擁護するために依拠した最大の思想的源泉が偽ディオニュシオス・アレオパギテースだったという事実も、ヘシュカスムと新プラトン主義との関係を考える上で重要なことであろう。*12
しかし、神の受肉への信仰が、正教会における神化思想と新プラトン主義的合一とを決定的に分かつ。本来、ユダヤ=キリスト教の伝統では、絶対的存在者である神は、被造物を無限に超越し、神と被造物との間に超えざる深淵があるとされる。
その深淵を超え、神が人間の身体をとってこの世界に現れたという決定的な出来事なしには、正教会の神化思想は存在しえない。それゆえ、パラマスにおいては、キリスト教の入信儀礼である洗礼が神化の必要条件とされるのである。
また、神の超自然的な恵みの力なしに(つまり、人間の自助努力のみでは)神化は達成されえないことへの強調や、神化に人間の身体も与るとされる点、そもそも人間の身体が卑しいものとはみなされず、したがって霊的完成をめざす修行の中で身体技法が積極的に用いられる点なども、パラマスにおける神化がプロティノスの神秘的合一と大きく異なるところである。
ー終わりー
『新プラトン主義を学ぶ人のために』(水地宗明/山口義久/堀江聡〔編〕)p.300-304.
関連資料
Dionysian Ponderings: Transcendence and the Plotinian Oneafkimel.wordpress.com
*1:とりわけ、多くの写本の伝承を通じて古代哲学の命脈を保ったことの意義は小さくない。プロティノス『エンネアデス』のフィチーノ訳も、ビザンツ帝国からもたらされた写本なしには実現しなかったであろう。
*2:管理人注:ポルフュリオス(Πορφύριος, 234ー305頃.ローマ?)ギリシアの新プラトン派の哲学者。生地はパレスチナのテュロスかバタナイアとされる。アテネでロンギノスに弁論術を、ローマでプロティノスに哲学を学んだ。著作は哲学、宗教、文献学にわたり、キリスト教に対して激しい攻撃を加えた『キリスト教徒駁論』 (Kata Christianōn)はのちに異端として焚書にされたが断片を残し、文献学的研究『ホメロス問題』 (Homērika zētēmata)はホメロス研究史上の金字塔であり,『オデュッセイア』における比喩的解釈の典型となっている。哲学的著作としては,『ピタゴラスの生涯』 (Pythagorou bios)、『禁欲について』( Peri apoches empsychon)、『アリストテレス範疇論入門』 (Eisagōgē eis tas Aristotelēs katēgorias)などがあり,プロティノスの著作の編纂 (『エネアデス』) と伝記は哲学史に多大の貢献をした。(参照)
*3:管理人注:偽ディオニュシオス・アレオパギテース(Ψευδο-Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, Pseudo-Dionysius Areopagita)は、5-6世紀ごろの(おそらく)シリアの神学者。『ディオニュシオス文書』(Corpus Dionysiacum)と呼ばれる一連の神学的文献群の著者と同定されている人物である。この文献群は、元々は『使徒行伝』(17:34)に一度だけ登場するアテナイのアレオパゴス評議所の評議員である「アレオパゴスのディオニュシオス」の手によるものと長年信じられてきたが、15世紀以降、その文書群が後世の別人によるものだと判明したため、著者の区別をつけるため、「偽」という接頭辞をつけて呼ばれるようになった。19世紀末までに、その成立年代は485年から531年の間と特定された。(参照:偽ディオニュシオス・ホ・アレオパギテース - Wikipedia)
*4:『エンネアデス』V, 3.9
*5:『聖なる仕方で修行するヘシュカストのための弁護』〔以下、『弁護』と略記〕I-2-3, I-2-8
*6:『弁護』I-2-5, I-2-8, I-2-10
*7:この点からすれば、ヘシュカスムにおける知性(ヌース)は、われわれが「精神統一」や「気を散らさない」と言うときに使う「精神」や「気」といったものに近いものであると言えよう。
*8:『弁護』I-2-5
*9:『エンネアデス』VI.9,7,16-18
*10:『弁護』II-3-36
*11:『弁護』II-3-52
*12:もちろん、パラマスにとって「ディオニュシオス文書」の真作性は微塵も疑われておらず、それは、ヨアンネス・スキュトポリスやマクシモスによる註解を通して正教会の伝統に位置づけられた大ディオニュシオスその人の権威によっている。