
目次
Michael Horton, The Unintended Reformation,Feb, 2016

マイケル・ホートン(カリフォルニア州ウェストミンスター神学大、組織神学)
一般に受け入れられているモダニティー解釈
「近代性は、宗教改革の《苗床》で生まれた。実際、宗教改革者たちにより、用途理性の科学的世界観が生み出され、その結果、ラディカル多元主義、リベラル民主主義、懐疑主義、資本主義が産出された。いや、それだけでなく何より重要なのは、彼らの生み出した科学的世界観が、礼典的コスモス(sacramental cosmos)を、神及び意味を欠く幻滅の宇宙に置き換えてしまったことにある。」
これが、過去数世紀に渡り、一般に受け入れられてきたモダニティー解釈です。そしてここでの焦点は、いわゆるこの先駆的役割に関し、「果たして宗教改革は称賛を受けるべきか、それとも責めを負うべきか?」という点にあります。
ノートル・ダム大の歴史家ブラッド・グレゴリーは、次に挙げる書名から分かるように、「然り、責めを負うべきである」という後者の立場を採っています。『意図されたものではなかった宗教改革:いかにして宗教的革命が社会を世俗化するに至ったか(Brad S. Gregory, The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society)』。
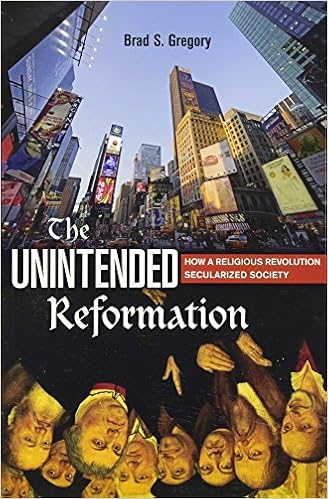
Bead S. Gregory, The Unintended Reformation: How A Religious Revolution Secularized Society, Harvard University Press.
こういった彼の立場は決して孤立したものではありません。事実、グレゴリーは、対抗宗教改革以来の、やや微妙な線上のローマ・カトリック論戦法を採用しています。
〈スコトゥス・ストーリー〉とは何か?
より端的に言えば、彼は、私が〈スコトゥス・ストーリー〉と呼んでいるものを、驚異的に拡大させつつ著述の中で繰り返しています。ーーもっとも、それはアンリ・ドゥ・リュバックやアモス・フンケンシュタインの繊細な含みに欠け、ジョン・ミルバンクの「ラディカル・オーソドクシー」系の著述家たちの哲学的深遠さには欠けていると思いますが。
スコトゥス命題をひと言でいうと次のようになります。
ーー異教的知恵とキリスト教的知恵の中世的綜合は、トマス・アクィナス(1225-74)の内にその絶頂を見ましたが、それはヨハネス・ドゥンス・スコトゥス(1265-1308)および、彼以上にラディカルな同僚であったフランシスコ会士オッカムのウィリアム(1287-1347)によって解体されました。そして、この解体には次にあげる4つの重大な動向が伴っています。
1.一義性(Univocity)
つまり、神の存在、人の存在という言う時の「存在」の意味が両者共に同じであるということ。それゆえに、神はその他の諸存在の中の一存在となり、もしくは全ての被造的諸存在が単に部分であるところの全体となる。どちらの場合にしても、喪失されたのは、「人間存在は神存在の類比的なもの(analogical)である」という伝統的信条である。
それゆえ、神が"存在する"と我々が言う時、この引用符("")が示唆しているのは、いかなる点においても、創造主なる神を被造物と同一視することを拒否しているという事である。一義性がもたらす一つの結果は、神的および人間の媒介者が、ゼロ・サム・ゲームになることである。しかし、類比的に言えば、神は、他の者たちの中にある一行為者では決してない。
2.節約の原理もしくは「オッカムの剃刀」
これは、「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでない。できる限りシンプルな説明が望ましい」とする指針のこと。実際面では、この原理により、次第に科学者たちは、自然への神的介入を排除し始め、ついには「諸現象はただ自然原因に訴えることのみによって説明がつく」と主張されるようになっていった。

三浦俊彦氏が描いた「オッカムの剃刀」の説明図。三浦氏はオッカムの剃刀について「ある事実Pを同様に説明できるのであれば仮説の数(または措定される実体の数)は少ないほうが良い」とするものだと説明しています。(参照)
3.知性そして自然から(神および私たち両方の)意志を分離させるラディカルな主意主義(voluntarism)
この見解によると、神の絶対的権力は全てを決定しているため、神の創造した世界はーー伝統的神学が「自然の中に内在している」と信じていたーー自然の構想や目的とラディカルに異なっている、あるいは相反してさえいるかもしれない、とされている。
こうして、「理性」と「啓示」、「神の通常の働き」と、「異例なる(恣意的でさえある)御意志」との間に亀裂が生じてくる。またこの主意主義は被造物にまで及び、こうして人間は、自らの自然(彼らの固有・生来のありさま)よりも、彼らの意志(彼らがそうなるよう選ぶところのもの)により決定されているのだと捉えられるようになる。
4.「普遍」よりも「個別」の方により焦点を置く
少なくともスコトゥスは精神の中に存在する普遍を信じていたが、オッカムに至り、「普遍はただ単に便利な用語・メタファーに過ぎない(それゆえに唯名論)」と結論づけられるようになった。
我々は類似の特徴に対し、個別的なものを一括すべくそういった用語を用いている。それゆえ、演繹的な根拠づけを通した自然(もしくは普遍的諸形態)分析によるのではなく、観察を基盤にした帰納法を通した事象(もしくは個別)分析により、我々は、自然哲学において真理に到達するのである。
ーーーーー
ちなみに、アンリ・ドゥ・リュバックはさらに溯って、このナラティブに、11世紀のグレゴリウス改革をも包含しています。また最近では、チャールズ・テイラーが著書「世俗の時代(A Secular Age)」の中で(彼のナラティブを豊かにするべく西洋改革諸運動の歴史を含めつつも)このスコトゥス・ストーリーに倣っています。
いろいろと度合の違いこそあれ、このテーゼは、モダニティー解釈に関するローマ・カトリックおよびアングロ・カトリック界を制覇している感があり、そういった論陣の中には、エティエンヌ・ジルソン(Etiènne Gilson)、ルイス・ドゥプレ(Louis Dupré)、それからジョン・ミルバンクの「ラディカル・オーソドクシー」陣営も含まれます。 ↓2012年にモスクワにある聖ティクホン正教会大学にて行われたミルバンク(ノッティンガム大)の特別講義。ミルバンクはこの講義の中で、西洋神学界の最近の動向を説明しつつ、なぜ西洋神学界の流れが、東方正教会の伝統の方に向かいつつあるのかについて彼の視点から解説しています。こういった潮流を私たちはどう捉えればいいのでしょうか? ">*1
また、この徴候は、ハンス・ボースマ(Hans Boersma)、ピーター・ライトハート(Peter Leithart)といった改革派の著述家たちの内にも顕れてきています。
つじつまが合う
一度、この〈スコトゥス・ストーリー〉を理解するなら、その他の全てはつじつまの合うものになっていきます。それによると、宗教改革は、近代の「幻滅」の運び屋です。
礼典的タペストリーの織物をビリビリと引き裂きつつ、宗教改革者たちは形而上学的「一義性」「主意主義」そして「個人主義」のロジックをその当然なる結論へと押し進めていきました。グレゴリーによると、宗教改革者たちは、創造主ー被造物の関係における、より聖書的な神学を回復させることを試みていました。「しかし」と彼は述べます。
「しかし、伝統的キリスト教見解からの彼らの離脱のいくつかは、一義的な形而上学的諸前提を含意していたように思われ、それがおそらく最終的には、幻滅した自然世界に関する概念へとつながっていったのではないかと思われます。そういった離脱の一つが、(ローマ教会で理解されているところの)サクラメント性へのまだらな拒絶です。
そして彼ら宗教改革者たちのそういった拒絶は、教会の七秘蹟だけにとどまらず、超越的神が、自然世界・物質世界の内に、そしてそれを通してご自身を顕示してくださっているリアリティーに関するその包括的・聖書的見解としてのサクラメント性への拒絶にも及びました。」(41)
ここでの問題ーー特に歴史的著述ーーは、そこに歴史的議論が皆無であるということです。〈スコトゥス・ストーリー〉は、ここ何十年に渡り、かなりの反証に直面させられているにもかかわらず、それがあたかも自明のものであるかのごとく前提されています。また、本書には、リチャード・クロス、メリリン・マクコード・アダムズ、アラン・ウォルターズ等のスコトゥス専門家たちの名前すら挙がっていません。
宗教改革に話が及ぶと、〈スコトゥス・ストーリー〉はさらに擁護不能なものになります。
グレゴリーの著書は、「彼らの離脱のいくつかは、一義的な形而上学的諸前提を含意していたように思われ、それがおそらく最終的には、幻滅した自然世界に関する概念へとつながっていったのではないかと思われます。」といった修飾句で両面作戦をとりつつ、結局それが、宗教改革に関する本であるというよりはむしろ、(彼自身の言葉を借りるなら)「私たちの失ってしまった世界(“The World That We Have Lost”)」に関する彼独自の思想を表明した本となってしまっています。
しかもこの中心的主題を正当化する源泉資料(もしくは二次的資料としての専門家の著述への言及)はただの一つとして本書の中で挙げられていないのです。
もちろんルターには何人か唯名論教師たちがいました。しかし彼らの金言である「神は、人の内にあるものを行なう者たちへの恩寵を拒否したまわない」にルターは幻滅しました*2。
哲学的には、ルターはドイツ神秘主義家たちにより関心を抱いていましたーー〈スコトゥス・ストーリー〉の擁護者たちが「今、私たちを救うものとなろう “will save us now”」(ミルバンク)と考えている、新プラトン主義の一種です。
カルヴァンは哲学者ではありませんでしたが、関連する点において言えば、彼は一般的にアクィナス側についており、神の「絶対的権力」というスコトゥス派的思想のことを「地獄で発明された悪魔的冒涜」だと言及しています。
ルター派および改革派のスコラ学者たちは、ローマ・カトリック側と比べた時、より一般的に言って、一義性の教理よりも、伝統的な「類比の教理(doctrine of analogy)」に忠実でありました。*3
実際の主題
しかし結局のところ、上記に挙げた一連の事柄はグレゴリーにとってそう重要なことではないのです。〈スコトゥス・ストーリー〉を前提しながら、彼の主張したい真の主題は、「宗教改革により、ラテン的キリスト教世界が破壊されてしまった」という点にあります。
改革後に起こった教会の分裂、そして多種多様な信仰信条への分化は、宗教改革の「聖書のみ(sola scriptura)」が大惨事を引き起こしたレシピに他ならないということを立証しているのではないか?ーーそう彼は主張しています。
Sola scripturaを、それがあたかもSolo scripturaであるかのようにーーあたかも宗教改革者たちが聖書の私的解釈を導入したかのように(彼らは実際そうしませんでした)ーー解釈することにより、グレゴリーは改革者たちの見解を、ラディカリズムに走った一部の再洗礼派と一緒くたにしてしまっています。
その結果は明白でした。ーーありとあらゆる教理的主張をめぐり、ヨーロッパ知識階級の間に宗教戦争および懐疑主義が生じた。そこで彼らは反動を起こし、今度は世俗的理性に向かっていった。その結果、われわれの世界および、世界に関するわれわれの認識の領域における神の臨在が消滅してしまった。。。
こうして形而上学的「一義性」テーゼで武装しつつ、各章は、宗教改革から、デカルト、ニュートン、スピノザ、ロック、ヒューム、カント、ヘーゲル、シュライエルマッハー、ニーチェ、フッサール、ハイデッガーに至る同じ道程を辿ります。
たといその悪役俳優が実際にはローマ・カトリック教徒であったとしても、「それはひとえに彼がプロテスタントの台本で演じていたから」という具合に取り扱われています。
従って、これは、宗教改革史およびモダニティーの中における諸出来事への影響を論じた本というよりは、「いかに宗教改革が西洋を破壊したか」についてのエッセー六本立ての論文集という感が拭えません。--「神を排除する」「教理を相対化する」「教会をコントロールする」「倫理性を主観化する」「物質生活を加工する」「知識を世俗化する」。そして当然出されるであろう反論に反撃するかのごとく、グレゴリーは「ノスタルジーに抗して」という終章でこの本を締めくくっています。
誤りを含み、且つ瑣末な諸主張
グレゴリーは、一義的形而上学の思想ーーおよびその影響ーーに対し危機感を持っていますが、それに対し私も共感しています。しかし(それがどう道を誤ったかに関する)ドゥ・リュバックの説明の中にさえ、宗教改革の遥か以前、さらにはスコトゥス以前にでさえ起ったその他の重要な出来事は包含されています。
懐疑主義を助長させるような教会論争の抱える問題に対するグレゴリーの強調は確かに正しいと言えます。ですが、そういった事は教会史を通しこれまで繰り返し繰り返し起こってきたことでありーー最近のものでは西方教会大分裂(1378-1417)があり、半世紀以上にも渡って教会は、競合する二人の教皇の間で分裂していました。そして当時、キリスト教世界の誰もが、どちらかの教皇から破門宣告を受けていたのです。

そうなると、自分が教会の真の指導者に忠実であり、それゆえに真に恩寵に与っているということに対し人はいかにして確信を持つことができるというのでしょう?この教会大分裂自体、「教会の中で究極的権威を持っているのは、教皇か、それとも公会議か?」を巡っての論争によって引き起こされたものでした。
グレゴリーは、中世期のコンセンサスを誇張しています。当時、汎神論に近似する神秘主義的諸構想は、物質の永遠性に関する議論と並行し、覇権を奪おうとしていました。
パリ大学とヴァチカンは自らの立場を転じる以前には、アリストテレス(そして含意として、アリストテレスに訴えていたアクィナスのような神学者たち)を糾弾していましたが、その事に関し彼はどう考えているのでしょうか。
また、異教魔術を復活させ、古代懐疑主義、快楽主義、ストア主義の新訳バージョンという絶え間ない奔流を、初期近代の〈血流〉に流し込んだルネッサンスの影響はどうでしょうか?グレゴリーの単色な記述の中ではそういった事は一切言及されていません。
そして、腐敗し切ったローマ教皇庁に対する暴力的反動が、なぜだか、ーーできるかぎり合意点を見いだそうと公会議に参加しようと試みていたーー宗教改革者たちのせいだということになっていますが、それはどうしてなのでしょうか。
本書の中の中心的主張は誤っていないと思いますが、それらは往々にして瑣末です。16世紀の宗教改革および対抗宗教改革が西洋教会を分裂させたことに同意しない人がそもそもいるのでしょうか?
もしくは、競合する真理の諸主張により、さらなる対立状態が生み出され、その結果、軍隊がキリストの御名によって諸都市を破壊し尽くし、さらなる国家統制への戸が開かれ、教理が私的領域へと制限されるようになっていった、、というような事実に異議を唱える人は果しているでしょうか。
「意図されたものではなかった諸結果」というのは啓蒙的カテゴリーではありますが、グレゴリーの語りの中で、それは、ーーアラスデア・マッキンデアの『美徳なき時代』の読者たちが、その書の中に見い出す、この時代の最も嘆かわしいありとあらゆる惨状ーーその一切合財をぽーんと放り込むことのできる〈何でもガラクタ箱〉と化しています。
宗教改革というのは、腐敗した中世教会のもたらした「意図せぬ結果」だったのでしょうか?それでは対抗宗教改革の「意図せぬ結果」は何だったのでしょうか。フランス革命でしょうか。
欠落したナラティブ
「意図的されたものではなかった宗教改革」のような論駁本と、数あるプロテスタント系の著書には、皮肉な類似性があります。
両者共に、複雑に入り組んだ16世紀を、ーー「科学的想像」「民主主義」「資本主義」といった中心的思想の周りを回るーー単純で(しかも時代錯誤的)ナラティブに変容させてしまっており、そうした上で、彼らはその先駆的役割を担った宗教改革を称賛したり、あるいは糾弾したりしています。
歴史記述における偏見という問題以外にも、ここで欠落しているのは、改革者自身および彼らの後継者ーープロテスタント・スコラ学者たちーーの持っていた形而上学的諸前提に関する正確な像です。事実、プロテスタント・スコラ哲学者たちは、驚くほど保守的であり、本書で焦点になっているいくつかの点において彼らはむしろアクィナス的でさえあるのです。
もしも人が、「宗教改革はただ単に再(re-)福音伝道だったにとどまらず、ある側面においては、むしろ、かろうじてキリスト教化していたヨーロッパの『主要福音伝道 “primary evangelization”』でもあった」とする多くの歴史家(ジャン・ドリュモー、パトリック・コリンソン等)の見解を概観するなら、宗教改革を、モダニティーの運び屋ーーましてや世俗化の運び屋ーーと見ることはますます困難になってきます。
しかしそれ自体が、ポレミカルな歴史叙述の逆の形態になるのかもしれません。一連のそういった記述に欠落しているのは、歴史それ自体と同じく、複雑にしてーーしかも興味深いーーナラティブです。
ー終わりー